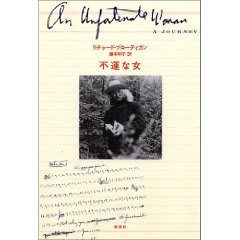
『不運な女』 リチャード・ブローティガン ☆☆☆☆☆
以前さっと斜め読みしただけだった『不運な女』を再読。いつもにもまして淡々としたとりとめのない作品で、初読時はあまり印象に残っていなかったが、今回じっくり読んで見事な小説だと認識を改めた。これはブローティガンの死後に発見された原稿で、評価は割れているらしい。それは良く分かる。酒にたとえれば端麗きわまりない、ほとんど真水に近いような味わいの作品で、とりとめなさすぎ、インパクト弱過ぎ、などと思う人の方が多いかも知れない。だから万人にお薦めはしない。しかし私個人の趣味で言わせてもらうと、この小説はほれぼれするほどの傑作だ。
体裁としては、数ヶ月の旅の合間に書き綴られた日記、ということになっている。とはいっても旅行記などではなく、それらの日々における日常の断片、とりとめのない回想、あるいは妄想、を断片的に気の向くままに書いた、という感じだ。ブローティガン自身が書いているところによれば、これは一冊のノートを文字でいっぱいにしようとする試みであり、ノートの余白がなくなったところで終わりになる。実際、この小説はそのようにして終わる。なんともあっけなく、また人を喰っている。
ちなみに、このノートは日本製である。
また別のところでは、これは現在と過去を混在させようとする試みであるとも書かれている。現在の記述と過去の回想がごちゃまぜに書かれているのはそのせいだろう。いずれにしろ、とりとめのない断片の羅列である。実にいい加減だ。求心力のあるストーリー、緻密に組み立てられたプロット、構成の妙、熱狂性、一貫性、整合性、伏線、伏線の回収、などは一切存在しない。
では本書をひとつの小説としてまとめているのは何かというと、「不運な女」というタイトルと、たびたび出てくる自殺した女への言及である。ブローティガンはこの女が自殺した家に何度か滞在する。そしてそれについてたびたび言及する。ところがこれがまたブローティガンらしいところだが、自殺した女が誰なのか、なぜ自殺したのかという背景、経緯などは、結局書かれないのである。読者はいつかそれが出てくるはずだ、そしてそれが本書のキモとなるはずだと期待するが、結局出てこないまま小説は終わってしまう。
これはどういうことなのか。単なる韜晦なのか。読者をケムに巻いているだけなのか。いい加減な人なのか。よく分からないが、この小説は要するに二つの読み方が可能、というか二つの顔を同時に持っているということだ。一つは、ゆるーい断片集、エッセイと小説と日記が融合した曖昧なテキストという読み方。もう一つは、記述不在の不運な女を不在という形で記述した小説、という読み方である。
要するに脈絡ない話をだらだら書いた小説ってことだろと言われればその通りだ。返す言葉はない。本書の美点を説明するのは難しい。前に書いたように、真水みたいな酒を飲んでいる感触に似ている。けれどもふとした瞬間に、消え入りそうにはかないけれどもうっとりする香りに鼻孔をくすぐられる、これはそんな小説だ。
もちろん、それがブローティガンの文体に多くを負っていることは間違いない。あとがきにも書かれているように、ブローティガンの「引力の影響を受けない」文体と、それが日常的なディテールを詩的に、不思議なものへと変容させていくやり方には抗しがたい魅力がある。ブローティガンは淡々としたリラックスした語り口で、時にコミカルに、時にリリカルに、透明で不定形な世界をほんのりと色づけしていく。それに加えて、小説の中にかけらのようにばらまかれている「不運な女」という、あるかなきかのモチーフが、死の想念でもって全体に微妙な陰影をもたらす。それはもちろん、オフビートでありながら胸に迫る「Nへ…」という序文によって、最初から通低音として導入されている。実際のところ、とりとめもなく日常をさまよう本書の真のテーマは「死」だと言ってもいい。
ブローティガンのリリシズムはロジックにも説明にも描写にも依存しない。それは言葉のイメージ、運動、リズムによってもたらされるが、このアプローチは小説家というより詩人のそれである。そしてそういったブローティガンの詩人的なアプローチが、ひっそりと、目につきにくい形で、けれどもなんとも精妙に花開いているのが、本書の魅力ではないかと思うのである。
以前さっと斜め読みしただけだった『不運な女』を再読。いつもにもまして淡々としたとりとめのない作品で、初読時はあまり印象に残っていなかったが、今回じっくり読んで見事な小説だと認識を改めた。これはブローティガンの死後に発見された原稿で、評価は割れているらしい。それは良く分かる。酒にたとえれば端麗きわまりない、ほとんど真水に近いような味わいの作品で、とりとめなさすぎ、インパクト弱過ぎ、などと思う人の方が多いかも知れない。だから万人にお薦めはしない。しかし私個人の趣味で言わせてもらうと、この小説はほれぼれするほどの傑作だ。
体裁としては、数ヶ月の旅の合間に書き綴られた日記、ということになっている。とはいっても旅行記などではなく、それらの日々における日常の断片、とりとめのない回想、あるいは妄想、を断片的に気の向くままに書いた、という感じだ。ブローティガン自身が書いているところによれば、これは一冊のノートを文字でいっぱいにしようとする試みであり、ノートの余白がなくなったところで終わりになる。実際、この小説はそのようにして終わる。なんともあっけなく、また人を喰っている。
ちなみに、このノートは日本製である。
また別のところでは、これは現在と過去を混在させようとする試みであるとも書かれている。現在の記述と過去の回想がごちゃまぜに書かれているのはそのせいだろう。いずれにしろ、とりとめのない断片の羅列である。実にいい加減だ。求心力のあるストーリー、緻密に組み立てられたプロット、構成の妙、熱狂性、一貫性、整合性、伏線、伏線の回収、などは一切存在しない。
では本書をひとつの小説としてまとめているのは何かというと、「不運な女」というタイトルと、たびたび出てくる自殺した女への言及である。ブローティガンはこの女が自殺した家に何度か滞在する。そしてそれについてたびたび言及する。ところがこれがまたブローティガンらしいところだが、自殺した女が誰なのか、なぜ自殺したのかという背景、経緯などは、結局書かれないのである。読者はいつかそれが出てくるはずだ、そしてそれが本書のキモとなるはずだと期待するが、結局出てこないまま小説は終わってしまう。
これはどういうことなのか。単なる韜晦なのか。読者をケムに巻いているだけなのか。いい加減な人なのか。よく分からないが、この小説は要するに二つの読み方が可能、というか二つの顔を同時に持っているということだ。一つは、ゆるーい断片集、エッセイと小説と日記が融合した曖昧なテキストという読み方。もう一つは、記述不在の不運な女を不在という形で記述した小説、という読み方である。
要するに脈絡ない話をだらだら書いた小説ってことだろと言われればその通りだ。返す言葉はない。本書の美点を説明するのは難しい。前に書いたように、真水みたいな酒を飲んでいる感触に似ている。けれどもふとした瞬間に、消え入りそうにはかないけれどもうっとりする香りに鼻孔をくすぐられる、これはそんな小説だ。
もちろん、それがブローティガンの文体に多くを負っていることは間違いない。あとがきにも書かれているように、ブローティガンの「引力の影響を受けない」文体と、それが日常的なディテールを詩的に、不思議なものへと変容させていくやり方には抗しがたい魅力がある。ブローティガンは淡々としたリラックスした語り口で、時にコミカルに、時にリリカルに、透明で不定形な世界をほんのりと色づけしていく。それに加えて、小説の中にかけらのようにばらまかれている「不運な女」という、あるかなきかのモチーフが、死の想念でもって全体に微妙な陰影をもたらす。それはもちろん、オフビートでありながら胸に迫る「Nへ…」という序文によって、最初から通低音として導入されている。実際のところ、とりとめもなく日常をさまよう本書の真のテーマは「死」だと言ってもいい。
ブローティガンのリリシズムはロジックにも説明にも描写にも依存しない。それは言葉のイメージ、運動、リズムによってもたらされるが、このアプローチは小説家というより詩人のそれである。そしてそういったブローティガンの詩人的なアプローチが、ひっそりと、目につきにくい形で、けれどもなんとも精妙に花開いているのが、本書の魅力ではないかと思うのである。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます