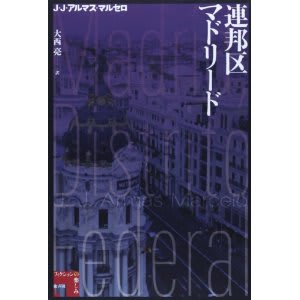
『連邦区マドリード』 J.J.アルマス・マルセロ ☆☆☆☆☆
これも5月に代官山の蔦屋書店で買ってきた中の一冊。店頭で見かけてためしに買ってみたのだが、これが大当たり。こんな素晴らしい作家がいたのかと驚いた。著者のマルセロ氏はスペイン語圏の作家で、出身はカナリア諸島。ラテンアメリカ文学にも精通しているそうだが、この『連邦区マドリード』もとてもラテンアメリカ文学的な感触を持っている。
第一の特徴は、このマニエリスティックで、饒舌で、思いがけない比喩に満ちた幻惑的な文体。なんとなくガルシア・マルケスやフエンテスを思わせるところがあるが、決してエピゴーネンではない強い個性がある。それからエピソードの繰り返し、時系列のシャッフル、「信頼できない語り手」などの手法が全面的に導入され、一人称の回想形式を最大限に生かしたとめどもない逸脱が常態となっている。その結果、スティーヴ・エリクソンに勝るとも劣らない妄想感炸裂の世界観が、砂漠の空に広がる蜃気楼のように壮麗に浮かび上がってくる。それは国際都市マドリードを舞台にし、映画や抽象美術など現代的な題材を扱い、スティーヴ・マックイーンやポール・ボウルズなど実在の人物名が平然と登場する小説でありながら、悲しみのあまり女が光に変身したり、その光を一人の少女を犠牲にすることで女に転生させたり、悪魔が雑踏に紛れ込んだりということが可能な世界なのである。
ためしにこのとりとめのない、薄明をさすらうような物語に投入されたモチーフをいくつか挙げてみると、光となってマファスカ島の浜辺を永遠にさまようアダ、彼女をマドリードに連れてきて蘇らせようとするローレンス大佐、妻と愛人が結託して犯す夫の殺人、彗星のように現れた天才的な少女ダンサー、ポロックを剽窃する画家、決して実現しない映画作りの計画、などなどである。物語冒頭のパラグラフを読むと主役はローレンス大佐のような印象を受けるが、実際は、常に映画づくりを夢見ながら口からでまかせを喋り続け、あらゆる人間を妄想の世界に取り込んでしまうミストレルこそが本書の主人公というべきだろう。もしくはどこにも主人公などおらず、本書はただ「私」の妄想の堂々巡りなのかも知れない。
しかしながら少なくともミストレルは、本当か嘘かはさて置き、映画作りのために病床にあるスティーヴ・マックイーンを訪ねて会見をしたり、タンジールまでポール・ボウルズに会いにいって映画音楽について会話したり、ボウルズの小説を実際に映画化したベルトリッチ監督を盗作者呼ばわりしたりする。主に映画作りの夢と挫折に関する彼の言動が、この物語の骨格をなしているのは間違いない。
また、訳者はあとがきで、本書に頻出する本物と偽者のモチーフに注目している。たしかにポロックの剽窃、ミストレルの職業であるゴーストライター、盗作、とアイデンティティをめぐるモチーフは多い。この部分の訳者の文章は本書の魅力をよく表していると思うので、引用してみよう。
「オリジナルの単なるコピーに甘んじていたはずの人間が、いつしかオリジナルを呑みこむほどの存在感を手にして動きはじめることがある。じつはこれこそ『連邦区マドリード』を支える重要な筋書きのひとつであり、分身や生まれ変わりによって結ばれた登場人物たちが織りなす不思議な人間関係は、この作品の最大の読みどころとなっている。ベトナム戦争で九死に一生を得たカバーリョ・リー・フォックスと、アメリカ南部のハイウェーで彼が轢き殺してしまうインディオ。マファスカ島の波にさらわれ、行方不明となってしまう少女と、不治の病に倒れるアナ・ルアンカ、それに、スペイン・バレエ界に彗星のごとく現れる謎の少女、トゥリア・サントメ。彼ら(彼女たち)はみな、時空を超えた運命の交錯のなかで互いに結び合わされ、時には他者の人格を呑みこもうと不気味な簒奪のゲームを繰り広げる」
途方もないエピソードが矢継ぎ早に繰り出され、虚構とも現実ともつかない黄昏の中で夢のように混ぜ合わされ、読者はその中を行く先も分からずたださまようしかないという、この読書の快感、愉悦。まるで都会を舞台にしたガルシア・マルケスだ。『空襲警報』のところで私はコニー・ウィリスの技巧を「あくまでジャンルのお作法をつきつめ、洗練したものではないだろうか」と書いたが、本書のような小説はその対極にある。逆に言うと、「登場人物がどうなるのか、この先何が起きるのか知りたい」ために小説を読むという人には、本書は向かない。そういう人は、逸脱に逸脱を重ね、何が本当で何が嘘か分からない本書のテキストに耐えがたくフラストレーションを募らせてしまうだろう。
しかし私のような読者にとっては、物語のエッセンスと詩的なイメージが凝縮され濃厚なスープとなったようなこの小説は、大傑作といっても過言ではない。ロマンと形而上学に満ちた幻覚的な世界、それが『連邦区マドリード』だ。前述のミストレルのキャラクターからも読み取っていただけると思うが、マルセロのマニエリスティックな音楽的な文章からは、ほのかなユーモアさえ漂ってくるのである。
あまりの素晴らしさに驚愕し、さっそく他の著作を探したけれども、ない。日本語訳はこれだけしか出ていない。なんということだ。他にも色々書いている人のようなので、これからどんどん訳して欲しい。
これも5月に代官山の蔦屋書店で買ってきた中の一冊。店頭で見かけてためしに買ってみたのだが、これが大当たり。こんな素晴らしい作家がいたのかと驚いた。著者のマルセロ氏はスペイン語圏の作家で、出身はカナリア諸島。ラテンアメリカ文学にも精通しているそうだが、この『連邦区マドリード』もとてもラテンアメリカ文学的な感触を持っている。
第一の特徴は、このマニエリスティックで、饒舌で、思いがけない比喩に満ちた幻惑的な文体。なんとなくガルシア・マルケスやフエンテスを思わせるところがあるが、決してエピゴーネンではない強い個性がある。それからエピソードの繰り返し、時系列のシャッフル、「信頼できない語り手」などの手法が全面的に導入され、一人称の回想形式を最大限に生かしたとめどもない逸脱が常態となっている。その結果、スティーヴ・エリクソンに勝るとも劣らない妄想感炸裂の世界観が、砂漠の空に広がる蜃気楼のように壮麗に浮かび上がってくる。それは国際都市マドリードを舞台にし、映画や抽象美術など現代的な題材を扱い、スティーヴ・マックイーンやポール・ボウルズなど実在の人物名が平然と登場する小説でありながら、悲しみのあまり女が光に変身したり、その光を一人の少女を犠牲にすることで女に転生させたり、悪魔が雑踏に紛れ込んだりということが可能な世界なのである。
ためしにこのとりとめのない、薄明をさすらうような物語に投入されたモチーフをいくつか挙げてみると、光となってマファスカ島の浜辺を永遠にさまようアダ、彼女をマドリードに連れてきて蘇らせようとするローレンス大佐、妻と愛人が結託して犯す夫の殺人、彗星のように現れた天才的な少女ダンサー、ポロックを剽窃する画家、決して実現しない映画作りの計画、などなどである。物語冒頭のパラグラフを読むと主役はローレンス大佐のような印象を受けるが、実際は、常に映画づくりを夢見ながら口からでまかせを喋り続け、あらゆる人間を妄想の世界に取り込んでしまうミストレルこそが本書の主人公というべきだろう。もしくはどこにも主人公などおらず、本書はただ「私」の妄想の堂々巡りなのかも知れない。
しかしながら少なくともミストレルは、本当か嘘かはさて置き、映画作りのために病床にあるスティーヴ・マックイーンを訪ねて会見をしたり、タンジールまでポール・ボウルズに会いにいって映画音楽について会話したり、ボウルズの小説を実際に映画化したベルトリッチ監督を盗作者呼ばわりしたりする。主に映画作りの夢と挫折に関する彼の言動が、この物語の骨格をなしているのは間違いない。
また、訳者はあとがきで、本書に頻出する本物と偽者のモチーフに注目している。たしかにポロックの剽窃、ミストレルの職業であるゴーストライター、盗作、とアイデンティティをめぐるモチーフは多い。この部分の訳者の文章は本書の魅力をよく表していると思うので、引用してみよう。
「オリジナルの単なるコピーに甘んじていたはずの人間が、いつしかオリジナルを呑みこむほどの存在感を手にして動きはじめることがある。じつはこれこそ『連邦区マドリード』を支える重要な筋書きのひとつであり、分身や生まれ変わりによって結ばれた登場人物たちが織りなす不思議な人間関係は、この作品の最大の読みどころとなっている。ベトナム戦争で九死に一生を得たカバーリョ・リー・フォックスと、アメリカ南部のハイウェーで彼が轢き殺してしまうインディオ。マファスカ島の波にさらわれ、行方不明となってしまう少女と、不治の病に倒れるアナ・ルアンカ、それに、スペイン・バレエ界に彗星のごとく現れる謎の少女、トゥリア・サントメ。彼ら(彼女たち)はみな、時空を超えた運命の交錯のなかで互いに結び合わされ、時には他者の人格を呑みこもうと不気味な簒奪のゲームを繰り広げる」
途方もないエピソードが矢継ぎ早に繰り出され、虚構とも現実ともつかない黄昏の中で夢のように混ぜ合わされ、読者はその中を行く先も分からずたださまようしかないという、この読書の快感、愉悦。まるで都会を舞台にしたガルシア・マルケスだ。『空襲警報』のところで私はコニー・ウィリスの技巧を「あくまでジャンルのお作法をつきつめ、洗練したものではないだろうか」と書いたが、本書のような小説はその対極にある。逆に言うと、「登場人物がどうなるのか、この先何が起きるのか知りたい」ために小説を読むという人には、本書は向かない。そういう人は、逸脱に逸脱を重ね、何が本当で何が嘘か分からない本書のテキストに耐えがたくフラストレーションを募らせてしまうだろう。
しかし私のような読者にとっては、物語のエッセンスと詩的なイメージが凝縮され濃厚なスープとなったようなこの小説は、大傑作といっても過言ではない。ロマンと形而上学に満ちた幻覚的な世界、それが『連邦区マドリード』だ。前述のミストレルのキャラクターからも読み取っていただけると思うが、マルセロのマニエリスティックな音楽的な文章からは、ほのかなユーモアさえ漂ってくるのである。
あまりの素晴らしさに驚愕し、さっそく他の著作を探したけれども、ない。日本語訳はこれだけしか出ていない。なんということだ。他にも色々書いている人のようなので、これからどんどん訳して欲しい。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます