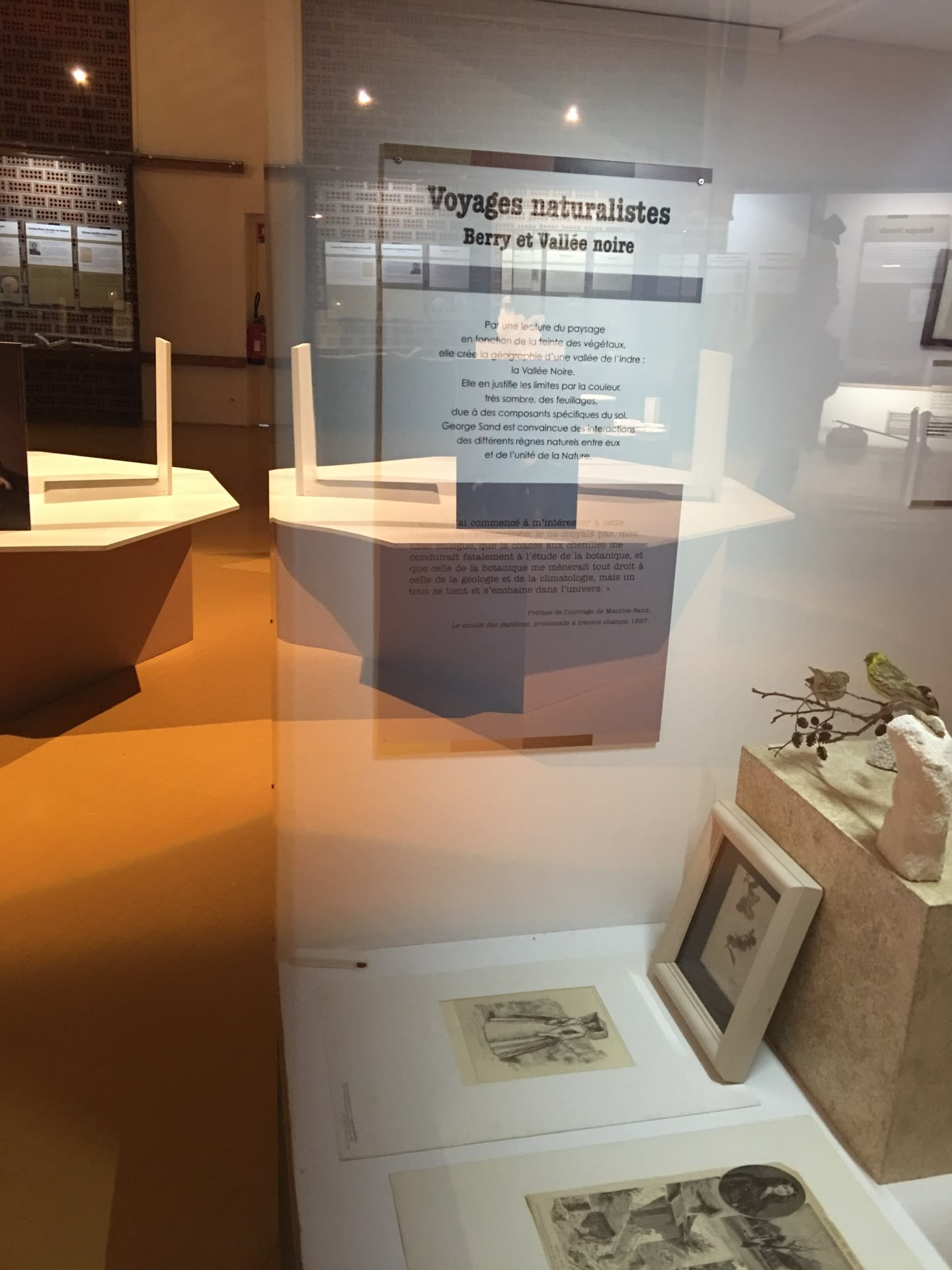Colloque « George Sand et les sciences de la vie et de la Terre »,
20-22 octobre 2016.
Haruko Nishio :
L'âme ou la science? ce que représente le choix de la reine dans La
Coupe de George Sand
L'âme ou la science? Cette question n'est pas sans rapport avec le
phénomène intellectuel de son époque: la montée du scientisme. Le XIXe siècle,
qui s'ouvre avec les Rapports du physique et du moral de Cabanis, est en effet un
siècle où la question de l'âme et du corps se pose avec acuité. En 1834, en
supprimant l'ancienne expression "philosophe scientifique" et en mettant au
monde le néologisme "scientiste", qui signifiait à la fois "philosophe"
et "celui qui faisait des recherches scientifiques", l'Association anglaise
d'avancement de la science a permis à l'idéologie du scientisme de se répandre
et de régner dans le monde intellectuel. Ainsi, en France aussi, sont apparus de
nombreux intellectuels qui soutenaient fortement le scientisme. Entre 1825 et
1840 les oeuvres complètes de Platon ont paru, traduites du grec en français
par Victor Cousin. En mai 1868, Paul Janet admire les deux études d'Alfred
Fouillée portant sur Platon et Socrate qui sont dirigées contre le scientisme et
couronnées par l'Académie des Sciences morales et politiques. Ainsi, à cette
époque-là, recourait-on à Platon pour lutter contre le scientisme.
Au sein de ce courant d'idées, quelle position George Sand a-t-elle
prise? Pour trouver la réponse à cette question, nous allons examiner en
premier lieu l’image ou la réminiscence de Platon qui apparaissent dans l'oeuvre
sandienne : l'Histoire du rêveur dans laquelle le Mythe de l'Androgyne est
représenté sur la scène où le personnage principal, Amédée, voit la moitié de
son corps sur la lave au moment où l'Etna entre en éruption volcanique. Ainsi,
sur la scène, se profile le mythe de l'Androgyne du Banquet de Platon que G.
Sand a lu plus tard, en 1835.
En deuxième lieu, notre approche vise à examiner ce qu'était la
métempsychose pour la romancière; dans La Coupe dont elle a fini la rédaction
2
en 1865, qu'elle a lu à Manceau alors à l'article de la mort, elle aborde la question
de l'âme et de la science. Elle y montre, nous semble-t-il, son attitude en
décrivant le monde des fées comme un monde “matérialiste” dans lequel les
fées ne mourront jamais tant que la planète continuera à exister. Toujours sans
quitter La Coupe, notre cible d'analyse, nous chercherons à mettre ce thème au
clair en tenant compte de la différence entre la métaphore et la métempsychose
dans certaines autres oeuvres comme Le Chien et la fleur sacrée, Ce que disent les
fleurs, Histoire du véritable Gribouille. Dans les Contes d'une grand-mère, Sand énonce
sa foi en la métempsychose ou la réincarnation, doctrine selon laquelle l'âme se
réincarne dans un autre corps, humain, animal ou végétal, théorie familière à
ceux qui, comme elle, avaient lu L'Encyclopédie nouvelle de Pierre Leroux et Jean
Raynaud.
En troisième lieu, nous nous pencherons sur l'aspect didactique du
roman. Sand, attentive aux problèmes sociaux de son époque, est, de ce point
de vue, à la fois très réaliste et scientifique. Elle lit De l'origine des espèces au moyen
de la sélection naturelle de Darwin et en recommande la lecture à son fils. Elle
partage les idées darwiniennes puisque, dans Promenades autour d'un village, elle
exprime ses vues philosophiques sur l'équilibre naturel et illustre par un exemple
précis la capacité des animaux de s'adapter à leur environnement. Dans Lettres
d'un voyageur à propos de la botanique, elle n'oublie pas d'insister sur le fait que "la
théorie de Darwin (...) ne doit pas conclure à la destruction systématique de tout
ce qui n'est pas l'ouvrage de l'homme. L'interpréter ainsi diminuerait son
importance et dénaturerait son but". La reine des fées de La Coupe représente
cette pensée écologique sandienne. Désireuse de conquérir une âme éternelle,
la reine choisit finalement de boire la coupe de la mort comme Socrate qui a
pris de la ciguë, de renoncer à son immortalité terrestre afin de trouver, par son
âme, la véritable immortalité. Elle laisse son testament à Hermann, prince d'un
pays d'êtres humains qui vit au royaume des fées : "par la sagesse, il (l'homme)
détruira l'homicide; par la science, il repoussera la maladie." La réflexion de la
reine au seuil de la mort s'étend jusqu'à l'avenir de l'homme; elle croit au progrès
humain par la sagesse et la science, elle pense aux générations futures. Ne
devrait-on pas voir dans cette façon de penser la volonté tenace de l'auteure
3
d'associer, par un tour de force magique, deux tendances totalement opposées
qu'il semble impossible de lier ?
Notre communication a donc pour objectif de tenter d’éclairer le parcours des
idées du progrès de G. Sand à travers La Coupe et ses autres fictions.
Haruko Nishio est Chargée de cours à l'Université d’Atomi, Japon
Bibliographie :
- George Sand, La Coupe, Paris, Calmann Lévy, 1876.
- George Sand, Nouvelles Lettres d’un voyageur, Paris, C.Lévy,1877.
- George Sand, Contes d’une grand-mère, Tome II, Grenoble, Glénat,
1995.
- George Sand, Promenades autour d'un village, Paris, Michel Lévy Frères,
1866.
- George Sand, “George Sand, Lettres d’un voyageur à propos de
botanique” La Revue des Deux Mondes, 1er juin 1868.
- George Sand, Œuvres autobiographiques, réunies et éditées par Georges
Lubin, 2 tomes, Paris, Gallimard, 1970,1971.
- George Sand, Correspondance, éditées par Georges Lubin, Paris,
Classiques Garnier, t.III, t.IV, t.V, t.XX, t.XXI, t.XXIV, 1964-1991
- Platon, Le Banquet, Paris, Les Belles Lettres, 2010.
- Platon, Phedon: Dialogues, Paris, Hachette, 2013.
- Alexandre Koyré, Introduction à la lecture de Platon, Paris, NRF
Gallimard, 2004.
- Luc Brisson et Francesco Fronterotta (dir.), Lire Platon, Paris, PUF,
coll. « Quadrige », 2006.
- Paul Janet, “Le spiritualisme français au XIXe siècle.”, in Revue des
Deux Mondes, 15 mai 1868.
- Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Histoire générale et particulière des
anomalies de l’organisation chez l’homme et les animaux, J.B.Baillière, 1832-
1837.
- Léon Szyfman, Jean-Baptiste Lamarck et son époque, préface de PierreP.
Grassé, Paris, Masson, 1982.
- Jean Reynaud, Terre et Ciel, Paris, Furne Éditeur, 1854.
- François Joseph Picavet, Les Idéologues, essai sur l’Histoire des idées et des
théories scientifiques, philosophique, religieuses, etc. en France depuis 1789,
Paris, Félix Alcan, Éditeur, 1891.
- Charles Darwin, Sur l’Origine des espèces, traduction de Thierry
4
Hoquet, Paris, Paris, Éditions du Seuil, 2013. (Il s'agit de la
traduction française complète de la première édition (1859) de
l’ouvrage.)
- Michèle Hecquet, Christine Planté (dir.), Lectures de Consuelo, Lyon,
PUL, 2004.
- Simone Bernard-Griffiths, Marie-Cécile Levet (dir.), Fleurs et jardins
dans l'oeuvre de George Sand : Actes du colloque international organisé du 4 au
7 février 2004, Clermont-Ferrand, Pu Blaise Pascal, 2007.
- Pascale Auraix-Jonchière, Simone Bernard-Griffiths, La marginalité
dans l'oeuvre de George Sand, Clermont-Ferrand, PUBP, 2012.
- Anna Szabo, George Sand. Entrées d’une Œuvre, PU de Debrecen,
2010.
- Isabelle Naginski, George Sand L’écriture ou la vie, Paris, Honoré
Champion, 1999.
- Philippe Régnier(dir.), Études saint-simoniennes, Lyon, Presses
universitaires de Lyon, 2002.
- Pierre Bourdieu, La Domination masculine, Éditions du Seuil, 1998.
- Bruno Viard, Anthropologie de Pierre Leroux, Editions Le Bord de
l'eau, 2007.
- Barbara Johnson, Gender and Poetry : Charles Baudelaire and Marceline
Desbordes-Valmore, eds. Joan de Jean and Nancy K. Miller, Baltimore,
Johns Hopkins University Press, 1991.
- Annie Camenisch, “Une croyante spiritualiste : George Sand”, in
Les Amis de George Sand, no.22, 2000.
- Juliette Azoulai, « L’âme et le corps chez Flaubert : une ontologie
simple », Flaubert [En ligne], Résumés de thèses, mis en ligne le 16
février 2013, consulté le 22 octobre 2015. URL :
http://flaubert.revues.org/1854.