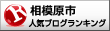2018.3.25訪問。東急中目黒駅から目黒川の桜を川下に向かって追いかけた。目黒新橋で目黒通りの坂を南方面へ上がる。山手通りと目黒通りの交差点の向こうに神社が見えた。ここから撮影したのがトップ画像です。
見頃の桜を追いかけるのを止め、立ち寄ったのは最近ハマってる巨木探訪のため。大鳥神社さんの大アカガシ見学をしたいっ。
山手通りの交差点で信号待ち。道向こうの大鳥神社の境内はこじんまり。それ自体は地価の高い都内の神社仏閣ではよくあること。でもさ、巨木は遠くからでも所在がすぐわかるんですよ。どこにあるのか?となるのは、巨木が沢山あって、どれが目的の木かわからない場合。む〜ン??大鳥神社さんには当てはまらないんだけどな〜?
1月に図書館で借りた『巨樹・巨木』の本に掲載されてた写真を境内で見比べる。

これか?右後ろの特徴的にくねってる幹が同じ。
『巨樹・巨木』の本によりますと大鳥神社の大アカガシ
樹高:16メートル 幹周り1、7メートル
樹種:アカガシ 樹齢:不明
都指定天然記念物。 大鳥神社の境内にある。根元付近は周囲より30センチほど高く、まわりは石で囲まれている。大鳥神社は目黒区最古の神社で、806年(大同1)に和泉国の大鳥の神を勧請したといわれている。目黒駅から徒歩10分」とあります。

見上げて幹を撮影。ごつごつとした木肌が特徴的。

根元。周りは石で囲まれてるから、根元が撮影しやすい。
感動してたらば、ダンナに呼ばれた。何かしら〜??
ダンナ「読んでみて」

大鳥神社の大アカガシ 東京都指定天然記念物
指定:昭和38年3月19日
指定解除:平成24年3月21日
大鳥神社境内に生育していたオオアカガシは、基本種のアカガシに比べ非常に大きく。薄い葉を繁らせ、また、雄花穂の花軸はアカガシの変種とみなされました。新変種命名の基準となった本樹は。学術上貴重な樹木として、昭和38年に東京都の天然記念物に指定されました。本樹の枝葉は、現在でもオオアカガシのタイプ教本として、国立科学博物館筑波実験植物園に保管されています。
指定時に樹高約16メートル、幹周り1、6メートルあった本樹は、生育環境の変化等により昭和50年代始めころから樹勢の衰退がはじまり、数回にわたる樹勢回復事業も実施されましたが、平成14年枯死が確認されました。また、後継育成のため挿し木による増殖も試みましたが、成功せず、平成24年に指定解除となりました。
ここに説明板を設置し、都内でも学術上貴重な名木が存在したことを後世に伝えるものです。
平成24年3月 東京都教育委員会」
ということは!?撮影した樹は目的の樹ではない!?天然記念物だった大アカガシの子孫でもない??
ならば、本に掲載されてる画像は何なの?
あ!あれか?「指名手配犯の写真を取り違えました。ごめんなさい」って事か?そりゃないよ〜。見頃の桜よりこっちを優先したのに〜。ざんねん〜っ!
境内の石のベンチで凹む。悲しく思いつつ大アカガシのコピーを眺めていたら、大アカガシの画像のしたに「2004、3、17」とあった。これってさ、撮影したのが2004年という事だよね?
今が2018年で平成30年だから、2004年は平成16年です。
大アカガシが枯死したのが平成14年。天然記念物指定解除が平成24年。
つまり、撮影時には既に目的の大アカガシは枯死してた。ということは、やっぱり本に掲載されてる写真が間違ってる。マジか〜。改めて凹む〜。
ということで、巨樹・古木探訪→神社探訪へ目的変更です。

説明板発見:大鳥神社
この神社は、ヤマトタケルの東征にゆかりがあるといわれるこの地に、大同元年(806)創建された区内最古の神社です。江戸地図として古いものとされる「長禄江戸図」に書かれている古江戸9社の一つで、目黒村の総鎮守でもありました。祭神はヤマトタケルを主神とし国常立尊(国開きの神様)と弟橘媛命(ヤマトタケルのお妃さま)を合祀しています。
毎年11月に開かれる酉の市は、東京では古いものの一つといわれており、現在も都内では有数の賑わいをみせています。この市のいわれは日本書紀に「10月己酉にヤマトタケルを遣わして、熊襲を撃つ」とあり、尊の出発日が酉の日であったことから、おこったと伝えられています。
毎年9月の例大祭には、目黒通りに大小30余基の町みこしが勢ぞろいします。それとともに社殿では「太々神楽・剣の舞」が奉納されます。11月の酉の市には、「太々神楽・熊手の舞」が神前で舞われます。
境内には、東京都の天然記念物に指定された「オオアカガシ」の老木や三猿だけの延宝塔、元禄時代(1688−1703)や宝永年間(1704−1710)の屋根付庚申塔など5基の石造物もあります。また、俗に切支丹燈籠といわれる「織部式燈籠」や、天保6年(1835)の酉の市に神楽を奉納した記念碑などもあります」
 先ほど紹介した大鳥神社のオオアカガシの石柱と説明板の手前にあります。
先ほど紹介した大鳥神社のオオアカガシの石柱と説明板の手前にあります。
説明板発見:切支丹灯籠 下目黒の大鳥神社所蔵で、昭和38年、守屋図書館に開設された郷土資料室に出品公開されて以来、中庭で展示していたものです。
もとは千代ヶ崎(現在の東京都教職員研修センター付近)の大村邸内にあり、かつてこの地にあった肥前島原藩主松平主殿守の下屋敷にまつられ、密かに信仰されていたものと伝えられています。
竿石の下部に刻まれた像には足の表現がなく、イエス像を仏像形式に偽装した珍しい型の切支丹灯籠で、キリシタンへの弾圧と迫害が厳しくなった寛永・正保・慶安の頃から江戸中期にかけて作られたものと考えられます」
頭の中で島原の乱(寛永14−15年)を連想した。切支丹灯籠は思いの外歴史物件でした。
さてと?うっかり後回しにしてた参拝をする。
なんか、本殿の装飾が変わってる?

これは何かしら?鳥?鳳凰?
ハッ!ここは大鳥神社さんでした。鳥の装飾があちこちにあっても不思議じゃないよね。

最後の絵馬を確認。「右のヤツガシラはヤマトタケルの八族平定を表し、左のぶどうの葉は、従者の眼を治したといわれる」絵馬はやっぱり興味深い。だから絵馬チェックをしてしまう。
見頃の桜を追いかけるのを止め、立ち寄ったのは最近ハマってる巨木探訪のため。大鳥神社さんの大アカガシ見学をしたいっ。
山手通りの交差点で信号待ち。道向こうの大鳥神社の境内はこじんまり。それ自体は地価の高い都内の神社仏閣ではよくあること。でもさ、巨木は遠くからでも所在がすぐわかるんですよ。どこにあるのか?となるのは、巨木が沢山あって、どれが目的の木かわからない場合。む〜ン??大鳥神社さんには当てはまらないんだけどな〜?
1月に図書館で借りた『巨樹・巨木』の本に掲載されてた写真を境内で見比べる。

これか?右後ろの特徴的にくねってる幹が同じ。
『巨樹・巨木』の本によりますと大鳥神社の大アカガシ
樹高:16メートル 幹周り1、7メートル
樹種:アカガシ 樹齢:不明
都指定天然記念物。 大鳥神社の境内にある。根元付近は周囲より30センチほど高く、まわりは石で囲まれている。大鳥神社は目黒区最古の神社で、806年(大同1)に和泉国の大鳥の神を勧請したといわれている。目黒駅から徒歩10分」とあります。

見上げて幹を撮影。ごつごつとした木肌が特徴的。

根元。周りは石で囲まれてるから、根元が撮影しやすい。
感動してたらば、ダンナに呼ばれた。何かしら〜??
ダンナ「読んでみて」

大鳥神社の大アカガシ 東京都指定天然記念物
指定:昭和38年3月19日
指定解除:平成24年3月21日
大鳥神社境内に生育していたオオアカガシは、基本種のアカガシに比べ非常に大きく。薄い葉を繁らせ、また、雄花穂の花軸はアカガシの変種とみなされました。新変種命名の基準となった本樹は。学術上貴重な樹木として、昭和38年に東京都の天然記念物に指定されました。本樹の枝葉は、現在でもオオアカガシのタイプ教本として、国立科学博物館筑波実験植物園に保管されています。
指定時に樹高約16メートル、幹周り1、6メートルあった本樹は、生育環境の変化等により昭和50年代始めころから樹勢の衰退がはじまり、数回にわたる樹勢回復事業も実施されましたが、平成14年枯死が確認されました。また、後継育成のため挿し木による増殖も試みましたが、成功せず、平成24年に指定解除となりました。
ここに説明板を設置し、都内でも学術上貴重な名木が存在したことを後世に伝えるものです。
平成24年3月 東京都教育委員会」
ということは!?撮影した樹は目的の樹ではない!?天然記念物だった大アカガシの子孫でもない??
ならば、本に掲載されてる画像は何なの?
あ!あれか?「指名手配犯の写真を取り違えました。ごめんなさい」って事か?そりゃないよ〜。見頃の桜よりこっちを優先したのに〜。ざんねん〜っ!
境内の石のベンチで凹む。悲しく思いつつ大アカガシのコピーを眺めていたら、大アカガシの画像のしたに「2004、3、17」とあった。これってさ、撮影したのが2004年という事だよね?
今が2018年で平成30年だから、2004年は平成16年です。
大アカガシが枯死したのが平成14年。天然記念物指定解除が平成24年。
つまり、撮影時には既に目的の大アカガシは枯死してた。ということは、やっぱり本に掲載されてる写真が間違ってる。マジか〜。改めて凹む〜。
ということで、巨樹・古木探訪→神社探訪へ目的変更です。

説明板発見:大鳥神社
この神社は、ヤマトタケルの東征にゆかりがあるといわれるこの地に、大同元年(806)創建された区内最古の神社です。江戸地図として古いものとされる「長禄江戸図」に書かれている古江戸9社の一つで、目黒村の総鎮守でもありました。祭神はヤマトタケルを主神とし国常立尊(国開きの神様)と弟橘媛命(ヤマトタケルのお妃さま)を合祀しています。
毎年11月に開かれる酉の市は、東京では古いものの一つといわれており、現在も都内では有数の賑わいをみせています。この市のいわれは日本書紀に「10月己酉にヤマトタケルを遣わして、熊襲を撃つ」とあり、尊の出発日が酉の日であったことから、おこったと伝えられています。
毎年9月の例大祭には、目黒通りに大小30余基の町みこしが勢ぞろいします。それとともに社殿では「太々神楽・剣の舞」が奉納されます。11月の酉の市には、「太々神楽・熊手の舞」が神前で舞われます。
境内には、東京都の天然記念物に指定された「オオアカガシ」の老木や三猿だけの延宝塔、元禄時代(1688−1703)や宝永年間(1704−1710)の屋根付庚申塔など5基の石造物もあります。また、俗に切支丹燈籠といわれる「織部式燈籠」や、天保6年(1835)の酉の市に神楽を奉納した記念碑などもあります」
 先ほど紹介した大鳥神社のオオアカガシの石柱と説明板の手前にあります。
先ほど紹介した大鳥神社のオオアカガシの石柱と説明板の手前にあります。説明板発見:切支丹灯籠 下目黒の大鳥神社所蔵で、昭和38年、守屋図書館に開設された郷土資料室に出品公開されて以来、中庭で展示していたものです。
もとは千代ヶ崎(現在の東京都教職員研修センター付近)の大村邸内にあり、かつてこの地にあった肥前島原藩主松平主殿守の下屋敷にまつられ、密かに信仰されていたものと伝えられています。
竿石の下部に刻まれた像には足の表現がなく、イエス像を仏像形式に偽装した珍しい型の切支丹灯籠で、キリシタンへの弾圧と迫害が厳しくなった寛永・正保・慶安の頃から江戸中期にかけて作られたものと考えられます」
頭の中で島原の乱(寛永14−15年)を連想した。切支丹灯籠は思いの外歴史物件でした。
さてと?うっかり後回しにしてた参拝をする。
なんか、本殿の装飾が変わってる?

これは何かしら?鳥?鳳凰?
ハッ!ここは大鳥神社さんでした。鳥の装飾があちこちにあっても不思議じゃないよね。

最後の絵馬を確認。「右のヤツガシラはヤマトタケルの八族平定を表し、左のぶどうの葉は、従者の眼を治したといわれる」絵馬はやっぱり興味深い。だから絵馬チェックをしてしまう。