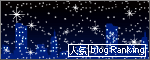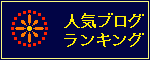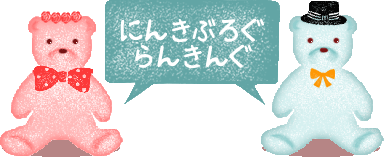せこすぎる都知事の辞職だの、IS支持者による同性愛者が集まるクラブでの銃乱射だの、ニュースを見ているといやになってきます。
また、職場では、外部資金獲得の算段だの、つまらぬ資料作成だの、くだらなすぎていやになります。
そんなとき、私の頭はどういうわけか、世の中で不思議と言われる現象を思い浮かべてしまいます。
不思議なことはたくさんあり、というか私がここにこうして存在していることが一番の不思議ですが、電卓をたたきながら、頭は宇宙の不思議に飛んでいました。
宇宙人の存在は間違いないところです。
宇宙に飛び立った我々地球人こそ、他の星の住民から見れば宇宙人であるに違いないからです。
この広い宇宙には無数の星があり、地球にしか生命が存在しないと考えるのは無理があるでしょう。
しかし、宇宙はあまりにも広いので、知的生命が他に存在していても、地球人と接触できるほどの能力を持っているかどうかはわかりません。
また、地球人が誕生し、しかも文明を築いたのは宇宙の歴史からみればごく最近のことなので、異星人の文明はすでに滅んでしまっているかもしれず、逆にまだ単細胞生物段階なのかもしれません。
時代が一致しないと異星人と接触することは不可能です。
また、人間の五感で感知できないような形状の生物であった場合、接触していても気づきません。
地球外知的生命との接触は、限りなく不可能のような気がしてきます。
SFでは、異星人が地球に攻めて来たり、逆に地球人を導いたり、ロマンティックな物語があまた作られてきました。
ことほどさように、私たち地球人は異星人との接触を求めています。
しかし、もしかしたら、異星人はもっとナイーブで、他の星との交流をあえて避けている可能性もあります。
昔から、じつは米国政府などの高官は異星人と接触している、という噂が絶えません。
何らかの取引をしたとか、あるいは地球にやってきた異星人を捕まえた、とか。
私はキリスト教やイスラム教など、ヤハウェの3宗教に詳しくありませんからよく分かりませんが、神様が宇宙を創造したとするなら、異星人も創造したことになり、異星人との邂逅はかの宗教関係者には都合が悪いような気がします。
逆に、神様とは人間よりもはるかに進んだ文明を持つ異星人だとする説もあり、甚だしきに至っては、異星人が実験場として地球を作った、という珍説すらあるようです。
分からないことに対しては、色々な想像が浮かぶようです。
ガリレオが地動説を唱えてローマ教皇庁から異端の罪で有罪判決をくらってからまだ380年ちょっと。
わずか380年前までは、地球が宇宙の中心に存在し、その周りを星々が回っていたわけです。
また、ライト兄弟が初めて空を飛んでからわずかに113年しか経っていません。
その後66年後には人類は月に降り立っています。
科学の常識も、科学技術も、日進月歩どころか秒進分歩の様相を呈しています。
それを思えば、100年後には、異星人と握手を交わしているかもしれませんね。
そんな夢想にひたることは、楽しいものです。
あ、でもいけません。
電卓を叩く指がお留守になってしまいます。
今日も今日とてつまらぬ仕事におわれ、時がながれてしまいました。
私は働きたくない病とでもいうべき精神状態のまま、毎日働いています。
しかし不思議なもので、面倒な仕事は早く片付けて楽になりたいという思いと、やり直しはしたくないという考えから、早くて精確に仕事をこなし、しかも残業をしないので、あいつは暇だと思われ、ますます仕事が増えるという悪循環に陥っています。
日々思うのは、宝くじが大きく当たって退職し、旨い物を食ったり旅行をしたり芝居を観たりして、遊んで暮らしたいという、煩悩にまみれたことどもです。
大乗仏教では、すべての人に仏性が有り、誰もが悟りを開く可能性を持っていると説きます。
しかし自分の心をのぞいてみても、仏性のぶの字も見当たりません。
およそ成仏など考えられないことです。
同じ仏教でも小乗仏教はすべての人に仏性があるとは説きません。
どこの宗派かは忘れましたが、誰にでも仏性があり、成仏できる可能性があると説くのは、衆生が絶望しないようにするための方便にすぎない、と説いていて、なかなか鋭いと思ったことがあります。
まぁ、冷静に考えて、誰にでも仏性が有るのだと仮定しても、大抵の人は悟りなど開けないのですから、仏性が無いのと一緒のような気がします。
私は寺で生まれ育ち、環境から言って仏教の影響を強く受けているのだろうとは思います。
門前の小僧習わぬ経を読む、と言いますしね。
しかし自覚的には、私は仏教信者とは言い難いですし(もちろん神道信者ではありませんが)、多くの日本人がそうであるように、無宗教と言ってよいのだろうと思います。
強いて言うなら、石原慎太郎が自らを石原教信者と言い放ったように、私もまた、仏教やら神道やら文学やらの美味しいとこ取りをした、とびお教信者としか言い様がありません。
多分大方の日本人もそんな感じじゃないでしょうかねぇ。
しかしとびお教には決定的な欠陥があります。
衆生はおろか、私一人すら救うことが出来ないのです。
衆生を導くべき教祖が迷いに迷っているのではどうしようもありません。
いっそ過激な思想を隠し持った新興宗教に、嘘でもいいから入信して、洗脳されてしまえば楽かもしれませんねぇ。
洗脳された人々というのは、気持ち悪いほど幸せそうですから。
今日は世界の歴史のなかでも、特に重要な日です。
1944年のこの日、連合国軍が海を渡ってナチス・ドイツ支配下のフランス、ノルマンディー地方への侵攻を開始した、ノルマンディー上陸作戦の火蓋が切って落とされた日、通称、Dデイです。
史上最大の作戦とも言われるこの戦い、ナチの崩壊の始まりを告げる戦闘でもありました。
これによって、ナチは対ソビエトと対英米という二つの長大な戦線で戦うことになり、ついにはベルリンの総統官邸地下壕が落ちるまで、破滅への道を突き進んだのです。
わが国はソビエトが突如として参戦するに及び、ナチの崩壊を知る人々は2正面作戦は不可能と判断したのでしょうか、本土決戦を避けて降伏するという道を選びました。
これには連合国も拍子抜けしたことでしょう。
わが国の狂信的な軍国主義者は、冷静な判断など出来ずに、ナチのように本土決戦を選び、宮城が落ちるまで戦い続けるだろうと思い込み、ために戦後の占領政策は、わが国が完全に崩壊した場合のみしか、シュミレーションしておらず、アジアなどに広大な領土を維持し、国家としての機能が生きているままの状態での占領を考えていなかったと聞き及びます。
当初連合国が直接統治する予定だったところ、大日本帝國の統治機構に乗っかったほうが楽だと思ったのか、大日本帝國政府を残し、間接的に統治するという道を選びました。
このことは、わが国の国民の最低限のプライドを維持するに大いに役立ったものと思われます。
ノルマンディ上陸作戦は映画などでたびたび取り上げられ、名作「史上最大の作戦」を生みました。
 |
史上最大の作戦 [DVD] |
| ジョン・ウェイン,ヘンリー・フォンダ,クルト・ユルゲンス,ウェルナー・ヒンツ,ロバート・ミッチャム | |
| 20世紀フォックス・ホーム・エンターテイメント・ジャパン |
それはそれは過酷で大規模な戦場となったことでしょう。
ドイツは死にもの狂いで防戦に努め、連合国軍はノルマンディー地方を落とすのに2ヶ月を要したそうです。
恒久平和を願いながら、人は争いの物語を好むものです。
例えばNHK大河ドラマ。
戦国時代や源平の合戦、幕末の動乱など、争いの時代を背景にしたものが圧倒的多数を占めます。
また、サラリーマンのドラマでも、「華麗なる一族」など、権力闘争を描いた物語がたくさん製作されています。
 |
華麗なる一族 [DVD] |
| 山崎豊子,山田信夫 | |
| 東宝 |
争いはいけないと言いながら、人はなぜ好んで争いの物語に接しようとするのでしょう。
結局のところ、人は争うのが好きなのでしょうか?
もし人間の本能が、人間同士の争いを求めるのだとしたら、恒久平和など、ちゃんちゃら可笑しい絵空事ということになってしまうような気がします。
平和を戦いとる、とか、平和を勝ち取る、などという物言いは、そもそも矛盾しているように思いますが、平和を求める左がかった運動などでは、よく聞く言葉です。
平和は、戦い取るものではありますまい。
しかし、人が本能の部分で闘争を好むのだとしたら、そうであるからこそ、恒久平和を目指す運動は尊いのだろうとも思います。
つまり、理性でもって、難事業に取り組むということですから。
時代の要請が、人同士の争いを克服せしめることは、おそらく無いでしょう。
人は人たることを自ら止めて、一段上の、神の領域にまで迫る気迫をもって、超人を目指すべきかもしれません。(ニーチェの「超人」とは関係ありません)
その時こそ、人は本能を克服する端緒をつかむことができるでしょう。
それははるか遠い未来ではありましょうが、求めなければ、恒久平和など、望むべくもありません。
世の中には不思議なことがたくさんありますが、一番の不思議は、私たちがこうして生きていることでしょうね。
その不思議を思えば、幽霊が出ようが、宇宙人が飛来しようが、どうということもありますまい。
で、その不思議の謎を解こうと、様々な宗教や学問が発達してきたわけですが、この世がどのように成り立っているかということは解明できても、なぜ存在しているかは、永遠に解明できないでしょう。
もちろん、唯一絶対神のようなものを設定すれば説明はできますが、ではその神様がなぜ存在するのかを問うたなら、たちまち答えに窮するでしょう。
結局私たちは、真っ暗闇の世界を手探りで進み、やがて死んでしまうだけの存在です。
そこに意味を見出そうとしたところで、それは空しい徒労に終わるでしょう。
うつ状態が激しいとき、主治医は今にも自殺してしまいそうな私の様子を見て、「人は生きているだけで意味があるのですよ」と諭しました。
自殺を思いとどまらせるための方便にしか過ぎないその言葉に、私は心動かされることはついにありませんでした。
しかしそれでも、人は生きることに意味を見出そうとします。
社会的成功とか、個人的幸福とか、自己実現などによって。
それは一時的に脳に快楽物質を放出させ、幸福を感じさせることでしょうが、酒の酔いや麻薬のトリップと大差ないでしょう。
それでも生きなければならない生命が、何をもって生きているのかと言えば、少なくとも私にかぎって言えば、死ぬのが怖いから、もしくは自殺する理由が無いから、としか言い様がありません。
厭世的に聞こえるかもしれませんが、私は本来享楽的な性格を色濃く持っています。
ただ、時折この世の不思議、私が存在する不思議を思うと、なんとも救いの無い思考にはまっていくのです。
デカルトは我思うゆえに我あり、と、存在をいくら疑っても、疑っている自分の存在は確かであろうと推論しています。
しかし、ビアスは悪魔の辞典で、我思うと我思う、故に我ありと我思うが正しいだろうと、あくまで本人がそう思っているに過ぎないと喝破しており、それは尤もだろうと私も思います。
 |
悪魔の辞典 (角川文庫) |
| アンブローズ・ビアス,奥田 俊介,倉本 護,猪狩 博 | |
| KADOKAWA / 角川書店 |
意識と世界の問題を追究すると、仏教の唯識や西洋の心理学など、ほとんど思考の遊びというか、思考の冒険に入らざるを得ず、それはたいそう面白い冒険ですが、物事の本質を突いたように錯覚するだけだろうと感じます。
このような思考の冒険が成立するのは、人というもの、よほどおのれの意識を信頼しているだろうからで、信頼しているものを疑うことに、面白さがあるのがその本質であって、なぜ私が存在するのかという命題の答えになることはあり得ず、そんな気になるだけです。
もし人が意識を持ち、それを理論的に考える言葉を持ったことに意味があるのだとすれば、答えの無い問いを問い続けるという不毛な冒険を続けるためだとしか思えません。
不毛な冒険を何千年でも何万年でも何億年でも続けることに意味があるのだと信じる以外、今の私たちが宗教以外に寄って立つ道は無いであろうと考えています。
日々の晩酌を楽しみに酔生夢死の享楽的な生活を続ける私ですが、時折、柄にもなく人類存在の意義を考えてみたくなるのです。
平成27年(2015年)も大晦日を迎えました。
これまでの一年一年がそうであったように、今年もまた、地獄のように長い一年でした。
よく、時があっという間に過ぎるという嘆きというか言説を耳にしますが、あれは私には理解不能です。
一年365日、ほんのわずかの楽しみはあるものの、圧倒的多数の苦しみと悪戦苦闘しながらどうにかこうにか一日をこなしているというのが私の本音です。
そしてその日月の積み重ねの末に、長い一年が終わります。
それを敷衍してみれば、おそらくは亡くなるまで、悪戦苦闘は続くのでしょうね。
そうであってみれば、死は福音なのかもしれません。
現世の苦闘から解放されるわけですから。
世の中では様々なニュースを振り返る愚行が繰り返される日でもあります。
確かに一つ一つを思い起こして見れば、多くのニュースがありました。
しかしそれは過ぎ去り、記憶の底にしまいこまれるだけです。
どんな大事件が起きたところで、人々の暮らしの基本は、食って寝て働いてという、つまらぬ日常があるに過ぎません。
私はもしかしたら、物心ついて以来、カタルシスを心の奥深くで願っているのかもしれません。
カタルシスを求める以上、悲劇的な出来事を求める他ありません。
それも空前の悲劇を。
それは詩的かつ美的でなければなりますまい。
自然災害なのか戦争のようなものなのか分かりませんが、黙示的ともいうべき悲劇にこそ、精神を浄化する作用があることは、アリストテレスの指摘を持ち出すまでもありますまい。
 |
アリストテレース詩学/ホラーティウス詩論 (岩波文庫) |
| 松本 仁助,岡 道男 | |
| 岩波書店 |
あるいはこのような精神性は幼稚なのかもしれません。
またはテロリストの美学なのかもしれません。
しかし殺人鬼が殺人により快楽を得、美を観、魂の解放を感じることを本能的にあるいは経験的に知っていて、それを続けざるを得ないのだとしたら、私の狂った魂が、黙示的ともいうべき巨大な悲劇を求めざるを得ないのは、当然のことなのかもしれません。
私は待つことと坂道を上ることが大嫌い。
もちろん階段を上がることも大嫌いです。
従って、登山が趣味なんて、マゾヒストとしか思えません。
その私が、学生の頃、山岳信仰に興味を持ち、恐山や月山、大峰山のふもとまで、バスで登れるところまで行き、登山者向けの宿に泊まって麓から霊力を得ようとしたことがあります。
平地にある寺院でも通常、「○○山××寺」のように、山を名乗るのが通例です。
インドで言う須弥山など、仏教にも山岳信仰的な要素が残っています。
役小角が始めたとされる修験道、山岳信仰と仏教、とくに密教とが融合した、不思議な宗教というか儀礼ですが、もともと山がちの国土で、我がくにびとが、恵みを与えてくれるとともに時にはひどい災厄をもたらすお山を畏れ敬ったのは謂わば当たり前とも言えるでしょう。
その昔は、サンカと呼ばれる山の民がいたそうです。
定住せず、山や山里を移動して暮らす人々で、被差別民とも盗賊とも言われ、未だに明確な定義は無いとか。
昭和30年以降、ほぼサンカは姿を消し、定住するようになったと言われます。
そういうわけで、私は登山をしたことがなく、今後もする気はありませんが、山への畏怖を抱き続けた人々の精神性には深い興味を持っています。
従って、エベレストをはじめとして、地元の人々が霊山として敬い、登ることを禁忌としてきた山に登る登山者に、不快感を抱いています。
お山はスポーツの場ではなく、多くが信仰の場なわけですから。
1970年代に、その名も「ホーリーマウンテン」というタイトルの映画が製作されました。
私の知る限り、最もカルト色の強い、性的で狂的で、すこぶる面白い映画です。
 |
ホーリー・マウンテン HDリマスター版 [DVD] |
| アレハンドロ・ホドロフスキー,ホラシオ・サリナス,ラモナ・サンダース,アリエル・ドンバール,ホアン・フェラーラ | |
| Happinet(SB)(D) |
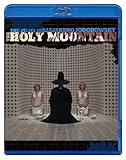 |
ホーリー・マウンテン HDリマスター版 [Blu-ray] |
| アレハンドロ・ホドロフスキー,ホラシオ・サリナス,ラモナ・サンダース,アリエル・ドンバール,ホアン・フェラーラ | |
| Happinet(SB)(D) |
しかし人によっては、その強烈さに吐き気を催すかもしれません。
9人の賢者が住むという聖山で錬金術の力を得ようとする男の物語ですが、物語がどうこうというよりも、映像の強烈さに圧倒されます。
聖山を描いてグロテスクとも言える強烈な映像が製作されなければならない所以のものは、そこにこそお山に対する人々の意識の根底があるからであるように思います。
私は生涯を平べったい関東平野の首都圏に住みながら、はるか霊山に思いを馳せる、怠け者に過ぎないのです。
そんな私に、霊山がその霊性を見せる瞬間など、到底あり得ないのでしょうねぇ。
永遠の片思いを続けなければならないようです。
水木しげる先生が93歳で逝去されました。
妖怪を題材にした漫画、戦争体験を元にした漫画、どれも印象深いものです。
私がこの人に深いシンパシーを感じるのは、かつて日本社会において実際に存在するものとされてきたこの世ならぬ存在への予感を、堂々と表明し、それを面白く描き出した点にこそあります。
第六感だか霊感だか、名前はどうでも構いませんが、私は、現在存在しないとされている何者かが、確かに在ると思っています。
それは日本に限らず、どこの社会においても、神話や怪談などで語り継がれてきたことで、それらが在るからこそ、人々はそれらの存在を近しいものと感じ続けてきたのであろうと思っています。
ただし、それらは恐怖すべき対象では無い、あるいは恐怖すべき存在はごくわずかでありましょう。
水木先生が描き出した妖怪の類も、どこかユーモラスで、人間と共生する存在とされており、おそらくはそれが実態に近いものと思われます。
また、芸術家などが感じるインスピレーションは摩訶不思議なもので、それこそまさに、この世ならぬ者との感応が生み出したものでしょう。
水木先生が示された、この世ならぬ者との親和性を、今こそ取戻し、もって人間を人間たらしめている所以のものを復活せしめねばなりません。
私が長期病気休暇を余儀なくされていた頃、精神科医からさかんに散歩を勧められました。
うつ状態にあると部屋に閉じこもってひたすら落ち込んでいくばかりでなく、急激に太って内臓の疾患にかかることも多いことがその理由のようです。
休み始めたばかりの頃はとても用もないのに外を歩き回る気になれず、寝てばかりいましたが、病状の回復とともに、医師の勧めにしたがって歩くことができるようになりました。
そこで気付いたことは、最初は嫌々でも、歩いているうちに調子が良くなって、気分も良くなるということ。
もともとスポーツをする習慣がない、運動嫌いの私であれば、運動で気分が良くなるという話を知ってはいても、実感するのは初めてのことでした。
そこで私は、肉体に閉じ込められた精神は、単に閉じ込められているのではなく、激しくその支配を受けていることを知ることになります。
もちろん、うつ病などの疾患が、体を動かせば治る、なんて、巷間ささやかれている俗説を主張する気はさらさらありません。
特に症状がひどい初期段階においては、服薬と休養が、良くなってきても服薬が重要であることは論を待ちません。
そのことを大前提に、精神障害者であれ健常者であれ、肉体の運動が及ぼす精神上の影響は大であることを、私は思い知らされたのです。
そんなことで、今ではすっかり散歩が好きになりました。
嘘か真か、臨死体験を持つ多くの人が、死に臨んで、肉体から解放された状態は、言語では表せないほどに軽やかで心地よいものであることを告白しています。
それが死の瞬間の苦痛を和らげるための一時的な脳内麻薬の放出であるのか、実際に精神が肉体から解放された快感なのかは、もちろん分かりません。
しかしそれが実際に起こるのなら、私たち人間、いや生物全体にとって、生命が存在する意味を問いかける重要な手がかりになるような気がします。
死が苦からの解放であるなら、なぜ生命はこれほど死を怖れるのでしょうか。
もちろん、これは仮定の話で、死が不明の事態であることに変わりはなく、そもそも生命が死を怖れなかったなら、生命を維持せしめることが出来なくなることは当然の話です。
しかしそれにしても、死が解放であるのなら、私たちは何をもって明日の生存に希望を持てば良いのか、という根源的な疑問を抱かずにはいられません。
そのことに本能的に気付いてしまったなら、人は自死を選ぶ他無いような気がします。
多くの自殺者が絶望の果てに死を選んだのだとしても、結果として彼らは賢明な選択をしたことになり、しかもそれは僥倖だったことになります。
以上のことは、肉体と精神についての思考の遊びに過ぎませんし、それでも私たちは生きなければならないわけですが、死を怖れるという健全な本能を維持しながらも、死が解放であると解釈することは、徒らに死に恐怖を感じずに済む、一種の処世術として、心深くに留めておきたいと思うのです。
夢でも野望でも大志でも、言葉はどれでも構いませんが、夢を諦めないで的な歌謡曲はあまたあります。
少年の頃は私も人並みにそれらの言葉に魅力を感じていましたが、年を取ると白けてくるというか、じつにどうでも良いことのように感じます。
夢や野望や大志というものは、要するにそうでありたいという自己実現欲求かと思いますが、それはまさしく執着というものです。
そう、お釈迦様が戒めた執着です。
最近では、何かにこだわることを、「こだわりの逸品」などのように、まるで一つの道に精進しているかのような使い方をしますが、本来の意味から言えば誤用です。
本来は、「~にこだわってはいけない」というように、こだわりを、一つのことに執着する悪い意味で使っていました。
いつから本来の意味が誤用に転じたのか分かりませんが、私が子供の頃にはそういう使い方はしていなかったように思います。
他にも、本来は自分には軽すぎる役目という意味の「役不足」という言葉を、自分には重すぎる役目という意味に使ったり、「不言実行」のパロディであったはずの「有言実行」という言葉が元々あった言葉であったかのように使われるようになりました。
言葉は変わっていくとはいうものの、真逆の意味で使われるのは気持ち悪いですねぇ。
夢や野望や大志という言葉に白けるようになったのは、精神の衰えもしくは怠惰と考えるべきなのかもしれませんが、自己弁護かもしれないですが、それらはもともと胡散臭い物言いなのではないかと感じています。
どんな冒険や夢を求めても、飯食って糞して眠るという人間生活の本質は変わりません。
そしてその生活を維持せしめるためには、収入を求めてつまらぬことでもやるのが生活というものだと思います。
そのつまらぬ生活のなかに人間本来の幸福があるのだろうと感じています。
長いこと、日本人の圧倒的多数は農民で、汗水たらして重労働に明け暮れ、一生を終えるというのがむしろ当たり前の生き方でした。
今はサラリーマンが多くなりましたが、その本質はお百姓さんのそれと変わりありますまい。
それを奴隷の幸せと呼ぶのは、あまりにも酷というものです。
三島由紀夫は、破滅の美学を美しく謳いあげ、ある評論家は「破滅を美とせず」と喝破しました。
浪漫主義的美学に彩られた三島由紀夫は、自らの生涯さえもおのれが信じる美の世界に昇華させましたが、破滅を美とせず、淡々と日を生きる一般庶民にこそ、生活の美を認めるべきなのかもしれません。
変わったところでは、指揮者のニコラウス・アーノンクールが、「究極の美は破滅の一歩手前にこそ宿る」と、言い放ちました。
なるほど。
破滅の美でもなく、生活者の美でもない、破滅一歩手前の美、なかなか説得力がある考えです。
いささか浪漫主義的傾向がある私にはたいへん魅力的な言説です。
破滅的美=私にとっての野望に白けながらも、生活の美を求めることに物足りなさを感じる私にとって、破滅一歩手前の美とは、なんとも甘美な香りが漂います。
少し前、新聞に地球上で人類が生存できる期間についての研究成果が公表されていました。
それによると、長くて32億5千万年、最短だと17億5千万年だそうです。
これを過ぎると、地球はホット・ゾーンと呼ばれる地帯に外れ、人類は暑くて生きられなくなるそうです。
現代の人間が生まれたと推定されるのは20万年前とのことですから、17億5千万年というのは途方もなく長い期間で、この間に何らかの理由で人類が滅んでしまう可能性は多いにあり得るでしょう。
しかしもし、人類がその叡智を結集し、17億5千万年を超えて生き延びたとしたら、私たちの遠い子孫はどうするのでしょうね。
地球に代わって居住可能な気温になるといわれている火星、あるいはその他の適切な惑星への移住を試みるのか、あるいは地球と一緒に滅ぶのか。
現代人の感覚で言うと、何が何でも生き残ろうとするとは思いますが、遠い子孫にはそのような気力が無くなっているかもしれないし、あるいは原始人のような生活に戻っているかもしれません。
地球の滅亡を描いたSF作品はあまたありますが、どれもどこか物足りないのは、人間にとってそれはあまりに遠い未来に感じられ、切実さをもって物語を作れないからかもしれません。
17億5千万年というのはあまりにも遠い未来です。
しかし、その日は必ずやってきます。
地球温暖化とかなんとか言いますが、人類のエネルギー政策によってそうなったとは、私はかけらも考えていません。
地球は全凍結していた時代もあったし、火の海だった時代もあると聞いています。
地球、あるいは太陽系全体の大きなバイオリズムを考えれば、人類が少々CO2を垂れ流したからと言って、何ほどのことも無いでしょう。
己の所業で地球全体が温暖化したなどと、自惚れるのもいい加減にしなさい。
それがいかに遠い未来であれ、少なくとも地球では人類は生きていけなくなる日が必ず来るという研究結果は、人類全体の喉元に鋭い刃を突きつけるような恐怖を感じさせます。
宗教や哲学、芸術やスポーツと言った、人類が残した素晴らしい遺産は、いずれ用をなさなくなるのでしょうか。
そのような黙示的な状況に立たされたとき、人類はその先にどんな地平を覗き見るのでしょうね。
また、安易な言い方ですが、そのような未来が必ず訪れるのだとしたら、人間同士の紛争など、いかにもみみっちいことです。
それなのに、紛争がやむことはありません。
利益という魅力的な果実を前にすると、人間はそれに心奪われ、それを手に入れることしか考えられなくなり、遠い将来を見越した宗教的・哲学的営為を放棄してしまうかの如くです。
それが人間というものだと言ってしまえばそれまでですが、何かもう一歩、人類が大きく前進するような、精神上の進化が起これば、紛争も減るかもしれません。
そのことがいかに難しいか、歴史が証明していますが、人類の歴史など宇宙全体から見ればほんの一瞬です。
これから千年、一万年と経つうちに、人類が精神上の進化を遂げる可能性なしとしません。
既成の、また新興の宗教ではなく、新たな精神上の進化を促す運動があるのなら、それに加わってみたいという欲求をもたらしたニュースではありました。
私がそう思うのだから、多くの人も感じることの多い報道だったのではないかと期待します。
人間、この世に堕ちるにあたって、生まれる場所も時代も家庭環境も選ぶことはできません(一部宗教などでは、自ら選んで生まれてくるとも言われます。過酷な環境を望むのは、そのほうが修行になるからだ、とも)。
平和な時代に、豊かな国の裕福な家庭に生れ落ちるというのはこの上ない幸運です。
広い意味で言えば、今の時代に日本に生まれるということは、それだけでまぁまぁ幸運なのではないでしょうか。
殺し合いもないし、食うに困るということも滅多にありません。
そして人は、生まれた場所や時代に縛られざるを得ません。
同じ日本に生まれるにしても、時代は大きな要素です。
大正時代に生まれていれば、太平洋戦争で兵隊にとられる可能性が高かったでしょう。
私たち日本人は、日本という呪縛から逃れることは出来ません。
気候、風土、歴史、文化、言語。
私たちはおぎゃぁと生まれた瞬間から、日本語の嵐にさらされ、日本的価値観を身に着けて成長せざるを得ません。
日本人の秩序や規律を重んじる高い倫理観は世界から評価されているようですが、同時に負の側面も身に着けてしまいます。
集団を重んじて個を軽んじることや、他人の目を気にしすぎること、宗教への無関心などなど。
そして、日本語。
学生の頃、一般教養で西洋哲学を受講した際、教員が「日本語で哲学を説明することは難しいから英語で講義したい」と言い出して、学生は一斉にブーイング。
結局日本語で講義したことがあります。
その時初めて、日本語はよほど論理的思考に向かないのだなと、思いました。
時を同じくして、中古文学概論の時間に、教授が「日本語は世界一詩歌に向いている情緒的な言語だ」と話すのを聞いて、哲学の講師と国文学の教授が、逆の方法で同じことを言うのだなと、思いました。
私たちは、通常、何か考える時には日本語で考えます。
話す時も書く時も、日本語を使用します。
それを不断に続けることにより、日本人は日本人になるのだろうと思います。
かつて川端康成がノーベル文学賞を受賞した際の講演を、「美しい日本の私」と題して行いました。
美しい日本の私。
 |
美しい日本の私 (角川ソフィア文庫) |
| 川端 康成 | |
| KADOKAWA/角川学芸出版 |
私たちには何の違和感も無い言葉ですが、これを西洋の言語に訳そうとすると、正確なニュアンスは伝わらないそうです。
強いて言えば、美しい日本国の国民であるところの私、みたいになると誰だか忘れましたが白人の日本文学研究者が言っていました。
また、英語圏の人々が概してオーバーアクションなのは、英語では微妙なニュアンスを表現できないからだ、という説を述べている学者もいました。
日本語は極めて繊細な言語ですから、細かなニュアンスもすべて言葉で言い表すことが出来るため、身振り手振りはあまり必要ない、とのことです。
英語が世界語になったのは、もちろん、大英帝国が世界を支配し、その後は米国が支配したからですが、その他に、英語は単純であり、比較的習得が楽だからというのも大きな理由の一つでしょう。
一つ言語をつかまえても、日本語は世界語の英語と大きく異なり、日常日本語だけで暮らしている人々の精神性に大きな影響を与えるであろうことは、容易に想像がつきます。
日本及び日本語の美しさにどっぷりつかって生きていければこんな幸せなことはありますまい。
内向きに生きていくのは淫靡ともいうべき快感がありますから。
私たちは日本という呪縛から逃れる術は持たないし、逃れる必要もありません。
逃れてしまったら、日本人としての誇りも失ってしまうでしょうから。
しかし、世界は狭くなりました。
世界を渡っていくには、私たちは日本の呪縛に囚われているのだということを自覚しつつ、さらにはそれを誇りながらも、それぞれの国の呪縛に囚われている人々と、共通の認識を持つべく努力を続けなければなりません。
それはこれまでも行ってきたことですが、情報革命まった只中の今、ますます日本人たるの自覚を高めつつ、世界との共通認識を求めていかなければなりますまい。
あぁ、面倒くさいですねぇ。
今朝の新聞で、文部科学省が国立大学に対し、人文社会学及び教育学系の学部・大学院を統廃合により縮小し、代わりに理系に重点を置くよう通知を出す予定だ、との報に接しました。
文部科学省所管の国立研究機関で働く者としては、来るべきものが来た、という感じです。
平成16年の国立大学等の法人化により、我が業界では手っ取り早く成果が上げられ、産学連携などで外部資金を引っ張ってこられる工学や医学・薬学などが重視されるようになり、人文系の部署は目に見えて金が減らされ、冷遇されるようになりました。
それがついに、あまりにも露骨な形で表れてしまったわけです。
私たち行政職にある者はそうでもありませんが、人文系の研究者にとっては恐怖の通知ですねぇ。
18歳人口の激減に対応するものだとかなんだとか屁理屈をつけていますが、要するに金にならない研究はいらないということでしょう。
しかし、文学や哲学などはもともと学問の祖ともいうべきもので、これを疎かにしては国民が教養を失い、人心は荒廃し、拝金主義の世の中が現出するのではないでしょうか。
本来、文部科学省は財務省などに対し、金にならない文学や哲学、理系でも基礎研究などを重視することが、ひいては金になる研究の礎になるのだと、説得すべき立場にあるはず。
それが率先して拝金主義の片棒を担ぐとは、泣ける話です。
文学者がよく口にする無用の用なんて野暮なことを言うつもりはありませんが、虚構のなかに真実を追求する文学や、人間の思索の歴史を踏まえて思想のなかに真実をさぐる哲学、人類の営みや歴史から現代社会の在り様に思いをめぐらす歴史学などは、最も古い学問であり、なぜ古いかと言えば、古来人間はそういった営みが死活的に重要だということを直感的に知っていたからに違いありません。
学徒出陣を思い出さずにはいられません。
太平洋戦争で劣勢に立たされた大日本帝國は、将来のわが国をしょって立つべきインテリ層をも、戦争に駆り出しました。
ただしそれは、文系の学生が中心。
理系の学生は、技術開発などで兵器の開発などにあたることが期待されたのか、学徒出陣を免除されたと聞きます。
わが国は70数年前に理系偏重の政策を打ち出し、太平を謳歌する現代においてなお、その愚を再び犯そうというのでしょうか。
確かに文学も哲学も社会学も歴史学も、新薬や家電製品、さらには武器の開発など、目に見える成果は上げられないことは事実です。
しかし営々と続けられてきた無用とも思える知の蓄積にこそ、人間が人間である所以があるものと思っています。
このたびの文部科学省の通知、私はその所管機関で働く者として、激しい失望を覚えざるを得ません。
もうこんな状況では働く気が起きません。
辞めちゃおうかとさえ思います。
そして学術や研究とは無縁の職場に移るのです。
どうせ事務職なので、研究機関にこだわる必要は無いのですから。
なんだかこのところ残業続きで疲労がたまっているようです。
ストレスからか、日々の晩酌もつい過ぎるようで、これでは体を壊してしまいそうです。
今の私には、若い頃のような、連日の残業に耐える体力はありませんから。
日々の仕事に追われ、それは第一に生活の糧を得るためであり、広い意味での社会参加でもありますが、それがため、重要な問題が置き去りにされているような気がしてなりません。
それは生老病死ということ。
お釈迦様が深く悩んで出家に至ったのは、生まれながらの苦しみ、老いる苦しみ、病気の苦しみ、死の苦しみについて考えるためです。
それはすべての人々が考えるべき重要問題です。
特に、死ぬということ。
私たちはおぎゃあと生まれた瞬間から、死の魔法にかけられています。
まっすぐに、いつか分からない死の瞬間に向かって突き進んでいるわけです。
今、この瞬間も。
普段あまり気にもかけませんが、考えてみると恐ろしい話です。
要するに私たちは全員死刑囚のようなもの。
私が死刑制度に強く反対なのは、誰だって必ず死ぬのに、それを早めることが刑罰になるとは思えないからです。
死の魔法から逃れようと、不老長寿の妙薬を求める権力者はあまたいましたが、今のところそれを得た人はいません。
生老病死ということが生きるうえで逃れられないことなら、それを受け入れるしかないのでしょうが、なかなか人は執着が強く、逃れられないまでも、先延ばしにしようと、愚かな努力を行っています。
アンチ・エイジングだとか、各種健康食品とか。
それは人それぞれ好きにすれば良いことですが、私は生まれてしまった苦しみをまず受け止め、病気の苦しみも受け止め、今は老いの苦しみを感じ始めるようになって、最後の難問、死の苦しみを受け入れる準備をすべき時期が近づいていることを思い、表面的な若返りとか健康法に精を出す気にはなれません。
そんな時間があるなら、静かに黙想するなり、先哲の著書を繙くなりして、老いと死について思いを巡らせることを優先したいと思っています。
私が抱える最大の問題は、多くの凡人がそうであるように、日々の仕事や雑事にかまけ、生老病死について考えることもせず、わずかな酒に慰めを求めて、時間を浪費していることだろうと思います。
しかし出家したところで、事情はそんなに変わらないと思います。
乞食坊主にでもなって放浪生活をするのならともかく、現在の仏教各宗派に属して寺院を運営するというのは、家族経営の零細企業の社長のようなもの。
サラリーマンほどでは無いにせよ、結局は仕事や雑事に時間を取られることになります。
それを思うと、人間が生きる根本は、雑事に追われることにあるのかもしれません。
逆に言えば、雑事に追われていないと、死の真実が迫ってきて、正気を保てないのでしょう。
なんだか漫然とした記事になりましたが、漫然とならざるを得ないほど死の魔法は怖ろしいわけです。
なにしろ全く不明の事態なわけですから。
私はただ、世捨て人となって死の魔法について考えながら、その恐怖耐えがたいときには美的世界に逃避するような、優雅な暮らしを夢想する愚か者に過ぎません。
あぁ、この記事を書くのに25分を費やしました。
25分、死刑執行の時刻が近づいたのですね。
あな、怖ろしや。
わが国ではあまり知られていませんが、今日は恐るべき命令が発出された日です。
1945年の今日、第三帝国総統の名で発出されたその命令は、ネロ指令とも、焦土作戦とも呼ばれます。
すなわち、東部からはソ連軍が、西部からは米英を中心とした部隊がついにドイツ本国に侵入し、敵に国内の基地や道路、工場などのインフラを利用されることを怖れ、敵の手に落ちる前にそれらインフラを破壊しろ、という命令です。
これをわが国に置き換えてみれば、その異様さが分るでしょう。
例えば本土決戦に突入し、米英ソ等の軍隊が破竹の進撃を行ったとして、わが国自らが、戦後のことなど考えず、わが国の建物や通信施設、軍事基地などを次々に破壊するということです。
ヒトラーは第三帝国が敗れればドイツはソ連に支配されると考えていたようで、しかも敗れるということは、アーリア人は、自らが差別していた東方の民族に劣ることが証明されるという意味であり、アーリア人の国家が存在する意味はなく、したがって戦後復興のことなど考える必要がないとまで考えていたようです。
なんという極端な考え方でしょうね。
勝負は時の運。
敗れたなら捲土重来を期して再び国力を蓄えようというのがまともな考えであろうと思います。
そして実際、わが国もドイツも復興を遂げました。
命令を受けた軍需大臣のシュペーアは総統に作戦の撤回を求めたものの叶わず、密かにこの命令をサボタージュして、かなりの程度ドイツのインフラを維持せしめたと聞き及びます。
 ヒトラーとシュペーアです。
ヒトラーとシュペーアです。
彼はニュルンベルク裁判で有罪を認め、罪一等を減じて、禁固20年の刑に服し、出獄後は半生記を出版したりしています。
 |
第三帝国の神殿にて〈上〉ナチス軍需相の証言 (中公文庫―BIBLIO20世紀) |
| Albert Speer,品田 豊治 | |
| 中央公論新社 |
 |
第三帝国の神殿にて〈下〉―ナチス軍需相の証言 (中公文庫BIBLIO20世紀) |
| Albert Speer,品田 豊治 | |
| 中央公論新社 |
幸いにしてシュペーアのような、勇気あるサボタージュを断行する人が軍需大臣に就いていたおかげで、焦土作戦はほとんど有名無実となったわけですが、例えばあのアイヒマンのような、命令に忠実な官僚タイプがその地位にあったなら、徹底的にインフラを破壊し、「上司の命令を実行しただけだ」、と開き直っていたことでしょう。
事実、アイヒマンは南米に逃亡中、モサドに捕えられ、イスラエルで裁判を受けていますが、その様子をBSで放送したことがあり、それを見ると、見事な自己弁護に終始しています。
要するに、組織の歯車に過ぎない自分は官僚として効率的にユダヤ人をアウシュビッツに運ぶ仕事をしただけだ、というわけです。
その弁舌は見事でした。
結局は絞首刑に処せられますが。
後に、特殊な環境下に置かれた人々が、どのように権威に従属していくかを調べる実験方法が考案され、アイヒマン実験と呼ばれるようになります。
 |
服従の心理―アイヒマン実験 (1980年) (現代思想選〈7〉) |
| 岸田 秀,スタンレー・ミルグラム | |
| 河出書房新社 |
仲の良い演劇部の女子生徒たちにそれぞれ権力者とか協力者とか役割を割り振るアイヒマン実験を描いた「私の中のアイヒマン」は衝撃的な映画でした。
権力者役が暴走したり、囚人役が叛乱を起こしたり。
しかも単なる実験なのに、かなり本気になっちゃってます。
 |
私の中のアイヒマン [DVD] |
| 清水美那,菜葉菜,兵頭祐香,他 | |
| エースデュース |
もっとひどいのは、「es」でした。
囚人役と看守役に分かれて行う実験を描いており、こちらは殺し合いにまで発展します。
しかも実話を基にしたというから戦慄すべきことです。
 |
es[エス] [DVD] |
| マリオ・ジョルダーノ | |
| ポニーキャニオン |
人はことほど左様に弱いもの。
自分だけは洗脳などされないと頑張ってみるより、もしかしたら自分も洗脳され、従属するかもしれないと気を付けているほうが、いざという時、自分を強くもてるような気がします。
日々組織で働いていて、まこと、世の中のあらゆる組織が、支配と従属の関係に堕する可能性を秘めていると思うのです。
![]()
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
今日は啓蟄ですね。
その由来を、暦便覧では、陽気地中にうごき、ちぢまる虫、穴をひらき出ればなり、と説明します。
昨日は父の命日でした。
まさに地中の虫たちが地上に出ようとする頃、父は亡くなったのですね。
まるで新しい命に道を譲るかのように。
よく、早春や初秋に亡くなる人が多い、という話を耳にします。
そういえば、父は早春でしたし、祖母は初秋でした。
夏や冬などの過酷な季節を乗り切り、寒暖の差が激しくなった頃に、人は亡くなることが多いのかもしれません。
西行法師が春、花の下での死を切望したことは有名ですね。
願わくば 花の下にて 春死なむ その望月の 如月の頃
と。
そしてそれは、ほぼ叶えられました。
幸せな人だと思います。
 |
西行全歌集 (岩波文庫) |
| 久保田 淳,吉野 朋美 | |
| 岩波書店 |
お盆の時期は極端に死者が減り、お盆の送りの後、人の死が激増すると、葬儀屋から聞いたことがありますが、本当でしょうか。
送られる死者が、生者を引っ張っていくんでしょうか。
不思議なことです。
父がこの時期に亡くなったせいか、私にとって啓蟄は、人さらに生物の死を考える季節になりました。
死ぬということは生きている者にとって全く不明の事態でありながら、人々は死、それに伴う死後の世界ということに思いを致さずにいられません。
最後の審判後、全ての人類は天国か地獄に行くというヤハウェの3宗教。
黄泉の国に行くという神道。
仏教はやや複雑で、輪廻転生及び解脱を説いてみたり、極楽往生を説いてみたり。
しかし仏教の死生観は、方便で色々なことを説きますが、結局は死んだ後のことなどわからない、それより現世をよりよく生きようというのが本当のような気がします。
そしてまた、死後は完全に無であるという現代的な考え方。
先進国では特に、死後は無であると考える人が多いのではないでしょうか。
死後について様々なことを人々は考え出しましたが、今のところ、誰にも本当のことは分りません。
そしておそらく、未来永劫分らないでしょう。
人類滅亡の日が来ても、人は何が何やら分らぬままに滅んでいくしかないものと予感します。
死後が如何なるものか、死んでみなければ分らないし、但しそれは死後の存在があり得た場合のみで、なおかつ一種類であった時、死後とはこういうものだと判明します。
無であればひたすら闇に沈んで何も意識しないでしょうし、死後の在り方が多様であった場合、自分が経験した世界以外のことは不明のままです。
人間が絶対に知りたいと思うことだけは、絶対に知ることができない、と嘆いたのは誰でしたか。
絶対に知りたいこと。
それはこの世の真理であり、その重要な一部が、死という不明な事態の解明であることは、間違いないように思います。
私は小難しい哲学や宗教の理論ではなく、神秘主義的な直感によってそれを感得し得るのではないかと考え、若い頃神秘思想にはまったことがあります。
 |
神秘学概論 (ちくま学芸文庫) |
| Rudolf Steiner,高橋 巖 | |
| 筑摩書房 |
しかし直感で感得し得るのは、せいぜい美的世界の存在くらいで、それ以外は何も知ることはできないのだと、深く失望したことがあります。
その後原始仏教、続いて大乗仏教へと興味が移り、その間には他の宗教や哲学も少し齧りました。
結果、失望は絶望に代わっただけでした。
真に、本当に知りたいことだけは、絶対に分らないようにこの世は出来ているようです。
そうであるならば、そういうものだと諦めて、せめて美的世界に遊ぶ他無さそうです。