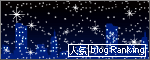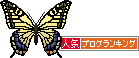ドイツでは長いこと、ヒトラーの著書、「わが闘争」は発禁でした。
あの暗い過去の記憶が、表現の自由よりも、禁書扱いにしたほうが楽だと思わせたのでしょう。
しかし、わが国においても、他の自由民主主義国家においても、「わが闘争」は容易に手に入れられる書物であり続けています。
 |
わが闘争(上)―民族主義的世界観(角川文庫) |
| 平野 一郎,将積 茂 | |
| 角川書店 |
 |
わが闘争(下)―国家社会主義運動(角川文庫) |
| 平野 一郎,将積 茂 | |
| 角川書店 |
私も学生の頃読んだ記憶があります。
これはミュンヘン一揆に失敗して監獄に入れらていた数年の間に獄中で書かれたもので、ナチズムの怖ろしさはまだそれほど伝わってきません。
この本はドイツでベストセラーになり、ヒトラーの個人資産は、ほとんどがこの本の印税であったと伝えられます。
このいわくつきの書物が、近々ドイツで再版されることになったそうです。
私は結構なことだと思います。
ナチズムの中核となる思想を一般のドイツ人が読めないのでは、ナチ統治下の反省をするにも、その理由が分らないでしょうから。
なぜナチズムはあれほどドイツ民族を熱狂させたのか、また、今なおナチズムに傾倒する者が存在するのか、それを考えるには最高のテキストであろうと思います。
じつは私も、一時期、ナチ親衛隊の格好よさに憧れていたことがあります。
黒づくめの制服に、髑髏をあしらった帽子。
ほとんど漫画のような、おどろおどろしくもスタイリッシュな制服です。
もちろん、彼らが行った戦争犯罪、人道に対する罪は許されるべきではないでしょう。
しかし制服に罪はないはずです。
また、ヒトラーの「我々は世界を焼き尽くす」という発言などは、未熟な少年の心をとらえるに十分な過激さを持っています。
少年というもの、多かれ少なかれ暴力への志向性を持っているものですから。
大人になるにつれ、普通は暴力への志向が消え失せ、やがて全てが面倒くさい、疲れたおじさんになってしまうのでしょう。
今の私がまさしくそういう状態です。
今更SSへの憧れなんて持ちようもありませんが、今も奇妙なものや不思議なもの、妖しい美を感じさせる芸術や文学は、私にとって最もシンパシーを感じさせる物であり続けています。
その心性が、私をしてSSへの興味を持たせた原因であろうと思います。
思想ではなく、パッと見ですね。
思い起こしてみれば、6歳の時に初めて書いた物語が、「ドラキュラの歯は無い」というタイトルでした。
年老いて牙を失った吸血鬼の悲しみを描いた作品です。
三つ子の魂百まで、と言いますが、本当に私は奇妙なものが好きなのだなと、我ながら呆れるばかりです。