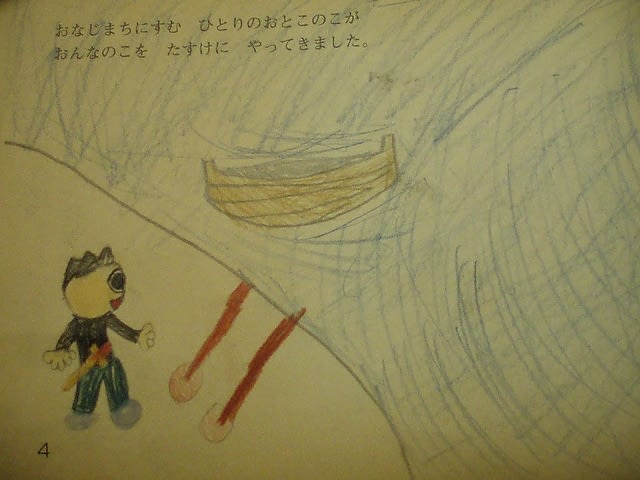土曜日は「食と命の教室」。
そして、夕方からは教室参加者の有志と一緒に公津の杜で開催された「日本と原発」の映画に行ってきました!
どんな映画かというと、詳しくはHPがありますのでご覧下さい。
→こちらから
「食と命の教室」の後なので、疲れ気味ですたが、いや~、とっても良かった

この映画は原発廃止を使命として掲げる河合弁護士が、大手メディアが報じない福島の実態、当時どういったことが起きていたのか?原子力ムラの構造からありとあらゆることを調べ上げ、司法闘争をしているのですが、その内容を一般市民にも伝えるために、自らが監督となって作った映画です。
さすが弁護士さんが監督をしているだけあって、論理的だし、映像や図解も抱負で、とてもわかりやすい。
例えば、「原子力ムラ」といううけど、企業と国と原発がどのように癒着しているのか、それが全て税金でまかなわれているということを映像で解説されていて、うちの奥様も昼の部に行ったのですが「わかりやすかった」と言っていました。
また、合間に河合弁護士がホワイトボードで「再処理、高速増殖炉、いかに両方破綻している?」とか「安部さんのいう原発がないと国富流出するというのは全く違う」といったことを、これまたわかりやすく講義のように解説する場面が挿入されていたり。
更に、色々な専門家のインタビューも入っていて、誰もが話がわかりやすい。
元、経済産業省の古賀さんの話なんて、とても面白くて「上役の3人の主な仕事は、天下り先を斡旋することですよ。官僚は若い頃から電力会社の人達と接待付けで、ゴルフとかをずっとやってきた中。だから、仲間のような同士のような感覚なんですね。だから規制する相手、という感じにはならないんです。そして、定年するときに、どこどこに行く、という割り振りがされる。3年とか5年経つと、後が詰まっているんで、ということで次の天下り先に行く。そして3つぐらいいくと、そろそろ70歳。そういった先輩には『そろそろ後ろも詰まってきているんで』と大変言いにくいのですが天下りをやめてもらう。そんなのが一番大変な仕事なわけです」といったあたりも痛烈で面白い

青木さんという弁護士は、新規制基準の問題点は「最後(最初?)の問題で、もし事故が起きたときに、周りに放射能の問題が起きないようなところに立地しなさい、というところが最初から抜け落ちている」という根本的な問題を指摘しています。
どういったことかというと、原発は「安心・安全・クリーンなエネルギー」という標語でずっとやってきわけです。
1957年に本格的に原発が日本でスタートした時は、「絶対に安心だ」ということを前提に、誘致を進めていったわけです。
「絶対に安心だ」という「安心神話」を信じさせた上で、進めていったわけですね。
ところが、2011の福島の事故で、今までに広島原爆200発近く分の放射能が漏れてしまった。
一部には、地下水流出で未だに1日1発分が漏れているとも言われています。
今もギリギリのところで、原因さえ究明できない状態が続いているわけです。
そういったことから「絶対安心」とは言わなくなった。
「事故が起きることもある。その場合も、大事故にならないようにこういった対策をとっている」という説明に変わったわけです。
しかし、そもそも「絶対安心だ」という前提の約束が反故にされてしまったわけで、この時点で「契約違反」となっているわけです。
福島なんていうのはひどいもので、政府・東電は「自然災害で、防ぎようがなかった」というスタンスをとり続けましたが、それは裁判などで覆されています。
まず、大地震発生から、津波の観測計の時刻を見ると、原子炉が崩壊して放射能が漏れ始めた時刻と、津波が到着する時刻を見比べた結果、津波が到着する前に放射能が漏れ始めていたということがわかったのです。
つまり「津波による自然災害」ではなく、「地震による家屋の損傷」という事故であった。
ということは、「そもそもの立地選定が間違っていた」ということになるわけです・
さらに、津波についても「大地震による津波が来た場合の防波壁を作ろう」という計画もあったのですが、費用がかかるということで、先延ばしにしたり、壁の高さの計画を低くしたり、という証拠があるんですね。
「予測不可能な自然災害」という言い訳はたたないのがはっきりしているわけです。
今も覚えていますが、私の住む千葉県の目と鼻の先の茨城県の東海村には原発があります。
JOCが事故を起こした際、「原発が爆発して制御不能になる」という事態になりそうになり、所長か責任者が現場の人に「危険かどうかいっていられない。爆発したら日本が終わりになる」といって、現場の2人を「突入」させて、最悪の事態にはならなかったわけですが、その2人は急性放射能中毒で亡くなったわけです。
そして、3.11の事故が起きた後、衝撃を受けたのは「東海村に大地震による津波が万が一来た時に、それを守る防波壁を建造し、それが完成したのが3.10。もし1日起きていたら、福島と同じことが東海村でも起きていた」という新聞記事。
覚えている人はほとんどいないでしょうが、私は「危機一髪だったんじゃないか

」と衝撃を受けました。
映画に話しを戻しますが、映画の後半で環境エネルギー政策研究所の飯田さんが「第四の革命」や「全国ご当地エネルギー協会」の紹介があったりとても希望が持てるような構成になっているのは、とても「希望」を持たせるものでした。
「第四の革命」とは、数年前に私も映画を観てブログに記事を書いたことがありますが、ネット検索すれば色々出てきます。
要するに、蒸気革命、IT革命に継ぐ、第四番目の産業革命のことで、それは「再生可能エネルギーによるエネルギー革命」のことです。
日本では「原発、原発しかない」というプロパガンダが広げられていますが、ドイツをはじめ、世界では「再生可能エネルギー」、つまり、風水、地力、太陽熱発電といったものの方が、倍々ゲームで伸びており、2025年には最大の電気供給源になる国も出てくるのです。
原発や火力発電のようなコストや廃棄物が出ないし、経済的な雇用もどんどん増えている。
また、太陽光パネルのような製造コストも毎年劇的に下がっていて、そろそろ火力発電のコストを下回る時代に入るんですね。
そういったことをフィンランドやヨーロッパで学び、日本でも広めている方の1人がエネルギー政策研究所の飯田さんで、「全国ご当地エネルギー協会」というのは、長野にある「おひさまファンド」という一般市民が資金を広く集め、地主ならぬ「屋根主」の屋根に太陽光パネルを設置させて頂き、売電収入でファンドを改修する、というのが日本でもどんどん広まっています。
これは「大会社支配」から「小口分散」「市民の手による事業」ということで電気は電気会社のものではない、ということを実現する流れを作っているんです。
世界に目を向けたり、ちょっと勉強すると、いかに日本がおかしいかがわかってきますよ。
しかし、11日に川内(せんだい)原発は再稼動されました。
どうしても再稼動を進めていきたい人達がいることに疑問を持ち続けます。
その川内原発についてこんなニュースがネットに載っていました。
「21日、復水ポンプ付近でトラブルがあり、21日に予定していた出力上昇を延期すると発表した。25日には原子炉の熱をフル出力する「定格熱出力一定運転」を予定していたが、遅れる見通し。」
トラブルがある方が多い原発を、さらに使おうとする人達に、是非、映画の中に出てきた、「大飯原発運転差止訴訟の判決文」を読んでもらいたい。この判決文、締めの言葉が痛烈で最高に良かったので、抜粋を以下貼り付けます。
ーーーーーーーーーーーー
日本列島は太平洋プレート、オホーツクプレート、ユーラシアプレート及びフィリピンプレートの4つのプレートの境目に位置しており、全世界の地震の1割が狭い我が国の国土で発生する。この地震大国日本において、基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しないというのは根拠のない楽観的見通しにしかすぎない上、基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというのであれば、そこでの危険は、
万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険と評価できる。このような施設のあり方は
原子力発電所が有する前記の本質的な危険性についてあまりにも楽観的といわざるを得ない。
国民の生存を基礎とする人格権を放射性物質の危険から守るという観点からみると、本件原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、むしろ、
確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであると認めざるを得ない。
他方、被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。
また、被告は、原子力発電所の稼動がCO2排出削減に資するもので環境面で優れている旨主張するが、原子力発電所でひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染はすさまじいものであって、福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害、環境汚染であることに照らすと、
環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることは甚だしい筋違いである。










 」ということで、以前、奥様と子ども達がやっていた「水色遊び」という朝顔を絞った液を使ったお絵かきをみんなでやることに
」ということで、以前、奥様と子ども達がやっていた「水色遊び」という朝顔を絞った液を使ったお絵かきをみんなでやることに


















 」ということで、以前、奥様と子ども達がやっていた「水色遊び」という朝顔を絞った液を使ったお絵かきをみんなでやることに
」ということで、以前、奥様と子ども達がやっていた「水色遊び」という朝顔を絞った液を使ったお絵かきをみんなでやることに