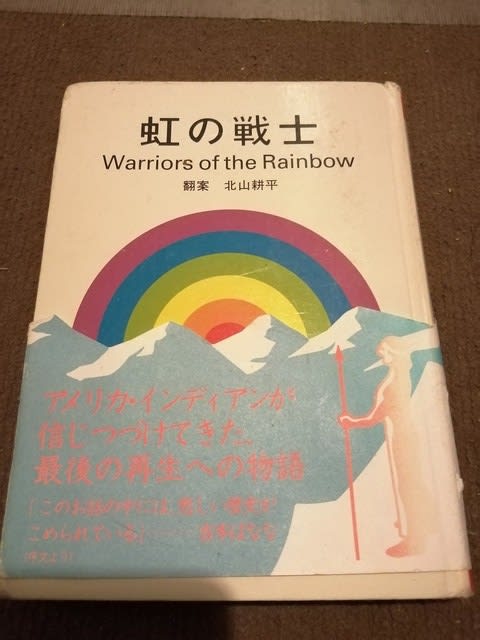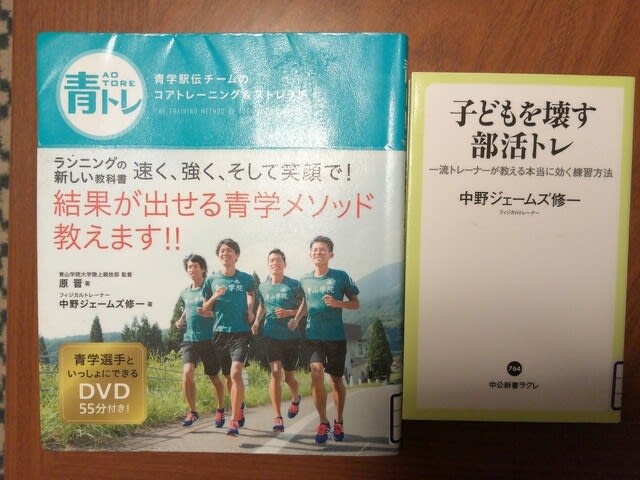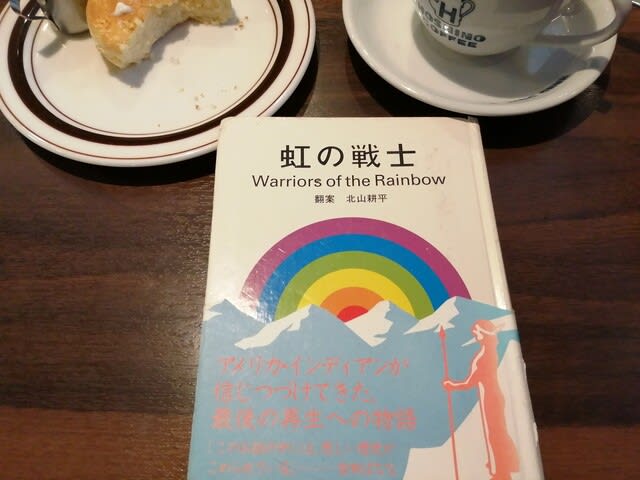秋は食欲の秋と同時に読書の秋です。
というわけでもないのですが、実は約1年半ぶりに図書館で本を借りてきました
図書館は習慣としてちょくちょく行っていたのですが、昨年の3月に中1の子供達向けに英語のお勉強の場「second note」を立ち上げるにあたって、10冊ぐらい英語の本を借りたのを機に、以後、行かなくなりました。
1つは、中3男子だった長男の受験の伴走が終わったので気を抜いたこと、また、secondnoteが始まったり5月の田植えなどで、ドタバタに入り、何となく本を読む気が起きなくなり、ダラダラ~っとルーチン仕事をしてきた感じです。
で、夏休みはちょっとゲームをやったり、コロナにかかったりと、まあ、なんだかんだいって時は流れるように過ぎてきたのです。
ただ、9月も終わりに近づき、田畑仕事も落ち着いてきたことで、久々に図書館に行ったのです
2冊借りたのですが、1つは「日本の歴史を英語で」という本で、まあこれは自分の英語勉強のためですね。
もう1つが表題の「村の若者たち」という宮本常一氏の著書の復刻版です。
宮本常一さんは民俗学者で有名で、柳田国男さんの次ときたら、やっぱり宮本常一さんじゃないでしょうか。
って、興味が無い人は全く知らないかもしれませんが、私は日本人がどう生きてきたのか、に関心があるので、イコールで民俗学とか伝記ものとかは面白く読めるタイプなのです。
ただ、柳田国男さんに遠野物語やちょっとした本は目を通したことがあるのですが、良く考えたら、きちんと宮本常一さんの本は読んだ事が無かったのですね
それが、図書館で何となく手にとってちらりと読んでみたら「面白そう 」ということで、借りて読んだのです。
」ということで、借りて読んだのです。
そこには私が知らなかった「村の若者たち」の姿が赤裸々に書いてありました。。。
私が知っているのは高柳さんなどまだ存命している農村の農家さん達が「俺が子供の頃はこうだったぞ」という話し。つまり、戦後、高度経済成長を始めて農村から都市部に人が流れていく中、まだ大工の日当がお米2升とか、現金経済が入り始めたり、公害時代に対する有機農業運動が起きたり、という辺りでした。
しかし、この本は昭和37年頃の本のようなのですが、江戸、明治、大正、昭和の戦争前後の農村の事が1つ1つ細かい事例、例えば東北の◎◎村はどうだったのか、島根の海辺の△△という村はどういった感じだったのか、という事が書かれているのです。
そこに一貫して書かれているのはこうです。
・農村は限られた土地に30戸住んでいるとしたら、その30戸がみんなその村で自給自足でそこそこの生活が出来る、というのはほとんど無かった
・そうなると、家を継ぐ長男は良いとして、次男、三男の処理をどするか、というのが一番の問題だった。女の子は売ればお金になるが、次男、三男は生まれたら川辺に捨ててくる、ということが当たり前だった地域も多かった
・村の掟のようなもので子供は1人、あとは処理するのが暗黙の了解で、何かしら生き残って仕方無く育てる事になった次男、三男がいたら、戸籍上は載っていない状態で、村人からは白い目で見られながら肩身狭く育てられた、なんてことも当たり前だった
・次男、三男を分家する、というのはよほどの土地が無いと不可能で、それは本家の土地が減ること、つまり本家がやっていけなくなるようなもので、季節労働者、丁稚奉公、あるいは他の土地へ流れていく、というのも普通で、良くて下男のような扱いで本家に扱われ、結婚も家も持たず死んで行くというのも当たり前だった
・要するに「どうやって食って生き延びていくか」が大事で、次男、三男、あるいは余分な若者は「どう処理するか」が村々の大きな問題だった
そんな感じなのです。
海辺の村は漁、陸の村は田畑でなんとか生きていこうとしていたのですが、それで満足出来るほど自給が出来ているのはほんの一握り。ほとんどが食っていけないので、次男、三男の処理、あるいは出稼ぎ、身売りが当たり前で、そういった時代が戦後ぐらいも普通だった、と。今の人が聞いたらゾッとするような状態ですが、良く考えてみたら、それはそうなんだろな~、と。
ちなみに私の小学校時代の記憶で、最も覚えている記憶の1つが、同級生の作文の発表です。何かというと、その家は貧しくて、でも子だくさんで、小学5~6年生の時だったのですが、「新しい子が生まれたけど、食わせていけないからそっと息を引き取ってもらった」という内容です。他の同級生はあまり反応していなかったのですが、私には衝撃的で今にも鮮明に覚えています。つまり、子供の間引き、というのは昔はあたりまえだった、ということです。
また村には青年団というものがあり、そこでは様々な交流がありました。長男は家を継ぐから良いとして、次男、三男などは村には必要が無いわけです。ただ、地域によっては祭り、塩田の働き手、自警、漁の漕ぎ手や網子などはこの青年団がになっていたわけです。
明治になると国として「徴兵制度」が始まり、ちょうど「生き場所が無い次男、三男問題」と、「兵力を集めなくてはいけない国」の思惑が一致し、青年団を中心に次男、三男が徴兵されていったそうです。後に、長男も徴兵対象になったのですが、最初は「家の継ぎ手が無くなると家、村が存続出来ない」というのは誰もがわかっていることなので、長男は免除されたわけです。
また、女子の青年団もあって、村の1つのたまり場に男は男、女は女で別々で固まり、仕事のつらさを分かち合いながら語り合ったりしたそうです。そして夜這いも当たり前にあった時代で、宮本常一さんの話では、半分は相思相愛でつきあった、と。当時は電気も無く、また夜這いも当たり前の習慣で、男は男の寄り合い所で先輩から性の手ほどきを受けるし、女は女で同様に先輩から男のあしらい方を教えてもらう。
夜這いに男が来るのは全く問題無く、ただ、女には選択権があり、嫌なら断る。通じ合えば夜這い成功で、ただ、子供を作ってはいけない、というルールもあり、子供が出来たのにその女を捨てた男は、仲間からボコボコにされ村八分のような制裁がまっている、なんてこともあったようです。
意思疎通が出来、通い合う中で将来の結婚を約束しても金も家も無いわけで、そういったカップルは、頑張って働き小屋なり家なりを手に入れる事ができたら、そこで始めて結婚する、という流れが普通だったようです。
明治後半から大正にかけて、東京や大阪などに工業や農や漁以外の第二次、第三次産業が出来てくると、次男、三男などはそこへ出稼ぎに行き、女子も紡績や繊維工場で出稼ぎに行く。また、大工、酒作りといった技術が必要な仕事にも流れるようになっていったそうです。
一方、小学校を卒業する、あるいは中学校に行けるような子供はある程度のお金がある中流の農家の長男以上だったわけで、そういった家は当然村でも1つ格が上で、そういった子以外は村の青年団でキズを舐め会いながら毎日労働にあけくれて、それでも飯が食えたら良い、という生活を送っている。そして青年団としては、リーダーも現われて「自分達の存在意義」ということで、例えば日清、日露戦争の際には「俺たちだってお国のお役に立とう」と、例えばワラジを編んで献上したり、といった活動もあったようです。
女子も人権という考え方が生まれてきて、男の運動に触発された、という事もあったそうですが、例えば紡績工場などの労働改訂として、夜は睡眠を取る権利がある、といった事を実現したそうです。逆に言えば、朝早くから夜通し働く、つまり徹夜仕事も当たり前で働かされて体を壊して死んで行く、というのが当たり前だったのが、夜は寝かせてもらえる、程度の改善運動は起きていた、ということ。
そんなこんなで続いてきた農村事情。太平洋戦争に向かう頃には男が少なくなって労働力不足の問題が出てきたものの、戦後はドッと戦地から男達が帰ってきて、また村の「どうやって食っていくか」問題が起き、各地に流れていくようにもなったわけですが、段々、村の外で一財産築ける人達も出来てきて、そういった村以外、都市部に地縁、血縁を頼って出て行く流れが出来てきました。
それまでは、大企業のサラリーマン、あるいは官公庁に勤められるのは、中流以上の農家の長男だけだった、つまりちゃんと学校に通わせられるのはそういった類いだけだったのが、農家の次男、三男でもそういった人達が出てきた。
300万人以上いるといわれた全国の青年団の数はどんどん減少していき、取り残された感が出てきた。また、家を継ぐ宿命の長男は、発展する都市部に対して衰退する村に残らなければいけないわけで、青年団の維持をどうするか、何のためにそもそもやっているのか、とか、苦しい状態になっているわけです。
そして、戦後はフォークダンスやう書の秋です。
というわけでもないのですが、実は約1年半ぶりに図書館で本を借りてきました
図書館は習慣としてちょくちょく行っていたのですが、昨年の3月に中1の子供達向けに英語のお勉強の場「second note」を立ち上げるにあたって、10冊ぐらい英語の本を借りたのを機に、以後、行かなくなりました。
1つは、中3男子だった長男の受験の伴走が終わったので気を抜いたこと、また、secondnoteが始まったり5月の田植えなどで、ドタバタに入り、何となく本を読む気が起きなくなり、ダラダラ~っとルーチン仕事をしてきた感じです。
で、夏休みはちょっとゲームをやったり、コロナにかかったりと、まあ、なんだかんだいって時は流れるように過ぎてきたのです。
ただ、9月も終わりに近づき、田畑仕事も落ち着いてきたことで、久々に図書館に行ったのです
2冊借りたのですが、1つは「日本の歴史を英語で」という本で、まあこれは自分の英語勉強のためですね。
もう1つが表題の「村の若者たち」という宮本常一氏の著書の復刻版です。
宮本常一さんは民俗学者で有名で、柳田国男さんの次ときたら、やっぱり宮本常一さんじゃないでしょうか。
って、興味が無い人は全く知らないかもしれませんが、私は日本人がどう生きてきたのか、に関心があるので、イコールで民俗学とか伝記ものとかは面白く読めるタイプなのです。
ただ、柳田国男さんに遠野物語やちょっとした本は目を通したことがあるのですが、良く考えたら、きちんと宮本常一さんの本は読んだ事が無かったのですね
それが、図書館で何となく手にとってちらりと読んでみたら「面白そう」ということで、借りて読んだのです。
そこには私が知らなかった「村の若者たち」の姿が赤裸々に書いてありました。。。
私が知っているのは高柳さんなどまだ存命している農村の農家さん達が「俺が子供の頃はこうだったぞ」という話し。つまり、戦後、高度経済成長を始めて農村から都市部に人が流れていく中、まだ大工の日当がお米2升とか、現金経済が入り始めたり、公害時代に対する有機農業運動が起きたり、という辺りでした。
しかし、この本は昭和37年頃の本のようなのですが、江戸、明治、大正、昭和の戦争前後の農村の事が1つ1つ細かい事例、例えば東北の◎◎村はどうだったのか、島根の海辺の△△という村はどういった感じだったのか、という事が書かれているのです。
そこに一貫して書かれているのはこうです。
・農村は限られた土地に30戸住んでいるとしたら、その30戸がみんなその村で自給自足でそこそこの生活が出来る、というのはほとんど無かった
・そうなると、家を継ぐ長男は良いとして、次男、三男の処理をどするか、というのが一番の問題だった。女の子は売ればお金になるが、次男、三男は生まれたら川辺に捨ててくる、ということが当たり前だった地域も多かった
・村の掟のようなもので子供は1人、あとは処理するのが暗黙の了解で、何かしら生き残って仕方無く育てる事になった次男、三男がいたら、戸籍上は載っていない状態で、村人からは白い目で見られながら肩身狭く育てられた、なんてことも当たり前だった
・次男、三男を分家する、というのはよほどの土地が無いと不可能で、それは本家の土地が減ること、つまり本家がやっていけなくなるようなもので、季節労働者、丁稚奉公、あるいは他の土地へ流れていく、というのも普通で、良くて下男のような扱いで本家に扱われ、結婚も家も持たず死んで行くというのも当たり前だった
・要するに「どうやって食って生き延びていくか」が大事で、次男、三男、あるいは余分な若者は「どう処理するか」が村々の大きな問題だった
そんな感じなのです。
海辺の村は漁、陸の村は田畑でなんとか生きていこうとしていたのですが、それで満足出来るほど自給が出来ているのはほんの一握り。ほとんどが食っていけないので、次男、三男の処理、あるいは出稼ぎ、身売りが当たり前で、そういった時代が戦後ぐらいも普通だった、と。今の人が聞いたらゾッとするような状態ですが、良く考えてみたら、それはそうなんだろな~、と。
ちなみに私の小学校時代の記憶で、最も覚えている記憶の1つが、同級生の作文の発表です。何かというと、その家は貧しくて、でも子だくさんで、小学5~6年生の時だったのですが、「新しい子が生まれたけど、食わせていけないからそっと息を引き取ってもらった」という内容です。他の同級生はあまり反応していなかったのですが、私には衝撃的で今にも鮮明に覚えています。つまり、子供の間引き、というのは昔はあたりまえだった、ということです。
また村には青年団というものがあり、そこでは様々な交流がありました。長男は家を継ぐから良いとして、次男、三男などは村には必要が無いわけです。ただ、地域によっては祭り、塩田の働き手、自警、漁の漕ぎ手や網子などはこの青年団がになっていたわけです。
明治になると国として「徴兵制度」が始まり、ちょうど「生き場所が無い次男、三男問題」と、「兵力を集めなくてはいけない国」の思惑が一致し、青年団を中心に次男、三男が徴兵されていったそうです。後に、長男も徴兵対象になったのですが、最初は「家の継ぎ手が無くなると家、村が存続出来ない」というのは誰もがわかっていることなので、長男は免除されたわけです。
また、女子の青年団もあって、村の1つのたまり場に男は男、女は女で別々で固まり、仕事のつらさを分かち合いながら語り合ったりしたそうです。そして夜這いも当たり前にあった時代で、宮本常一さんの話では、半分は相思相愛でつきあった、と。当時は電気も無く、また夜這いも当たり前の習慣で、男は男の寄り合い所で先輩から性の手ほどきを受けるし、女は女で同様に先輩から男のあしらい方を教えてもらう。
夜這いに男が来るのは全く問題無く、ただ、女には選択権があり、嫌なら断る。通じ合えば夜這い成功で、ただ、子供を作ってはいけない、というルールもあり、子供が出来たのにその女を捨てた男は、仲間からボコボコにされ村八分のような制裁がまっている、なんてこともあったようです。
意思疎通が出来、通い合う中で将来の結婚を約束しても金も家も無いわけで、そういったカップルは、頑張って働き小屋なり家なりを手に入れる事ができたら、そこで始めて結婚する、という流れが普通だったようです。
明治後半から大正にかけて、東京や大阪などに工業や農や漁以外の第二次、第三次産業が出来てくると、次男、三男などはそこへ出稼ぎに行き、女子も紡績や繊維工場で出稼ぎに行く。また、大工、酒作りといった技術が必要な仕事にも流れるようになっていったそうです。
一方、小学校を卒業する、あるいは中学校に行けるような子供はある程度のお金がある中流の農家の長男以上だったわけで、そういった家は当然村でも1つ格が上で、そういった子以外は村の青年団でキズを舐め会いながら毎日労働にあけくれて、それでも飯が食えたら良い、という生活を送っている。そして青年団としては、リーダーも現われて「自分達の存在意義」ということで、例えば日清、日露戦争の際には「俺たちだってお国のお役に立とう」と、例えばワラジを編んで献上したり、といった活動もあったようです。
女子も人権という考え方が生まれてきて、男の運動に触発された、という事もあったそうですが、例えば紡績工場などの労働改訂として、夜は睡眠を取る権利がある、といった事を実現したそうです。逆に言えば、朝早くから夜通し働く、つまり徹夜仕事も当たり前で働かされて体を壊して死んで行く、というのが当たり前だったのが、夜は寝かせてもらえる、程度の改善運動は起きていた、ということ。
そんなこんなで続いてきた農村事情。太平洋戦争に向かう頃には男が少なくなって労働力不足の問題が出てきたものの、戦後はドッと戦地から男達が帰ってきて、また村の「どうやって食っていくか」問題が起き、各地に流れていくようにもなったわけですが、段々、村の外で一財産築ける人達も出来てきて、そういった村以外、都市部に地縁、血縁を頼って出て行く流れが出来てきました。
それまでは、大企業のサラリーマン、あるいは官公庁に勤められるのは、中流以上の農家の長男だけだった、つまりちゃんと学校に通わせられるのはそういった類いだけだったのが、農家の次男、三男でもそういった人達が出てきた。
300万人以上いるといわれた全国の青年団の数はどんどん減少していき、取り残された感が出てきた。また、家を継ぐ宿命の長男は、発展する都市部に対して衰退する村に残らなければいけないわけで、青年団の維持をどうするか、何のためにそもそもやっているのか、とか、苦しい状態になっているわけです。
そして、戦後の青年団は、フォークダンスなど娯楽なども入ってきて、今までは男の青年団、女の青年団が一緒に活動するのは無かったのが、同じ団に属するようになってきた。ある意味、お見合いの場のようになってきたよう。ただ、それでも青年団は衰退の一途を辿っていった。
こんな話でした。
宮本常一さんの書き方で、一番良かったのは、「若者は不確定で未来が決まっていないからこそ、不安もあるし葛藤もあるが、それだけ可能性があるということ」というエールでしょうか。
逆に言えば、大人は何をして生きていくか、ある程度、固まってきているので、不安や葛藤が減ってきているかもしれないけど可能性も狭まってきている、ということですよね。
若者が悩み葛藤を持っているのは、確固たる場所に根付いていないからで、でもだからこそいつでも何回でもやり直せるし、何をしても許される。だから村の若者たち、未来を開いていこう、というエールが伝わってきました。
また、私としては、目の前におつきあいしている高柳さん達に繋がる農村の若者たちの歴史は、ほぼ「食っていくために不必要に生まれた子供達をどう処理するか」という歴史で有り、1人1人がきちんと食っていけるようになって殺されることもなくどう自分の人生を考え生きていくのか、といったことが当たり前に出来る時代は、戦後しばらく経ってからなのだな~、という事がわかりました。
そう思えば、今の私達は贅沢三昧ですよね。まあ、逆に根無し草がが多いわけですが。
長い歴史を思うと、やっぱり戦後の世界は特異な世界で、歴史や文化が壊れていくのも仕方無いというか、今までの延長ではない新時代なんだな~と思います。