帰り道、車の中でラジオを聴いていたら、季節外れのクリスマス・ソングが流れてきました。
題して、「サンタと天使が笑う夜」。
 |
サンタと天使が笑う夜 |
| DREAMS COME TRUE | |
| Epic Records Japan Inc. |
 |
LOVE GOES ON・・・ |
| エピックレコードジャパン | |
| エピックレコードジャパン |
その中で、一生一度しかない、今年のクリスマスというフレーズが印象に残りました。
それはそのとおり。
しかし、何もことはクリスマスに限ったことではありますまい。
思春期を迎える13歳の春の一日は一生一度しかなく、17歳の盛夏の一夜も一生一度しかなく、22歳、そろそろ人生を真剣に考えなければならない春の日も一生一度しかありません。
不惑などと言いながら、惑いに惑うのが凡人の常である40歳の誕生日も一生一度しかありません。
すなわち、私たちが生きている毎日は、一生一度しかない一日の連続で、さらに敷衍するなら一瞬一瞬が、一生一度しかない刹那です。
生まれては滅びを繰り返す刹那滅こそが、人生の本質と言えるでしょう。
だからその日その瞬間を大切に生きましょうなどと、馬鹿げた説教を垂れる気はさらさらありません。
大切に生きるということの解釈にも依りますが、人は大抵毎日を雑事にかまけて暮らしています。
その雑事こそが社会を成り立たせているのであり、雑事を誠実にこなすことが、じつは刹那滅を生きるありとあらゆる生物の宿命だと言えるでしょう。
刹那滅の大半は、食うことを目的として費やされます。
肉食獣であれば狩り、草食獣であれば草を食み、なおかつ肉食獣からの攻撃を避けること。
平時において人間は収入を得るために大半の時間をさき、戦時にあっては戦うことを本旨とするでしょう。
どちらも生き残りを賭けた戦いであることに変わりはありません。
その切ないばかりに愛おしい一瞬を思うとき、私は沈黙せざるを得ません。
その沈黙は、もちろん哲学的なものでも文学的なものでもありはしません。
ただ一つ、私は生きとし生ける者が、一様に背負わされた業とでも言うしかないものを思って、悲哀の情に駆られ、沈黙するのです。
この悲哀は、何も仏教徒だけでなくても、この世で多少の経験を積んだ人なら誰でも理解できると思います。
刹那滅とそれに伴う業による日々の生活を思うとき、私は無条件に、善人であれ極悪人であれ、同時代を生きる人々、過去を生きた先人たち、そして未来を生きる子孫たちのすべてに、限りない愛情を感じます。
過去世・現世・未来世を生きるすべての人々に、幸多かれと祈らずにはいられません。
それにしても、ポップスの1フレーズから、このような憂愁に囚われてしまうとは、私もよほど因果な質に生まれついたものだと嘆かずにはいられません。
![]()
にほんブログ村 ![]()
人文 ブログランキングへ





















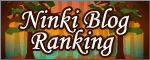





 出口なおです。
出口なおです。
 こんな感じです。
こんな感じです。












