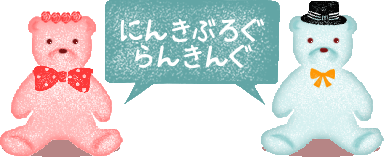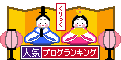理研の特別顧問が、小保方氏のSTAP細胞再現実験の際、監視カメラを使うことについて、「世の中にはそこまでやらないと、彼女が魔術を使って不正を持ち込むのではないかという危惧があるのではないか」と語ったそうですね。
私が見るところ、彼女は稀代の詐話師だとは思いますが、魔女だとは思いません。
理研の大幹部としては、不適切な発言のように感じます。
魔女というと、現代ではアニメやドラマなどに登場する、愛嬌のある若い女性というイメージがあります。
ちょっと古いですが、「奥様は魔女」だの、「魔女っ子メグ」だの、「魔女の宅急便」だの。
要するに魔術が使えるというだけで、悪魔を崇拝し、仕える伝統的な魔女とは似て非なるものですね。
魔女の概念は非常に多様ですが、大雑把に言って、悪魔を崇拝し、悪魔と性的関係を結ぶなどして契約を交わし、強い魔力をもって、人や自然に災いを為す存在、といったところでしょうか。
実際は、キリスト教を信じず、古くからのシャーマニズムを信じていた人々が存在し、土俗的な儀式をおこなったりして、それがキリスト教徒には悪魔崇拝に見えたのかもしれませんね。
中世ヨーロッパで行われた魔女狩り・魔女裁判は、それは凄惨を極めたと伝え聞きます。
宗教に寛容な国に生まれて本当に良かったと思います。
汝の敵を愛せ、とキリストは説いたと伝えられます。
これは普通に考えれば到底受け入れがたいことです。
受け入れがたいことを受け入れるから立派な行為だとされるのでしょうね。
ただし、ただ単純に敵を愛するというよりも、敵を愛するという行為が、神様を愛するという行いにつながり、もって、人は神を愛し、愛される、という理屈のようです。
それによって、天国の門が開かれる、という利益が得られるというわけで、神の愛は無償かもしれませんが、人の愛はどこまでいっても対価を求めるもののようです。
死ねばみな 黄泉に行くとは 知らずして ほとけの国を ねがふおろかさ
本居宣長の和歌です。
この人、日本神話に書かれていることを頭から正しいと信じ、仏教を批判しました。
神話では、黄泉の国は穢れた場所だとされていますから、誰だってそんなところに行くよりも、極楽往生を遂げたいと思うのが人情でしょうに。
この人、仏教や儒教などに侵されたわが国の思想体系を深く憂い、大和心をこそ良しとして、その本質に迫ろうと、「古事記伝」などの大作や、「源氏物語玉の小櫛―物のあわれ論」を著しました。
 |
古事記伝 1 (岩波文庫 黄 219-6) |
| 倉野 憲司,本居 宣長 | |
| 岩波書店 |
 |
源氏物語玉の小櫛―物のあわれ論 (現代語訳本居宣長選集) |
| 山口 志義夫 | |
| 多摩通信社 |
その中で、死があるからこそ宗教が生まれると考え、神道はいわゆる宗教ではなく、一種の倫理規範であり、それに依って生きることを称揚せしめようと考えたものと推量します。
その当然の帰結として、一種の無宗教に陥り、死後の世界を認めないという態度を、死後は黄泉に行くだけだ、と逆説的な言い方をしたのではないかと思います。
私もまた、大和心というものに深く心惹かれる日本人でありますが、しかし、外つ国々(とつくにぐに)の長きに学び、わが短きを補うこともまた、重要だと思うのです。
そうでなければ、独善に陥ってしまうように思います。
現在未開の民族の習俗と考えられている素朴な自然崇拝やシャーマニズムは、かつてどの民族でもみられたものと思います。
東洋においては仏教や儒教がおこり、それらは廃れました。
もっともわが国においては、なぜか仏教受容後も神道という形で残り、連綿と現在まで続いています。
これはわが国の人々の精神性に、寛容とバランス感覚という優れた資質を生み出す素になったことでしょう。
一方、西洋・中東ではユダヤ教・キリスト教・イスラム教という、よく似た教義を持つ三つの宗教が隆盛を極め、彼らの道徳規範となってきました。
その過程で彼らは自然崇拝やシャーマニズムを捨て去り、ために独善が生まれたものと推測します。
ナチズムはキリスト教を否定し、古代ゲルマン民族の土俗的な宗教を復活せしめようとしましたが、敗戦により頓挫。
当時、SS(親衛隊)将校のじつに99%がキリスト教を棄教したというから徹底しています。
ヤハウェの3宗教では、最後の審判ということが説かれます。
遠い将来、救世主が現れて、死者も含め、この世に存在した、あるいは存在するすべての人間は審判により天国行きか地獄行きかを決められるというのです。
いわばこれらの宗教の道徳は、最後の審判を脅迫に使って維持せしめているとも言えましょう。
イスラム過激派が自爆テロを繰り返すのも、それが善なる行為だと信じ、善を為せば天国への切符を手に入れられると考えるからで、欧米人が彼らの自爆テロをカミカゼと呼ぶのはお門違いも甚だしいというべきでしょう。
私には最後の審判ということが、どうしても理解できません。
それはほとんどお伽噺かSFと言うべきでしょう。
しかし多くの預言者が、幻視を見たのか、お告げを聞いたのか知りませんが、似たようなことを言っているところをみると、もしかしたらそういうこともあるのかな、という気分にはなります。
仏教では、地上での修行を積めば、仏となって涅槃に至る、と説きました。
チベット仏教では、輪廻転生を繰り返し、しかる後、悟りを開いて涅槃に至る、と説きました。
しかし釈迦入滅後、仏教は大きく展開し、主に中国で花開いた大乗仏教では、即身成仏(生きたまま悟りを開き、仏になること。ミイラになることではありません)、山川草木悉皆成仏(山や川、草木、あらゆる自然物には仏性があり、仏になれる)というところまで行き、わが国では大乗仏教の教えが一般的です。
そこには地獄も極楽もなく、まして救世主による最後の審判などというおどろおどろしいことは全く想定されていません。
悟りの境地とか涅槃というのは、全てを理解し、この世の苦しみ楽しみを超越した境地というべきで、いわゆる天国とは異なります。
大乗仏典には、法華経に見られる観音様の超自然的な力を称える教えや、お釈迦様が教えを説いているとそれを祝福して地中から現れた地涌の菩薩など、SF的な要素も見られますが、それは一貫したものではなく、多分に暗喩めいたもので、最後の審判のような迫力はありません。
人間が考え出すお話や宗教は、奇妙で不思議です。
私が奇妙で不思議な物語を好むというより、世の中にあふれるお話は奇妙で不思議なものばかりです。
それは一にかかって、この世が不思議で奇妙だからだろうと思います。
すると必然的に、この世の真理を求める宗教もまた、不思議で奇妙なものにならざるを得ないでしょう。
私はどの宗教も信仰していません。
強いて言えば、様々な宗教や疑似科学、さらには神秘思想などをブレンドミックスして、自分なりに咀嚼したとびお教とでも言うしかないものを信じていると言えるかもしれません。
そして当然ながら、教祖は私であり信者は私一人です。
私はすべての人々が、自ら教祖となり、自分一人が信者という、宗教というよりもおのれの信念に従って生きる社会を夢見ています。
それは自己を尊重し、自己を尊重するがゆえに他者をも尊重せずにはいられない社会であろうと思います。
しかし、世界の宗教対立を思うと、そんなことは夢のまた夢という気もしますねぇ。
学生の頃、夢日記をつけていたことがあります。
枕元にノートとシャープペンを置き、目覚めたなら、覚えているかぎりの夢を書き留めるのです。
そのうち、奇妙なことが起きました。
夢の記憶が鮮明になり、それが夢の出来ごとなのか、現実なのか、曖昧になってきたのです。
これは危険だと思い、夢日記を止めてしまいました。
筒井康隆は長く夢日記を書き続けており、時にはそこからインスピレーションを得て、作品化することもあるそうです。
精神的に強い人なのだと思います。
現実が夢に飲み込まれる恐怖を感じないのでしょう。
名匠、ヴィム・ベンダース監督に「夢の涯てまでも」という佳品があります。
夢、わけても幼いころの幸せな夢に溺れ、眠ってばかりいる人々を描いて、痛々しくも切ないえいがでした。
いわば、夢中毒。
夢日記に危険を感じた私には、ヴェンダース監督の意図が良く分かります。

 |
夢の涯てまでも [VHS] |
| ウィリアム・ハート,ヴィム・ヴェンダース | |
| 電通 |
夢か現か幻か、なんて言いますね。
また、人生の栄華は一炊の夢、とも。
これは中国の故事で、ある青年がうとうとし、栄華に満ちた人生を夢に見るのですが、起きてみるとまだ飯が炊けていないほどの短い時間だった、ということです。
現実がしんどいものである以上、わずかの間でも、夢の世界に溺れたいものです。
もちろん、夢中毒に陥ってはいけませんが。
日米開戦三ヶ月前の御前会議において、昭和陛下は祖父である明治天皇の御製、
よもの海 みなはらからと思ふ世に など波風の 立ちさわぐらむ
を読みあげられたと伝えられます。
従来、開戦を憂慮し、暗に開戦に反対の意向を表明したものだと解釈されてきました。
しかし、近年、某近現代史家の発表によると、当時会議に出席していた近衛文麿ら複数名のメモから、昭和陛下は波風を、あえて仇波(あだなみ)と読み替えられた、と主張しているそうです。
よもの海 みなはらからと思ふ世に など仇波の 立ちさわぐらむ
と、なります。
そうだとすると、まるで意味が異なってきます。
仇波と読み替えられたというのが本当なら、日本人は平和を希求しているのに、なんだってまた敵は騒ぎを大きくするのじゃ、これでは戦を避けようがないではないか、と慨嘆しているような印象に変わってきます。
昭和陛下が開戦を望まず、外交努力によって日米間の対立を解消したいと願っていたことは間違いないでしょう。
しかし、全く日本の言い分を聞こうとせず、一方的に要求を突きつけてくる米国に苛立っていたであろうことも、想像に難くありません。
大御心が奈辺におありであったのか、私には当然分かりません。
国民の多くがもやもやした状態に嫌気がさし、いっそ開戦を望んでいるらしいことも、米国は容易に勝てる相手ではないこともお分かりであったことと思います。
そのような鬱屈が、平和を望んでいるからこそ、相手への苛立ちとなって、あえての読み替えとなったものと思われます。
これを聞いた時、おそらく御前会議の出席者たちは、ついに陛下が腹を括られた、と感じたことでしょう。
それにしても過去というもの、ほんの70数年前のことも、真偽のほどは分からないのですねぇ。
してみると、邪馬台国論争など、馬鹿馬鹿しくも感じます。
はるか古代のことなど、そう簡単に判明しますまい。
歴史研究ということの虚しさを痛感しますねぇ。
明治7年から昭和23年まで、今日、4月3日は祭日でした。
以前だったらお休みできたのですねぇ。
悔しい。
初代天皇である神武天皇の忌日ということで、神武天皇祭と呼ばれていたそうです。
この日、かつては現役の今上陛下は奈良の橿原神宮に詣でることを慣例にしていたそうです。
嘘か真か、没年は紀元前586年と伝えられますから、ずいぶんべらぼうな話です。
実在したかどうかすら疑わしい天皇ですが、わが国民は古事記や日本書紀に伝えられる神話をわが国がわが国たるための物語として受け入れ、それによって国柄が形成されていったものと思われます。
今も、先帝とその3代前の天皇と神武天皇の忌日には、宮中で祭祀が行われているそうです。
そしてもちろん、橿原神宮をはじめとする全国の神武天皇を祀る神社ではこの日に祭祀を行っています。
記紀には、古代、120歳を超える天皇が何人も登場し、これが古代の天皇はフィクションだとする説の根拠の一つになっていますが、中国の古い歴史書によれば、わが国ではかつて、半年に一つ年齢を加算する風習があったとのことで、そうであれば130歳は65歳ということになり、当時としては長生きにしても、あり得ない年齢ではないことになります。
だから神代の天皇は実在した、と言い張るつもりはありませんが、実在した可能性は否定できないと思います。
もちろん、その頃は天皇という称号は存在せず、スメロギ、スメラミコト、オオキミなどと呼ばれていたそうです。
中華帝国の朝貢国となって中国皇帝から王の称号を授けられることを潔しとせず、スメロギは中国皇帝と同等あるいはそれ以上の存在であることを明らめるため、後に天皇という偉そうな称号を考え出したわけです。
聖徳太子が有名な、日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙無きや、という国書を隋の皇帝に送った際、隋の皇帝は日が昇るとか沈むとかいう言葉には反応せず、二人ともに天子という、本来中華帝国皇帝にしか許されない称号を使ったことに激怒したと伝えられます。
最近のわが国は中韓の顔色をうかがって大人しくしていますが、聖徳太子の時代も、元寇の時も、朝鮮出兵の時も大日本帝国時代も、一貫して誇り高く、傲慢な態度を貫いていたのですね。
しかし、国民性はそう簡単に変わるものではありません。
一朝ことあらば、わが国民は一夜にして誇り高く傲慢な態度を取り戻し、誰が相手でも臆することなく対峙するものと私は確信しています。
楽しみや喜びが、必ず痛みを伴うものなのだとしたら、私たちは何を楽しみに生きれば良いのでしょうね。
私のお気にりのバンド、サンタラに、「joy & pain」という意味深長な曲があります。
joy(楽しみ)とpain(痛み)は、いつも一緒の仲良しの双子という設定で、ブルージィに歌い上げてみせます。
両面観ということが大事だという人が大勢います。
物事には良い面と悪い面があり、その両方を覚悟して見据えよ、ということでしょうか。
そしてまた、白黒はなく、世の中は灰色でできているのだ、とも。
私の思考はわりと単純で、良い物は良い、悪いものは悪いと、白黒をつけたがる癖があります。
それはむしろ欧米やイスラム社会などの一神教の世界に見られる考え方で、わが国や東洋の国々では諫められるべき思考パターンです。
私もまた、明治以来の西洋崇拝に陥った愚かな日本人の一人だったということでしょうか?
それでいて、多様性を認めることの重要さを、このブログでもたびたび述べてきました。
私の思考は分裂気味なのかもしれませんね。
他人には多様性を認めろと説きながら、おのれのこととなると途端に白黒つけずにいられないという具合に。
しかしそれならそれで、私は構わないのではないかと思うのです。
なんとなれば、そのような分裂もまた、多様性の中の一個であって、当然尊重されるべきものだからです。
三つ子の魂百まで、とか申します。
私の分裂がもって生まれたものならば、堂々と貫くしかない、と思わずにいられません。
 |
Joy & Pain / 好き |
| 田村キョウコ,砂田和俊 | |
| エピックレコードジャパン |
3月2日を迎えましたが、今週末は土日とも冷たい雨で、冴えない感じです。
リビングでひたすらごろごろするよりほか、仕方がありません。
最近土曜日の夕方、BSで「刑事コロンボ」を放送していて、観るともなく観ています。
 |
刑事コロンボ 完全版 コンプリートDVD-BOX |
| ピーター・フォーク | |
| ジェネオン・ユニバーサル |
 |
刑事コロンボ コンプリートDVD-BOX |
| ピーター・フォーク | |
| ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン |
 |
刑事コロンボ コンプリート ブルーレイBOX [Blu-ray] |
| ピーター・フォーク,ジョン・カサヴェテス,ベン・ギャザラ,ジーナ・ローランズ,アン・バクスター | |
| ジェネオン・ユニバーサル |
ストーリーは基本的に毎回一緒で、「水戸黄門」みたいなものです。
 |
水戸黄門DVD-BOX 第一部 |
| 東野英治郎,杉良太郎,横内正,中谷一郎,岩井友見 | |
| エイベックス・エンタテインメント |
わりと社会的地位の高い人が用意周到に殺人を犯し、コロンボが追い詰めていって最後はお縄になる、というお話。
「古畑任三郎」はまんま「刑事コロンボ」のパクリと言って良いでしょうね。
 |
警部補 古畑任三郎 1st DVD-BOX |
| 三谷幸喜 | |
| ポニーキャニオン |
社会的地位が高いだけあって、最後、犯人は潔くお縄につきます。
英国軍では、戦闘の際、指揮官をはじめとする将校は伏せる時、最後に伏せ、立ち上がる時は最初に立ち上がると伝えられます。
社会的地位が高い者には重い義務が課せられているということで、それを放棄するのは卑怯者であり、名誉を重んじる英国軍人はそれを守り、ために現場指揮官に任ぜられることの多い大尉クラスの死亡率が突出して高いのだとか。
英国で将校となる者はイートン校出身者が多く、第二次大戦での英国の勝利を称して、イートン校の勝利と呼ぶそうです。
日本軍はどうだったんでしょうねぇ。
日本軍の下士官兵は世界一勇猛果敢と恐れられたそうですが、将校はイマイチ評価が低いようです。
日本の職場でも同じことがいえそうです。
管理職はふんぞり返って文句を言うだけで、下の者の頑張りや創意工夫に頼っているような感じがします。
トップ・ダウンを嫌い、ボトム・アップを良しとするわが国の官僚組織はより一層、そういった慣習が強いのではないでしょうか。
貴人の義務を放棄しているように見受けられます。
ボトム・アップであっても、責任の所在は上の者にあるわけですから、貴人の義務をきちんと果たすのが当たり前の社会に変革したいものです。
最近、私のお気に入りの歌い手は、SEKAI NO OWARIです。
皮肉めいたひねりの効いた歌詞を、スタイリッシュに歌って見事です。
一番のお気に入りは、「不死鳥」。
ロボットの女性と恋に落ちた男の歌で、ロボットが不死身であることから、自らも永遠の命を得ることを望んでみたり、彼女にいずれ死が訪れることを望んでみたり。
それは切なくも美的な歌詞です。
ライブでは意外にも元気いっぱいで、不思議な感じがします。
また、「天使と悪魔」という曲では、正義を生み出した神様聞こえてますか、あんなものを生み出したからみんな争うんだと歌ってみせます。
いかにも相対主義的な日本人らしいものです。
かなり日本人的な感覚をスタイリッシュに歌う姿は、好感が持てます。
こういう人々が人気を博すあたり、近頃の若者も捨てたものではありません。
知らず知らずのうちに、日本的な価値観を身につけているということでしょうねぇ。
この国に生まれ育てば、特別の教育を受けなくても、自然に仏教的無常観、神道的清明心、儒教的道徳感などを身に付けるものと思われます。
それが伝統であり風土というものなのでしょう。
したがって、私たちには理解不能なイスラム原理主義や、お隣、韓国の滑稽としか思えない感情的な行動もまた、彼らの伝統と風土が産み育てたものと考えなければなりません。
彼我の間に優劣はなく、ただ相違があるだけです。
私たちは相違があることを肝に銘じて、違いを尊重する態度を涵養せしめねばなりますまい。
建国記念日の朝、またもや雪がちらついています。
昨日は雪で通勤に難儀したので、晴れるか大雨か、どっちでもいいから溶けて欲しいと思っていたのですが、なんだか振り出しに戻ってしまった感じです。
建国を祝う気もしぼみます。
明治初期に定められた紀元節が始まりの建国記念日。
皇紀元年の一月一日を太陽暦に換算した日なんだそうですね。
この日、初代の神武天皇が即位あそばし、万世一系の皇統が始まったというわけです。
神武天皇はそのまま天照大神の子孫ですから、誠におめでたい日と言うべきで、国民こぞってこの日を寿ぐのが当然ですが、たかだか天候不順のせいでそんな気が失せるとは、私には愛国心というものが欠けているようです。
恥ずかしながら。
本当のところ、今日が神武天皇の即位の日にあたるのか、そもそも神武天皇とは実在したのか、古代史家の間では疑問視されていることは知っています。
しかし私は、それが本当なのかどうかについて、さしたる興味を持っていません。
それを仮にでも本当だと信じ、わが国の来し方を愛でるための物語としての機能は、今も健在だからです。
「古事記」や「日本書紀」に綴られた神話から古代史にいたるわが国草創期の物語、よくできていると思います。
 |
新版 古事記 現代語訳付き (角川ソフィア文庫) |
| 中村 啓信 | |
| 角川学芸出版 |
 |
日本書紀 5冊 (岩波文庫) |
| 坂本太郎 | |
| 岩波書店 |
少なくともこのような物語を持つ国に生まれたことは、奇跡とも言うべき幸運であるに違いありません。
わが国の人々には、今日くらい、自分たちがいかに幸運か、思いを致していただきたいものです。
昨夜、母と電話で話しました。
なんでも姪が中学受験で第一志望校に合格したとのこと。
渋谷に建つ私学の女子大学附属中学校です。
本当に良かった。
兄は姪を「勉強が出来ない」と言っていましたが、そうでもなかったようです。
これで普通にしていればその女子大に進めるはずです。
楽しい学校生活を送って欲しいものです。
また、私立の小学校に通う甥は、母校のパンフレットのモデルを務めることになったそうです。
甥はわが一族の特徴をすべて備えた端正な外見ですからねぇ。
年頃になったらもてちゃってしょうがないんじゃないでしょうか。
おのれの若い頃を思い出しますねぇ。
これまためでたい。
子どもがいないおじさんたる私は、わが事のように喜ばしく感じます。
2人とも、おめでとう。
おじさんはうれしいぞ。
ホーキング博士が衝撃的な論文を発表したそうです。
すなわち、光などが抜け出せなくなるような、今までの概念どおりのブラックホールは存在しない、というもの。
他の宇宙物理学者はこの意見に懐疑的なようですが、なかなかエキサイティングな論ですねぇ。
ホーキング博士が考えるブラックホールとは情報とエネルギーを消滅させるのではなく、新しいかたちでまた空間に開放するというもの。
古典的な理論では、エネルギーと情報はブラックホールの事象の地平面を抜け出せないと主張していますが、量子物理学はそれが可能であると示唆されるというパラドックス=ブラックホール情報パラドックスを取り上げ、下の図のようなものをブラックホールとしてイメージしているそうです。
私は難しい宇宙物理学のことは全然分かりませんが、どこか仏教の考えと似ているような気がします。
般若心経には、不生不滅、という文句が出てきます。
 |
般若心経・金剛般若経 (岩波文庫) |
| 中村 元,紀野 一義 | |
| 岩波書店 |
 |
現代語訳 般若心経 (ちくま新書 (615)) |
| 玄侑 宗久 | |
| 筑摩書房 |
悟りの境地を表す言葉とも言われますが、私はもっと単純に、現実社会に存在するものは生まれることも滅びることもなく、水が水蒸気になったり氷になったりするように、変化していくだけだ、と解釈しています。
情報とエネルギーを消滅させるのではなく、変化させて再び放出するとは、まさしく不生不滅と同じではありますまいか。
仏教が辿り着いた地平が、最新の宇宙物理学や量子力学に近付くのだとしたら、人間の知見は何千年も前から変っていないということでしょうか?
私は寺で生まれ育ちましたが、仏教に関する知識は中途半端でいい加減なものです。
出家するような発心を起こすことは未来永劫無いと思いますが、もう少し体系的に仏教の深みを学んでみたいと思わせるホーキング博士の論考でしたねぇ。
ジェンダー教育については、賛否両論があり、時には行きすぎた教育も行われているようです。
元々ジェンダー研究は、男女の社会的性差及びそれに伴う男女差別を研究し、男女同権を目指すものであったはずです。
先ごろ日教組のジェンダー教育実践例の報告で、首を傾げたくなる事例が報告されました。
例えば小学校1年生の授業で、男女の全裸のイラストを黒板に張り、それを基に男女の肉体的性差をおしえたとか、桃太郎の鬼退治の童話を、桃から桃太郎と桃子の男女が生まれ、鬼退治には桃子だけが出向き、桃太郎はこれを拒絶したというストーリーに変えて教えたり。
こうなると男女同権を目指していたはずのジェンダー研究が、男女逆転して女性優位の社会を目指しているようにも感じられます。
私はかつてお茶の水女子大学で契約事務をしていたことがありますが、この大学にはジェンダー研究センターというのがあり、おっかないおば様たちがせっせとイチャモンをつけに来ていました。
予算規模が小さくて楽なはずのジェンダー研究センター担当は、おば様たちの怖ろしさのせいで、最も嫌われるお役目とされていましたね。
とにかくヒステリックな教員が多いのですよ。
それはさておき。
6つか7つの子どもに全裸のイラストは、子どもの発達段階を無視したものとしか思えませんし、童話の改竄にいたっては、童話を教える意味を履きちがえているとしか思えません。
いい加減にしなさい。
男らしさや女らしさをことさらに強調する必要はありませんが、男女間には知力・体力などで明確な差異がありますね。
一般的に男の方が力が強いし勝負事にも強いし瞬間的な判断力も優れていると思われます。
女性は一般的に男よりも細かいことによく気が付き、争いを好まず、表面的には円滑な人間関係を築くことが得意なように見受けられます。
それらの差異が存在することはきちんと認めて、権利義務などの社会的役割を平等にするというのが現実的でありましょう。
そうでなければ、男女は恋に落ちるか永遠に対立するか、二つに一つになってしまうような気がします。
世の中には暇な会社があるもので、入社年代別の、入社時と現在の幸福度を出身大学別に尋ねるアンケートを行ったそうです。
私は1992年に就職しましたので、1990年代入社組の一覧を以下に掲載します。
男性では、入社時も現在も早稲田大学がトップ。
東京大学じゃないんですね。
ただし、入社時36ポイントから、現在18ポイントに半減しています。
それでもトップなのですから、分からないものです。
そう言えば私の周りの早稲田大学出身者は、他の大学出身者に比べ、やたらと早稲田大学卒であることを言いふらしたり、逆に他人の学歴を聞いてきたりします。
嫌らしいですねぇ。
概ね偏差値の高い有名大学か、偏差値はそこそこでも巨大なマンモス校出身者が上位を占めているようです。
もちろん、幸福度を尋ね、しかる後出身大学を尋ねるわけですから、恣意的な調査ではなかろうと想像します。
幸福感と言うのは人それぞれですから、一概に比較はできません。
上昇志向の人であれば、早い出世や高い収入がそのまま幸福感に繋がるでしょうし、仕事は生活の糧を得るための苦役と観念し、趣味の世界に生きる人はなるべく気楽な仕事に就いて、自由時間が多いことに幸福を感じるでしょう。
私は明らかに後者です。
後者の場合、出身大学はほとんど意味をもたないでしょうね。
面白いのは、東京では偏差値が高くても、男性の場合ミッション系の名前がほとんど登場しないこと。
上智とか青学とか。
なんででしょうねぇ。
関西では上位に食い込んでいるのに。
キリスト教風の教育が合わないんでしょうか?
私も国立大学や国立博物館、国立研究所などの高等教育機関に勤める身。
このアンケート結果から一定の有意な結論を導くのは難しいと思いますが、教育行政に携わる者として、興味深い調査結果ではあります。
各年代の入社組の調査結果を仔細に眺め、当時の社会情勢や現代のそれを勘案して規則性を考えてみることは、楽しい作業になりそうです。
1960年代、主に先進国で、学生運動の嵐が吹き荒れました。
70年代には、その失敗から、ニュー・エイジ運動などが起き、盛んにLove &Peaceということが叫ばれましたね。
 |
ニューエイジ・ブック―新しい時代を読みとる42のニュー・パラダイム |
| C+Fコミュニケーションズ | |
| フォー・ユー |
 |
ニューエイジムーブメントの危険 |
| 尾形 守 | |
| プレイズ出版 |
直訳すれば、愛と平和。
なんとも素晴らしい、高邁な理想です。
それが実現すれば、人類は新たな地平にたどり着くことができるでしょう。
しかし、猿の子孫たる人類には困難なことであったようです。
世界を支配しているのは、力。
軍事力だったり経済力だったりのハードと、文化やスポーツなどのソフト、両方の力です。
そして力を持つ者が考える正義がそのまま正義となり、それに反する者は悪と見なされ、場合によっては掃討の対象となります。
それによって、世界の平和は保たれます。
いわば、Love &War=愛と戦いですね。
かつてわが国は、大東亜共栄圏、五族協和、八紘一宇など、白人による植民地支配の打破という高邁な理想を大義として、言わば恒久平和を目指して戦い、力及ばず敗れてしまいました。
誠に残念なことです。
しかし、Love &Warの法則に従い、わが国はその後70年もの平和を享受することになりました。
もちろん、恒久平和ということは考えられません。
例え千年間平和が維持されても、その翌年に戦争が勃発するかもしれません。
重要なのは、彼我の総合的な力の差を見極めて、もっとも平和を維持できる方法を永遠に、毎日模索し続けるしかありません。
面倒なことですが。
現実としてLove & Warが世界平和の基本だとするならば、一体正義というのは何者なのでしょうね。
善と悪、光と闇、天使と悪魔。
対立する概念があり、一方を懲らしめることでしか平和を維持できないのなら、悪が悪であり、闇が闇である理由は、敗れたという事実しかありはしません。
絶望的な考えではありますが、世界は絶望的に出来ているという冷厳な事実を受け止め、Love & Warが世界の平和を維持せしめているということを認めなければ、社会を構成する大人として、世界平和に貢献することは不可能でしょうね。
それにつけても厭な社会です。