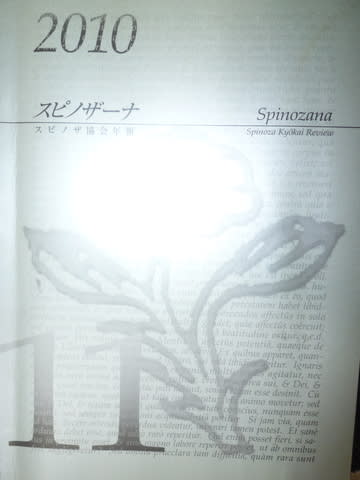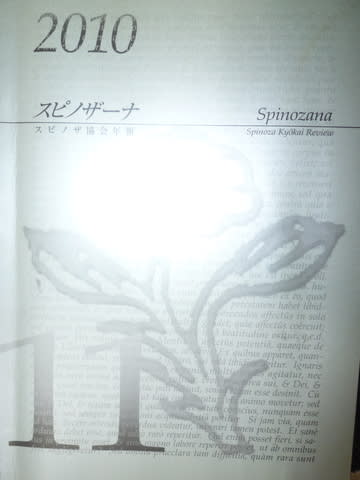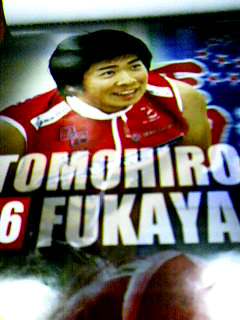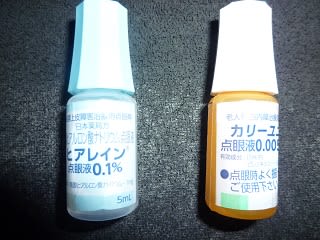スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。
10月31日の京王閣記念の決勝 。並びは新田‐佐藤の福島,藤井‐柴崎の中部,中釜‐東口の近畿,晝田‐香川の瀬戸内で北井は単騎。新田祐大選手 は4月の高知記念 以来の優勝で記念競輪11勝目。京王閣記念は初優勝ですが2015年の日本選手権 を京王閣で優勝しています。ここは力では北井と新田が上位ですが,北井は単騎になりましたので新田が有利でした。北井が単騎でかましていったのは意外でしたが,そのときの位置の関係から追うことができたので,展開も有利に運べました。北井はかますにしてもタイミングがあまりに早かったように思います。ただ,もしも追い掛けてくるのが新田でなかったら,あれだけ早い段階で捲られることはなかったかもしれませんので,作戦として理解できないものではありません。道中の並びがかましていくにはあまりよくなかったということになるでしょう。ライプニッツ Gottfried Wilhelm Leibnizに関してはこれまでに何度も言及してありますので,今回はこれだけにしておきます。スピノザーナ11号 』はこの後,平尾昌宏の「メンデルスゾーンとスピノザ主義の水脈」,後藤正英の「スピノザ『神学政治論』からメンデルスゾーン『エルサレム』へ」と,メンデルスゾーンMoses Mendelssohnに関連する論文が続いています。スピノザとの関連でメンデルスゾーンが主題になっているものは,僕が知る限りでそう数が多いわけでなく,これらは希少でありかつかなり有益なものであるといえるでしょう。ただし僕はメンデルスゾーンの思想についてはほとんど知るところがないので,メンデルスゾーンについて論考できる力は持ち合わせていません。まず最初に,なぜ事情がそのようになっているのかということを説明しておきます。汎神論論争 との関連を抜きにして考えることができません。ただ,この論争にメンデルスゾーンが参加するとき,それはメンデルスゾーンの本意であったというより,止むを得なかったという側面があるように見受けられるのです。いい換えれば,メンデルスゾーンはある積極的な理由があって汎神論論争に参加したわけでなく,消極的な事情から汎神論論争に参加せざるを得なかったという面があるように思われるのです。しかしこれは僕にそのように見えているというだけであって,実際にはそうでなかったかもしれません。このような意味で,メンデルスゾーン自身がスピノザの哲学をどのように解していたのかという研究は,貴重なものですし,また有益なものとなってきます。仮に汎神論論争に参加したこと自体はメンデルスゾーンにとって本意ではなかったのだとしても,メンデルスゾーンがスピノザの哲学と触れたとき,そこに積極的なものが何もなかったということはあり得ないのであって,その積極性が具体的にどのような事柄であったのかということは,様ざまな角度から検証されるべきことであろうと僕は考えます。つまりこの点では,汎神論論争の当事者としてのメンデルスゾーンという観点だけに注目するべきではないのです。
弥彦競輪場 で争われた昨日の第32回寛仁親王牌の決勝 。並びは小松崎‐佐藤‐渡部の福島,古性‐南の大阪,犬伏に諸橋で和田と河端は単騎。福井記念 以来の優勝。ビッグは6月の高松宮記念杯 以来の7勝目。寛仁親王牌は初優勝。このレースは脚力では古性が断然というメンバー構成になりましたので,あとは位置取りがどうなるかがポイント。福島ラインの後ろを回り,だれも福島ラインを抑えに来なかったのでそのまま福島ラインが先行するという展開は,このラインの番手の佐藤にとって最高でしたが,このラインを追走していた古性にとっても悪いものではありませんでした。犬伏は自分が勝てるところから発進したということだったのでしょうが,それまでに何も動きがありませんでしたので前に追いつくところまで至りませんでした。これは厳しくいえば,自分の脚を過信しすぎていたということになるでしょうし,作戦負けともいえるでしょう。現実的本性 actualis essentiaとBの現実的本性は異なります。このことも第三部定理二 から明らかです。この定理Propositioによれば事物と事物の本性は一対一で対応し合うことになっています。このことは当然ながら事物の現実的本性にも適用されます。したがってAの現実的本性とBの現実的本性が一致するということは,AとBが同一人物であるということを意味しなければなりません。これはAとBというふたりの人間が存在するという前提に反します。したがって,Aの現実的本性とBの現実的本性は異なるのです。第三部定理七 に一致するということになるのです。よって,ホッブズThomas Hobbesは生命を維持するために力を行使することが自然権jus naturaeを行使することだといっていますが,AもBもその力を行使していることになります。つまり,生命を維持するということを,単純に生命を永らえることであると解することはできません。少なくとも存在するということが力の発現であるということを肯定するaffirmare場合には,力を維持するということが生命を維持するということと同じ意味になるので,文字通りに生命を維持するというように解釈することはできないのです。
小田原競輪場 で開催された昨日の小田原城下町音頭杯の決勝 。並びは宿口‐河野‐磯田の関東,北井‐大塚の神奈川に大森で柴崎と山本と久田は単騎。京王閣記念 以来となるGⅢ3勝目。このレースは北井が前受けして,後方からの動きがなかったので単調なレースに。単騎の選手が動けなかったのは,北井がかましを警戒して早い段階から後ろの動きを封じたためではあるのですが,そのために北井はオーバーペースとなってしまい,宿口の捲りを許したというレースになりました。一列棒状となっている間はそれほどペースを上げなくてもかましには対応できる筈なので,北井が負けたのは自滅という印象。4番手を確保できていたことが宿口の勝因になるでしょう。イエレス Jarig Jellesに宛てた書簡というのは書簡五十 のことです。この書簡の中でスピノザは,ホッブズThomas Hobbesとの間にある国家論の相違について語っています。神学・政治論 Tractatus Theologico-Politicus 』を読んでいて,その読後の感想として,剣の柄までぐっさりとやられてしまったということばを洩らしたとされています。『神学・政治論』に書かれているほど大胆に書く勇気が自分にはないとホッブズは感じたようです。ただこれはその大胆さに驚いたというほどのことであって,必ずしもホッブズがスピノザの国家観に同意したというように解する必要はないでしょう。ただ,ホッブズがスピノザの国家論を全面的に否定するnegareということもまたおそらくないのであって,部分的にスピノザとホッブズの国家観に共通する部分があるのは間違いありません。
久留米競輪場 で開催された昨日の熊本記念の決勝 。並びは新山‐菅田‐永沢の北日本と松岡‐嘉永‐中本‐塚本の熊本で郡司と山田は単騎。共同通信社杯 を勝っていますが記念競輪は初優勝。このレースは久留米での開催とはいえ地元といえる熊本勢が4人ということで,松岡の先行が有力。分断もなさそうなので最有力候補は番手の嘉永。脚力上位は郡司と新山ですが,ラインが4人なのでそのふたりよりも嘉永の番手の中本が優勝候補の2番手ではないかと考えていました。結果的に僕が考えていたような結果となりましたので,4人でラインを組むことができたということが大きかったといえるでしょう。第二部定理七備考 で,延長Extensioの様態modiとその様態の観念ideaは同一物であるとスピノザはいっているからです。延長の様態は,無限様態modus infinitusを除けば物体corpusを意味しますので,物体とその物体の観念は同一物であるとスピノザはいっていることになります。第三部定理二 は,延長の属性Extensionis attributumと思惟の属性Cogitationis attributumが実在的に区別されるということを前提として証明されているといえるからです。第一部定理五 は,AとBとを区別することができないのであれば,AとBは同一物であるということを前提として証明されています。これは逆に,AとBが区別できるのであれば別のものであるといっているのに等しいといわなければなりません。つまりスピノザはこのことも認めているのです。同一個体 であるという意味だと解釈するのです。
1日の豊橋記念の決勝 。並びは新山に稲川,川口‐岡本の中部,町田‐松本‐香川の瀬戸内で,山田と荒井は単騎。国際自転車競技支援競輪 を勝っていますが,記念競輪は初優勝。このレースは新山の脚力が断然上位。対して瀬戸内ラインは二段駆けもあり得るという並びで,作戦で対抗するという図式。松本が町田との車間を大きく開けて,番手から出るのではなく新山を牽制するという形になりました。この牽制が大きすぎたために失格となりましたが,これは松本がどの程度まで牽制をすればよいのかが分かっていなかったということだと思います。町田はそれで恵まれることになりましたが,後味としては悪いレースになってしまったように思います。第二部定理七 に依拠する限り,平行論 を採用しようと同一説を採用しようと,スピノザの哲学の解釈に大きな間違いを生じさせるものではありません。それでも僕が同一説を斥けて平行論を採用するのは,形而上学的な理由によります。その基礎が第一部公理一 です。この公理 Axiomaでいわれているのは,自然 Naturaのうちに存在するのは実体substantiaあるいは実体の属性attributumであるか,そうでなければ実体の変状substantiae affectioすなわち様態modiのどちらかであるということです。第一部定理四 にあるように,ふたつあるいは複数の事物は実体あるいは同じことですが属性の相違によって区別されるか,様態としての相違によって区別されるかのどちらかでなければなりません。実体ないしは属性と様態だけしか存在しないのですからこれは当然です。このとき,実体あるいは属性の相違によって区別されるのであればその区別 distinguereは実在的区別 といわれ,様態としての差異によって区別されるのであればその区別は様態的区別 といわれるのが基本です。
昨日の松阪記念の決勝 。並びは菅田‐新田の北日本,郡司に岩津‐坂本の岡山,浅井‐皿屋の三重,山田‐中村の九州。富山記念 以来の優勝で記念競輪18勝目。松阪記念は初優勝ですが,2019年の共同通信社杯 を当地で勝っています。このレースは菅田が先行するということを郡司が読んでいたような立ち回り。3番手が最高でしたでしょうが,5番手ならば捲ることができるとみていたのでしょう。新田は郡司を待って発進しようとしたのですが,菅田がすでに失速してしまっていたため,結果的に無抵抗のような内容に。菅田が失速しかけたところで郡司を待たずに発進するか,もっと菅田との車間を開けておくかするべきだったのではないでしょうか。浅井は前を回ることを選択したので,場合によっては番手への飛びつきも考えているのではないかと予想していたのですが,こちらは思い描いていたのと異なった展開になってしまったのではないかと思われます。第二部定理四八 の様式でこの人間の精神のうちに生じるのです。つまりそれはたとえばZを肯定する意志作用を起成原因とするのです。しかしこのZを肯定する意志作用もまたこの定理Propositioの様式に沿って説明されなければなりません。この関係が無限に続いていくことになります。よって,どこまでいってもこの人間の精神の自由意志に辿り着くことはできません。もしもこれを否定するのであれば,この意志作用の起成原因を辿っていけばどこかで第一原因causa primaに到着することができるといわなければなりませんが,これは僕が河井の主張を観念について否定したのと同じ論理によって否定されます。観念と意志作用は同じものなのですから,観念についていわれ得ることは意志作用についても妥当しなければならないからです。
第39回共同通信社杯の決勝 。並びは渡辺‐深谷の静岡,三谷‐南の近畿,佐々木‐清水‐隅田の瀬戸内で新山と嘉永は単騎。松戸記念 に続いて連続優勝。ビッグは2014年のサマーナイトフェスティバル 以来となる6勝目。共同通信社杯は初勝利。青森では2016年 と2017年 に記念競輪を連覇しています。競輪はラインができた方が有利なのですが,このレースはラインの前を走る選手より単騎のふたりの方が脚力は上なので,予想が難解でした。新山は結果的にいえばかましていくタイミングが早く,もう少し静岡ラインを追ってから発進した方がよかったのかもしれませんが,そうすると嘉永が捲ってきて捲るタイミングを逸するということもあり得ますので,致し方なかったのかもしれません。深谷は嘉永をしっかりと止めてから新山を追っていき,突き抜けていますから内容は文句なし。番手での走りというのに慣れてきたという面もあるように感じました。第四部定理三七備考一 のこの部分でいスピノザがいいたいのは,神 Deusを認識するcognoscere限りにおける僕たちから生じるすべての欲望cupiditasと行為について,それを一般的にいわれている宗教心religioという語と関係づけるということではありません。そうした欲望および行為の源泉を宗教心というということなのです。したがって,いってみればこれは『エチカ』における宗教心の定義Definitioに類することなのであって,宗教心とは,現実的に存在する人間が神を認識する限りにおいて生じる欲望および行為の十全な原因causa adaequataであるとか,そうした欲望および行為の原因となる能動的な感情affectusであるということなのです。
立川記念の決勝 。並びは新山‐守沢の北日本,真杉‐森田‐平原‐佐々木‐高橋の関東で北井と犬伏は単騎。知性 intellectusが円の真の観念idea veraを有するのに資する命題です。実際にこの命題でいわれていることをなすことによって,それをなした人間が円の形相的本性essentia formalisを正しく認識するcognoscereことがあり得るということは僕は否定しません。だからそのようにして実際に円を描いてみることが,知性が円を正しく認識するために無益であるとはいいません。しかしこの命題が知性が円を正しく認識するのに資するというのと同じ意味で,そうした認識cognitioに資するということはできないのです。これは一般に円を描くことすべてに妥当する事柄ですから,コンパスを用いて正確な円を描いてみる場合も成立します。つまりコンパスを用いて正確な円を描くことは,知性が円の真の観念を有するために無益であるとは僕はいいませんが,そのことに資するともいえないといいます。第二部定理一七 から明白であるといえるでしょう。これは円の表象像なのですから,その円の真の観念であるどころか誤った観念idea falsaです。そしてこうしたことが生じるということは,すでにこの人間が円の真の観念を有しているかいないかということと関係ありません。第四部定理一 がいっているのはそういうことだからです。
向日町記念の決勝 。並びは坂井に和田,北井に佐藤,山田‐村上‐川村の京都,太田に尾形。無限知性 intellectus infinitusのうちではあらゆる観念ideaが神Deusと関係させられます。よって無限知性のうちにある限り,あらゆる観念は真の観念idea veraです。これに対して,観念が限定された知性,たとえば現実的に存在する人間の精神mens humanaのような有限なfinitum知性のうちにあるとみられる限りでは,神と関係させることができる観念もあるのですが,神と関係させることがその知性によっては不可能な観念もあります。したがって,ある観念がたとえば現実的に存在する人間の知性のうちにあるとみられる限りでは,誤った観念idea falsaもあるといわなければなりません。しかしそうした誤った観念も,無限知性のうちにあるとみられる限りでは神と関係させることができるので,その場合は真の観念となるのです。おそらくこうしたことが第二部定理三二 の背後にはあるのであって,これがスピノザがこの定理Propositioに託したことであると僕は解します。いい換えれば,このように河井の主張を修正するということです。
29日の松戸記念の決勝 。並びは平原‐諸橋の関東,岩本‐和田の千葉,川越‐深谷の南関東に大森,岩谷‐小川の福岡。大宮記念 以来の19勝目。松戸記念は初優勝ですが,2014年にサマーナイトフェスティバル を勝っています。このレースは南関東の4人が地元とそれ以外に分かれました。なので川越がどういうレースをするのかに注目していたのですが,前受けをして残り2周半から突っ張って先行というレース。番手も自力の深谷だったので,ほかのラインはほぼ何もできないというレースになりました。深谷は自力を使ったのは概ね1周ほどですから,わりと楽な形での優勝になったのではないでしょうか。最初に上昇していった岩谷の動きはやや中途半端だったように感じます。第二部定理三二 は,僕が示したような,すべての観念ideaは神Deusに関係する限りで十全adaequatumであるということを経由しても証明することができました。ところがスピノザによる証明 は,その手続きを省略しています。それは取りも直さず,スピノザがこの定理Propositioで証明したかったことが,僕が示したこと,すなわち,神に関係する限りで十全な観念idea adaequataは神に関係する限りで真の観念idea veraであるということではなかったからだと僕は考えます。つまり,本来的特徴denominatio intrinsecaからみた場合に十全な観念は,外来的特徴denominatio extrinsecaからみるなら真の観念であるということを,スピノザはこの定理によって示したかったのではなく,神に関係する限りですべての観念は真verumであるということを,直接的に,つまり観念の外来的特徴にも本来的特徴にも依拠せずにスピノザは示したかったのだと僕は考えます。第一部定理一五 によれば,あるものはすべて神のうちにあるQuicquid est, in Deo estのです。したがって,何らかの観念があるというのであれば,その観念は神のうちにあるのだといわなければなりません。そして第一部定理一八 にあるように,神は神に内在するすべてのものの内在的原因causa immanensですから,そうした観念もまた神を内在的原因として存在するといわなければなりません。第一部定理二八備考 でスピノザがそれを否定しているからですが,この否定negatioは,この内在的原因の場合にも適用されなければなりません。つまりこの定理でいわれている観念に対して神は,内在的原因であり同時に最近原因causa proximaでもあるのです。
西武園競輪場 で争われた昨晩の第66回オールスター競輪の決勝 。並びは吉田‐真杉‐平原‐武藤の関東,清水‐山田の西国,犬伏‐松本の四国で古性は単騎。宇都宮記念 以来の優勝でビッグは初制覇。このレースは残り2周を前に吉田が発進し,そのまま残り1周から真杉が番手発進。すぐ後ろが競り合いになり,この競り合いに決着がつかなかったため,真杉にはもってこいの展開になりました。関東勢の結束が導いた優勝といえるでしょう。吉田は規則に反する走行で誘導を追い抜いて先行したため失格になりましたが,僕はこれはいただけないと思います。犬伏も吉田が規則は守るという前提で叩きにいっているのですから,規則違反を覚悟で突っ張られてはレースにならないでしょう。第二部定理八備考 を記述していることは明白です。そしてこれは読者にとって有益でまた重要な情報といえます。しかし岩波文庫版の『エチカ』では,このことについて何も触れられていません。畠中はいくつかの訳注を付していますし,また本文の中にも自分自身で語句を補ったりしているのですが,この箇所では何も触れていないのです。たぶんこれには次のような理由があります。カール・ゲプハルト Carl Gebhardtが編集した,いわゆるゲプハルト版を元のテクストとして,それを邦訳しています。このゲプハルト版にはこの点に関する言及はありません。さらに,ゲプハルト版にも図が示されているようなのですが,その図ではスピノザが示している線分Dと線分Eが直交しているようです。つまりそれは岩波文庫版の図に一致しています。つまりこの部分を邦訳するにあたって,畠中はゲプハルト版に完全に依拠したのだと考えられます。
京王閣競輪場 で争われた昨晩の大阪・関西万博協賛名輪会カップの決勝 。並びは鈴木‐河村の東京,窓場-松岡の近畿,河端‐久保田‐田尾‐室井の中四国で大坪は単騎。スピノザーナ11号 』の中から,僕の関心を惹いた部分,僕が気になった部分,あるいは僕にとって有益であった部分について,それぞれ紹介し,それについて僕自身の考察も加えていきます。第二部定理八備考 について触れられています。これは個物 res singularisの形相的本性essentia formalisと現実的本性actualis essentiaの関係を,円の内部でふたつの直線が交わる点で分割される線分によって形成される矩形の面積が,相互に等しくなる例によって説明している部分です。ただしここでは,この説明によってスピノザが主に何を意味しようとしているのかということはあまり関係ありません。むしろこの説明の背景にあるものが何であるのかということについて河井は敷衍しています。
和歌山競輪場 で争われた大阪・関西万博協賛競輪の決勝 。並びは阿部‐竹山の宮城,小林‐金子‐芦沢の関東,岡崎‐古賀の近畿,立部‐中村の九州。スピノザーナ 』はすでに15号 と10号 を読んでいますから,3冊目になります。これは2011年4月22日に発行されたものです。ざっと内容を紹介しておきましょう。スピノザ「共通概念」試論 』です。この書評を担当しているのは藤井千佳世です。この本は僕も読んでいて,内容は紹介していますから,それも参考にしてください。
富山記念の決勝 。並びは真杉‐恩田の関東,北井‐郡司の神奈川に佐藤,松浦‐柏野‐小倉の中四国で浅井は単騎。小田原記念 以来の優勝で記念競輪17勝目。富山記念は初優勝。このレースも小松島記念に続いて郡司と松浦が決勝に進出。ただここは郡司には北井という強い味方がいた上,後ろも佐藤が固めることになり,圧倒的に有利でした。さすがにこのように並ばれてしまってはほかの選手たちは厳しかったろうと思います。庇ってもらったところがあったとはいえ,早い段階から真杉を突っ張って2着に残った北井は強い内容で,記念競輪の優勝も近いかもしれません。О眼科 に赴き,目薬 の処方箋を出してもらい,薬局 で処方してもらいました。
名古屋記念の決勝 。並びは新田‐守沢の北日本,渡辺‐武藤の東日本,取鳥‐桑原の山陽で,山口と南と伊藤は単騎。日本選手権 以来,GⅢは2月の伊東温泉での施設整備等協賛競輪 以来で2勝目。記念競輪は初優勝。このレースは脚力から新田と山口の優勝争いになるだろうとみていました。新田は山口より後ろの位置になり不発に終わりましたが,前受けをするのに脚を使ったことが多少の影響を与えたかもしれません。その意味では山口に捲られて2着と3着になりましたが,山陽のふたりが前を取りにいく構えをみせたのが,いい作戦だったといえそうです。山口は単騎で好結果を出すことが多い選手ですが,単騎でこれだけ走れるということは,本当はラインができればもっと強い筈だと思います。О眼科 に行って診察を受ける予定でした。ただそのために必要な保険証およびおくすり手帳 を,妹が持参していませんでした。目薬 の在庫にはまだ余裕がありましたので,診察は中止にしてそのまま帰宅しました。なお,この日に妹を迎えに行ったのは,翌日から妹が年末年始の休みに入るからです。つまり妹は年末年始は家で過ごしました。