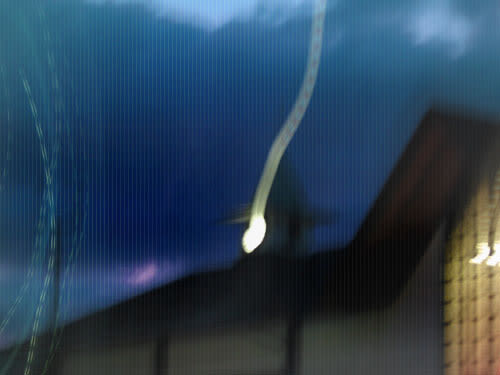アンナ・カヴァンの短編集「ジュリアとバズーカ」を読んだ。買ったわけではなく、杉並区の図書館で所蔵していることがわかったので、取り寄せてもらい、借りてきた。サンリオSF文庫から出ていたこの本は現在稀覯書になっていて、入手はなかなか困難である。ごく稀に見つけることもあるが、ただの文庫本に一万円近い値段がつくから、なかなか買う気になれなかった。同じサンリオから邦訳のある「氷」と「愛の渇き」は出版された時に買っていて、読んでいるから、これで邦訳のあるカヴァンの本は全部読んだことになる。
「ジュリアとバズーカ」は短編集だが、どの作品も同じ話という印象。命あるものへの嫌悪感と歪んだ自己愛の羅列で、ストーリーなど、ないに等しい。いや、アンナ・カヴァンの小説は、邦訳のある他の二冊の長編も含めて、全て同じ話といっていいかもしれない。アンナ・カヴァンの小説を読むということは、彼女の自伝を読むことと同義であり、その自伝は一方向のモノローグである。
晩年を精神病院で過ごしたアントナン・アルトーは「器官なき身体」という言葉で自らの到達点を夢想し、同じく精神病院で過ごしたことのあるヘロイン中毒のカヴァンは、自らの最終地点を「穢れのない真っ白な粉」の中に見た。言い方は違うが、二人の幻視していた先は、「生物としての人間からの脱却」であったと思える。しかも、感情を抱えたままで。
彼女たちは、あるいは彼らは、一体何処を目指しているのだろう。「寂しい、孤独だ」と叫びながら、同時に「ぶよぶよとした生身の」現実を拒否している。絵や写真の二次元の世界に、自分たちが存在出来たらと願っている。
だがもちろん、それは不可能なのだ。「身体の内側から綺麗になろう」とテレビから流れるコマーシャルが言っている。あるいは、「オーラを綺麗にしよう」と宗教家が言っている。そうしたものは全て、絵や写真の中にしかない、二次元の考え方だ。それはこの世界では実現しない。
おそらくそのことはカヴァンにしても分かっているのだろう。だが、その気持ちを捨てきれない。だから、死の直前まで同じ話を書き続けた。だからこそ、カヴァンの書く小説には魅力がある。それが「人をうんざりするような気持ちにさせる」という種類の魅力であっても、確かな魅力だ。カヴァンの小説を書架に収めるとき、その場所がうっすらと寒く白い場所のように思える。なぜなら、彼女の本がすなわち彼女自身の孤独であるからだ。
ところで、アンナ・カヴァンの代表的な短編集「アサイラム・ピース」は、中から数編が翻訳され、NW-SF誌に掲載されたことがあるが、一冊にまとめられたことはない。代わりに、現在ウェブ上でこの短編集から数編を、翻訳で読むことができるようだ。
アサイラム・ピース