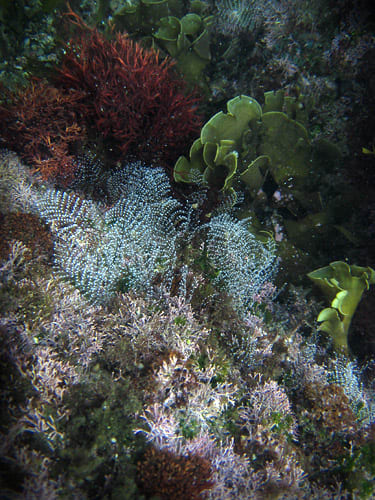青という色彩を摘んで、集めてみたい。
青という色彩は、どこか別の時間の、別の場所への入り口のような気がするから。
じっと見詰めていると、その向こうの世界が見えてくる。
そうした「青」を捜して、ひとつづつ、並べてみよう。

「青色コレクション」の最初は、「銀河鉄道の夜」にしたい。
言うまでも無く、宮沢賢治の未完の小説である。
余りにも美しい、日本の童話を代表する作品だ。
「青色コレクション」の冒頭を飾るのに、これほど相応しい作品は、僕には思いつけない。
カンパネルラが入ったという川の、その水面の揺れる青黒い色彩と、見上げた夜空の色彩を、僕は摘みたいと思う。
だが、僕の中にはそれ以外にも、三つの「銀河鉄道の夜」がある。
それらの「青」も、僕は摘まずにはいられない。
最初の「銀河鉄道の夜」は、
岩波書店からハードカバーで出ていた「銀河鉄道の夜」だ。
それは、現在流布している定本とは違う構成の「銀河鉄道の夜」で、叙情的な印象を受ける。大きく違うのは、「天気輪の柱」の章とラスト、それにブリタニカ博士が登場するという点だ。
実は、僕が始めて読んだ「銀河鉄道の夜」はこの本だった。
小学校の五年生の時、夏休みの読書感想文を書くために学校の薄暗い図書室の棚から借りて、読んだのだ。ものすごく感動したことを覚えている。だから、一生懸命に読書感想文を書いた。そう書いているだけで、小学校の図書室のことを思い出して、懐かしくなる。その頃手にした本の、一冊一冊を思い出す。
この本は、美しい本だった。図書室でそうして手にした本の中でも、特に印象的な本だった。青い色彩の中に、ペン画の銀河鉄道が描かれている。その絵が、目の奥に沁み付いて離れない。だから、僕はこの本の表紙の、青い色を摘みたい。
次の「銀河鉄道の夜」は、宮沢賢治の作品をベースにした松本零士の漫画「銀河鉄道の夜」だ。
今ではもう無くなってしまった出版社、奇想天外社から出ていた
「ヤマビコ13号」という単行本の、冒頭に収められていた。
しっとりと湿ったようなこの短編は、少年時代との別れを描いた美しい作品だった。単行本では、墨と藍の二色で刷られた冒頭部が特に美しかった。汚れている筈の空が青く見える。その幻の青さをそっと摘みたい。
最後の「銀河鉄道の夜」は、
ますむらひろし作画でアニメーション化された「銀河鉄道の夜」である。登場人物が殆ど全て猫で描かれたこの作品は、美しい色彩で彩られていた。余りにも美しいから、この作品のどこから青を摘もうかと迷うほどだ。
この作品から摘むべき青い色彩は、多分ジョバンニの毛の色なのだろうが、全編を覆うトーンの中に、深い青さがあるような気もする。