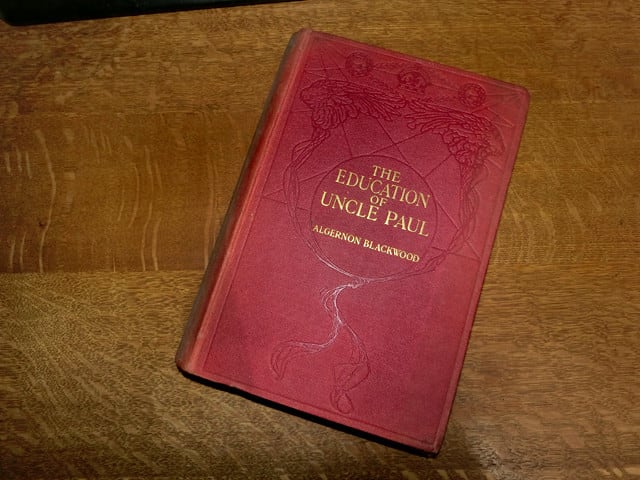「ウルフヘッド」 チャールス・L・ハーネス著 秦新二訳
サンリオSF文庫 サンリオ刊
を読む。
積読になっている本がやたらと多いサンリオSF文庫だが、少しでも減らさなければと、読んでみた。
ストーリーは、以下のようなもの。
舞台は未来の地球。核戦争が起こり、世界が壊滅状態になってからいろいろあって長い時間が流れ、ゆっくりと復興を遂げつつある時代というのが基本的な物語の背景である。主人公は、ウルフヘッドと呼ばれる一族の後継者たる青年ジェレミー。彼は「われわれの一族のだれかが大神の頭を手にして地底へと降り、大いなる悪の文化を打ち砕き、ふたたび生きて戻るであろう」という謎めいた予言の下にある一族の青年である。彼はふとしたことで見初めた女性と結婚をするが、<神々の目>と呼ばれる宇宙に弧を描いて消える星、おそらくはかつて人類が打ち上げた人工衛星だが、を見るために新婚早々でかけたところで、妻を地底人に攫われ、自分も瀕死の重症を負う。一命を取り留めたジェレミーは、負傷がもとで偶然手にいれることとなった超能力を使い、暗闇でも目が見えるという雌狼ヴァージルとともに、妻を奪還するために地底へと下ってゆく。やがてその旅は、二つに分裂した人類を再びひとつにすることとなる……
というような感じだが、正直、かなりくだらない小説だった。以前に翻訳してみた、シェーバーの「レムリアの記憶( I Remember Lemuria !)」にちょっと似ているところがある。というより、パルプフィクションによくあるフォーマットというべきか。底人の正体が、かつて核戦争の後に地下に潜って生き延びたアメリカのホワイトハウス周辺の人々であるというあたりは、なかなかブラックではあるが、ありふれた、遠未来を舞台にしたヒロイック・ファンタジーである。
このチャールス・L・ハーネスという人は、「十億年の宴」の中でブライアン・オールディスによって初めて「ワイドスクリーン・バロック」という名称が与えられて絶賛された作品「Flight into Yesterday」の著者であり、この作品の時点で、30年以上の作家歴で長編が4冊という寡作だというから、結構期待して読んだのだけれど、まあそんな感じだった。どうせなら、その「Flight into Yesterday」の翻訳が欲しかったところであるが、まあ、未だに翻訳されていないということは、推して知るべし、ということなのだろうか。
サンリオSF文庫 サンリオ刊
を読む。
積読になっている本がやたらと多いサンリオSF文庫だが、少しでも減らさなければと、読んでみた。
ストーリーは、以下のようなもの。
舞台は未来の地球。核戦争が起こり、世界が壊滅状態になってからいろいろあって長い時間が流れ、ゆっくりと復興を遂げつつある時代というのが基本的な物語の背景である。主人公は、ウルフヘッドと呼ばれる一族の後継者たる青年ジェレミー。彼は「われわれの一族のだれかが大神の頭を手にして地底へと降り、大いなる悪の文化を打ち砕き、ふたたび生きて戻るであろう」という謎めいた予言の下にある一族の青年である。彼はふとしたことで見初めた女性と結婚をするが、<神々の目>と呼ばれる宇宙に弧を描いて消える星、おそらくはかつて人類が打ち上げた人工衛星だが、を見るために新婚早々でかけたところで、妻を地底人に攫われ、自分も瀕死の重症を負う。一命を取り留めたジェレミーは、負傷がもとで偶然手にいれることとなった超能力を使い、暗闇でも目が見えるという雌狼ヴァージルとともに、妻を奪還するために地底へと下ってゆく。やがてその旅は、二つに分裂した人類を再びひとつにすることとなる……
というような感じだが、正直、かなりくだらない小説だった。以前に翻訳してみた、シェーバーの「レムリアの記憶( I Remember Lemuria !)」にちょっと似ているところがある。というより、パルプフィクションによくあるフォーマットというべきか。底人の正体が、かつて核戦争の後に地下に潜って生き延びたアメリカのホワイトハウス周辺の人々であるというあたりは、なかなかブラックではあるが、ありふれた、遠未来を舞台にしたヒロイック・ファンタジーである。
このチャールス・L・ハーネスという人は、「十億年の宴」の中でブライアン・オールディスによって初めて「ワイドスクリーン・バロック」という名称が与えられて絶賛された作品「Flight into Yesterday」の著者であり、この作品の時点で、30年以上の作家歴で長編が4冊という寡作だというから、結構期待して読んだのだけれど、まあそんな感じだった。どうせなら、その「Flight into Yesterday」の翻訳が欲しかったところであるが、まあ、未だに翻訳されていないということは、推して知るべし、ということなのだろうか。