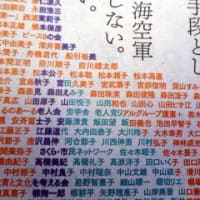開会式を見ていないので、雰囲気を伝えるドイツ記者の微妙な言い回しを間違った方向に捉えていなければ良いのですが。
最後の「選手たちが主役」というくだりは、私はやはりCOVID-19も今回は役割を大会中も大会後も果たしていく存在であり、当然大会に反対の姿勢を貫く抗議者も主役であり続ける権利と義務を持っていると思っております。
IOCと組織委・政府は黙っていても大きな顔をする存在なのですから、ほうっておけば良いと思います。彼らが大きな顔をする権利と同等の権利を市民は持っているわけですから。
***
一年遅れのオリンピックが始まる。開会式を見る限り、IOCはどうやらパンデミックから何事も学ばなかったようで、重要なメッセージを伝える機会を無にしてしまった、とDeutsche WelleのSarah Wiertz記者は伝えている。(DeutscheWelle,2021年7月23日)
開会式会場となる競技場の外ではデモ隊が開催反対を叫び、そのメガフォンを通しての声は競技場の中まで届いていた。照明が消され、開会を祝う音楽が奏でられ始めても、抗議者達の声は競技場内に明らかに届き続けていた。
選手らの入場が始まり、競技者らは手を振るもその先は観客のいないシートの列、列、列。ただ少人数のジャーナリストと、同じく少人数の大会関係者がいるのみ、そして彼らの気がねがちな拍手は確かに有った。だが歓声はなく、振られる旗もなく、競技場内の雰囲気はシュールそのものだった。
「不毛であり隔たりが残り」
開催会場の新競技場は68000人収容能力を有し、今夜は選手たちにとっては、世界中から集まった観衆からの声援で忘れられない晩になる筈だった。
実際には10人程の各国リーダーが姿を見せるだけで(リオの時には40人ほどは参列していた)、しかも目立つのはジャーナリストたちというむなしさ付きであった。
ここ数十年の開会式はテレビ画面を意識した、水膨れで、奇抜さを競う見世物に退化してきている。選手たちはいつものように場内にいるものの観客はいない。こんな出し物はなおさらに不毛に感じるし、隔たりを感じるし、そして感動もなおさらないと感じてしまう。
唯一光彩を放ったスポット(現れては直ぐに消えてゆく映像)は、大画面に映る家族の姿・友人の姿・スポーツを愛する人々の姿のコラージュだった。
「感動は何処に」
開会式と閉会式の存在価値は“感動による一体化”。作られたテレビ用画面を超えた感動を産むものは、手作りの衣装を着て、打ち融けあいじゃれ合う入場を待つ選手たちだ。
組織委はパンデミック絡みの話題を式に組み込むことが出来なかったし、彼らの得点になるようなこともしなかった。行ったことは二人の振付師と一人の作曲家を不行跡で解雇したことだった。聞こえてくる音楽の幾つかが放てきされたという事実がすべてを物語っている。
「招き猫」
何年にもわたる練習の後、選手たちはスポットライトの栄を得た。けれども式典中世界至るところから集まった彼ら青年たちが主役になり、喜び合う姿が伝わってくるのではなく、何か古く日本に伝わる招き猫のように、彼らは見えてしまっていた。
若者達の多くが競技を目の前にして感染に気遣っている。それに加えて多くの選手たちが不参加という事実が全てであり、公正公平な競技が期待されることも、世界最高水準の競技大会が期待されることもないだろう。熱狂の雰囲気は望むべきもない。
「この話の結末の筋書きは誰が書くのか?」
IOCと組織委は、COVID-19に立ち向かい挑戦している世界に勇気を送りたかった。だが実質のメッセージは異なったものだった。すなわち何時もの様に、即ち4年ごとにお決まりのやり方で、ショウを続けることに意味がある、というメッセージ。
パンデミック中を考慮して、競技者たちとスポーツに焦点を当てて、最小限の式典にすればまだ意義があっただろう。
今や舵をとるのは選手たちだ。選手の心意気でオリンピックの良き精神を高揚させる番だ。躍動する選手たちが新たな物語の作り手は我らだと自覚していくだろう。IOCではなく、COVID-19でもなく、抗議者達でもないことを。
「護憲+BBS」「メンバーの今日の、今週の、今月のひとこと」より
yo-chan
最後の「選手たちが主役」というくだりは、私はやはりCOVID-19も今回は役割を大会中も大会後も果たしていく存在であり、当然大会に反対の姿勢を貫く抗議者も主役であり続ける権利と義務を持っていると思っております。
IOCと組織委・政府は黙っていても大きな顔をする存在なのですから、ほうっておけば良いと思います。彼らが大きな顔をする権利と同等の権利を市民は持っているわけですから。
***
一年遅れのオリンピックが始まる。開会式を見る限り、IOCはどうやらパンデミックから何事も学ばなかったようで、重要なメッセージを伝える機会を無にしてしまった、とDeutsche WelleのSarah Wiertz記者は伝えている。(DeutscheWelle,2021年7月23日)
開会式会場となる競技場の外ではデモ隊が開催反対を叫び、そのメガフォンを通しての声は競技場の中まで届いていた。照明が消され、開会を祝う音楽が奏でられ始めても、抗議者達の声は競技場内に明らかに届き続けていた。
選手らの入場が始まり、競技者らは手を振るもその先は観客のいないシートの列、列、列。ただ少人数のジャーナリストと、同じく少人数の大会関係者がいるのみ、そして彼らの気がねがちな拍手は確かに有った。だが歓声はなく、振られる旗もなく、競技場内の雰囲気はシュールそのものだった。
「不毛であり隔たりが残り」
開催会場の新競技場は68000人収容能力を有し、今夜は選手たちにとっては、世界中から集まった観衆からの声援で忘れられない晩になる筈だった。
実際には10人程の各国リーダーが姿を見せるだけで(リオの時には40人ほどは参列していた)、しかも目立つのはジャーナリストたちというむなしさ付きであった。
ここ数十年の開会式はテレビ画面を意識した、水膨れで、奇抜さを競う見世物に退化してきている。選手たちはいつものように場内にいるものの観客はいない。こんな出し物はなおさらに不毛に感じるし、隔たりを感じるし、そして感動もなおさらないと感じてしまう。
唯一光彩を放ったスポット(現れては直ぐに消えてゆく映像)は、大画面に映る家族の姿・友人の姿・スポーツを愛する人々の姿のコラージュだった。
「感動は何処に」
開会式と閉会式の存在価値は“感動による一体化”。作られたテレビ用画面を超えた感動を産むものは、手作りの衣装を着て、打ち融けあいじゃれ合う入場を待つ選手たちだ。
組織委はパンデミック絡みの話題を式に組み込むことが出来なかったし、彼らの得点になるようなこともしなかった。行ったことは二人の振付師と一人の作曲家を不行跡で解雇したことだった。聞こえてくる音楽の幾つかが放てきされたという事実がすべてを物語っている。
「招き猫」
何年にもわたる練習の後、選手たちはスポットライトの栄を得た。けれども式典中世界至るところから集まった彼ら青年たちが主役になり、喜び合う姿が伝わってくるのではなく、何か古く日本に伝わる招き猫のように、彼らは見えてしまっていた。
若者達の多くが競技を目の前にして感染に気遣っている。それに加えて多くの選手たちが不参加という事実が全てであり、公正公平な競技が期待されることも、世界最高水準の競技大会が期待されることもないだろう。熱狂の雰囲気は望むべきもない。
「この話の結末の筋書きは誰が書くのか?」
IOCと組織委は、COVID-19に立ち向かい挑戦している世界に勇気を送りたかった。だが実質のメッセージは異なったものだった。すなわち何時もの様に、即ち4年ごとにお決まりのやり方で、ショウを続けることに意味がある、というメッセージ。
パンデミック中を考慮して、競技者たちとスポーツに焦点を当てて、最小限の式典にすればまだ意義があっただろう。
今や舵をとるのは選手たちだ。選手の心意気でオリンピックの良き精神を高揚させる番だ。躍動する選手たちが新たな物語の作り手は我らだと自覚していくだろう。IOCではなく、COVID-19でもなく、抗議者達でもないことを。
「護憲+BBS」「メンバーの今日の、今週の、今月のひとこと」より
yo-chan