国際アンデルセン賞受賞後の初作品。
実は1回読みでは消化不良だったので、じっくり二回読み。
なんたって、国や民族の間に持ち込まれた病気戦争(黒狼熱)が、民族ごとの食習慣の違いによって備わる免疫力が異なる(黒狼に噛まれて死に至る民族とそうでない民族がいる)ということに基づいているから、それを物語の中で説明というか解明していくのだけれど、生活の場が変わるってことは食べ物の質やら生活習慣やら育つ動物までいろんな事柄が変化するし、黒狼熱はどうやらウイルス性の病気らしいけど、そっちも変異して罹患可能性が変わっていくということも理解せねばならず、医学書みたいな様相を呈しているところもある。
さらに病気の対処法には、西洋医学的だったり漢方的だったりさらには宗教的なものまで登場する。
そんな状況の中、登場人物は多いし、国や民族の思惑も複雑に絡み合って、頭の回転をキープしないとぼーっと読んでると意味が解らなくなる。
上橋さん相当気合入れたってとこでしょうか。
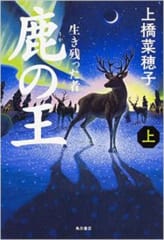

だけど二度読みしたら、そんなこんながある程度理解できて、
とてもスケールの大きな、命の渦というか意志というかそんなものが見えてくる。
人の体内を見てみれば、ウイルスやら細菌やら免疫細胞やらとさまざまな命が支えあって森の様相を呈しながら人というある個性を作りあげている。その中には淘汰される命もある。それは自然の意志だろう。
そして人は国や民族を超えて自分にあった暮らし方を選んでいく。もちろん動物たちも。きっとそこにも自然の大きな意志がある。
小さな命が集まって集まって出来上がる大きな意志。
圧巻です。
上橋菜穂子:1962年7月15日東京都生まれの児童文学作家、ファンタジー作家、SF作家、文化人類学者。
獣の奏者 守り人シリーズ 狐笛のかなた など


 漢方の空間ファインエンドー薬局HP
漢方の空間ファインエンドー薬局HP
 生理・不妊症・更年期・婦人科疾患のための漢方薬
生理・不妊症・更年期・婦人科疾患のための漢方薬
 アトピーらんど
アトピーらんど
 漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいね!クリックどうぞよろしく
漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいね!クリックどうぞよろしく
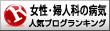 女性・婦人科の病気 ブログランキングへ
女性・婦人科の病気 ブログランキングへ
実は1回読みでは消化不良だったので、じっくり二回読み。
なんたって、国や民族の間に持ち込まれた病気戦争(黒狼熱)が、民族ごとの食習慣の違いによって備わる免疫力が異なる(黒狼に噛まれて死に至る民族とそうでない民族がいる)ということに基づいているから、それを物語の中で説明というか解明していくのだけれど、生活の場が変わるってことは食べ物の質やら生活習慣やら育つ動物までいろんな事柄が変化するし、黒狼熱はどうやらウイルス性の病気らしいけど、そっちも変異して罹患可能性が変わっていくということも理解せねばならず、医学書みたいな様相を呈しているところもある。
さらに病気の対処法には、西洋医学的だったり漢方的だったりさらには宗教的なものまで登場する。
そんな状況の中、登場人物は多いし、国や民族の思惑も複雑に絡み合って、頭の回転をキープしないとぼーっと読んでると意味が解らなくなる。
上橋さん相当気合入れたってとこでしょうか。
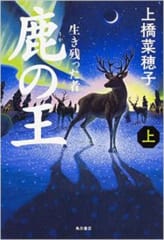

だけど二度読みしたら、そんなこんながある程度理解できて、
とてもスケールの大きな、命の渦というか意志というかそんなものが見えてくる。
人の体内を見てみれば、ウイルスやら細菌やら免疫細胞やらとさまざまな命が支えあって森の様相を呈しながら人というある個性を作りあげている。その中には淘汰される命もある。それは自然の意志だろう。
そして人は国や民族を超えて自分にあった暮らし方を選んでいく。もちろん動物たちも。きっとそこにも自然の大きな意志がある。
小さな命が集まって集まって出来上がる大きな意志。
圧巻です。
上橋菜穂子:1962年7月15日東京都生まれの児童文学作家、ファンタジー作家、SF作家、文化人類学者。
獣の奏者 守り人シリーズ 狐笛のかなた など


 漢方の空間ファインエンドー薬局HP
漢方の空間ファインエンドー薬局HP 生理・不妊症・更年期・婦人科疾患のための漢方薬
生理・不妊症・更年期・婦人科疾患のための漢方薬 アトピーらんど
アトピーらんど 漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいね!クリックどうぞよろしく
漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいね!クリックどうぞよろしく









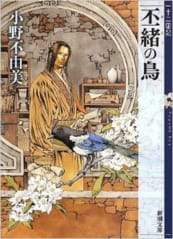
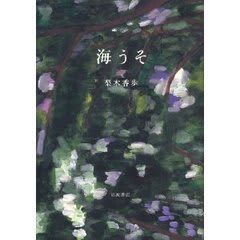



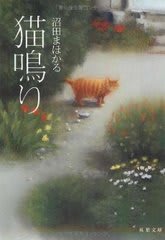


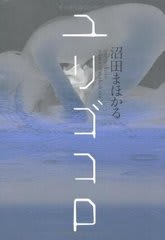



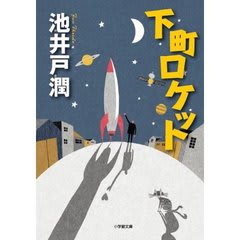

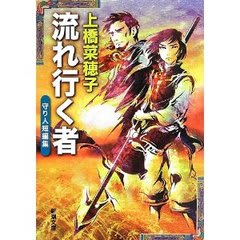 流れ行く者: 守り人短編集
流れ行く者: 守り人短編集 獣の奏者 外伝 刹那
獣の奏者 外伝 刹那  物語ること、生きること
物語ること、生きること