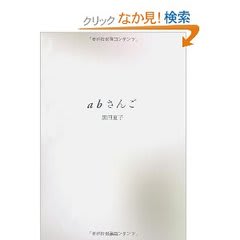先日、作家の梨木香歩さんの講演会に参加することができた。
個人的にはもっとも敬愛している作家のひとりだし、
とにかく顔写真を出さない人なので、拝顔できるだけでも私にとっては大事件。
だけど講演会って、教えていただくとか、お説教を聞くとか、
そんなのしか経験がなくて、作家の講演会ってどんなんだろうと、
不安と興味が交錯してましたが、
とりとめのないようだけど、まったりした楽しい空間、
親しい友達の話を聞いてるみたいでした。
梨木さんは自然体で親しみのある女性で、
小学校のころあんな友達がいたような気がする懐かしみもある人。
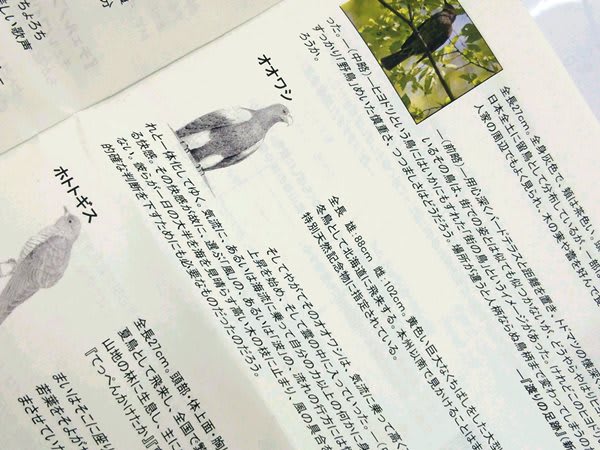
講演会のテキストは、鳥の写真とそれにまつわる梨木さんの作品の文章が。
30分もかけて梨木さんが朗読を聞かせてくれて、
すっかり想像の世界に入り込んでしまった。
梨木香歩と言えば映画化された「西の魔女が死んだ」が有名だけど、
圧倒的に「家守綺譚」が好き。
そして「f-植物園の巣穴」や「水辺にて」「鳥と雲と薬草袋」などは
動植物がどっさり登場して、図鑑を横に置いて読みたいくらい。
文章のなめらかさ、美しさはピカイチ。
個人的にはもっとも敬愛している作家のひとりだし、
とにかく顔写真を出さない人なので、拝顔できるだけでも私にとっては大事件。
だけど講演会って、教えていただくとか、お説教を聞くとか、
そんなのしか経験がなくて、作家の講演会ってどんなんだろうと、
不安と興味が交錯してましたが、
とりとめのないようだけど、まったりした楽しい空間、
親しい友達の話を聞いてるみたいでした。
梨木さんは自然体で親しみのある女性で、
小学校のころあんな友達がいたような気がする懐かしみもある人。
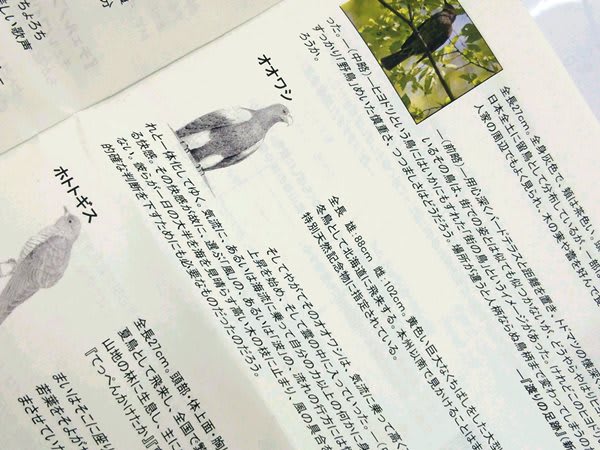
講演会のテキストは、鳥の写真とそれにまつわる梨木さんの作品の文章が。
30分もかけて梨木さんが朗読を聞かせてくれて、
すっかり想像の世界に入り込んでしまった。
梨木香歩と言えば映画化された「西の魔女が死んだ」が有名だけど、
圧倒的に「家守綺譚」が好き。
そして「f-植物園の巣穴」や「水辺にて」「鳥と雲と薬草袋」などは
動植物がどっさり登場して、図鑑を横に置いて読みたいくらい。
文章のなめらかさ、美しさはピカイチ。










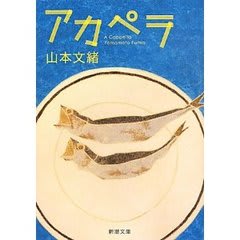
 表紙が万華鏡のようにキラキラする
表紙が万華鏡のようにキラキラする




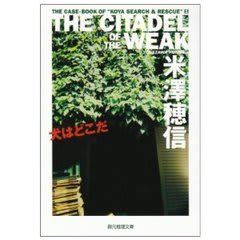


 (梨木さんのヒヨドリの表現はさんざん過ぎて面白かった)
(梨木さんのヒヨドリの表現はさんざん過ぎて面白かった)

 「毬」「タミエの花」「虹」
「毬」「タミエの花」「虹」