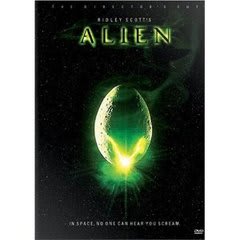
『エイリアン』 リドリー・スコット監督 ☆☆☆☆☆
昔ビデオで持っていた『エイリアン』のDVDを入手した。ディレクターズ・カットというものが収録されていて、以前から観てみたいと思っていたのである。もともと好きな映画で、シリーズの中でもこの最初の『エイリアン』が一番好きだ。恐くて、しかも美しい。憂鬱な不安の情緒が全篇を覆っている。『エイリアン2』も人気があるようだが、あれは完全なSFアクション映画で、この美しき不安の情緒はかけらもなくなっている。
今回見直してあらためて思ったのは、これは完全にゴシック・ホラーだなということだった。SFの衣装をまとっているけれども、見間違えようのないゴシック趣味に溢れた、暗く、装飾的な、憂鬱な美をたたえた映像の数々。あの中世の寺院みたいなノストロモ号のデザインや、薄暗くて湿り気を帯びた、それまでのSF映画におけるピカピカした清潔さとは似ても似つかない宇宙船の内部からしてそんな感じだが、異星の宇宙船の探索に行くあたりからそれが全開になってくる。暗くて巨大な、生物学的曲線に満ちた異星人の建築物内部は、モンス・デシデリオの絵画でも見ているような壮麗さだ。
そしてなんといっても秀逸、というか気色悪いのが、あの悪夢的なエイリアンのデザインである。エイリアンの頭部の形状が男根を模しているのは有名な話だが、つまりエイリアンは鋭い歯を持つ男根なのである。まさに悪夢から抜け出してきたクリーチャーだ。デザインしたのはスイス人の画家H. R. ギーガーで、彼の不気味な芸術は本作のヒットによって一躍世界中に知れ渡ることになった。しかしこの異様な美術に着目し、これをSFホラー映画の骨子とした制作者の判断こそ、本作を成功に導いた最大の要因だったんじゃないだろうか。
ギーガーのデザインも素晴らしいが、後に『ブレードランナー』を創り出すリドリー・スコット監督の映像センスももちろん見事だ。彼の特徴は光と影、そして水の使い方にあると思うが、本作でも主要な舞台となるノストロモ号の内部は陰影としたたる水に満ちていて、たとえばブレットが猫を探す場面では、高い天井から雨のように水が滴り落ちている描写がある。もちろん、クライマックス、ノストロモ号から脱出しようとしてリプリーが必死にあがく場面では、気が狂ったように明滅して不安を煽り立てる光、そしてその中に亡霊のように浮かび上がるエイリアンのシルエットが最大限の効果を上げている。本作の独特の美しさは、ギーガーのデザインとスコット監督の映像センスが化学反応を起こして生まれたものなのである。
ホラー映画として見ると、限定されて空間で展開されるシンプルなプロットが非常に効果的だ。外は宇宙、逃げ出すことはできない。そして一人、また一人と殺されていく。古典的なシチュエーションだ。このシチュエーションに投入されたジョーカーたるエイリアンの使い方がまたうまく、その姿がはっきり見える場面はほとんどない。ちらっと見えてはまた見えなくなる。エイリアンの全身が見えるのは最後の最後、リプリーがシャトルの中でエイリアンを発見する場面になってからだ。この「チラ見せ」がどれほど恐怖を高めているかは言うまでもない。
シンプルなプロットの反面、エイリアンの生態は複雑だ。まず異星の宇宙船内部の卵、そこから飛び出してきてケインの顔面に付着するフェイス・ハガー、ケインの胸を食い破って出てくるチェスト・バスター、そして人間サイズに成長したエイリアン。これほど様々な形態を見せるクリーチャーは珍しい。つまり本作のエイリアンは人を殺すから恐い、強いから恐いというより、その生態がすでに恐いのである。他者に寄生して繁殖するという、人間が寄生虫に理屈抜きで感じるおぞましさをエイリアンは持っている。そしてこの生態を、特に誰が解説することもなく、映像だけで観客に知らしめていくプロットはかなり巧みだ。
もう一つ、本作の巧みさの例として科学者アッシュの設定を上げたい。アッシュの正体が分かる場面は物語上エイリアンとは無関係だが、エイリアンに勝るとも劣らない恐さだ。あの設定は、もともとは「科学者がいるのにどうしてなりゆきを予測できなかったのか」という疑問を解消するために導入されたものかも知れないが、その結果見事に背筋が凍る場面をもう一つ生み出した。まさに一石二鳥である。
ところでこうやって見直してみると、船長のダラスはかなり無能である。異様な生物を顔面に貼り付けたケインを船内に運び込む時リプリーは反対するが、船長はいいから開けろと言ってルール違反をする。ルールの意味が全然分かっていない。あそこでルールに従ってケインを隔離していたら、残りの乗組員は助かっていたかも知れないのである。他の場面でも、決断できずアッシュにつけ込まれてしまったりする。やっぱりリーダーが無能だと組織は滅ぶんだな。
ところで肝心のディレクターズ・カットだが、三箇所ほど明らかに変わっている場面がある。特に最後の変更は重要で、「エイリアンはなぜ人間を殺すのか」という興味深いポイントに影響してくる。本当は変更点のそれぞれをここで詳しく説明したいところだが、それをやるとネタバレだと言われそうなので止めておく。ただ、このディレクターズ・カットがスコット監督の言うように劇場公開版より良くなっているかどうかは、まあ微妙である。
私は子供の頃にこの映画を見て、メチャメチャ恐かった覚えがある。特に恐かったのは、ダラス船長がエアダクトに入っていく場面、アッシュの正体がバレる場面、それからもちろんケインの胸を食い破って幼生エイリアンが飛び出してくる場面である。あまりに恐くて、絶対宇宙になんか行きたくないと思ったもんだ。しかしその『エイリアン』、今観ても充分に恐い。これはやはりクラシックだ。
昔ビデオで持っていた『エイリアン』のDVDを入手した。ディレクターズ・カットというものが収録されていて、以前から観てみたいと思っていたのである。もともと好きな映画で、シリーズの中でもこの最初の『エイリアン』が一番好きだ。恐くて、しかも美しい。憂鬱な不安の情緒が全篇を覆っている。『エイリアン2』も人気があるようだが、あれは完全なSFアクション映画で、この美しき不安の情緒はかけらもなくなっている。
今回見直してあらためて思ったのは、これは完全にゴシック・ホラーだなということだった。SFの衣装をまとっているけれども、見間違えようのないゴシック趣味に溢れた、暗く、装飾的な、憂鬱な美をたたえた映像の数々。あの中世の寺院みたいなノストロモ号のデザインや、薄暗くて湿り気を帯びた、それまでのSF映画におけるピカピカした清潔さとは似ても似つかない宇宙船の内部からしてそんな感じだが、異星の宇宙船の探索に行くあたりからそれが全開になってくる。暗くて巨大な、生物学的曲線に満ちた異星人の建築物内部は、モンス・デシデリオの絵画でも見ているような壮麗さだ。
そしてなんといっても秀逸、というか気色悪いのが、あの悪夢的なエイリアンのデザインである。エイリアンの頭部の形状が男根を模しているのは有名な話だが、つまりエイリアンは鋭い歯を持つ男根なのである。まさに悪夢から抜け出してきたクリーチャーだ。デザインしたのはスイス人の画家H. R. ギーガーで、彼の不気味な芸術は本作のヒットによって一躍世界中に知れ渡ることになった。しかしこの異様な美術に着目し、これをSFホラー映画の骨子とした制作者の判断こそ、本作を成功に導いた最大の要因だったんじゃないだろうか。
ギーガーのデザインも素晴らしいが、後に『ブレードランナー』を創り出すリドリー・スコット監督の映像センスももちろん見事だ。彼の特徴は光と影、そして水の使い方にあると思うが、本作でも主要な舞台となるノストロモ号の内部は陰影としたたる水に満ちていて、たとえばブレットが猫を探す場面では、高い天井から雨のように水が滴り落ちている描写がある。もちろん、クライマックス、ノストロモ号から脱出しようとしてリプリーが必死にあがく場面では、気が狂ったように明滅して不安を煽り立てる光、そしてその中に亡霊のように浮かび上がるエイリアンのシルエットが最大限の効果を上げている。本作の独特の美しさは、ギーガーのデザインとスコット監督の映像センスが化学反応を起こして生まれたものなのである。
ホラー映画として見ると、限定されて空間で展開されるシンプルなプロットが非常に効果的だ。外は宇宙、逃げ出すことはできない。そして一人、また一人と殺されていく。古典的なシチュエーションだ。このシチュエーションに投入されたジョーカーたるエイリアンの使い方がまたうまく、その姿がはっきり見える場面はほとんどない。ちらっと見えてはまた見えなくなる。エイリアンの全身が見えるのは最後の最後、リプリーがシャトルの中でエイリアンを発見する場面になってからだ。この「チラ見せ」がどれほど恐怖を高めているかは言うまでもない。
シンプルなプロットの反面、エイリアンの生態は複雑だ。まず異星の宇宙船内部の卵、そこから飛び出してきてケインの顔面に付着するフェイス・ハガー、ケインの胸を食い破って出てくるチェスト・バスター、そして人間サイズに成長したエイリアン。これほど様々な形態を見せるクリーチャーは珍しい。つまり本作のエイリアンは人を殺すから恐い、強いから恐いというより、その生態がすでに恐いのである。他者に寄生して繁殖するという、人間が寄生虫に理屈抜きで感じるおぞましさをエイリアンは持っている。そしてこの生態を、特に誰が解説することもなく、映像だけで観客に知らしめていくプロットはかなり巧みだ。
もう一つ、本作の巧みさの例として科学者アッシュの設定を上げたい。アッシュの正体が分かる場面は物語上エイリアンとは無関係だが、エイリアンに勝るとも劣らない恐さだ。あの設定は、もともとは「科学者がいるのにどうしてなりゆきを予測できなかったのか」という疑問を解消するために導入されたものかも知れないが、その結果見事に背筋が凍る場面をもう一つ生み出した。まさに一石二鳥である。
ところでこうやって見直してみると、船長のダラスはかなり無能である。異様な生物を顔面に貼り付けたケインを船内に運び込む時リプリーは反対するが、船長はいいから開けろと言ってルール違反をする。ルールの意味が全然分かっていない。あそこでルールに従ってケインを隔離していたら、残りの乗組員は助かっていたかも知れないのである。他の場面でも、決断できずアッシュにつけ込まれてしまったりする。やっぱりリーダーが無能だと組織は滅ぶんだな。
ところで肝心のディレクターズ・カットだが、三箇所ほど明らかに変わっている場面がある。特に最後の変更は重要で、「エイリアンはなぜ人間を殺すのか」という興味深いポイントに影響してくる。本当は変更点のそれぞれをここで詳しく説明したいところだが、それをやるとネタバレだと言われそうなので止めておく。ただ、このディレクターズ・カットがスコット監督の言うように劇場公開版より良くなっているかどうかは、まあ微妙である。
私は子供の頃にこの映画を見て、メチャメチャ恐かった覚えがある。特に恐かったのは、ダラス船長がエアダクトに入っていく場面、アッシュの正体がバレる場面、それからもちろんケインの胸を食い破って幼生エイリアンが飛び出してくる場面である。あまりに恐くて、絶対宇宙になんか行きたくないと思ったもんだ。しかしその『エイリアン』、今観ても充分に恐い。これはやはりクラシックだ。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます