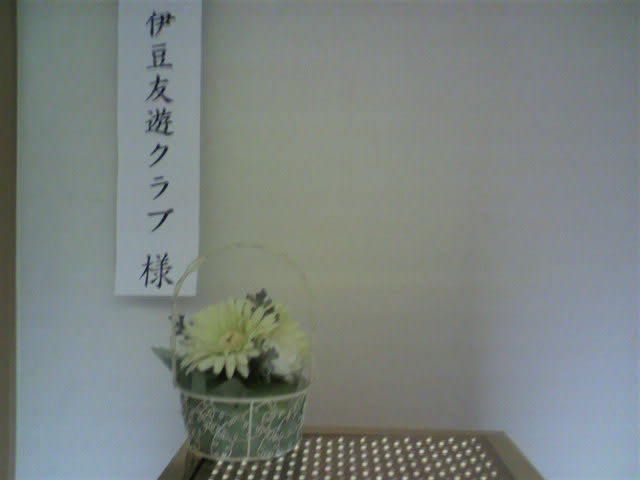伊豆高原の5月は緑があふれかえるような季節です。伊豆高原ではアートフェスティバルが実施されていて、私も何か所かまわってみました。
一人で行ったところ、夫といったところ。何度かは友人と行きましたが、さすがに十人十色。
興味を持つところがそれぞれ違うのですね。
この前の日曜日に、大学の後輩たちが訪ねてくれました。短い時間でしたが大急ぎで回りました。素敵な写真をFBに載せてくれましたから、お許しをもらってアップします。
桜美林伊豆高原荘(ここも会場)より大室山を臨む

重岡建治先生の彫刻アトリエ
去年11月にアップしたムービーメーカーの舞台は「なぎさ公園」です。
ムービーメーカーがコピーできませんから、ブログのページを張り付けておきましょう。http://ageing.blogzine.jp/boke/2013/11/post_72e2.html
ここに設置されている作品はすべて重岡先生作です。
公園はブロンズですが、ここのアトリエでは樟のいい香りが漂っています、木彫作品がたくさんあります。
そのお隣 田嶋淳展

難解な現代美術ですが、作者と話してみると少し分かってくる(左脳的に理解できるのではなくて、作者のモチベーションというものが何となくわかる。感じる。まさに右脳の働き)のが不思議でした。
玄関ホールに、何も描かれていない絵画が展示されています。
一面がベージュの濃淡で塗り込まれていました。そして小さな穴から赤い糸が出ていました。
その糸が家の中、洗面所、居間、食堂。更には緑の森に囲まれたようなベランダにまで延びて、そこに赤い糸でできた人体ができあがっているのです。
食堂のテーブルを挟んで対面する。ベランダで一緒に並んで森を見てみる。
ざわつくのです。この気持ちを感じさせることが作者の意図かもしれません。
エンゲルスブルク ドイツ人形のかわいいお店

後輩はとっても喜びましたよ。買ったお土産を見て、なんだか彼女の理解が深まったような気がしました。
ここは、一人でも行きましたし、友人とも何度か行きました。お土産を買ったのは今回の友人だけでした。
今思い浮かべると、彼女とあの煙出し人形のイメージが不思議なほど一致するのです。
気に入って求めるということは、一番ベースにあるのは右脳が「好き」とか「かわいい」と感じたからでしょう。(これは理由を聞かれても答えられません。「だって可愛いんですもの」)
次に値段。これは左脳の典型的な働きです。
高いか安いか(左脳)好き具合(右脳)、飾り場所など家の事情、何もかも考えて買うという決断を下すのは前頭葉ですね。
一緒にその時を過ごすことで、彼女の脳の働き方が、分かってくるのでしょうね。だからちょっと理解が深まった感じがしたのでしょう。
ヒロ画廊
ここは伊豆高原で一番おしゃれなギャラリーかもしれません。建てた人たちの思いを感じることができる空間です。この様に感じるのも、感じないのも、右脳のしわざ(笑)だからこの感想はあくまでも、私の個人的なものですよ。
前日には、小泉八雲の怪談の朗読会もありました。
夕方から、ろうそくの明かりで行われました。
誰からもそういわれたわけではないのですが、朗読が始まると目を閉じるのです。そちらの方がイメージが脳内いっぱいになる。
演者も「しっかり読み込んでおけば、読み始めたときには何人もの声色に、考えるというようなことはしていないすぐなる。」ということを解説してくれました。こういうことができるのも右脳でしょう。

伊豆高原アートフェスティバル(まさに右脳の祭典)で行ってみたいものがたくさんある。行ってみたらやってみたくなった。
こういうタイプの人はボケるタイプではありません。
認知症予防には「牛に惹かれて善光寺」とい言葉がありますが、何から始めてもいいと思います。とにかく楽しみで、ずーと続けたくなるものを持っている人は幸いです
針と糸でも、絵でも、陶芸でも、コーラスでも。確かに趣味は右脳中心ですね。
ところが仕事以外何もないと訴える初期の認知症高齢者がどれほどいるでしょうか!
趣味を勧めたときに聞かれる言い訳の常套句は「苦手だから」か「やったことがないから」です。
つまり興味が持てることをたくさん体験させておくことが認知症予防には最も効果的。
そしてよくよく心にとめておかないといけないのが、右脳の教育です。臨界期がごく小さい時ですから、感性の教育は計算や漢字ドリルに先行すべきものです!













 質問の答えです。
質問の答えです。