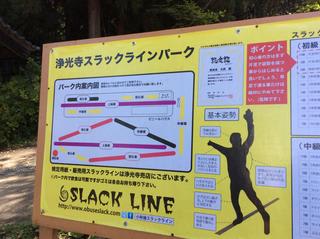松代地区担当のT橋保健師さんと、事前の打ち合わせをしました。
「認知症予防教室の活動中の写真がないかしら。講演で紹介してあげたいの」とお願いしたら写真が送られてきました。
なんと平成20年に開始した、木和田原地区の写真でした。ということは7年間継続できているということです。
写真しか送られてきませんでしたから、脳機能検査はできていないのかと思っていました(エイジングライフ研究所は教室の開始時と、その後は年一度の脳機能検査をすべきだと指導しています)。写真がはつらつとした楽しそうな活動風景でしたから、「脳機能は維持できているはずなのにもったいないこと…」と残念に思っていました。
ところが勉強会で、担当のT橋保健師さんが「やってありますよ」と笑いながらデータを見せてくれたのです!一瞥しただけで素晴らしい結果だということはわかりました。今年の検査は来週だかに行われるということでしたから、平成26年の最終検査を受けていて、それ以前に比較できる検査結果がある人たち9人のまとめです。
大歩危は渓谷が深いので、危険個所の注意を促すために妖怪伝説が生まれたそうです。
データが平成21年から平成26年までのものでしたから、グラフには5年間と書きましたが実際は7年間の教室の経過と考えていいと思います。
教室開始時の年齢で言うと72歳から85歳、平均77.7歳。

7年たったのです!この年齢で、改善している人がいることに感動しませんか?
脳機能にも、正常老化があって年齢とともに低下していくものです。ということは維持していれば、それだけでも「認知症予防教室」の効果があったと考えられます。
有効率は改善群と維持群の合計88.9%ということになります。

低下の方は、家庭内で介護その他大変な状況を乗り越えたところだそうです。
もともと脳機能はイキイキとしていたのですが、介護ばかりの生活が続くと脳は元気をなくすのです。いったん元気をなくしていた状態から、はっきりと改善中。生活にはもう困難はないでしょう。
T橋保健師さんは「元気になられました」といってましたね。今年の検査ではきっともう少しいい成績になっていることと思います。1回目の成績が良すぎる場合には「改善」にならずに「維持」になる可能性が高いことは予測できますね。
T橋保健師さんはデータを眺めながら「この方も、この方も、ほらこの方も」と指さすのです。そして隣に座っている前任のK井保健師さんと笑いあっています。
脳機能検査の結果は、生活実態をそのままに表します。
お二人は、生活実態の方がよく見えているのでしょう。日常感じている皆さんの元気さがデータと一致していることに、改めて感動しているように見えましたよ。
「検査ができている教室とできていない教室の差はどういうものですか」と聞きました。
「木和田原の人たちは、『教室が認知症予防に必要なもの』という考えがあるように思います。だから言われて参加するというのではなくとても自主的」
「教室に来て『一か月分楽しんで、一か月分笑ってます』って。『みんなに会うのが何より楽しみ』って言ってくださいます」
「検査をしないと、何かあるとすぐ来なくなる傾向があると思います」
講演会の感想が届きました。
講師冥利に尽きるような感想がたくさんありました。またご報告しましょう。