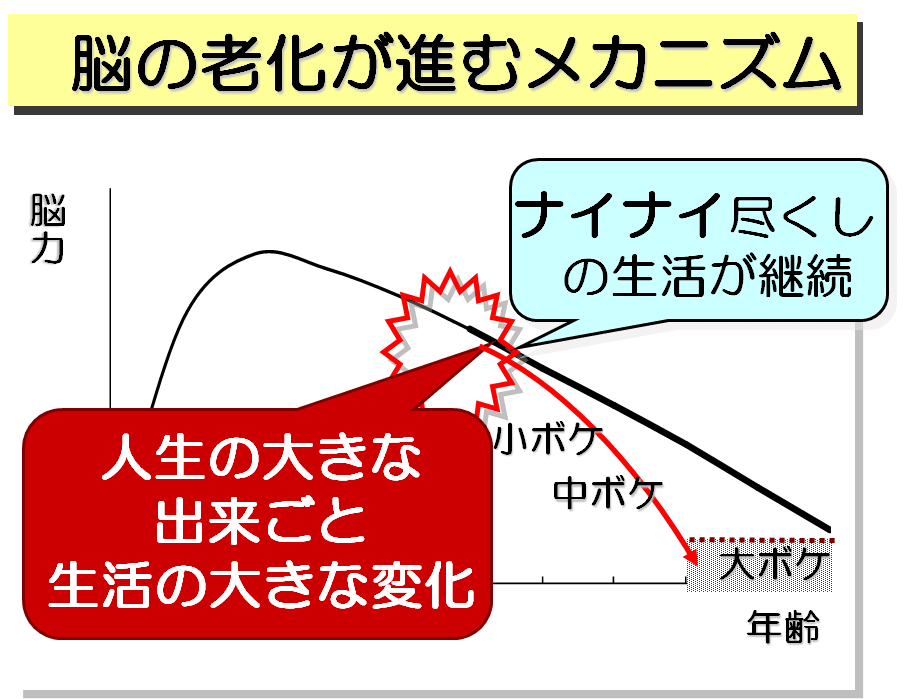義理の娘(長男のお嫁さん)と話をしていたら「接触冷感生地を使ってマスクを作ってみた」というので「うわー。興味ある!一枚余分ができたら送って」と言ったら
「実はもうできあがっていて送ろうかと思ってたところ」というやり取りがありました。
それが届いたのです。マスクにしたら大きな紙袋?と思って開きました。
白い箱がまず目に飛び込みました。
長男の会社の20周年の記念品。今回は何だろうとワクワクしながら開けました。
前回10周年記念の時送られてきたコメントも興味深く読みましたので。
「実はもうできあがっていて送ろうかと思ってたところ」というやり取りがありました。
それが届いたのです。マスクにしたら大きな紙袋?と思って開きました。
白い箱がまず目に飛び込みました。
長男の会社の20周年の記念品。今回は何だろうとワクワクしながら開けました。
前回10周年記念の時送られてきたコメントも興味深く読みましたので。
今回はおしゃれなメモ帳かと思いました。艶消しの黒地に青金で七宝模様。

取り出して広げると、これはご挨拶文でした。今回も記念品は香りなんですって。

ちょっと探してしまいました。左側の細長い箱。ここに記念品が入っていました。
「あきつしま」と名付けられた香水。さわやかな柑橘系の香りが多分ベースなのだと思いますが、もう少しシャープでモダンな香り。香りも言語化しにくいですね…「あきつしま」のロゴが、少し手助けしてくれているかな。
この書体は調香師の方が選ばれたそうですが、香りを作られたときのイメージに重なるものがあったに違いありません。
かなの連綿体なのに柔らかくない。あきつしまは日本の別名ですから、日本の持っている多面性を強調されたかったのかもしれません。

屏風たたみになっているメッセージは、一枚にひとつのテーマでまとめられていました。下部には英文でも表記されています。

取り出して広げると、これはご挨拶文でした。今回も記念品は香りなんですって。

ちょっと探してしまいました。左側の細長い箱。ここに記念品が入っていました。
「あきつしま」と名付けられた香水。さわやかな柑橘系の香りが多分ベースなのだと思いますが、もう少しシャープでモダンな香り。香りも言語化しにくいですね…「あきつしま」のロゴが、少し手助けしてくれているかな。
この書体は調香師の方が選ばれたそうですが、香りを作られたときのイメージに重なるものがあったに違いありません。
かなの連綿体なのに柔らかくない。あきつしまは日本の別名ですから、日本の持っている多面性を強調されたかったのかもしれません。

屏風たたみになっているメッセージは、一枚にひとつのテーマでまとめられていました。下部には英文でも表記されています。
【世界の人口】
20 世紀半ばには 30 億人未満だったが、その後アジアやアフリカを中心に急速な増加を続け、現在では70 億人を超えていると言われている。
そして今後は、次第に増加のペースは鈍化していくものの、2020 年代に 80 億人、2040 年代に90 億人、2080 年代には 100 億人に達するものと推計されている。
【土地資源の現状】
過去50年間に、世界の作物栽培面積はわずか12%しか増えなかった。Food and Agriculture Organization of the United Nationsの統計によれば、世界の作物栽培地面積は、1961年の13.7億haが2009年には15.3億ha増加したとあるが、比率にすると過去50年間にわずか12%しか増えなかったことになる。
【農地の生産力】
過去50年間に、投入資材施用量の増加、農業の機械化と灌漑によって、世界の農業生産力は2.5〜3倍に増加してきている。人口は急増したため、世界平均で人口1人当たりの作物栽培面積は1961年の0.44 haが2009年には0.22 haに半減したが、生産力の向上によって、現在は何とか70億人の人口を支えていることになる。
【水資源の現状】
過去50年間に、食料生産の増加分のうち40%は、灌漑農地を倍増させて賄ってきたが、灌漑用水量は、帯水層、河川および湖沼から取水した農業用水総量の70%を占めるに至っている。灌漑農地面積は、2009年の301百万haが2050年には318百万haに増加すると見込まれているが、そのための取水量は2030年までに2900 k㎥超/年、2050年までに3000 k㎥超/年に増加し、現在と比べて2050年の間に10%の増加が必要になると予測されている。
【搾取と共生】
これまでは、有限の系である地球の中でいわば“搾取”を続ける営みであった。これは、産業革命以降の人類と地球の関係そのものかも知れない。しかし、いよいよ限界が目前に来ていることは明らかである。閉じた系である地球の中で持続的に“共生”できる営みを創出しなければならない。
【西洋と東洋】
大胆に言い切るならば、前者は西洋の文化、後者は東洋の文化と言えるかも知れない。そして、我が国日本は、その架け橋となることができる使命を背負った唯一の国である。東洋に属しつつも、いち早く西洋の産業革命以降の流れにのり、その便益を取り入れてきた国だからである。世界が“共生”を求めているときに、東洋と西洋の双方から叡智を抽出し、提示していく役割がある。
【日本の価値を世界に】
インスパイアは全力でその地平を切り開いていく。装粧香『あきつしま・蜻蛉島』は先導事例かくあるべしと願って企画し、多くの方々の協力の御蔭で顕在化した。基剤となるアルコールは、うち捨てられるはずであったポプラの小片を微生物に与え、そこから生成された グリーン アース エタノール。調香の鍵となる命題は『時空の和音・蜻蛉島の人』である。
母なる地球との “共生”を感じていただけたなら、望外の喜びである。
母なる地球との “共生”を感じていただけたなら、望外の喜びである。
株式会社インスパイア 代表取締役社長 高槻亮輔

「インスパイアは投資会社じゃなくて、事業会社。世の中に必要な事業を作っていくんだよ」と、その昔長男から聞きました。ぶれてない。ちょっと胸が熱くなりました。
本題はマスクでした!

びっくりするほど、きちんとしていてかっちりとしたできあがり。裏地もついているし、フィルターも入れられるようになってます。涼しげな木綿生地で、その生地とデザインがぴったりマッチしています。接触冷感生地かどうかはなんだかよくわからずじまいでしたが、このマスクとっても気に入りました。一つは夫が使いたいとのことで、喜んで上げましたよ。
それにしても、何といいセンス。それに手際がきれいです。お礼の電話の時、もう一つうれしい情報が。『あきつしま』は彼女の筆なんですって!すごい!
今も飾ってある古希祝のプレゼントも紹介します。和紙で作る川崎ローズの飾り物。親指大と人差し指大のバラたちが70輪!大変な手間がかかることは知っていました。あとで聞いたのですが、半年近くもかけてつくってくれたのですって。

この時もちょっと面白いことが起きました。その時のブログ記事より抜粋。
「古希おめでとうございます」というメッセージに
「えっ!どうしましょう。今年69歳になるんだけども。せっかくの好意に対して、どう言ったらいいだろうか」とちょっと悩み、「来年はメッセージだけでいいので、送り返してと言わないで」とメールしました。
電話がかかってきて「お祝いですから『数え』で」と。安心して、電話の向こうとこちらで大笑い。まったく「負うた子に教えられ」です。
コロナと梅雨でちょっと気分が下がりがちのところに、ありがたいプレゼントでした。