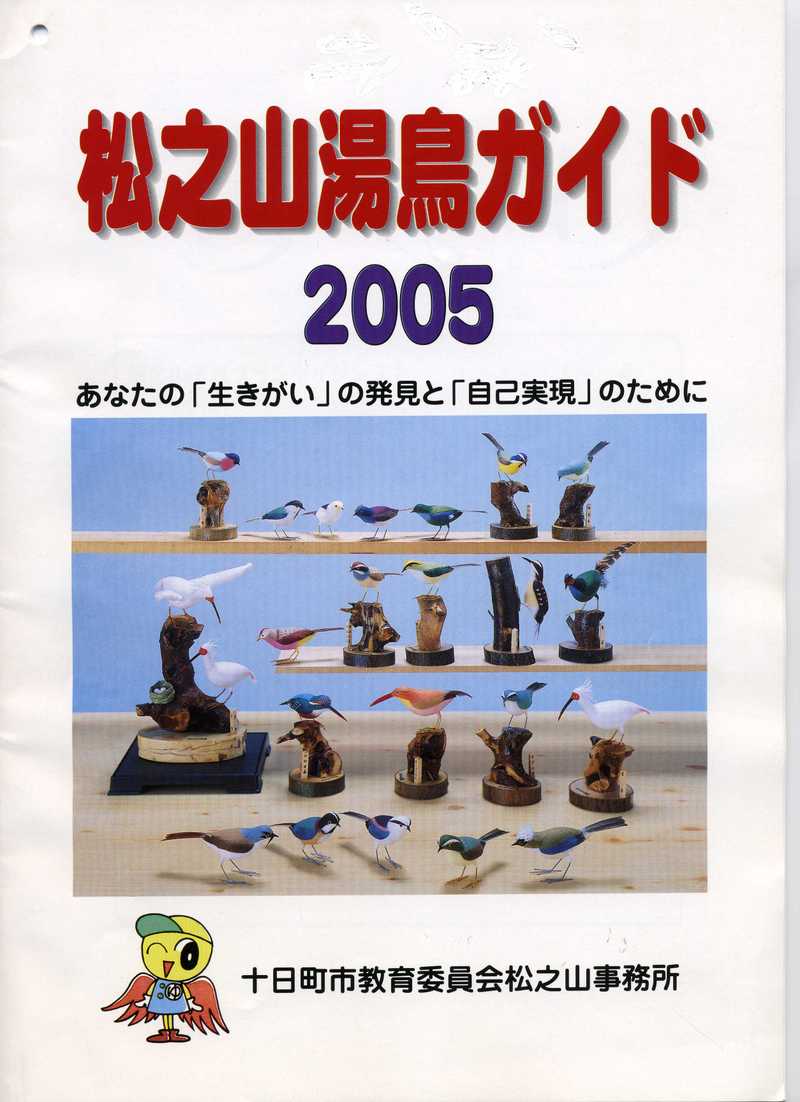新十日町市は、平成17年4月1日に旧十日町市、川西町、中里村、松代町及び松之山町の5市町村が新設合併して誕生しました。二段階方式を導入していたのは、旧十日町市でしたが、認知症予防活動は必須の事業ということで、新市でも取り組むことになりました。
まず講演会。去年は中里、そして今年が松之山。
(3月6日のブログも読んでください)
全国でも、名だたる豪雪地帯。そして高齢化率42.88%・・・
私は、「松之山存続のために、大切なことを伝えなくては」と、いつもの講演よりもちょっと気合を入れて、ほくほく線十日町駅に降りました。
迎えに来てくださっていたのは、松之山支所の福原滋さん。「雪国の大変さと、それだけでない豊かな人間らしい生活を支える松之山のこと全部を知ってほしい」という気持ちが、お会いしてすぐ読みとれました。
松之山を復習していたら素敵なブログに出会いました。
松之山ってこんなところです。
http://blog.livedoor.jp/satoakihiko/
何代の人の手がかけられているのだろうかと、頭が下がる思いの棚田。少しの土地も無駄にせず、田が無理なら畑。そこここで農作業をしている高齢者に出会いました。常に手を加えるからこそ、維持できている松之山の風景なのです。
美人林と呼ばれるぶな林へも行きました。
福原さんに言われてわかったこと二つ。
ひとつは、足元にびっしり生えているぶなの赤ちゃん。まったく気にせず歩いていたのですが、いったん気付いたら、踏みはしないかとハラハラし通し。
もうひとつは、「ぶなは少なくとも10本はないと大木に育っていかない」ということ。あの赤ちゃんが何本成長していけるのか?1本ではだめということも、どこか人間に似ている・・・などと感慨新たでした。
福原さんのお宅へも寄りました。天水越というところです。
話を聞いているとちょうど、お母さんが畑から帰宅。お隣の方と一緒に温泉に行くのが日課とか。80歳過ぎとはとても思えないほどお若い!
お宅の隣はよく手入れされた畑(福原さんが耕してあげると、後はお母さんが担当)その隣にお堂が。福原さんのお宅で数百年経つ十一面観音像をお祭りしてあるのです。
「お講のときは、ご馳走を作って振舞うのが楽しみだもんな。このお堂を守ることも、大変でもお母さんの生きがいだろう」
話は続きます。今年の雪は多くて何と6M。「雪下ろしをするとまあ8Mにはなったな」
高齢者の暮らしでもっとも大変なのがこの雪下ろし。福原さんは雪下ろしのボランティアをやっているそうですが、手を合わせられることもしばしばとか。
「雪のない時期は、いいですよ~。田畑を守るのも義務というか生きがいだし、暖かい交流はあるし、何よりこの自然!」
さて、講演です。
人口2900人弱。参加者は130人。会場いっぱいでしたから
たくさんの方が聞きに来てくださったということがわかりました。
エイジングライフ研究所の講演の最重要な点は、「脳の健康を守るには、右脳・左脳・運動脳を発揮できる場が必要。その状況の中で前頭葉をいきいきと自分らしく使い続けるのです」ということですが、右脳=趣味・人付き合いと単純化せずに次のように説明しました。
「松之山にはあいた土地がない。田ができるところは田、無理なら畑。でも田や畑の隅には必ずお花が咲いています。道沿いの花も地域のみなさんの丹精だと聞きました。花を育て、めでる心が右脳の働きです」
「田畑で働いて一休みするとき、山の緑や空の青さに改めて心が洗われるような気持ちになるでしょう。そんな時に右脳が活性化されています」
「初雪のときに、また厳しい季節が始まるなあ。でも、なんときれいなこと!と思わずにはいられないでしょう」
「各分野で秀でた実績をお持ちの70歳以上のお年寄りの方々を名老百選として選任。松之山町の宝」
この情報も前日福原さんから教えていただいたものでした。
見事に右脳優秀者がそろっています。その名老百選の話もしました。この人たちが教室参加してくださればいいのです。
参加者の方々は97%が「参加してよかった」といわれたそうで、高齢福祉係長さんとしての福原さんも「主催してよかった」といわれました。私もホッ。
私は予習しなくては、地域に密着した話ができませんが、保健師さんたちはお年寄りを納得させ、心を捉える話ができるはずです。また人材についてもよくご存知ですよね。
後は脳機能テストと生活改善指導です!
おまけ:日本三大薬湯
有馬温泉・草津温泉・松之山温泉(山中なのに塩味)