①信時 潔:交聲曲「海道東征」 湯浅卓雄指揮東京藝大シンフォニーオーケストラ、東京藝術大学音楽学部声楽科学生、NHK東京児童合唱団その他(2015年11月録音 Naxos盤)
②中田喜直:組曲「時間」、組曲「光と影」、ピアノ・ソナタ (1969) 宮沢明子(ピアノ)(1967年、1969年録音 King International盤)
このところ当ブログはフィギュアスケートの話題ばかりになってしまいましたが、クラッシック音楽のCDもコツコツと聴いています。
久し振りに最近購入したCDから。
日本人作品のCD.
私は日本人作品に興味があり、少しずつですが聴いています。特に Naxosレーベルからの発売の日本作曲家選輯シリーズは私にとって好シリーズで、ほとんど揃っています。特に戦前のオーケストラ音楽に大きく目を開くものがあり、あの時代、たいへん充実した作品が多く楽しませてもらいました。
そのためか映画「ゴジラ」シリーズの伊福部昭の音楽を聴くと血が騒ぐのもこのためかな?
さて戦前の日本人作曲家によるオーケストラ音楽のことを調べていたら、どうしても避けて通れない作品がありました。
信時 潔作曲の交聲曲(カンカータ)「海道東征」である。日本最初のカンタータということで、一度は聴いてみたい作品だった。どんな曲なのか?長い間、興味津々だった。
1940年(昭和15年)11月、紀元二千六百年奉祝演奏会で初演。
神武天皇が日向国から海路紀伊半島に渡り、大和を征服して初代の天皇になるまでの物語をカンカータにしたもので、北原白秋の作詞で、やはり日本語が美しい。
また演奏自体も、これで良いのだろう。
しかしながら何か、単純に音楽の面白さを感じようとするには何か引っかかる。その何かが何なのか正直よく分からない。
戦前に、これだけの大作が日本で生まれていたことを素直に喜び、この作品の意味を読み取るべきなのだが・・・。どうも引っかかる。素直になれない私がいる。
同じ年に初演された橋本國彦の交響曲第1番は純粋に楽しむことができたのに、何故だろう?
私にとって何故?だらけの作品。
初演から76年。今となっては聴き方の、たいへんむずかしい作品であることは間違いない。
「海道東征」で何かモヤモヤした気持ちの時に、もう1枚の日本人作品のCDが届く。
中田喜直のピアノ作品集。
作曲家・中田喜直と言えば「夏の思い出」や「雪の降る街を」などの歌曲をすぐに思い浮かべますが、作曲家自身は東京音楽学校(現・東京芸術大学)ピアノ科を卒業し、ピアニストを目指していたとのこと。
それだけに、今回聴いたピアノ作品は力作揃い。
また宮沢明子のピアノ演奏は、彼女の才気が十分に出ていて聴いていてたいへんな充実感を感じた。そして面白かった。
そして宮沢明子の演奏を聴くのは久し振りである。LPレコードの時代は、何枚かレコードを持っていたがCDは今回が初めてである。
宮沢明子のレコードでは忘れられない録音がある。
菅野沖彦が録音を担当した「マイクと楽器の対話」というタイトルの1枚のレコード。
CDで復刻されているにかな?
現在、我が家のレコードプレーヤーは壊れたままなので、このレコードを聴くことが出来ない。
何とかしなくては・・・。

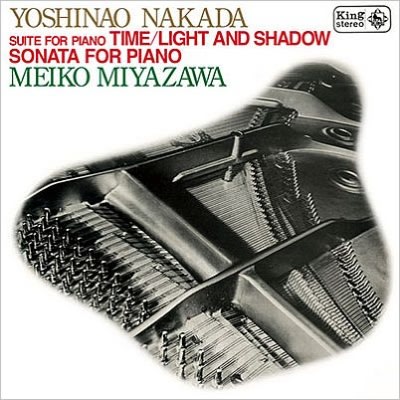
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
②中田喜直:組曲「時間」、組曲「光と影」、ピアノ・ソナタ (1969) 宮沢明子(ピアノ)(1967年、1969年録音 King International盤)
このところ当ブログはフィギュアスケートの話題ばかりになってしまいましたが、クラッシック音楽のCDもコツコツと聴いています。
久し振りに最近購入したCDから。
日本人作品のCD.
私は日本人作品に興味があり、少しずつですが聴いています。特に Naxosレーベルからの発売の日本作曲家選輯シリーズは私にとって好シリーズで、ほとんど揃っています。特に戦前のオーケストラ音楽に大きく目を開くものがあり、あの時代、たいへん充実した作品が多く楽しませてもらいました。
そのためか映画「ゴジラ」シリーズの伊福部昭の音楽を聴くと血が騒ぐのもこのためかな?
さて戦前の日本人作曲家によるオーケストラ音楽のことを調べていたら、どうしても避けて通れない作品がありました。
信時 潔作曲の交聲曲(カンカータ)「海道東征」である。日本最初のカンタータということで、一度は聴いてみたい作品だった。どんな曲なのか?長い間、興味津々だった。
1940年(昭和15年)11月、紀元二千六百年奉祝演奏会で初演。
神武天皇が日向国から海路紀伊半島に渡り、大和を征服して初代の天皇になるまでの物語をカンカータにしたもので、北原白秋の作詞で、やはり日本語が美しい。
また演奏自体も、これで良いのだろう。
しかしながら何か、単純に音楽の面白さを感じようとするには何か引っかかる。その何かが何なのか正直よく分からない。
戦前に、これだけの大作が日本で生まれていたことを素直に喜び、この作品の意味を読み取るべきなのだが・・・。どうも引っかかる。素直になれない私がいる。
同じ年に初演された橋本國彦の交響曲第1番は純粋に楽しむことができたのに、何故だろう?
私にとって何故?だらけの作品。
初演から76年。今となっては聴き方の、たいへんむずかしい作品であることは間違いない。
「海道東征」で何かモヤモヤした気持ちの時に、もう1枚の日本人作品のCDが届く。
中田喜直のピアノ作品集。
作曲家・中田喜直と言えば「夏の思い出」や「雪の降る街を」などの歌曲をすぐに思い浮かべますが、作曲家自身は東京音楽学校(現・東京芸術大学)ピアノ科を卒業し、ピアニストを目指していたとのこと。
それだけに、今回聴いたピアノ作品は力作揃い。
また宮沢明子のピアノ演奏は、彼女の才気が十分に出ていて聴いていてたいへんな充実感を感じた。そして面白かった。
そして宮沢明子の演奏を聴くのは久し振りである。LPレコードの時代は、何枚かレコードを持っていたがCDは今回が初めてである。
宮沢明子のレコードでは忘れられない録音がある。
菅野沖彦が録音を担当した「マイクと楽器の対話」というタイトルの1枚のレコード。
CDで復刻されているにかな?
現在、我が家のレコードプレーヤーは壊れたままなので、このレコードを聴くことが出来ない。
何とかしなくては・・・。

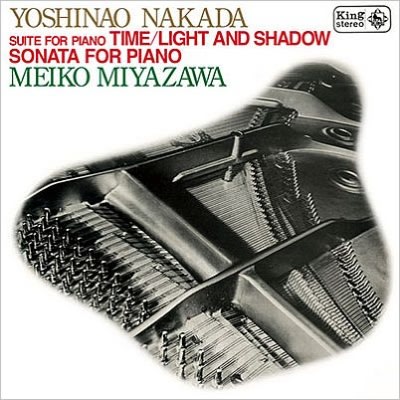












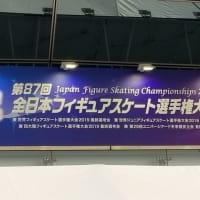







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます