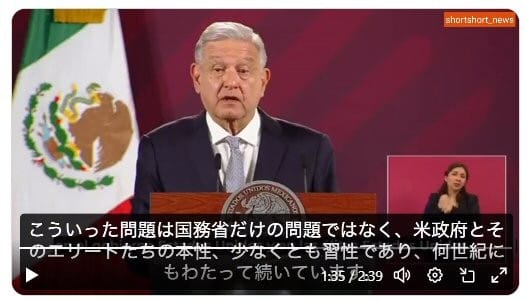先日、ロシア南部のダゲスタン(タジキスタン)で起きたテロに関し、朝日新聞は「相次ぐ襲撃、統治能力に疑問符」と題する記事を掲載しました。ロシアは、外国勢力がロシアを混乱させるために計画し、実行したと主張しているのに、そのことについては、事実の確認や取材をせず、また、教会やシナゴーグ(ユダヤ教の礼拝所)を襲い、神父や警察官を殺し、火を放つという悪質なテロであるにもかかわらず、そのことに目をつぶり、プーチン大統領の統治に問題があるかのような記事を掲載することは、いかがなものかと思います。このテロが、アメリカをはじめとする西側諸国で起きたテロであれば、あり得ない記事だと思います。
ロシア政府系ニュースサイト「コムソモリスカヤ・プラウダ」は、”「西側全体」がロシアに対して「第二戦線を開こうと」している”と非難したようですが、私は、それが事実ではないかと想像します。だから、上記のような朝日新聞の記事は、アメリカの反米政権転覆戦略に加担するものだと思います。現実の無視といってもいいと思います。
”3月にモスクワ郊外で大規模襲撃事件が起きていて、ウクライナ侵攻後、国民の間に広がる政権への潜在的な不満が一段と強まる可能性もある”などと、モスクワ郊外のテロ事件も、その実行犯の目的や背景をきちんと把握しないまま、プーチン大統領の統治の問題として論じているように思います。でも、それはアメリカの外交政策や対外政策の問題点(反米政権転覆戦略)に目をつぶることだと思います。アメリカは中南米やアフリカを中心とする国々で、反米政権転覆作戦をくり返してきたのです。
このモスクワ郊外のテロ事件に関して、ロシアのパトルシェフ安全保障会議書記が、「捜査の過程で、実行犯とウクライナの民族主義者との直接的なつながりが確認された」と語っているので、まずは、その事実をきちんと確認することが大事だと思います。
下記は、6月28日、english.pravdaが報じたものですが、アメリカはボリビアを不安定化させ、アメリカの産業へのリチウムの供給を確かなものにしようとしているというような内容です。
”The United States will continue to destabilize Bolivia in order to install a government that will ensure the supply of lithium to the American industry.(See more at https://english.pravda.ru/news/world/159869-bolivia-coup/ )
そして、この報道と関わって、Twitterには、CIAの関与を指摘する下記のような投稿がありました。
![]()
CIAの任務を考えれば、こうした問題にCIAが無関係であるわけはない、と私は思います。アメリカが圧倒的な経済力と軍事力を持っているのは、こうしたことを積み重ね、利益をあげてきた結果であると思います。現実を見なければいけないと思います。
再び、沖縄のアメリカ軍嘉手納基地に所属する兵士が、16歳未満の少女をわいせつ目的で誘い出し性的暴行をするという事件がありました。でも、外務省は、ことし3月の起訴の時点でアメリカのエマニュエル駐日大使に抗議していたにもかかわらず、県に対しては3か月近くたった25日になって、県の問い合わせを受けたあとに伝えたといいます。日本政府は、アメリカの忠僕であり、沖縄県民を蔑ろにしている、と私は思います。
今、私がとり上げている日航123便墜落事故でも、アメリカは、事実を偽り、隠然とした力の行使をしていることは明らかだと思います。
下記は、「日航123便墜落 疑惑のはじまり 天空の星たちへ」青山透子(河出文庫)から、私が、記憶しておきたいところを抜萃しました。圧力隔壁破壊説は、客観的事実に反するのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第2部 エマージェンシー 墜落か不時着か
第3章 原因は何か 新聞報道から見える事実
ボイスレコーダーの一部解明─8月18日の事故原因
・・・
第二次中間報告…
9月6日付で突然発表されたニューヨーク・タイムズ紙によるボーイング社の修理ミス説が主力となり、7年前の大阪空港における尻もち事故の修理を全面委託されて請け負ったボーイング社が、後部圧力隔壁の修理の際、決められたリベットより少ない数で修理したことによって金属疲労が生じ、それが原因で隔壁が破壊された。(1985年9月14日発表)
これを受けて各新聞や雑誌では、
「ボーイング社は、世界中飛んでいるたくさんのジャンボジェット機の構造にミスがあるのではなく、悪いのはあの修理ミスを行った一機のみであるとしたくて発表したのだろう」
とか、わざわざ弱い所を作るような修理をしたとは、信じられない。あれほどひどい修理をよく日航だまって通したと思いますよ」という意見があり、さらに、
「事故調にお願いしたいのは、単なるつじつま合わせではなく、事故原因を突き詰めてもらいたい、今後に役立つようにしてほしいということだ」
などの声が上がった。
1987年6月19日、最終事故調査報告書…
橋本竜太郎運輸大臣に提出した内容は、やはり、事故機が1978年6月2日に大阪空港で胴体後尾部を滑走路にこすった際にボーイング社が修理し、その修理ミスを起因とした後部圧力隔壁が、疲労亀裂となって破壊されて急減圧が生じ、垂直尾翼を突風が吹き飛ばしたというものであった。
日航側もその修理ミスを見逃したということで、責任を指摘された。
報告書のほとんどは修理の際にミスをした断面図や隔壁の状況説明である。
乗客、乗員の死傷についての解析では、機体前方部は即死状態、後方胴体のさらに後方にいた生存者は奇跡であるとした。
また、運行乗務員は急減圧による低酸素状態で操縦したことにより、知的作業能力、行動能力がある程度低下したものと考えられるとした。
さらに捜索活動については、登山道がなく落石危険の多い山岳地域であり。夜間ということで、機体の発見及び墜落地点確認まで時間を要したことはやむを得なかったとしている。
事故から1か月後、第二次報告書が出た時の日本航空側の河野宏明整備部長のコメントだが、「ボーイング社の修理ミスは考えられない。修理後7年間も無事に飛び続けていたという事実がある。隔壁の亀裂発見については、隔壁の亀裂は1インチ(2.54cm)程度になったものを目視で発見して手当をすればよい規定になっている。仮に数ミリの亀裂があっても、客室内のタバコのヤニはここに付着するので、あればすぐわかるはずだ」と点検ミスを否定している(1985年9月15日付毎日新聞朝刊)。
この言葉を重く受け止めた学生Aは、
「これはJAL整備部長の単なる言い逃れと思えないです。だってこれほどまでに言うということは、この人は信念を持っていると思うし、記者もそれを知ってわざわざ書いたのだと思います」
と言った。
おそらくこの学生は、インターンシップで航空会社の整備士と接していたから、特にそう感じたのだろう。
たしかに当時はタバコ(機内で喫煙可のため)のヤニ付着によって亀裂部分がすぐ発見できるということを整備さんから聞いたのを思い出した。
事故から7ヶ月後の1986年3月28日に報道された『事故調査に関する報告書』の中で、まるでこの日航整備本部長の発言にヒントを得たかのごとく、いきなりヤニについての記事が出たのである。なぜ突然ヤニになのか?
ヤニが付いていた事故機のリベット部分を指さしながら見せるヘルメットをかぶった人の写真が公表されたのだが、その新聞をみんなで回して見た。
3月28日付各新聞記事によると、そのヤニは修理ミスの継ぎ目に付着しており、長時間にわたって空気が漏れ続けていた証拠であるとしている。
報道書案に添えられた7枚の写真には、継ぎ目とリベット周辺にこびりついた黒ヤニが鮮明に写され、中には垂れかかったものまであるという。
垂れかかったものとは、長年洗浄していないということか?
ーーー
第3部 乱気流の航空業界 未来はどこへ
第1章 過去からのメッセージ
先輩の墓標
・・・
「それからこの辺りは、歯の骨まで真っ黒で、炭化状態になってしまった。通常の火災現場の遺体と異なって、なんか二度焼かれたぐらいひどい状態だったよ。ちょっとさわるとポロポロと崩れそうだった。ジェット燃料のケロシンって、そんなに燃えるのかね」
そのように当時を思い起こして真剣なまなざしで語る大國氏の言葉を受けて私はこう答えた。「ジェット燃料はJET─A/40という灯油の部類でケロシンと言いますが、マイナス50度の上空でも凍ってしまわないように、灯油よりも純度が高くて水分の少ないものです。基本は灯油です。両方の主翼内の区切られたタンクに入っていますが、事故機の胴体部分には入っていませんでした。翼が激突で壊れた時、燃料が飛び散ったとしても、この高い木々の上を、例えばフランス料理のフランベのように炎が立ち上がっても燃えて爆発するイメージですね。さらに夏山でもありますし、当時の墜落直後の写真を見ても、木の幹は茶色に焦げた程度ですよね。
木々の葉っぱが黒くなっていても、幹は炭化していませんし、こげ茶のままです。さらにケロシンは灯油よりも燃焼性がよいので、炭素分子の『すす』の発生量が少ない、つまり黒くならないのです」
「ええ? ジェット燃料って灯油程度? それでは家の火事ぐらいだなあ。私は群馬県警察医として千体ほど焼死体を見てきたが、それでも歯は「すす」で黒くても、裏側や一部は白いままだし、骨もそこまで燃えてない。
なのに、あの事故の時は骨の奥まで炭化嗚呼する燃えていた。まるでガソリン頭からたくさん被って亡くなった方のような状態だったよ。それを検死担当の先生は二度焼きしたような状況だと表現している」
二度? 両翼はそれぞれ機体からもがれて、乗客の席とは分離して右と左の沢に落ちている。そこから燃料が飛び散り、二度爆発があったとしても、それは木々を焦がしているが、幹の中までは燃えていない。なぜか地上に落ちた遺体の広範囲にわたって黒々と骨の芯まで燃えているというのだ。
なぜだろうか? ジェット燃料でもガソリンでも、炭焼き釜でも、すべて圧力のかかった限られた狭い範囲(燃焼室)おいて、爆発的に燃えて高温になるが、この山の上にばらまかれた燃料は、圧力がかかった状態でもなく、狭い範囲でもなく、広範囲の山の木々に散らばり、広い空間に放出されたのである。
尾根を伝って流れ落ちることや、夏山の青々としたみずみずしい草木や、大気の中に放出されたケロシンは、ガス化しやすく、「すす」も出にくい成分だが、霧状に噴霧された時、土や臭いの上にある遺体が骨の芯まで黒く炭化するのだろうか。各科学的にも考えにくい。
唯一、火炎の難を逃れた生存者が発見された場所であるスゲノ沢付近の遺体は、まったく異なる方向に後方の機体(Eコンバートメント)が分離して、この沢の下までかなりの距離を滑落した。尾根の頂点から見えないほど、急な斜面をかなり下まで滑り落ちたため、✕岩付近から随分と見えない場所に落ちている。
それ以外は、主翼の燃料タンクから遠いところに投げ出された遺体も、俺の頂上付近で激突したところも、遺体が集中した場所が特に黒こげ炭化状態であったという。
夏の軽い衣服にジェット燃料が付着したとしても、生身の体が骨の芯まで炭化する前にガス化してしまう。そびえ立つ木々の幹や土はそこまで燃えていないのだから。
大國氏によると、ある炭のようになった遺体は固く抱き合った新婚夫婦のものだったという。そのままの状態で炭化したために、耳の穴が三つ確認できるが、二体を分けようとしても、
ちょっとさわると炭がボロッと崩れるになってしまうために、身元を割り出すのに大変苦労されたということであった。
大國氏のように、自分の命さえも投げ出して献身的に身元確認作業をした人々は、骨の奥まで、520名もの故人を思い、遺族を思い、その方々の無念を皮膚感覚で感じ取ったのであった。 さらにその時の惨状を黒澤氏はこう語ってくれた。
「生存者を見つけた日が13日だったから、あれが一番だね。うれしかったよ。
その後は、何日かしてから、手伝ったんたけど、1メートル間隔でナイロン袋を持たされて肉片とか拾ったけど、ウジが湧いて…、ハラワヤもも木に引っかかっていて、とにかくすごい臭いだったよ。椅子に座った状態でさあ、胴体がベルで切れてしまって…
それで家に帰ってね、焼肉を出されたけど、気持ち悪くて食うなかった… 噛んでいるだけでグッと飲み込めないいんだよ。腹が減ってるけど、本当につらかったよ。何も飲み込めないんだから」
消防団員として火事も経験していたそうだが、あれほどの炭化した遺体を見たことがないということであった。
大國氏も身元確認作業で、頭部がめり込んでしまった遺体に自分の手で歯の部分を引き出して、必死に確認しと語る。お二人はまさにあの時、仕事としての責務を超えた状況の中で、自分の命さえもなげうって必死に作業したのである。