3月1日のリサイタル、プログラムの三曲目はショパンのスケルツォ第2番です。ショパンはスケルツォを全部で4曲作曲していますが、中でもこの第2番は最もポピュラーな曲でしょう。
この曲の出だしのところ、とても印象的な「囁くような声(ソット・ヴォーチェ)」とそれに続く大げさでもったいぶったフレーズの掛け合いが登場します。ショパンはこの掛け合いを「質問と応答」だと弟子に教えたそうです。その後も繰り返し登場するこの掛け合いと、それを取り巻く流れるような劇的な旋律の美しさはショパンならではのもの。ここでショパンが思い描いていた問いとその答え、そしてそれを取り巻く情景とは一体どんなものだったのでしょうか? 美しく劇的ではあるけれど、どこか一筋縄ではいかない、若きショパンの冷めたまなざしが感じられる作品です。
手持ちのCDやYouTubeなどで色んなピアニストの演奏をチェックしてみましたが、一番ユニークで面白いと思った演奏がカツァリスの演奏です。この演奏を聴いた時は、衝撃でした。若い頃から弾いてきたこの曲、私はもっと大上段にかまえて大きくて深刻な曲ととらえていたのですが、カツァリスは、「これ、こんな風にね!」とウインクでもしそうなほどの余裕の演奏です。そもそも「スケルツォ」というイタリア語は「冗談(ジョーク)」という意味です。そして「スケルツァンド」という楽語は「気楽に、戯れるように」というほどの意味。カツァリスの演奏を聴くと(観ると)、なるほど「スケルツォ」というのはこういうことなんだと改めてよく分かる気がしました。
というわけで、カツァリスの解釈や演奏ぶりはやり過ぎか?と感じないわけでもないのですが、根底に「スケルツォ」らしさを醸し出しつつ、私自身、これまでとは違った「スケルツォ第2番」を完成させていきたいと思っています。
Scherzo No.2 op.31 Cyprien Katsaris
クリックしていただけると嬉しいです。励みになります。
 にほんブログ村
にほんブログ村
この曲の出だしのところ、とても印象的な「囁くような声(ソット・ヴォーチェ)」とそれに続く大げさでもったいぶったフレーズの掛け合いが登場します。ショパンはこの掛け合いを「質問と応答」だと弟子に教えたそうです。その後も繰り返し登場するこの掛け合いと、それを取り巻く流れるような劇的な旋律の美しさはショパンならではのもの。ここでショパンが思い描いていた問いとその答え、そしてそれを取り巻く情景とは一体どんなものだったのでしょうか? 美しく劇的ではあるけれど、どこか一筋縄ではいかない、若きショパンの冷めたまなざしが感じられる作品です。
手持ちのCDやYouTubeなどで色んなピアニストの演奏をチェックしてみましたが、一番ユニークで面白いと思った演奏がカツァリスの演奏です。この演奏を聴いた時は、衝撃でした。若い頃から弾いてきたこの曲、私はもっと大上段にかまえて大きくて深刻な曲ととらえていたのですが、カツァリスは、「これ、こんな風にね!」とウインクでもしそうなほどの余裕の演奏です。そもそも「スケルツォ」というイタリア語は「冗談(ジョーク)」という意味です。そして「スケルツァンド」という楽語は「気楽に、戯れるように」というほどの意味。カツァリスの演奏を聴くと(観ると)、なるほど「スケルツォ」というのはこういうことなんだと改めてよく分かる気がしました。
というわけで、カツァリスの解釈や演奏ぶりはやり過ぎか?と感じないわけでもないのですが、根底に「スケルツォ」らしさを醸し出しつつ、私自身、これまでとは違った「スケルツォ第2番」を完成させていきたいと思っています。
Scherzo No.2 op.31 Cyprien Katsaris
クリックしていただけると嬉しいです。励みになります。
 にほんブログ村
にほんブログ村












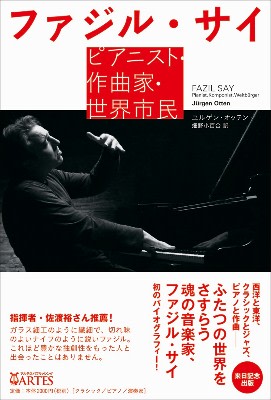



 ©樋崎香
©樋崎香
 ←ここにタイトルが
←ここにタイトルが

