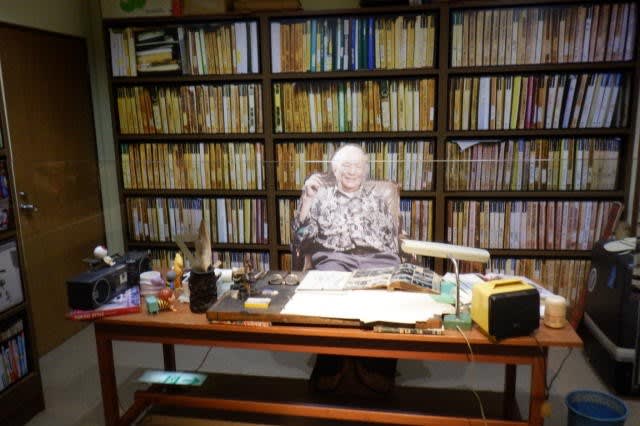大滝根山からしばらく進むと、あぶくま洞がある。ここはもともと石灰岩の採石場で、目の前には採掘の跡が生々しい白い岩山がそびえている。

駐車場を出ると、周りには八重桜や芝桜が咲いている。まだ、この辺りは春になったばかりだ。

入洞券売り場が見えてきた。

長い通路を下っていくと、あぶくま洞の中に入る。ここが、あぶくま洞発見時の入り口だ。この鍾乳洞が発見されたのは昭和44(1969)年。次の採石場を求めて山をダイナマイトで爆破した作業員が偶然見つけたという。開洞は4年後の昭和48(1973)年で、48年前になる。

中に入ると、いろんなネーミングの鍾乳石が出てくる。まずは、妖怪の塔。

恋人の聖地と呼ばれる場所からは、下の方にハートに輝く石の塊が見える。

黄金のカーテン。

滝根御殿。

観音像。

約8000万年をかけて形づくられてきたという大きな鍾乳洞が、この場所に広がっていたとは驚きだ。

あぶくま洞は、鍾乳石の種類と数では東洋一ともいわれるそうだ。

白銀の滝。

樹氷。

龍宮殿。

クリスマスツリー。

出口近くには、ワインセラーがやはりあった。地元・田村市滝根町で採れた山ブドウを使ったワイン「北醇(ほくじゅん)」が貯蔵されている。年間を通して気温変動の少ない洞窟内で半年~1年ほど寝かすと、味がまろやかになるそうだ。

外に出ると、立派な庭園と白い岩山が見える。これもまた絶景である。

あぶくま洞からは、この日の宿となる二岐温泉に向かう。
「2021福島・日本三百名山登山ツアー:2日目二岐山」に続く。

駐車場を出ると、周りには八重桜や芝桜が咲いている。まだ、この辺りは春になったばかりだ。

入洞券売り場が見えてきた。

長い通路を下っていくと、あぶくま洞の中に入る。ここが、あぶくま洞発見時の入り口だ。この鍾乳洞が発見されたのは昭和44(1969)年。次の採石場を求めて山をダイナマイトで爆破した作業員が偶然見つけたという。開洞は4年後の昭和48(1973)年で、48年前になる。

中に入ると、いろんなネーミングの鍾乳石が出てくる。まずは、妖怪の塔。

恋人の聖地と呼ばれる場所からは、下の方にハートに輝く石の塊が見える。

黄金のカーテン。

滝根御殿。

観音像。

約8000万年をかけて形づくられてきたという大きな鍾乳洞が、この場所に広がっていたとは驚きだ。

あぶくま洞は、鍾乳石の種類と数では東洋一ともいわれるそうだ。

白銀の滝。

樹氷。

龍宮殿。

クリスマスツリー。

出口近くには、ワインセラーがやはりあった。地元・田村市滝根町で採れた山ブドウを使ったワイン「北醇(ほくじゅん)」が貯蔵されている。年間を通して気温変動の少ない洞窟内で半年~1年ほど寝かすと、味がまろやかになるそうだ。

外に出ると、立派な庭園と白い岩山が見える。これもまた絶景である。

あぶくま洞からは、この日の宿となる二岐温泉に向かう。
「2021福島・日本三百名山登山ツアー:2日目二岐山」に続く。