★10/04 避難訓練の様子。「決意」すると人間は強くなる◆10/03 全校朝会のスピーチ(あらまし)。
学校からわたしの家までは約10㎞あります。
わたしのはなむけ号(折りたたみ自転車の名前)だと、35分~40分です。
はなむけ号の周りにはたくさん自動車が切れ目なく走っています。
スーパー周辺を通ると、はたくさんの人々が集まっています。
こういうなかを、折りたたみ自転車で、ひとり、タラタラと走る「孤独感」がわたしは大好きです(*^_^*)。
まわりには人々がいる。
たくさんいる。
だけれども、そのだれともつながっていない。
会話を交わしあうような状態ではない。
ポツンと孤独。
わたしはこういう孤独を、「開かれた孤独」と呼んでいます(^_^)v。
この孤独感の中で、わたしは、教師のわたしでもない、夫のわたしでもない、親のわたしでもない、いわば本来の自分?(←そんなもん、あるわけないやろ←ホンネ)とつきあえると感じています(^_^)v。(←錯覚かもしれない。しかし、この錯覚時空間を愉しむ←ホンネ)。
いよいよ秋本番。
みなさんも「開かれた孤独」の中で、自分のこと、自分の過去のこと、自分の先々のことを考えてみることを勧めます。
◆しばらく前から、みなさんに聞いてみたいと思っていることがあります。
前回(市中体秋季大会壮行式)、前々回(市中体報告会)と、ある同じ話をしました。
「人間は決意すると強くなる。」
「感謝すると大人になる。」
「他のためにがんばると美しくなる。」
3つのうち、なんとなくわかる、自分もやれそうだ……というのと、よくわからない、自分にはむずかしそうだ……というのがあると思う。
そこで聞きます。
よくわからない、自分にはむずかしそうだ……と思うものを1つ選んでください。
「決意すると強くなる。」
「感謝すると大人になる。」
「他のためにがんばると美しくなる。」
この中から、自分にはむずかしいというものを1つ選んで手をあげてください。
では、
決意すると強くなる。(8人)
感謝すると大人になる。(300人)
他のためにがんばると美しくなる。(100人)
◆この3つはだれかが言っているとか、どこかの本に書いてあるというのではなく、わたしの体験から言っていることです。
きょうは、みなさんの手がいちばんあがらなかった、すなわち、みなさんが「いちばんわかる」と言っている「決意すると強くなる」について、短く、わたしの体験を話します。
春休みで、だらだらとして、遅く起きて、寝っ転がってテレビで高校野球をみたりしていました。
そういうわたしが、ふとしたことで父親の汗水流して働く姿をみてしまったんです。
父親は気づいていなかったです。
父の姿をみて、「もうしわけない」と思いました。
もう1つ、同じ時期のこと。
わたしは中学のとき、アマチュア無線をやっていました。
当時は送信機や受信機は全部自分で作っていました。
その技術をサークルで教えてもらうんです。
まわりはみんな大人。
当時は中学生の無線技士はめずらしかった。
自己紹介の場面。
大阪朝日放送で○○をしている早川です。
○○高校の島田です。物理を教えています。
生野区の林寺で電気店をやっている五十川です。
いやぁ、格好いいなぁ……と、中学生のわたしは思いました。
みんな自分の仕事をもって、自分で稼いでアマチュア無線をやっているんだなぁ……と。
親の金でやっているのは自分だけだ……。
父の働く姿を見、仕事を持ってがんばっている仲間に出会い……これ以降、わたしは「決意」して、確実に変わりました。
◆その頃のわたしとみなさんが同じ歳です。
みなさんは、日々、決意し、大きく強くなっていく時期です。
決意の10月になることを願っています。(全校朝会のコメントのあらまし、以上)
青い山脈型授業が延々と続く 日本は滅びるでぇ~ イライラ◆10/04、午後から市内中学校教育研究協議会〈領域〉が開かれた。
会場は市内○○中学校。
公開授業が道徳3本、特別活動2本、進路指導1本。
市内の中学校教員600人が参会するというのに、合計6本の公開授業では、ちょっとさびしい。
「いったい、なに考えトンネン!」
最低12本はほしい。
こんなことをしていると、この市は、いや、日本は滅びる。
進路指導の授業、そのあとの進路指導の問題提起(2本)に参加する。
◆部会(道徳3、特別活動2、進路指導1)の閉会式で10分間話す。
まず、授業へのコメント――「いったい、なに考えトンネン。こんなことしてたら、この市は、いや、日本は滅びるでぇ~」という感情が残っていたのか、コメントが乱れる。
乱れる……というのは、「この場面で言うか? いや、やめておくか?」のうち、「やめておくか?」のブレーキが効きにくくなっている……という意味だ。
コメントがアトランダムになっているが、これは乱れではない。
あえて、乱れさせている。
(1)授業冒頭からタラタラと青い山脈型授業――教師が発問をし、数人の生徒がパラパラと手をあげる。教師が1人を指名し、1人が発言。その発言が望んでいたものでない場合、教師は「ほかに?」とさらに挙手を促す。これをくりかえす――をやっている。
はっきりいうけど、半ばあきれて観ていた。
が、結果として15分後、生徒全員(1人1人)に学習課題をしっかりつかませていた。
これは見事だ。
感激した。
スゴイ。
ただし、できれば5分間で、この過程は終わらせたい。
(2)今、述べた青い山脈型授業だが、冒頭だけでなく、授業の終わりまで延々と続く。
決して、青い山脈型の全部を否定するわけではない。
しかし、ポイント、ポイントでは、たとえば、賛成か反対かを挙手させたり、あるいは短くその理由を書かせたりする等、適切な「短い作業」を取り入れる授業設計が必要だ。
(3)指導者の目線に課題がある。
全体を見ていない。
教卓からみて左後方に厚く、右後方に薄い。
前方は、ほとんど欠落。
くわえて、目線が流れている。
教室の隅から隅まで、1人1人と目をあわせ、指示し、語り、授業が終わったあと「わたしと目があった人」と聞いたら、全員挙手するような目の配り方が必要だ。
(4)「これから5分間でやってもらいます。3分間で切り上げるかもしれません」というような指示・時間設定はしない。
「まだの人もいますが、はい、やめなさい」もマズイ。
(5)授業の展開に積み重ねがない。
次から次に学習課題に取り組ませるだけで、前の学習があとの学習に生かされていない。
「ニートが増える理由」をグループで話し合わせ、発表させたあと、それに対する教師の評価やまとめがないまま、次にいきなり「生徒のグッジョブ前後のアンケート」が提示される。
わたしだったら、生徒のグッジョブ体験をもとにして、「ニートが増える理由」を考えさせる。
授業者はきょうの授業の展開を「力わざ」と言っているが、「力わざ」の意味を取り違えているのではないか?
こういう授業のやり方を「力わざ」とは言わない。
こういう授業でいいなら、こんなに楽な仕事はない。
(6)語りが魅力的だ。
自分の思い(楽しい・興味がある等)が的確に生徒に伝わっている。
これは、うらやましい。(授業対するコメント以上)
というようなコメントを述べたのだが、やはり授業する者としての基礎・基本(みなみ中でいうと「授業力向上の5原則」のようなもの)をきちんとマスターしないと伸びない。
みなみ中の授業を見慣れていて、他の授業を見ると、その落差に驚く。
このままでは日本は滅びる。
◆問題提起2本に対しては、2本に共通していた「新入試制度」に関する管見を短く述べる。
ここでは、その骨子のみ。
①学力測定方法の追究
②中学校・高等学校の関係の追究。
③学校教育と社会教育の関係の追究。
今のオマエの姿で
その人の前に立てるか?
★10/04 北校舎2F・図書室からの風景。◆前回(10/1)の「職員室通信」で、わたしが「公式HPのDiary」に「1ヵ月の空白」+「2週間の空白」をつくってしまうくらい、精神的絶不調に陥ったという話をした。
そして、(長期の休み明けに)「アイデンティティの空間軸の崩壊が、それに複雑に絡みつつ形成されている時間軸の崩壊につながる」中・高校生の症状に似ているとも述べた。
「空間軸」(所属する社会との連続性)というのは、「同級生のU君のようになりたい」とか「同僚のVさんに負けたくない」とか「職場の同僚たちに認められたい」という「同じ時空間に存在する他の人間」と「自分」の関係だ。
「時間軸」(自己の時間的・歴史的連続性)というのは、ま、いってみれば、「わたしは、将来、新聞記者か放送記者になりたい」とか「わたしは、将来、医療で社会に貢献できる人間になりたい」という「現在あるいは過去の自分」と「未来の自分」の関係だ。
当然、この2軸は絡み合っている。
ただ、経験的にいうと、世の中には、やたら時間軸にこだわる人間と、反対に、やたら空間軸を気にする人間とが存在する。
わたしは、自分のことを、U君も、Vさんも、関係ない……、ひたすら、わが道を驀進する、徹底した「時間軸」人間だと思いたがるところがある。
そのように見せたがるところがある。
しかし、ほんとうのところは、その逆なのだ。
証拠に、わたしは「オマエは、今のオマエの姿で、その人の前に立てるか?」という「その人」を「空間軸上」に設定している。
4人いる。
設定の根拠については、4人が存命中なので触れないが、この「4人の設定」は、自分が死ぬまで解除するつもりはない。(1人、2人と追加することはあり得る。)
いわば、同空間軸上に存在する4人を北斗七星として、大海原=時間軸上を疾駆している……ということになる。
◆この同空間軸上に存在する4人と、9月の絶不調とが密接不離の関係にあるのではないか?
4人は、いずれも、かつて、わたしと同じ空間に存在した人物だ。
それぞれ時代は違う。
やがて、みんな、別々の空間へと別れることになった。
別々の空間に存在しているから「今のオマエの姿で、その人の前に立てるか?」と言えるわけだ。
ところが、運命のイタズラなのだろうか?
2005~2006にかけて、万にひとつの確率で、次々にわたしの目の前に現れることになる。
結論だけをいう。
「今のオマエの姿で、その人の前に立てるか?」
残念ながら、立てなかったのだ。
この打撃が、8月終わりから9月に一気に来たのだ。
今の姿と、願わくは、同空間軸上に存在する4人の前で、こうありたいと思う姿との、微妙なヒズミが、たまりたまって、9月に巨大なヒズミとしてむき出しになったのだ。
もう一度、「職員室通信」を引用する。
「空間軸の崩壊が、それに複雑に絡みつつ形成されている時間軸の崩壊につながるのだろう。
いわゆる日本的美意識としての無常観に少し似ている。
わたしはキライではないが、子どもが長期間、この精神状態にあることは危険だ。」
冗談ではなく、今、わたしは「危険」な状態にある。
◆きょう、珍しい人に遭遇した。
(断っておくが、先の「4人」とは関係ない(^o^)。)
現実から遠い遠い距離の、古い古い時間の層が崩れ、ひょっこり出てきたという感じで、心臓が止まるくらい驚いた。
その人は、病院の自動ドアの向こうにいた。
一歩出たところで、
「おひさしぶり」
と声をかけられた。
ほんとうにひさしぶりで、指を折って数えたら25年ぶりだ。
2度、3度と「変わってないね」と言われたので「いやぁ、やはり加齢とともに、あちこち、いろいろと……ね」と笑ったら、
「その言い方が変わっていないよ」
とからかわれた。
わたしも負けないように「あなたも変わってないね」と言いかえしたのだが、これはウソではない。
ボールペンが万年筆くらいに体型は変わっていたけれど、空間への存在の仕方と、その空間から次の空間へと移動しようとするエネルギーの質は昔のままだった(*^_^*)。
翌日、しかし、なにかが変わっている……と感じた。
ここはエッセーを書くスペースではないので、わたしがその「なにか」にたどりつく過程はパスする。
喫茶店などで向かいあって語りながらでも、うちにシンと鎮まり、遠くを見つめているような「視線」(これは現実のなにかをみる視線でも、他人から見られることを意識した視線でもない)が、欠落していた(ように思えた)。
知人の25年の見過ぎ世過ぎの「時間軸」と「空間軸」を想った。
エッセーだと、ここで自虐的に自分の側にふるという「オチ」が来るのだが、きのうもきょうも自虐、自虐だから、これはパスする^^;^^;σ。
◆同空間軸上に存在する4人の北斗七星について話をつづける。
実は、2005~2006にかけて、その「4人」は、今、述べたように、万にひとつの確率……といった感じで、次々にわたしの目の前に現れた。
ここでは4人目の「八木」という男の現れ方を紹介しよう。
八木というのは、このHPの右サイドバーの下のほうに張り付けてあるハガキ(←今は削除)の主だ。
学生時代、八木からもらったハガキだ。
現在、某企業の研究所で所長をやっている。
何度か、このハガキを削除しようとしたのだが、削除すると、サイドバーのカタチが崩れてしまうので、仕方なく、ズルズルと、そのままにしてあった。
4月25日の全校朝会で、わたしは生徒に次のような話をした。
骨子をアップする。
中学という時代、思春期という時代は、未来にむかって人生、独立のために一歩一歩前進していく時代だ。
「お父さん、お母さん、ここまでこんなふうに育ててくれて、ほんとうにありがとう。まだまだ心配をかけるけれども、これからは自分でやれることは自分でやるようにがんばり、お父さんやお母さんに心配をかける量をへらしていきます。」
親に心配をかける量を減らしながら、逆に、自分で判断し、自分で責任をとる量を徐々に増やして、親の庇護から離れ、一歩、一歩、大人の仲間入りをしていく。
心も体も飛躍的に成長していく。
これが中学という時代だ。
しかし、自分で判断し、自分で責任をとるということはなかなかたいへんなことだ。
迷うことも多い。
苦しみ、悩み、時には大失敗をしてしまう。
そういう君たちにひとつアドバイスをしたい。
自分が何かをしようとするとき、「意識する人間」、「気にする人間」を3、4人持つといい。
こうしようと思うが、この人はどんなふうに思うだろう?……と。
今のような自分の姿で、この人の前に出られるか?……と。
わたしにも意識する、意識してきた人間が4人いる。
1人は八木という男で、わたしと同じ年齢で、高校・大学時代の友人だ。
2人目は教え子で、教師1年目、学級担任をしていたクラスの生徒だ。
3・4人目は同じ教師で、わたしより歳が若い。
◆ま、だいたい、こんな話だった。
「八木」という実名を出したのは、勢いあまったのか? あるいは、他の3人は現れたが、八木は現れていない……もう現れることもないだろう……という、わたしの人生の中では、現存在の人物というより、既に非現実の存在という認識が強かったのか?
と、なんと、その夜、八木からメールが届いた。
36年間、相互に音信不通状態だったのに、全校朝会で八木の話をしたとたん、その本人からメールというのは、どう考えても、あり得ない話だ。
(みなみの生徒には、ほんとうに申しわけないが)瞬間的に、生徒のイタズラメールだと思った。
しかし、読みすすめていくと、「阿倍野カトリック教会」「天王寺区清水谷の公園」「生野区の喫茶店」など、八木とわたししか知らない単語がでてきて、ホンモノの八木だとわかった。
八木のメールによると、4/24の昼休み、部下の、生まれたばかりの子どもの名前で盛り上がり、互いの名前の同姓同名を「グーグルって」いるうちに、「所長(←八木のこと)、こんなのがありますよ」と、わたしのHPを教えられたそうだ。
「自分の昔の葉書がそのまま掲載されている君のHPに衝突した。なにか虚空に向かっているような気がした」と八木は書いている。
◆「今のオマエの姿で、その人の前に立てるか?」の「その人」が、マサカ、マサカで次々に眼前に現れ出たことで、わたしは絶不調に陥る。
現れ出なければ、わたしは絶不調に陥ることはなかった……と思う。
2004までの、ま、好調とはいえないが、絶不調ではない、それなりの安定したペースで、ずっと生きていったと思う。
そのままのほうがよかったのか、今の絶不調に陥るほうがよかったのかは、微妙だ。
絶不調は、ほんとうに苦しい。
もう立ち直れないだろう。
しかし、この絶不調を知らないで、生きていくというのは、また大きな不幸であるような気もする。
「4人」の話は、シンドイので、これで、いったん休むことにする。
いや、もう話すことはないだろう。
★メモ あいかわらず市内の中学校は学年1年→2年→3年と進むに連れて成績が下降している。
かつ、2つのグラフ(Web版では省略)を重ね合わせるとよくわかるのだが、下降の度合いがよりきつくなっている。
この市は、ピンチだ。
そのなかにあって本校の2学年、3学年はともに学力を維持している。
「絶対に下げない作戦」が実った格好だ。
今後は、低学力生徒に対して具体的な対策が立てられるかどうかが重要な課題になる。
公立中のプロ教師として、塾や高等学校に「丸投げ」することだけは絶対に避けたい。
対策強化期間第1期=9/21(木)~10/13(金)の2週間、第2期=10/25(木)~11/24(金)の3週間。
叡智を結集。
| |
★今年もカリンが実った。豊作だ。カタチもきれい。しかし、なんだか実が大きすぎる(←カリン酒の心配をしている(*^_^*)。 |
|
〈文責=小高 進〉
★公式ホームページへ
★WEB無人駅線ページへ



































 毎度、毎度、提示する図だ。
毎度、毎度、提示する図だ。









 ――場末の寄席
――場末の寄席






















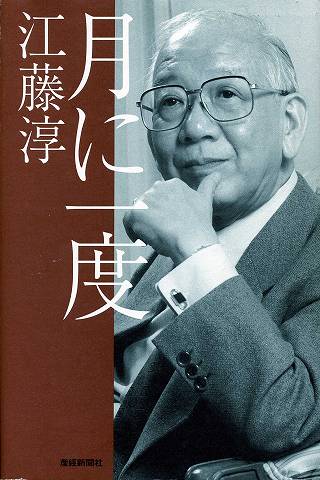 ◆今年の初夢(1/2)に江藤淳氏が登場した。
◆今年の初夢(1/2)に江藤淳氏が登場した。

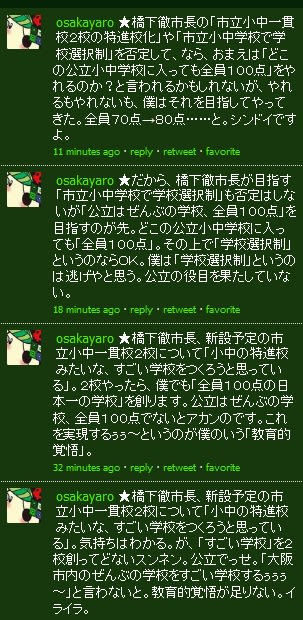 ★左の画像は、僕のtwitterのプロフィールウィジェットだ。(HPをご覧の方は、――画像ではなく――左側にホンモノのプロフィールウィジェットが見えるはずです。)
★左の画像は、僕のtwitterのプロフィールウィジェットだ。(HPをご覧の方は、――画像ではなく――左側にホンモノのプロフィールウィジェットが見えるはずです。)









