★日曜日の朝――僕のなかでは、6月21日午前5時半(ローカルタイム午前6時半)、辛坊治郎氏からの「定時連絡」=「現在位置 北緯33度03分 東経152度34分。曇り。西南西の風25ノット。波うねりは2メートル程度と依然かなり高く、時折右舷真横からの波に大きく傾斜させられるものの、概ね右舷後方からの波を受けながら南東方向に6~7ノットで快走中。船内にいると、計器上の風が本当に吹いているのかと思うほど穏やかで快適な走り。レギュラージブ、ヘッドセールチョイだし。メインは降ろしたままです。」――を受けた時点で時計が止まっている。 辛坊は今でも太平洋を南東方向に驀進するエオラス号の中でコーヒーを沸かしている。 その辛坊とガラス1枚隔てたDAKA古書店跡のウッドデッキで朝食をとる。 朝食メニュー=グリーンリーフの山盛り・キュウリステックと味噌・薄くバターをぬったトースト1枚・コーヒー2杯(マンデリン)・プロセスチーズ1個・森永ビヒダスヨーグルト1個。 先日(6/25)、HPを更新した直後から少し逡巡することがあり、落ち込んでいたが、エオラス号の辛坊のことを考えていたら、また元気になった。 ★朝食後、あしゅら堂主人宛てにメール ――おはよう!(^_^)v ライオンズは現在=34勝34敗(ノ△・。)。 ここ10試合=3勝6敗1分(ノ△・。)。 ま、しかし、首位の頃は、勝ちながら徐々に弱くなっていく――先発陣の疲労がたまったら終わり……打撃陣がいつまでも打ちつづけるわけがない……中継ぎ陣の弱さも露呈……)という居心地の悪さがあったが、最近は、負けながら徐々に強くなっていく感じがする。 きのう、7回裏に投げた増田達至。 初登場から注視してきた。 しかし、コイツはアカン……とても使えない……なんでこういうヤツをドラ1で獲るんや……と思っていた。 が、きのうは本領発揮。 将来性を感じた。 それに8回裏に投げた岡本洋介。 前回の楽天戦は1インニング5失点とボロボロやったが、きのうは思いっきりのよさ&鋭さ――ま、ちょっと主審のストライクゾーンが広かったけど――を感じた。 それに、いつやったか期待の涌井がボロボロでひっこんだあとに投げた中雄太。 彼は絶対にいけると思うよ。 今、負けつづけてはいるけれども、こうやって確実に次の戦力が増殖中。 先日2軍で好投したウィリアムスもベンチに入っている。 もうすぐ、先発が5、6回まで投げたら、あとはOKという体制が整う。 そのうち西口も先発で出てくるんやないやろか。 7、8月、大爆発や。 右のおかわり、左のおかわりのそろい踏み。 最後は伊東ロッテと激突や。 二伸――きょうは岸。 ま、90%、だいじょうぶやと思う。 小爆発でロッテの次に、すなわち2位になったら天満の奥田でいっしょに飲みまひょ(^_^)v。
★さらにリアルな情報は僕の公式ホームページへ★ ★僕のWEB無人駅線ページへ |
|||||||||





















 先日紹介した「オマエは、今のオマエの姿で、その人の前に立てるか?」という「その人」のうちの1人=Yと別れた場面も、そうだ。
先日紹介した「オマエは、今のオマエの姿で、その人の前に立てるか?」という「その人」のうちの1人=Yと別れた場面も、そうだ。


 小高進〈大阪野郎〉 @osakayaro
小高進〈大阪野郎〉 @osakayaro
 ★僕は、自分がいい気にならないように、「オマエは、今のオマエの姿で、その人の前に立てるか?」という「4人」の「その人」を設定してきた。
★僕は、自分がいい気にならないように、「オマエは、今のオマエの姿で、その人の前に立てるか?」という「4人」の「その人」を設定してきた。 ★ところが、運命のイタズラなのか? ある年、4人が次々と僕の目の前に現れた。
★ところが、運命のイタズラなのか? ある年、4人が次々と僕の目の前に現れた。 でも、やはり苦しい。
でも、やはり苦しい。











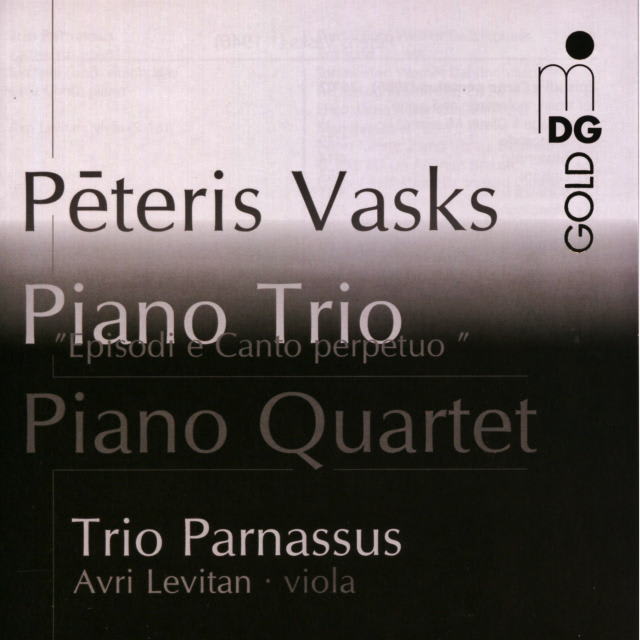













 小高進〈大阪野郎〉 @osakayaro
小高進〈大阪野郎〉 @osakayaro

























