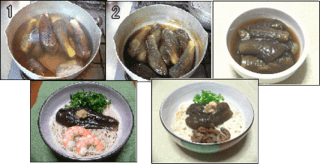リーフサラダ・・・青い葉物ばかりのサラダです。
葉っぱものは、重さが軽いので、写真のような大皿にもりつけても、
180gしかありません。
カロリーにしたら、60キロカロリーあるなしです。
でも、これにオイルをまぶして、ドレッシングソースを大さじ1杯ずつ、
ふりかけると、170Kilocal.も増えて、230kilocal.になります。
ダイエットを目指すときは、油気なしの野菜をたっぷり食べてから、
ご飯と主菜をたべるようにします。
野菜でおなかが半分ふくれて、ご飯と主菜は少なくなるはずです。
少ない調味料で、生野菜をたくさん食べるのは、慣れないとつらいもの、
そんなときは、先にお送りした、温野菜と組み合わせて食べます。
温野菜と生野菜とを、交互に食べると、案外おいしくいただけます。
リーフ野菜は、9種類も書きましたが、全部をまぜて食べるのではなく、
5~7種類を取り合わせてサラダにします。
写真のダンディリオンは栽培種のタンポポで、種からそだてました。
タンポポの葉の切れ込みが、ライオンの「たてがみ」に似ているとして
ダンディライオン=ダンディリオンと名づけられました。
ロゼット状になったダンディリオンの葉は、さしわたしで60センチも
あります。食べたら柔らかくて、野生のものほど苦くありません。
スティックセニョール(茎ブロッコリー)の中心が欠けているのは、
切りとったあとです。こうすると周囲のつぼみがぐんぐん伸びてきて、
30センチほどのスティック状のブロッコリーになるすぐれものです。
茎は柔らかく、茹でてマヨネーズで食べますが、アスパラガスに似た
味で、これから春先まで、つぎつぎに伸びてまいります。
リーフはプランターでも簡単に作れ、ベビーリーフの種も売っています。
興味のある方はやってみてはいかがですか。
リーフサラダの葉っぱの熱量はすくないのですが、オイルとドレッシングが高カロリーになります。
葉っぱだけでは食べにくいので、オイルも使いますが、できるだけ控えめにしましょう。
材料
ダンディリオン(西洋タンポポ)
ルッコラ(ロケット・サラダ)
サラダ水菜
サラダほうれんそう
しゅんぎく
パセリ
みつば
せり
レタス
以上は手でちぎる
人参
スティックセニョール(ブロッコリーの一種)
( 軽く茹でるか生でも良い )
イタリアン・ドレッシング・ソース
作り方
葉っぱものは、5~7種類を使う。
ダンディリオンは少し苦味があるので、
量を加減する。
香りの強い、パセリ、芹、ミツバと
水菜、ほうれんそう、ルッコラなどと
組み合わせて盛り合わせる。
彩りににんじんを薄く切ったのや
プチトマトを添える。
葉っぱものは、嵩が高くても重量は
少ない。写真のリーフサラダは大皿に
盛ってありますが、これでも200gしか
ありません。
葉っぱには、オイルをたらしてさっくりと
混ぜ合わせて、ドレッシングソースを
適量振りかけていただきます。
オイルは大さじ1=12g、110㎉あり、
ドレッシングも大さじ1=15g、60㎉
あるので、控えめに使ってください。
葉っぱものは、重さが軽いので、写真のような大皿にもりつけても、
180gしかありません。
カロリーにしたら、60キロカロリーあるなしです。
でも、これにオイルをまぶして、ドレッシングソースを大さじ1杯ずつ、
ふりかけると、170Kilocal.も増えて、230kilocal.になります。
ダイエットを目指すときは、油気なしの野菜をたっぷり食べてから、
ご飯と主菜をたべるようにします。
野菜でおなかが半分ふくれて、ご飯と主菜は少なくなるはずです。
少ない調味料で、生野菜をたくさん食べるのは、慣れないとつらいもの、
そんなときは、先にお送りした、温野菜と組み合わせて食べます。
温野菜と生野菜とを、交互に食べると、案外おいしくいただけます。
リーフ野菜は、9種類も書きましたが、全部をまぜて食べるのではなく、
5~7種類を取り合わせてサラダにします。
写真のダンディリオンは栽培種のタンポポで、種からそだてました。
タンポポの葉の切れ込みが、ライオンの「たてがみ」に似ているとして
ダンディライオン=ダンディリオンと名づけられました。
ロゼット状になったダンディリオンの葉は、さしわたしで60センチも
あります。食べたら柔らかくて、野生のものほど苦くありません。
スティックセニョール(茎ブロッコリー)の中心が欠けているのは、
切りとったあとです。こうすると周囲のつぼみがぐんぐん伸びてきて、
30センチほどのスティック状のブロッコリーになるすぐれものです。
茎は柔らかく、茹でてマヨネーズで食べますが、アスパラガスに似た
味で、これから春先まで、つぎつぎに伸びてまいります。
リーフはプランターでも簡単に作れ、ベビーリーフの種も売っています。
興味のある方はやってみてはいかがですか。
リーフサラダの葉っぱの熱量はすくないのですが、オイルとドレッシングが高カロリーになります。
葉っぱだけでは食べにくいので、オイルも使いますが、できるだけ控えめにしましょう。
材料
ダンディリオン(西洋タンポポ)
ルッコラ(ロケット・サラダ)
サラダ水菜
サラダほうれんそう
しゅんぎく
パセリ
みつば
せり
レタス
以上は手でちぎる
人参
スティックセニョール(ブロッコリーの一種)
( 軽く茹でるか生でも良い )
イタリアン・ドレッシング・ソース
作り方
葉っぱものは、5~7種類を使う。
ダンディリオンは少し苦味があるので、
量を加減する。
香りの強い、パセリ、芹、ミツバと
水菜、ほうれんそう、ルッコラなどと
組み合わせて盛り合わせる。
彩りににんじんを薄く切ったのや
プチトマトを添える。
葉っぱものは、嵩が高くても重量は
少ない。写真のリーフサラダは大皿に
盛ってありますが、これでも200gしか
ありません。
葉っぱには、オイルをたらしてさっくりと
混ぜ合わせて、ドレッシングソースを
適量振りかけていただきます。
オイルは大さじ1=12g、110㎉あり、
ドレッシングも大さじ1=15g、60㎉
あるので、控えめに使ってください。