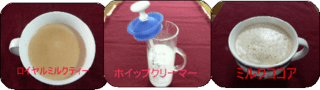4月から特定検診・特定保健指導が実施されるそうで、検診結果の
次第では毎日の食事が影響されそうです。
毎日の食事を制限されるのは、生活習慣として、当人としては面食らうものです。
今回のオペのあと、毎日の食事はかたいもの避けて「とにかく柔らかいもの」を食べること
そして「酒をはじめ刺激物」を当分ダメ・・・と担当医から申し渡されました。
食材が制限されるので、毎日の摂取カロリーが足りないのでは・・・と思い、
少しでもカロリーを増やそうと考えたのがレシピのミルクティーとミルクココアでした。
レシピのティー・ココアはミルクをベースにするので、水ベースのものよりも
カロリ-は高いと思います。
子供たちが幼いころ、ミルクココアをよく作りましたので、そのころを思い出しました。
ハーシーとヴァンホーテンに微妙な味の違いがあるのも再認識しました。
レシピのミルクココアは塩を加えてありますが、これはハーシーのときでした。
ヴァンホーテンをつかうときは、加えないでもよろしいか・・・と思います。
ティータイムのとき、一度お試しください。
ロイヤルミルクティー・ミルクココア
寒い日の朝食にトーストのお供に、午後のアフターヌーンティーのとき、濃厚な味のロイヤルミルクティーは
体のしんから温まってほっこりします。 ホイップしたミルクか生クリームを乗せたミルクココアは午後の
ティータイムに、また夜遅くお腹が空いて何か欲しい・・・そんな時頂くとおいしいものです。
ロイヤルミルクティー
材料
紅茶 大さじ 1
牛乳 2カップ
お湯 大さじ3~4杯
好みにより砂糖 適宜
作り方
小鍋(専用のミルクバンが望ましい)に紅茶を入れて
お湯を(茶葉に)万遍なく振りかけて2~3分蒸らす。
(丁寧にするならふたをして冷めないように蒸らす。)
別鍋で温めておいた牛乳2カップを鍋に入れてマドラーか
スプーンでかき混ぜながら中火でじっくり(紅茶を)煮出す。
沸騰直前に火から下ろして全体をかき混ぜて
茶漉しで漉して出来上がり。
(牛乳を温めるとき、沸騰点近くになって沸点を超えると一気に
ワアーッと沸きあがって煮こぼれる。この紅茶を作るときは
出来上がりまで、鍋につきっ切りで作る。)
温めた器に注いで熱いうちに飲む(砂糖はグラニュー糖がベター)。
ミルクココア
材料
ココア 大さじ 2杯
牛乳 2カップ
お湯 大さじ3~5杯
グラニュー糖 大さじ3~4杯
しお 少々(ほんとに少し)
作り方
小鍋にココアとグラニュー糖を入れてマドラー(又はスプーン)で
良くかき混ぜる(ココアと砂糖をまんべんなくなじませる。)
次に、お湯を加えてマドラーで良く練りながら混ぜる。
(ここで砂糖を良く溶かしながらココアがダマにならないよう練りこむ。)
別鍋で温めておいた牛乳1.7カップを鍋に入れてマドラー
かスプーンでかき混ぜながら中火でじっくり煮る。
味見して甘味が足りないようなら適宜加え、美味しい味に
なったらふっとう直前に火を止めて、仕上がりに食卓円を
ほんの少々加える(これで味がグッと締まってこくのある美味しい
ミルクココアができる・・・塩を入れすぎると逆効果になるので控えめに。)
器に注ぎ、ホイップした牛乳を注いで出来上がり。(ホイップクリーマーを使うと手軽で便利)。
牛乳の残り0.3カップを温めてホイップクリーマー(写真)か泡だて器などでホイップする。
次第では毎日の食事が影響されそうです。
毎日の食事を制限されるのは、生活習慣として、当人としては面食らうものです。
今回のオペのあと、毎日の食事はかたいもの避けて「とにかく柔らかいもの」を食べること
そして「酒をはじめ刺激物」を当分ダメ・・・と担当医から申し渡されました。
食材が制限されるので、毎日の摂取カロリーが足りないのでは・・・と思い、
少しでもカロリーを増やそうと考えたのがレシピのミルクティーとミルクココアでした。
レシピのティー・ココアはミルクをベースにするので、水ベースのものよりも
カロリ-は高いと思います。
子供たちが幼いころ、ミルクココアをよく作りましたので、そのころを思い出しました。
ハーシーとヴァンホーテンに微妙な味の違いがあるのも再認識しました。
レシピのミルクココアは塩を加えてありますが、これはハーシーのときでした。
ヴァンホーテンをつかうときは、加えないでもよろしいか・・・と思います。
ティータイムのとき、一度お試しください。
ロイヤルミルクティー・ミルクココア
寒い日の朝食にトーストのお供に、午後のアフターヌーンティーのとき、濃厚な味のロイヤルミルクティーは
体のしんから温まってほっこりします。 ホイップしたミルクか生クリームを乗せたミルクココアは午後の
ティータイムに、また夜遅くお腹が空いて何か欲しい・・・そんな時頂くとおいしいものです。
ロイヤルミルクティー
材料
紅茶 大さじ 1
牛乳 2カップ
お湯 大さじ3~4杯
好みにより砂糖 適宜
作り方
小鍋(専用のミルクバンが望ましい)に紅茶を入れて
お湯を(茶葉に)万遍なく振りかけて2~3分蒸らす。
(丁寧にするならふたをして冷めないように蒸らす。)
別鍋で温めておいた牛乳2カップを鍋に入れてマドラーか
スプーンでかき混ぜながら中火でじっくり(紅茶を)煮出す。
沸騰直前に火から下ろして全体をかき混ぜて
茶漉しで漉して出来上がり。
(牛乳を温めるとき、沸騰点近くになって沸点を超えると一気に
ワアーッと沸きあがって煮こぼれる。この紅茶を作るときは
出来上がりまで、鍋につきっ切りで作る。)
温めた器に注いで熱いうちに飲む(砂糖はグラニュー糖がベター)。
ミルクココア
材料
ココア 大さじ 2杯
牛乳 2カップ
お湯 大さじ3~5杯
グラニュー糖 大さじ3~4杯
しお 少々(ほんとに少し)
作り方
小鍋にココアとグラニュー糖を入れてマドラー(又はスプーン)で
良くかき混ぜる(ココアと砂糖をまんべんなくなじませる。)
次に、お湯を加えてマドラーで良く練りながら混ぜる。
(ここで砂糖を良く溶かしながらココアがダマにならないよう練りこむ。)
別鍋で温めておいた牛乳1.7カップを鍋に入れてマドラー
かスプーンでかき混ぜながら中火でじっくり煮る。
味見して甘味が足りないようなら適宜加え、美味しい味に
なったらふっとう直前に火を止めて、仕上がりに食卓円を
ほんの少々加える(これで味がグッと締まってこくのある美味しい
ミルクココアができる・・・塩を入れすぎると逆効果になるので控えめに。)
器に注ぎ、ホイップした牛乳を注いで出来上がり。(ホイップクリーマーを使うと手軽で便利)。
牛乳の残り0.3カップを温めてホイップクリーマー(写真)か泡だて器などでホイップする。