





1949年、ポーランドのウッチ造形大学の教授で前衛画家のヴワディスワフ・ストゥシェミンスキは、野外の授業で学生たちと談笑を交えながら、熱く自らの理論を説く。
「残像は、ものを見たときに目の中に残る色なのだ。人は認識したものしか見ていない」
ある日、アパートで真っ白なキャンバスに向かって絵筆を走らせようとした瞬間、窓の外に真っ赤な垂れ幕が掛かったため、キャンバスは鈍い赤色に染まる。これでは絵を描けないと、ストゥシェミンスキは部屋の中から窓の外の垂れ幕を杖で切り裂く。それは、スターリンの肖像が描かれたプロパガンダの垂れ幕だった、、、。
ここから、ストゥシェミンスキが死に至るまで、芸術弾圧との闘いの日々を描く。昨年急逝したワイダの遺作。
、、、嗚呼、ポーランド。
☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜
また、ポーランド映画です。これは前から見たかったので、出不精の私が、わざわざ週末出かけて見に行きました。相変わらず、岩波ホールの観客は年齢層が高く、こういう映画は、若い人は興味ないのかな、、、と、ちょっと淋しくもあり。
◆ポーランド人のお名前が難しいの件。
ストゥシェミンスキ、、、というお名前。何度聞いても、見ても、ゼンゼン覚えられない。ポーランド人の名前、ちょっと難しいです。
“ヴワディスワフ”というファーストネームは、あの『戦場のピアニスト』の主役であるウワディスワフ・シュピルマンのそれと同じのようです(原語表記が同じ)。シュピルマンは、作中、親しい人たちに“ウワディク”と呼ばれていましたが、本作では、ストゥシェミンスキが教授=先生としての立場で描写されているシーンが多いので、親しく“ウワディク”と呼んでいる人はいなかったような気がします。見落としただけかも知れませんが。
いずれにしても、ウワディスワフというファーストネームは、割とポピュラーなものなのだと思われます。
シュピルマンは、すんなり頭に入ってくる響きだけれど、ストゥシェミンスキはどうも、、、。ようやく、今頃になって頭にも目にも馴染んできたかな、、、という感じです。
◆戦争が終わっても、ポーランドの苦悩は続く、、、。
さて、『戦場のピアニスト』では、戦争が終わって地獄の様な日々にも終止符が打たれた、、、という余韻で終わったけれど、ストゥシェミンスキ氏が、ポーランド統一労働党(共産党)に目を付けられ、どんどん追い詰められていく様が淡々と描かれている本作を見ると、戦争が終わっても全然ポーランド国民は心安らぐ平穏な生活など、手に入れることが出来ていなかったのだと思い知らされました。
もちろん、シュピルマンも、戦後、共産党に目を付けられていたことは後になって調べて分かったのだけれども、『戦場のピアニスト』ではそこまでは描かれていなかった。ポーランド軍とソ連軍の力関係、両国の地勢関係や政治体制からくる事実上のソ連支配の下、ストゥシェミンスキやシュピルマンなどの芸術家たちは、程度の差はあれ、皆、不本意な思いを抱かされていたということ、、、。
作中、こんなセリフがあります。「芸術家を殺すには、無視するか、徹底的に批判するかだ」(セリフ正確ではありません)。
ただ、ここでいう「無視する」は、ストゥシェミンスキの受けた仕打ちから見て、文字通りの「無視」ではなく、一般市民たちから無視される様に仕向ける=一般市民たちの目に入らない様にする、ということであって、そのためには、共産党は凄まじい労力を厭わないのだから、怖ろしい。
ストゥシェミンスキを、大学から追い出すのなんて当たり前。表だった仕事はとことんその門戸を閉ざされる。背に腹は代えられず、と悟ったのか、こっそりと始めた共産党のプロパガンダ看板に絵を描くという、一見主義に反する様な仕事をしてわずかな食い扶持を稼ぎ始めたのも束の間、どこからかバレてクビになる。食料配給券ももらえないので、食べ物にもありつけず、芸術家協会から追い出されて会員証も取り上げられたために画材も売ってもらえない。徹底的に監視して、生命維持が不可能なほどまでに追い詰める、、、。
まぁ~、とにかく陰険極まりないです。美術館からはストゥシェミンスキの作品は乱暴に残らず撤去され、学生たちとの展覧会会場であるギャラリーには党員たちが乱入して作品をメチャメチャに叩き壊す。自尊心を徹底的に破壊する方法を取るわけね。それでもストゥシェミンスキはめげないんだけど、やっぱり兵糧攻めは、いかな信念の人でも、物理的にヤラレてしまう。食べなきゃ、衰えるか病気になるかしかないものね、人間なんて。
一方では、テキトーに共産党にすり寄りながら、生き延びる芸術家たちも当然いるわけで、そういう人たちの中には、ストゥシェミンスキみたいに、信念を貫く生き方をしている人を羨ましく思う人もいる。いるけど、じゃあ、自分もそうできるか、というと、できないし、そんなことしてまでポリシーを貫く意味を感じられない、ってことなのかも知れない。生きてなんぼ、と思うのもまた、決して間違いではないし、安全な場所にいる我々が責められる立場にないことも確か。
私なら、もちろん、体制にテキトーに迎合していると見せつつ、腹の中では、早くこんな世の中終わっちまえ! と、どこかの前事務次官じゃないけど「面従腹背」を地で行くと思うなぁ。人間、死んだら終わり、というのは真理だと思うので。
ただ、芸術家というのは、それが非常に難しい。フジタも戦時下で従軍画家だったことを、戦後かなり批判されたけれど、結局、そういう“変節”が許されない人たちだから、、、。生きる術であっても、変節と受け止められてしまう。虐げられても信念を曲げることが許されない、それこそ、白か黒かを強いられる。人間なんて、そもそもいい加減で、いくらでも都合良く変節する生き物だと思うんだけど、、、。
◆だめんずストゥシェミンスキ。
思想面では信念を貫くストゥシェミンスキも、私生活の方はだめんずっぽい。
ポーランドの著名な彫刻家だったカタジナ・コブロとは離婚。元妻コブロが非業の死を遂げても、葬式にも参列できない。一人娘のニカだけは参列するが、赤いコートしか持っておらず、他の参列者に「葬式に赤いコートなんて」と陰口を叩かれる。しかし、ニカは黙っていない。「これしかないの!!」と怒り、コートを脱ぐと裏返して、黒っぽい裏地の方を表にして着直す、、、。
元妻の死で、ニカと2人暮らしを始めるが、学生の一人ハンナが足繁くストゥシェミンスキの家に通ってくるため、ニカは居場所がないと感じ、「学校の寮に入る!」と言ってストゥシェミンスキの家を飛び出す。なのに、ストゥシェミンスキは止めもしない。荷物を持って、寒空の下、泣きながら歩くニカが可哀想すぎる。
芸術家と、良き家庭人、ってのはイメージ的にあまり結びつかない気はするけど、ストゥシェミンスキはまさにそう。こういう人は、結婚なんぞしない方がいいんじゃないですかねぇ。結婚生活なんて、赤の他人同士が細々としたことに妥協し合いながら一緒にどうにか暮らしていくことなんだから、自己主張が強くないとやっていけいない芸術家は、なかなかハードルが高いんじゃないかしらん。
一応ストゥシェミンスキの弁護をすると、ストゥシェミンスキは、ハンナのことを憎からず思っていたではあろうけど、恋愛感情はほとんど抱いてなかったと思うなぁ。そういう描写だったと思う。でも、ニカは(当然のことながら)ストゥシェミンスキに反抗的になり、メーデーのパレードに参加する。ニカが赤い旗をふりかざして行進する姿を窓から見て、ストゥシェミンスキがそっと窓を閉めるシーンは、胸が痛む。
……でも、彼にとって大事なのは、彼の信じる前衛美術であって、その他のことは二の次三の次。娘のことを気にはかけても、家族のポジションは彼にとってあまり高くなかったってことです。
芸術家としても、夫としても、父親としても、高潔な人間、、、なんてつまらないので、だめんずなストゥシェミンスキを美化せず描いているところは好感が持てる。ちなみに、ストゥシェミンスキが亡くなった後、ニカが父親が亡くなったときに横たわっていた空っぽのベッドをじっと見つめているシーンがあります。このとき、ニカの心を去来したものは何だったのか、、、。表情からは、読み取れません。哀しそうでもあり、厳しい視線でもあり、、、。
◆ワルシャワ行きまで1か月もない、、、。
私は、ワイダのファンでも信奉者でもないので、遺作となった本作にもそれほどの感慨は持たなかった。本作は、鑑賞したというより、勉強になった、という感じ。他の映画を見る感覚とは微妙に違う。
でも、本作を見て、未見の作品をもっと積極的に見ていきたいなぁ、とは思いました。
それは、ワイダの作品に興味があると言うよりは、ポーランドという国に興味があるから。いまだに無知に等しいけれども、映画を見たり本を読んだりしながら、少しずつその歴史に触れると、やはり、もっと詳しく知りたいと思うことばかり。見れば見るほど、分からないことが増えるわけで、、、。
ワルシャワ行きまでには、知識を身につけるのは到底間に合わないけど。残り時間、1本でも多くポーランド映画を見るぞ~!
ストゥシェミンスキが片手・片脚を失ったのは、第一次大戦出征のため。
★★ランキング参加中★★
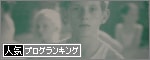














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます