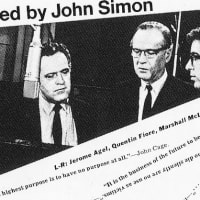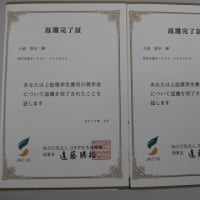元少年Aの手記『絶歌』のアマゾン・カスタマー・レビュー数をみたら、6/19日10時時点で1,258件もあった。ベストセラーならばたいがい3桁には達するが、4桁というのははじめてみた。4桁のレビューをもらっている商品って他にあるのだろうか。これらレビューを上手く編集すればこれがまた本になるのではないかとも思った。こういうことを考えるの不謹慎かな?
出版されて早い時期のレビューを数点読んでみた(全部はちょっと無理)。ほとんどはこの本が出版されることに対する嫌悪感の表明である。しかし、たいていは根源的な嫌悪感というのを巧く表現できていない気がする。理由に挙げられているのは「被害者遺族が了承していない」「真摯な反省に見えない」「匿名である」という点である。それではこれらがクリアされているならば、このような手記に胸糞悪さを覚えないのか。覚えないという人もいるかもしれないが、まだ覚えるという人も多くいるはずだ。おそらくその理由は「殺人の経験が商品となってしまう」ことにあるのだと思う。たとえ『絶歌』発行が遺族から了承され、実名で真摯な反省が書かれていても、加害経験をネタにお金を稼いでいるという事実には変わりない。この点が多くの人の倫理感に触れるというのが本当のところではないだろうか。
そういうわけで「読みもせずに批判するな」という支持者の批判は当たっていない。あの本への嫌悪感は、主題が本人の加害行為であるという以外、書籍の詳細な内容や表現とは関係ないからだ。あくまでも、読まなくても分かる部分の、自身の犯罪をネタに商売しているということが嫌なのだ。『絶歌』に文学的価値があろうが犯罪者心理を描いた資料的価値があろうがこの嫌さには関係ない。
しかし、探せば犯罪者による自身の犯罪をネタにした手記など他にもあるだろう。レビューが嫌悪感の表明に留まるならば共感できるものだし、そうした心情は馬鹿にされるべきではないとも思う。だが、絶版や販売停止を呼びかける意見に対すると、僕は理性的の方が先に立って「それはちょっと」という気になる。こういう本が出るというのが、表現の自由を持つ資本主義社会なのだと受け入れるほかない。
図書館学研究者としては、事件当時とある雑誌の少年Aの顔写真掲載問題が図書館界を騒がせたことを思いだす。今回の『絶歌』の所蔵はまた図書館ネタになるだろうか。ただ、永山則夫を所蔵しておいて今さら『絶歌』を拒絶するというのも難しいだろう。
出版されて早い時期のレビューを数点読んでみた(全部はちょっと無理)。ほとんどはこの本が出版されることに対する嫌悪感の表明である。しかし、たいていは根源的な嫌悪感というのを巧く表現できていない気がする。理由に挙げられているのは「被害者遺族が了承していない」「真摯な反省に見えない」「匿名である」という点である。それではこれらがクリアされているならば、このような手記に胸糞悪さを覚えないのか。覚えないという人もいるかもしれないが、まだ覚えるという人も多くいるはずだ。おそらくその理由は「殺人の経験が商品となってしまう」ことにあるのだと思う。たとえ『絶歌』発行が遺族から了承され、実名で真摯な反省が書かれていても、加害経験をネタにお金を稼いでいるという事実には変わりない。この点が多くの人の倫理感に触れるというのが本当のところではないだろうか。
そういうわけで「読みもせずに批判するな」という支持者の批判は当たっていない。あの本への嫌悪感は、主題が本人の加害行為であるという以外、書籍の詳細な内容や表現とは関係ないからだ。あくまでも、読まなくても分かる部分の、自身の犯罪をネタに商売しているということが嫌なのだ。『絶歌』に文学的価値があろうが犯罪者心理を描いた資料的価値があろうがこの嫌さには関係ない。
しかし、探せば犯罪者による自身の犯罪をネタにした手記など他にもあるだろう。レビューが嫌悪感の表明に留まるならば共感できるものだし、そうした心情は馬鹿にされるべきではないとも思う。だが、絶版や販売停止を呼びかける意見に対すると、僕は理性的の方が先に立って「それはちょっと」という気になる。こういう本が出るというのが、表現の自由を持つ資本主義社会なのだと受け入れるほかない。
図書館学研究者としては、事件当時とある雑誌の少年Aの顔写真掲載問題が図書館界を騒がせたことを思いだす。今回の『絶歌』の所蔵はまた図書館ネタになるだろうか。ただ、永山則夫を所蔵しておいて今さら『絶歌』を拒絶するというのも難しいだろう。