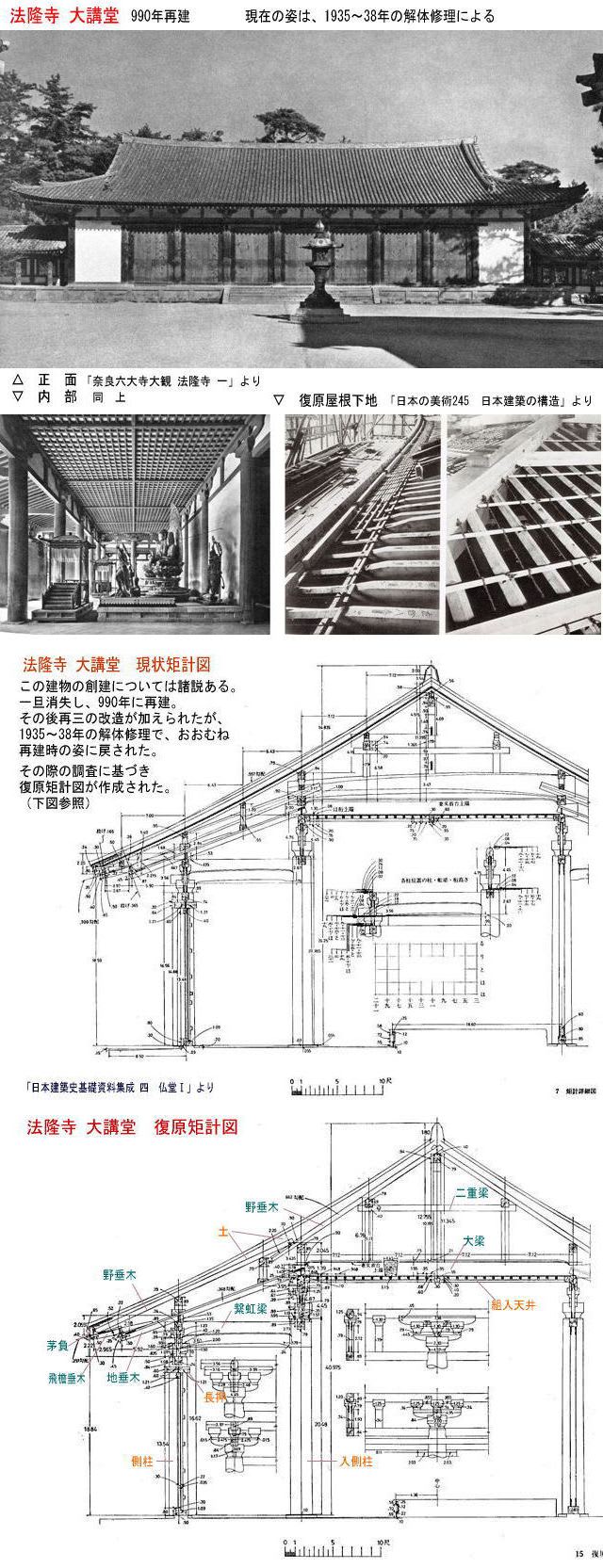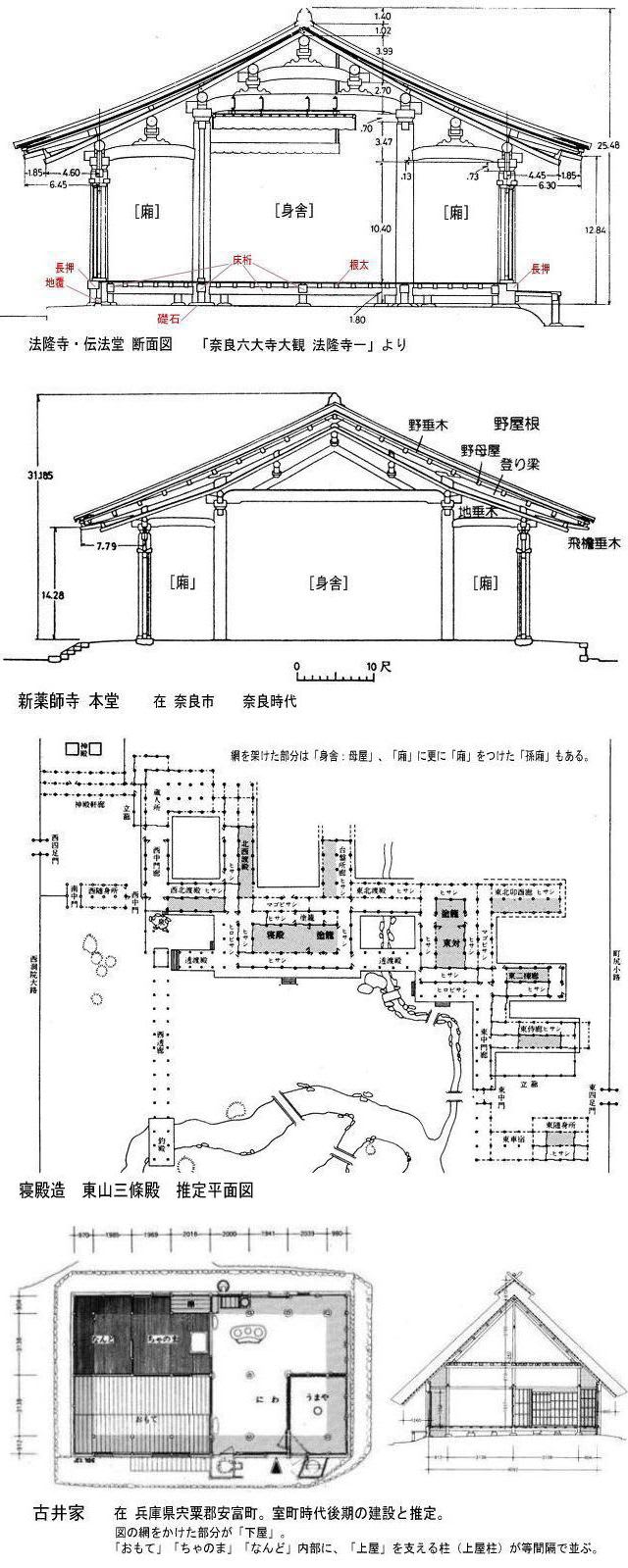天井を張り、「桔木」を用いる工法が広く普及する一方、少し大きな建物になると、柱列を「長押」で補強しても、架構が強度的に不安なことが分かってきた。
そこで生まれた衝撃的な構想による工法。それが「東大寺再建」で出現したいわゆる「大仏様(だいぶつよう)」である。
ことによると、東大寺の再建が企てられなかったならば、「大仏様」は生まれなかったのかも知れない。
東大寺大仏殿:金堂の創建は751年(天平勝宝3年)という記録があるが、その形は具体的には分かっていない。
創建時の建物は、1180年(治承4年)平家の焼き討ちで類焼焼失するときまで建っていたと伝えられているが、それは、古代では最も進んだ高級な「唐招提寺金堂」で使われた技法を拡大・巨大化したものであったらしい。
それは、軒桁を柱の直上に置くのではなく、柱の列よりも外側に出す方式:「出桁(でげた)」を使って、軒を極力深く出す「三手先(みてさき)」の技法であった。防雨の効果は向上し、見掛けも堂々とした姿になる。
註 近世の農家や商家などでも
簡単な「出桁」による軒の出の確保の技法は使われ、
「だしげた」などと呼ばれる。
上掲の図は、唐招提寺金堂で使われている「三手先」の詳細と、唐招提寺金堂の推定復原断面図である。
註 現在の唐招提寺金堂の屋根は後世の改造によるもの。
元は緩い勾配だった。
明治期の修理には、身舎の部分にトラス組が使われた。
この技法をいわば拡大コピーしてつくられた巨大構築物:東大寺大仏殿は、記録によると、建立後間もなく、副木(添え木)で柱が補強され、また軒先も垂れ下がっていたらしい。
そのため、古代の工法による復興・復元は無理と判断され、そこで考案されたのが、後に「大仏様」と呼ばれるようになる工法である。
これを推進したのが東大寺復興を使命とした僧:勧進職、重源(ちょうげん)である。
つまり、危なげな巨大建築大仏殿の復興が、技術の進展のきっかけになったのである。
この方法で、東大寺の伽藍はほぼ創建時の規模で復興が成し遂げられたのだが、復興大仏殿はふたたび焼失し、東大寺境内の大仏様の遺構は、「南大門」「法華堂」「鐘楼」などだけである。
註 現在の大仏殿は江戸期の復興で、規模が若干小さくなり、
大仏様の工法は部分的である。
他の大仏様の事例に「浄土寺浄土堂」がある。
この工法の特徴は、すでに何度か触れてきたが、部材が全て丸見え、天井はもちろん、化粧材を一切使わないこと(06年10月20日、11月28、29、30日に紹介⇒下註)。
天井を張り、「桔木」を使う方向へ進んでいた当時の技術の主流にとって衝撃的であったことは言うまでもない。
註 「浄土寺・浄土堂・・・・架構と空間の見事な一致」
「東大寺・南大門・・・・直観による把握、《科学》による把握」
「浄土寺・浄土堂、ふたたび・・・・その技法」
「浄土寺・浄土堂、更にふたたび・・・・続・その技法」
その内容について、次回、多少詳しく説明してみたい。
なお、以上の説明は、「奈良六大寺大観 東大寺一」「同 唐招提寺一」「日本建築史基礎資料集成 四 仏堂Ⅰ」「日本建築の構造」(先回紹介)などによった。