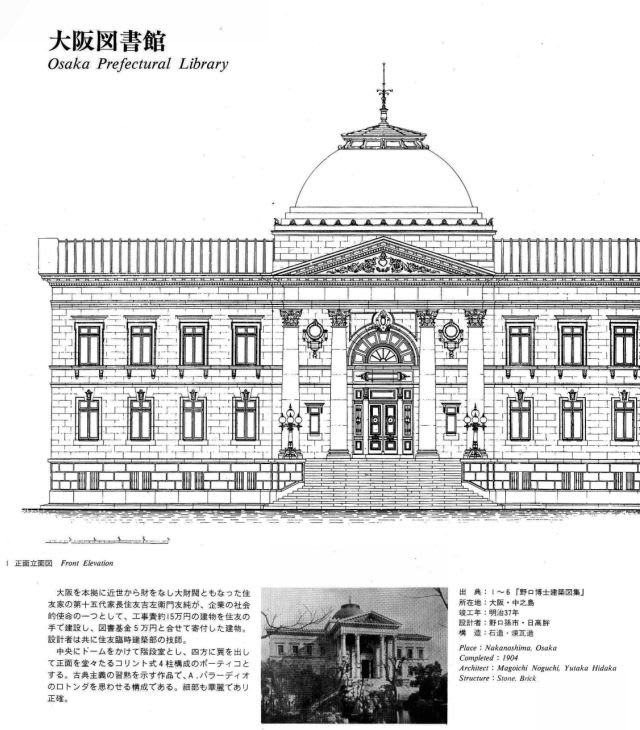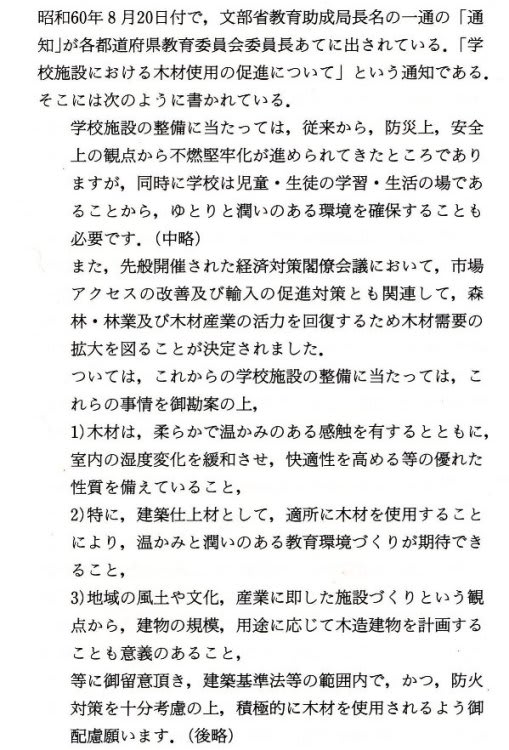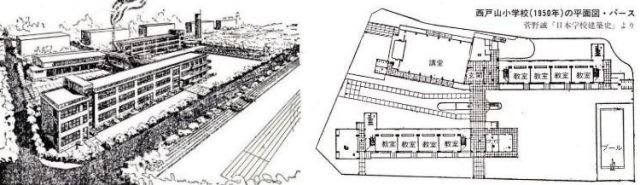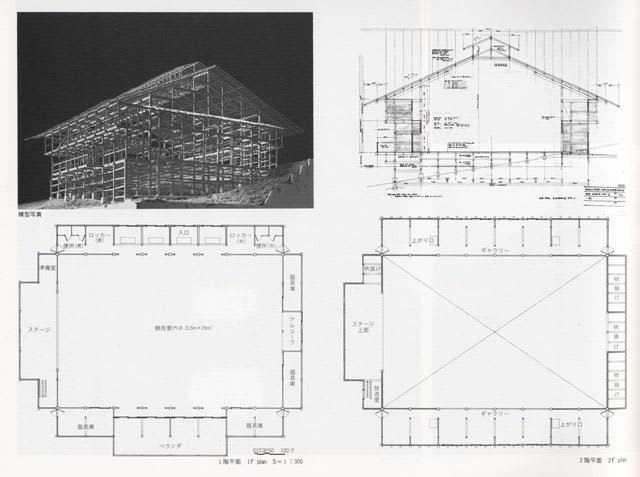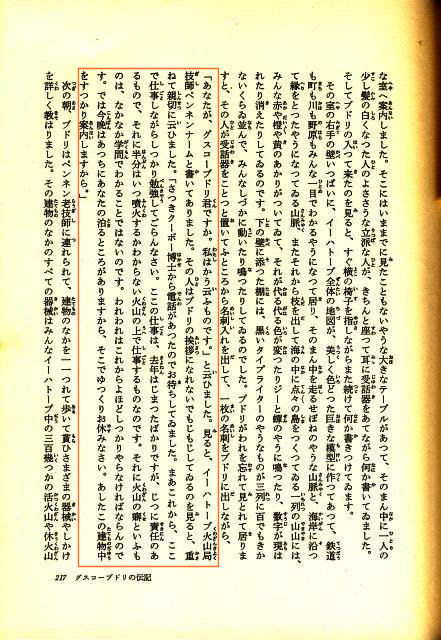春は名のみの風の寒さよ・・・当地の梅は、やっとこの程度まで開きました。
雪こそ消えましたが、啓蟄が過ぎたとは言え、寒さが厳しい毎日です。
暑さ、寒さも彼岸まで・・、というのは本当だな、と毎年思います。
[文末に3月11日付東京新聞社説を転載させていただきました。11日9.27]
[追録追加 8日16.55]
もう直ぐ、東日本大震災から三年になります。
ここしばらくの間、「防潮堤」「防波堤」、「耐震」「耐震補強」の語が飛び交うのではないかと思います。
少し前のTVで、「耐震補強」工事の費用が捻出できないので廃業に追い込まれるという老舗の旅館の話が伝えられていました。それは、
映像で見る限り、私には、簡単には壊れそうにないように思える昔ながらのつくりの木造建物でした。
そうかと思うと、耐震補強で、客室の窓に鉄骨の筋違:すじかい:ブレースが設置され、それまで一望に見渡せた海の目の前に障害となって立ちふさがり、客室としての意味がなくなってしまった、という海浜のホテルの例も報じられていました。
そしてまた、東京都では、一度に全面的に補強ができない場合、たとえば今年は一階だけ、次の機会に他の階を、というように分割して補強を行う「施策」を講じて「支援」している、という話もありました。
いずれも「理の通らない」話です。
なぜこういう報道がとりたてて行われたか。
それは、平成7年(1995年)制定の「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が施行されているにもかかわらず、不特定多数の人びとが使う公共的建物などの「耐震化」が遅々として進んでいないからです。今後は耐震補強を促すため、、未施工の場合は、建物名・建主・持主名を公表で、着手を強いるのだそうです。
これも「理不尽な」話です。
何故なら、いずれも竣工時点では「合法的」な建物であったからです。法律の「基準」が、「勝手に変った(変えられた)」からに過ぎません。
何度も書いてきましたが、「耐震」「耐震建築」「耐震補強」という語・概念の理解・認識は、一般の方がたと制定者・専門家とでは大きく違っている、のは明明白白の事実です。
たとえば、「耐震補強の目的」について、先の「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の冒頭に、次のようにが書かれています。
この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、
建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、
もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
これを、一般の人びとは、どのように理解するでしょうか。
おそらく、耐震策を施してある合法的な建物(すなわち「確認」済の建物)は、大地震に遭っても、無事に地震をやり過ごし、使い続けることができる建物、そこで暮し続けることができる建物である、と理解するでしょう。
これは、「耐震」の語に対して人びとが抱く共通のイメージ、つまり「常識的認識・理解」に他ならないのです。
辞書にも「耐震:地震に耐えて損傷しないこと」とあります(「広辞苑」)。「耐震」の「耐」という字の語義は、「支えることができる、負担することができる・・」といった意味ですから、この理解は決して間違ってはいない、具体的に言えば、「この建物は震度7程度の地震に耐える基準で設計されている」という文言を、その建物に住んでいる人たちが、文言通りに、「この建物は、震度7程度の地震に耐えられ、それゆえ地震後も住み続けられる」と理解しても、何ら間違いはないのです。
耐震を売り言葉にしている《住宅メーカー》の住宅も、多くは、そのように理解されているはずです。
ところが、先の法律の言う「耐震」とは、具体的には、次のことを指しているのです。
1)建物の供用期間中に数回起こる可能性のある中規模の地震に対して、大きな損傷は生じないこと。
または、
2)建物の供用期間中に一度起こるか起こらないかの大地震に対して、居住者の命にかかわるような損壊を生じないこと。
もう少し具体的に言うと、次のようになります。
中規模地震(震度5程度)に於いては建物の水平変位量を仕上・設備に損害を与えない程度(階高の1/200以下)に押え、構造体を軽微な損傷に留める、
また大規模地震(震度6程度)に於いては中規模地震の倍程度の変位は許容するが、建物の倒壊を防ぎ圧死者を出さない
ことを目標とする。
すなわち、地震に拠って建物に生じた損傷が、人命にかかわらない程度の損傷であったならば、その建物は「耐震性のある建物」の範疇に入る、ということになるのです。
そしてこれが、行政の方がた、及び、この法律に拠りどころを与えている「有識者」「(耐震工学の)専門家」の方がたの「耐震」についての「認識・理解」であって、一般の人びとの「耐震」という語・概念に対する「認識・理解」とは天と地の如くかけ離れているのです。
「有識者」「専門家」の用語法が、世の中のそれと異なることは、例の三階建木造建物の実物大振動実験の際の「倒壊」の語の「解釈」で露見しています。
原発事故関係についての「有識者」「専門家」のそれや、「宰相」の「福島原発はコントロール下にある」との「「認識・理解」も同じです。
すなわち、法令の言う、たとえば「この建物は震度7程度の地震に耐える基準で設計されている」という文言は、「この建物は、震度7程度の地震で、人命に損傷を与えるような破壊は生じない(だろう)」という意味に過ぎず、「地震に遭っても住み続けられる」ということは、何ら保証していない、ということなのです。
「耐震(基準)」「耐震補強」の「耐」の字を、字義通りに、つまり通常の用語法で、理解すると、とんでもないことになるのです。
しかし、「耐震基準」をつくった人たちは、行政も含め、この意味するところを正確に伝える努力をせず、ただ念仏のごとく「耐震」を唱えているだけです。
それゆえ、このままでは、「一般の人びと」と「「行政」及び「有識者・専門家」の間の認識の差:齟齬は、大きくなるだけでしょう。
けれども、この「一般の人びと」と「「行政」及び「有識者・専門家」の間の認識の差:齟齬について深く考えることこそが、地震に拠る災禍を考えるにあたって最も重要な視点であるのではないか、と私は思います。
なぜなら、単に建物が壊れるか、どの程度壊れるか、ではなく、地震に遭ったとき、どのように生き抜けられるか、暮し続けられるか、について考えることこそ最重要の課題のはずだからです。
建物の損傷が、人命に損傷を与えない程度であるかどうかは、そのほんの「部分」の話なのであって、
その損傷の中で、どのように生き延びられるか、暮らせるか、それこそが、そこに実際に生き、暮している人びとにとっては、最重要の課題なのです。
しかし、「耐震」基準を決めた方がたは、このことを、考えているでしょうか、考えてきたでしょうか。
人命にかかわらない損傷でも、損傷は損傷です。
「人命にかかわらない程度の損傷」と言うとき、その損傷した建物の中に居続けられるか、あるいは、そこから逃げ出せるか・・・、そこまで考えて言っているでしょうか。
考えてみれば、多くの法令に「・・・国民の生命、身体及び財産を保護するため、・・・公共の福祉の確保に資することを・・・」云々同様の文言が必ずありますが、その具体的な方策は語られていないのが実際ではないでしょうか。
それは何故か?
それは、どのように生き抜けられるかという問題は、この方がたの視界にはないからです。それは、別の専門家の領域・分野の問題だ・・・。
このことを考えさせるコラム記事が、2月27日付毎日新聞朝刊に載っていました。下記に転載します。

ここには「防潮堤」「防波堤」の例が挙げられています。
「防潮堤」「防波堤」は、通常は、護岸のための一般名詞でありますが、数多く津波被害を被った地域では、「防潮堤」「防波堤」とは、「耐・津波構築物」を意味します。
その場合の「防潮堤・防波堤の設計」も、建物の「耐震設計」が「耐えるべき地震の大きさ」を設定する(仮定する)ことから始まるのと同じく、
「前提」として、防ぐべき波の大きさを設定(仮定)します。そして、「耐えるべき・防ぐべき大きさ」として、過去に経験した「最大値」を計上するのが常です。
その値を超える事態・事象が生じるとき、それが「想定外」の事態・事象です。
法令の「耐震基準」が、何度も変ってきたというのは、すなわち、想定外の事態・事象が、少なくともその改変の回数だけ過去に起きた、ということに他なりません。
ということは、「想定外」の事態・事象の発生の「予想」は、字の通り、想定不能である、ということを意味します。
これを普通は、「自然界には『人智の及ばない』事態・事象が厳然として存在する」、と言います。
ところが、何度も書いてきましたが、工学の世界では、「人智の及ばない事象が存在する」、などということを嫌います。科学・技術は何でもできると思い込んでいるからです。
本当にそう思うのならば、「想定外」は禁句のはずですが・・・。
しかし、この科学・技術への絶大な「信仰」に依拠した「工学的設計」は、
えてして、耐震設計をした建物は(過去最大と同規模の)地震に遭っても安全・安心である、防潮堤・防波堤を設ければ(過去最大と同規模の)津波に遭っても安全・安心である、という「信仰」を人びとの間に、広めてしまうのです。
そして、今回の地震にともなう津波では、人びとが防潮堤・防波堤があるから大丈夫だからと思い込み避難しなかった事例がかなり起きていたということを、先の記事は紹介しているのです。
私は、この記事は、「工学的対策≠安全・安心の策」という「警告」である、として読みました。
そして、「被災者に学ぼう」とする地震学の方法論の「転換」に共感も覚えました。
そして更に、単に当面の震災の被災者に学ぶだけでなく、過去に津波の被害を被った人びとにも学ぶべきなのではないか、と私は思います。
なぜなら、そのような事態に遭うことの多い地域に暮す人びとは、そういうところに暮す「知恵」を培ってきているはずだからです。
本来、人は、どのような地域に暮そうとも、自らが暮さなければならない地域・場所の「特性」を勘案しつつ暮すのが当たり前です。「特性」とは、その地の「環境の様態・実態」と言ってもよい。
数日前に、ヘリコプターから見た津波の実相が報じられていました。
その中で、「浜堤(ひんてい)」という初めて聞く用語を耳にしました。
河川沿いに形成される「自然堤防」のごとく、海の波により永年のうちに自然に形成される「堆積地」のことのようです。そして、海岸の集落はこの「浜堤(地)」に営まれることが多い、というのも「自然堤防」と同様のようでした。
水に浸かったり波に襲われることの多い土地に暮さなければならない場合、当然のこととして、少しでもその状況を避けられる場所を人は探します。比高の高い所です。
そういう場所として、「自然に形成された場所」を選ぶのです。
それは、単に探すのが容易だからではありません。
「自然に形成された場所」は、形状を維持し続ける可能性が高いことを知っていたからです。
と言うより、「形状を維持し続けることができるような場所」だからこそ、そういう地形が形成される、ということを知っていたからだ、と言った方が的確かもしれません。
それが、その地に暮す人びとのなかに培われ定着した「知恵」であり、その地に暮す人びとの認識した「その地の特性」に他なりません。
「被災者に学ぶ」とは、その地に暮さなければならない人びとの「知恵」を知ること、そのように私は思います。
海岸の「浜堤」上の集落立地は、「浜堤」についての「学」の成立以前から存在しているのです。
縄文・弥生集落の立地も同様です。
私の暮す地域には、縄文・弥生集落址が多数在ります。いずれもきわめて地盤堅固なところです。
と言うよりも、私の暮す通称「出島」と呼ばれる霞ヶ浦に突出す半島様の地形自体、地盤・地質ともに堅固であるが故に、その形状を為しているのです。
現在の地形図で確認すると、この半島は、福島~茨城にかけての八溝(やみぞ)山地から筑波山に至る山系の端部にあたることが分ります。
山並みという形を維持できるのは、その一帯が周辺に比べ堅固であるからのはずです。
古代の「常陸国」の「領域」を見てみると、先の山系の東から南側の、太平洋に面した一帯であることが分ります。
一帯は肥沃で、気候は比較的穏やか。人びとは暮すにはきわめてよい、と判断し、その一帯の比高の高い地に定着したようです。
古墳の多さとその建設地の位置がそれを示しています。
群馬県東南部(板倉町など)の利根川沿いに、かつて、屋敷内に「水塚(みづか)」を設けるのが当たり前であった地域があります。
「水塚(みづか)」とは、屋敷内の一角に土盛りをして、母屋とは別に、そこに二階建ての建物を建て、一階を備蓄倉庫、二階を非常時の住まいとし、
加えて、軒には小舟を吊り下げている場合もあります。利根川の氾濫時への対策で、小舟は、建物が危険になったときの避難のための用意です。
留意しなければならないのは、単に盛り土をしているのではない、つまり、単に洪水の予想水位より高ければいい、という判断ではない、という点です。
氾濫時の利根川の水流をまともに受けない場所を選定しているのです。それは、現地を見ると納得がゆく。
いま、「予想水位より高ければいい、という判断」と書きました。
この「予想水位より高ければいい、という判断」こそが、現在の「工学設計」の拠って立つ「基点・前提」です。耐震設計も防潮堤設計も、皆同じです。
小舟を吊り下げることまで、考えが及ぶわけもない・・・・。
では、建物の設計では、被災者・被災地からに何を学ぶか。
構築物の頑丈さを得る方策、それはその一つではあっても、それで全てではないはずです。
転載した記事の最後に、「歩いて行ける高台に頑丈な小学校を建て、避難所の機能を持たせ、数十年ごとにより頑丈に建て替える・・」という記述があります。
私は、先ず、建設地の選定に心することが第一ではないか、と思います。
同じ高台でも、自然形成の高台と人工の高台では性質が異なります。
自然形成でも、たとえば土石流のつくった高台は、人工とほとんど同じはずです。
つまり、自然形成の場合でも、その土地の「経歴」「履歴」を「理解する」「知る」ことが重要なのではないでしょうか。
いわゆる科学・技術を信じると、とかく、人は何処にでも暮せる、建物は何処にでも建てられる、と考えがちです。その考え方を「学」が率先して正す必要があるように、私は思います。
「人びとの長きにわたる営為に学ぶ」姿勢があったならば、どんな土地でも建てられるのだ、という考えを、人は抱かないはずです。そうであれば、たとえば、低湿地に住宅地を造成し「液状化」に遭遇して慌てふためくなどという事態も起きないのです。
これは、一言で言えば、それぞれの土地の歴史を知ることに他なりません。
先の「浜堤」地に集落が営まれているように、「長い歴史のある集落の立地、そしてそこでの住まいかたは、その地域に暮す人びとの、『その地域の環境特性』についての『理解に基づく判断』の結果を示しているのだ」と、今に生きる私たちは理解すべきなのです。
『その地域の環境特性』とは、「日本という地域全体としての特性」及び「その地域に特有・固有の特性」の両者を含みます。四季があり、四季特有の気候の諸相(たとえば台風や梅雨など)がある、頻繁に地震や火山活動がある、などは前者であり、たとえば台風時の特有な風向き・・、などは後者にあたります。
このようないわゆる「自然現象」に対して、人智で抵抗できると考えるようになるのは(津波には防潮堤を考え、地震には耐震構造を考えるようになるのは)、近現代になってからのこと、それ以前は、人智では対抗できないと考え、そのような自然現象のなかで、如何に生き抜くか、暮し続けるか、に人智をそそいだのです。
「構造力学」は、誕生した当初は、「人びとの為す判断」の「確認」のために機能していたのです。
では、その「人びとの判断」は如何にして為されたのか。
それは、人びと自らの「事象の観察」を通して得た「事象についての『認識』」に拠って為されたのです。
その「認識」を支えたのは、「人びとの『直観』」です。
そのために、人びとは「感性」を養いました。「観察⇒認識⇒知恵」、この過程を大事にした、大事に養ったのです。
つまり、「学」が「判断」を生んだのではありません。これは、厳然たる事実です。
本来、諸「学」は、人とのかかわりの下に出発したはずです。
ゆえに先に転載した記事にある「被災者に学ぶ地震学」への「転換」は、
「学問のための学問」から「人にとっての、人としての学問」への転換、「原点への回帰」を意味しているように私には思えました。
建築学もまた、建築学こそ、建築:建物をつくること、その本来の意味を問い直すことを、今からでも決して遅くはない、始めるべきであるように私は思います。
先人の知恵の集積は、例えば、遺跡・遺構や数百年にわたり永らえ得た建物や集落・町・街・・などは、私たちの目の前に多数遺されているのです。
それはいずれも、人びとの営為、すなわち人びとの「認識」「判断」の結果に他なりません。
そこから、私たちは、たとえば地震に対しては、「耐震」ではなく、人びとの「対震」の考え方、その「蓄積」を学べるはずです。
そしてそこから得られる「知」は、如何なる「《実物大》実験」で得られる「知」よりも、比較にならないほど豊饒である、と私は考えています。
「有識者」「専門家」の言辞に惑わされないために、自らの「感覚」「感性」に、更に磨きをかけたい、と思います。
[追録 8日16.55][さらに一記事を追加しました 12日 9.00]
同様なことを、下記でも書いています。なお、それぞれにも関連記事を付してあります。
想像を絶する「想定外」
此処より下に家を建てるな・・・
建物をつくるとはどういうことか-16
建物をつくるとはどういうことか-16・再び
保立道久著「歴史の中の大地動乱」を読んで
わざわざ危ない所に暮し、安全を願う
さらに関連記事を追加します。
/gooogami/e/dced003d265269bc123c36e66a4f38b9">建物は「平地・平場」でなければ建てられないか
さらに追加[14日 9.15]
取り急ぎ・・・・「耐震の実際」
3月11日付東京新聞社説を転載させていただきます。全く同感です。[3月11日9.27追録]