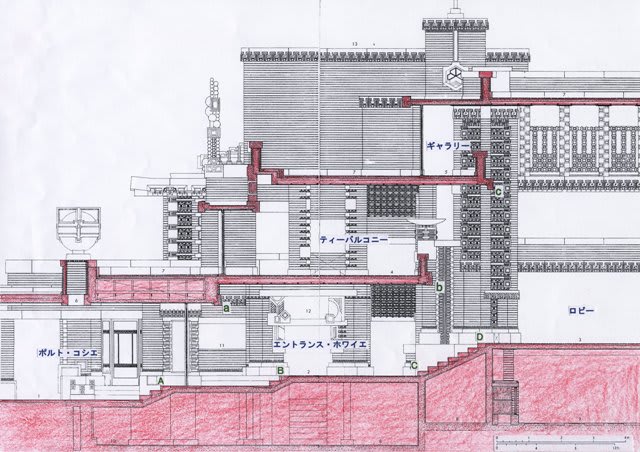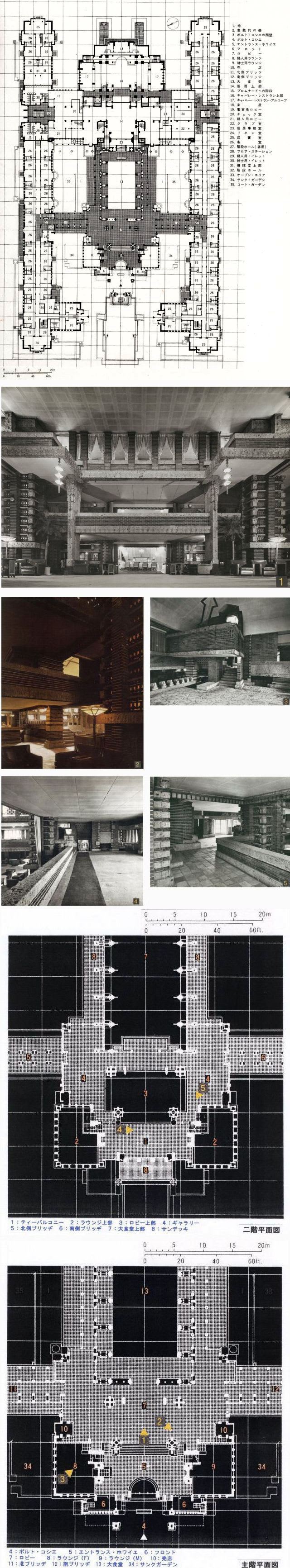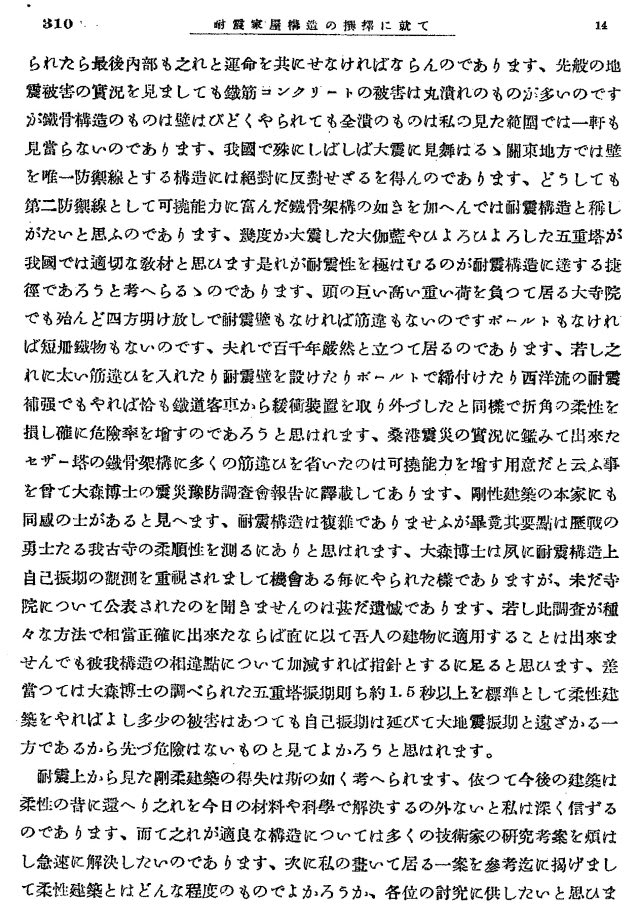先日、30代の「建築士」が、「継手・仕口を加工できる大工さんはいない、だから、継手・仕口を用いる設計をしても意味がない」と真面目な顔で語るのを聞いた。
これと同じような発言は、「建築を専門とする方々」から、私は何度も聞いている。
試みに、身近にいる「建築士」に日本の建物(当然木造建築)の「継手・仕口」について、訊ねてみてほしい。
おそらく、「建築士」の多くが、「それは昔のやりかたで、今は継手・仕口をつくれる大工さんが少なくなった、今は、それに代って丈夫な金物がある・・・」と言うに違いない。
しかし、これらの「建築士」の言には、本当は、「ある言」が隠れ潜んでいる。
それはすなわち、「そういう時代だから、継手・仕口を知っていても意味がない、だから継手・仕口について知る必要はない、ゆえに私は知らないし知るつもりもない・・・」という言だ。
しかし、いくつかの設計を通して、現在でも「継手・仕口で建物をつくれる大工さん」は世の中にたくさん居られることを、私は身を持って知った。
その大工さんたちは言う、「継手・仕口を使ってつくる設計がない、少なくなった」と。多くの「設計士」の言うこととは、まるっきり反対なのだ。
いろいろな地域・場所で大工さんに会うたびに、そのあたりのことについて尋ねてみると、ほとんどの大工さんが、「継手・仕口でつくる仕事をさせてくれない。そういう機会がない」と語る。
そこで気がついた。
多くの「建築士」の「発言」は、《為にする発言》なのだと。
簡単に言えば、自分が継手・仕口を知らないことについての「言い訳」、更に言えば、「継手・仕口を使う設計はできない」ということの「白状」に他ならないのだ。
もしも、「私は継手・仕口について弱い:詳しくない」と言う人がいたら、むしろ、その人は類い稀な「正直な人」。
私は、「継手・仕口」は、、日本に於いて(日本という環境に於いて)醸成された建物づくりの「技術」であり「思想」であると考えている。そこには、日本という環境に於いて生き、暮してゆくための「知恵」が凝縮されている、と言っても過言ではない。単なる「思い付きではない」ということ。
ではいったい、なぜこんな状況、すなわち、自国で長い年月をかけて醸成された技術・思想をないがしろにするような状況が生じてしまったのだろうか。
これについては、すでにたびたび触れてきたが(下註)、最大の「原因」は、明治以来進められて来た「近代化」策にある。「近代化」策は、当初は専ら「入欧」策だったが、第二次大戦後はそれに「米国迎合」策が加わる。
この「国策」は、それまで日本の建物づくりを担ってきた「実業者」すなわち大工職をはじめとする「職人諸氏の存在」と「彼らの成し遂げてきた蓄積」を無視して進められて来たこともすでに再三触れてきた。
当然ながら、「近代化」策を実施する担い手の養成を目的とした「教育」においても、それまでの「蓄積」は無視された。と言うより、「積極的に放棄する」ことを目指した、と言ってもよいだろう。
この教育の《伝統》は、現在に於いてもなお《健在》で、長い歴史を有する工法については、まったくと言ってよいほど触れられない(「建築史」という教科はあるが、そこで「工法」「工法発展の経緯」はもちろん「継手・仕口」について触れられることは先ずない)。
そればかりか、建築にかかわる法令もまた、「近代化」策の延長上で「体系化」された。
現行建築法令では、日本の建築技術の蓄積は、まったく無視・放擲されている。「継手・仕口」に拠る工法を知る実業者たちは、法令によって、その腕を奮うことを禁止されてしまったのだ。
しかし、建築法令の差配してきた時間はやっと半世紀、これに対して、日本の建物づくりの歴史は、そんな半端な時間ではない。この事実に対して、なぜ、皆が平然としていられるのだろうか?
それは、この「事実」「経緯」が、世の中に対して「隠蔽されている」からだ。
あたかも、昔から、「建築法令」があった、かのように喧伝されているからであり、あたかも、「建築法令」が絶対的「正」であるかのごとくに喧伝されているからである。
その最もよい例が、「軸組工法」を「在来工法」の名で一くくりにする呼び方である。これは、「かつての工法」と「法令の規定する工法」では大きな差異があることを、一般の人の眼から隠蔽する上で「絶大な効果」があった。
だから、若い世代の「建築士」諸氏が、「継手・仕口」について知る機会もなく、ひいては、知らなくて当然、知る必要もない・・・と考えるのも、むしろ当然と言えるのかも知れない。
しかし、建築の仕事に関わりを持っていながら、自国の建築の歴史、自国の建築技術について、無知で済ます、無知で平然としていられる、という国は、おそらく日本だけと言ってよい。
以前、「日本の建築技術の展開」で、日本の建築工法の変遷を私なりに見てきた。その中では、特に「継手・仕口」に焦点をあてた書き方はしなかった。
そこで、次回からしばらく、一般の方々にも通じる書き方で、「継手・仕口」に焦点をあてながら日本の建築技術の変遷をあらためて見てみようと思う。と言うのも、この件に関する限り、「専門の方々」も「一般の方々」と何ら変りはないと考えてよさそうだからである。
註 「『実業家』・・・・職人が『実業家』だった頃」
「『在来工法』はなぜ生まれたか-1」
「『在来工法』はなぜ生まれたか-2・・・・『在来』の意味」
「『在来工法』はなぜ生まれたか-2 の補足・・・・『在来工法』の捉え方」
「『在来工法』はなぜ生まれたか-3・・・・足元まわりの考え方・基礎」
「『在来工法』はなぜ生まれたか-3の補足・・・・基準法以前の考え方」
「『在来工法』はなぜ生まれたか-4・・・・なぜ基礎に緊結するのか」
「『在来工法』はなぜ生まれたか-4の補足・・・・日本建築と筋かい」
「『在来工法』はなぜ生まれたか-5・・・・耐力壁依存工法の誕生」
「『在来工法』はなぜ生まれたか-5の補足・・・・筋かいと面材の挙動」
「『在来工法』はなぜ生まれたか-5の補足・続・・・・ホールダウン金物」
「日本の『建築』教育・・・・その始まりと現在」
これと同じような発言は、「建築を専門とする方々」から、私は何度も聞いている。
試みに、身近にいる「建築士」に日本の建物(当然木造建築)の「継手・仕口」について、訊ねてみてほしい。
おそらく、「建築士」の多くが、「それは昔のやりかたで、今は継手・仕口をつくれる大工さんが少なくなった、今は、それに代って丈夫な金物がある・・・」と言うに違いない。
しかし、これらの「建築士」の言には、本当は、「ある言」が隠れ潜んでいる。
それはすなわち、「そういう時代だから、継手・仕口を知っていても意味がない、だから継手・仕口について知る必要はない、ゆえに私は知らないし知るつもりもない・・・」という言だ。
しかし、いくつかの設計を通して、現在でも「継手・仕口で建物をつくれる大工さん」は世の中にたくさん居られることを、私は身を持って知った。
その大工さんたちは言う、「継手・仕口を使ってつくる設計がない、少なくなった」と。多くの「設計士」の言うこととは、まるっきり反対なのだ。
いろいろな地域・場所で大工さんに会うたびに、そのあたりのことについて尋ねてみると、ほとんどの大工さんが、「継手・仕口でつくる仕事をさせてくれない。そういう機会がない」と語る。
そこで気がついた。
多くの「建築士」の「発言」は、《為にする発言》なのだと。
簡単に言えば、自分が継手・仕口を知らないことについての「言い訳」、更に言えば、「継手・仕口を使う設計はできない」ということの「白状」に他ならないのだ。
もしも、「私は継手・仕口について弱い:詳しくない」と言う人がいたら、むしろ、その人は類い稀な「正直な人」。
私は、「継手・仕口」は、、日本に於いて(日本という環境に於いて)醸成された建物づくりの「技術」であり「思想」であると考えている。そこには、日本という環境に於いて生き、暮してゆくための「知恵」が凝縮されている、と言っても過言ではない。単なる「思い付きではない」ということ。
ではいったい、なぜこんな状況、すなわち、自国で長い年月をかけて醸成された技術・思想をないがしろにするような状況が生じてしまったのだろうか。
これについては、すでにたびたび触れてきたが(下註)、最大の「原因」は、明治以来進められて来た「近代化」策にある。「近代化」策は、当初は専ら「入欧」策だったが、第二次大戦後はそれに「米国迎合」策が加わる。
この「国策」は、それまで日本の建物づくりを担ってきた「実業者」すなわち大工職をはじめとする「職人諸氏の存在」と「彼らの成し遂げてきた蓄積」を無視して進められて来たこともすでに再三触れてきた。
当然ながら、「近代化」策を実施する担い手の養成を目的とした「教育」においても、それまでの「蓄積」は無視された。と言うより、「積極的に放棄する」ことを目指した、と言ってもよいだろう。
この教育の《伝統》は、現在に於いてもなお《健在》で、長い歴史を有する工法については、まったくと言ってよいほど触れられない(「建築史」という教科はあるが、そこで「工法」「工法発展の経緯」はもちろん「継手・仕口」について触れられることは先ずない)。
そればかりか、建築にかかわる法令もまた、「近代化」策の延長上で「体系化」された。
現行建築法令では、日本の建築技術の蓄積は、まったく無視・放擲されている。「継手・仕口」に拠る工法を知る実業者たちは、法令によって、その腕を奮うことを禁止されてしまったのだ。
しかし、建築法令の差配してきた時間はやっと半世紀、これに対して、日本の建物づくりの歴史は、そんな半端な時間ではない。この事実に対して、なぜ、皆が平然としていられるのだろうか?
それは、この「事実」「経緯」が、世の中に対して「隠蔽されている」からだ。
あたかも、昔から、「建築法令」があった、かのように喧伝されているからであり、あたかも、「建築法令」が絶対的「正」であるかのごとくに喧伝されているからである。
その最もよい例が、「軸組工法」を「在来工法」の名で一くくりにする呼び方である。これは、「かつての工法」と「法令の規定する工法」では大きな差異があることを、一般の人の眼から隠蔽する上で「絶大な効果」があった。
だから、若い世代の「建築士」諸氏が、「継手・仕口」について知る機会もなく、ひいては、知らなくて当然、知る必要もない・・・と考えるのも、むしろ当然と言えるのかも知れない。
しかし、建築の仕事に関わりを持っていながら、自国の建築の歴史、自国の建築技術について、無知で済ます、無知で平然としていられる、という国は、おそらく日本だけと言ってよい。
以前、「日本の建築技術の展開」で、日本の建築工法の変遷を私なりに見てきた。その中では、特に「継手・仕口」に焦点をあてた書き方はしなかった。
そこで、次回からしばらく、一般の方々にも通じる書き方で、「継手・仕口」に焦点をあてながら日本の建築技術の変遷をあらためて見てみようと思う。と言うのも、この件に関する限り、「専門の方々」も「一般の方々」と何ら変りはないと考えてよさそうだからである。
註 「『実業家』・・・・職人が『実業家』だった頃」
「『在来工法』はなぜ生まれたか-1」
「『在来工法』はなぜ生まれたか-2・・・・『在来』の意味」
「『在来工法』はなぜ生まれたか-2 の補足・・・・『在来工法』の捉え方」
「『在来工法』はなぜ生まれたか-3・・・・足元まわりの考え方・基礎」
「『在来工法』はなぜ生まれたか-3の補足・・・・基準法以前の考え方」
「『在来工法』はなぜ生まれたか-4・・・・なぜ基礎に緊結するのか」
「『在来工法』はなぜ生まれたか-4の補足・・・・日本建築と筋かい」
「『在来工法』はなぜ生まれたか-5・・・・耐力壁依存工法の誕生」
「『在来工法』はなぜ生まれたか-5の補足・・・・筋かいと面材の挙動」
「『在来工法』はなぜ生まれたか-5の補足・続・・・・ホールダウン金物」
「日本の『建築』教育・・・・その始まりと現在」