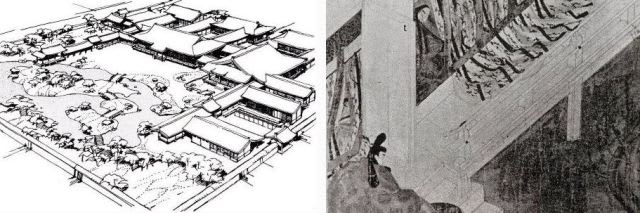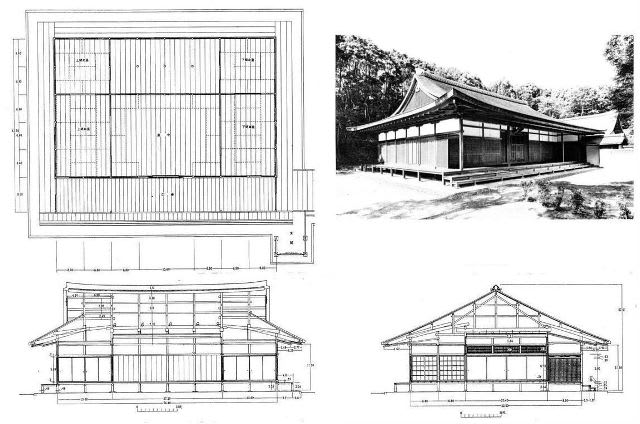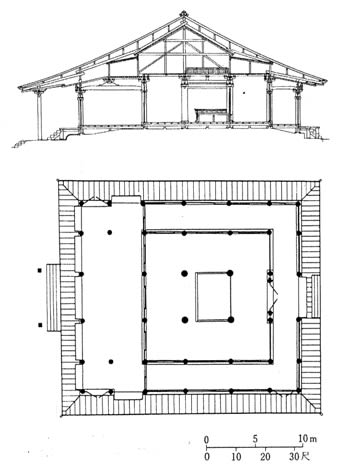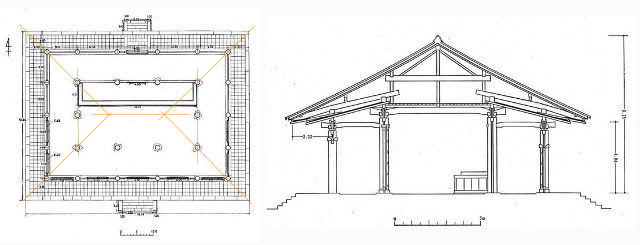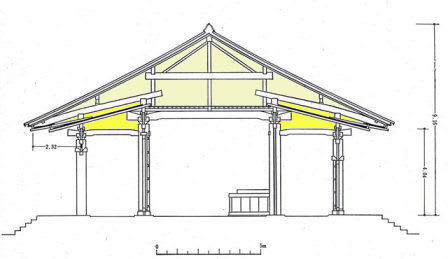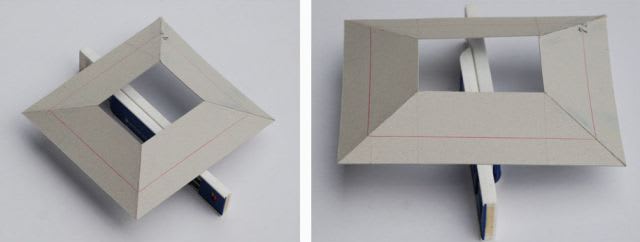先回の記事を書いたのは、世の中が「猛暑」と大騒ぎしていたときでした。
ところが、その後、当地域は北東風が流れこみ、まるで初秋のような気候が続いています。今朝の気温は18度でした。
例年ならとっくに盛りを迎える合歓の木(ネムノキ)の花も、やっと咲き始めたところで、しかも、このところの雨不足のせいか、きれいに咲いていません。

昨日の朝の合歓の木。まだ、ほとんどが蕾。
例年なら、このように咲いている頃です。

発症から一ヶ月経った 2月19日、「回復期病院」へ転院しました。
まだ車椅子でしたから、介護タクシーの厄介になりました。街ではよく見掛けていましたが、自分が乗るなどとは思ってもいませんでした。
転院先の病院では、「急性期病院」からの患者だからでしょう、ナースステーションの直ぐ前の病室に私のベッドが用意されていました。
トイレは、車椅子用のトイレを使うことになりましたが、自走できないので、その都度、看護師さんの援けを借らざるを得ませんでした。これは大変心苦しいものがありました。
翌日からリハビリが始まりました。
「回復期病院」のリハビリは、「理学療法:PT」「作業療法:OT」「言語療法:ST」各40分で、それぞれ主に担当する療法士さんが決まっています。
時間帯は日により異なり、午前は9時から11時半ごろまで、午後は1時半から5時半ごろまでのどこかに設定されます(前日の夕方、翌日の時間割が知らされます)。
その時間になると、担当の療法士さんが、わざわざ1階のリハビリ室から3階の病室まで迎えに来られます。転院当初は、リハビリ室まで、療法士さんに車椅子で搬送してもらいました。これも大変心苦しいものでした。
リハビリ室担当の療法士さんは、「理学療法士」「作業療法士」「言語療法士」合せて30人以上居られたようです。
「理学療法:PT」の初回は、リハビリ室に着くと、「急性期病院」と同じ「四点杖」で、片道20mほどを往復歩行しました。
療法士さんは、その歩行の様子から、私の「問題点」を判定されるようです。
PTで、最初に指摘された「問題点」は「猫背」つまり、姿勢の悪さと、左脚への体重移動のぎこちなさ(左の膝が「挫屈」を起こすことが多い)、右手右脚への過剰に頼り過ぎ(転院時にあった右膝痛は、その結果)、そしてそれに起因すると思われる右半身の「硬さ」などでした。
姿勢の悪さの他は、本人ははっきり気がついてはいないのですが、療法士さんには、たちどころに分るようです。
「作業療法:OT」の初回では、左手の動作の様態が観察され、私の「問題点」が判定されました。
そのとき、私の上肢は、左手は「万歳」の恰好を維持できず(後にそのとき撮った写真を見せていただきましたが、我ながら情けない姿でした!)、手の掌は、握ることも完全に開くこともできず(つまりグーパーができず)、指折り数えることなどまったくできませんでした。各指を独立に動かすことができないのです。すでに触れた「左手の置き忘れ」や車椅子の「左ブレーキの掛け忘れ」なども伝えられていました。
このPT、OTの初回の「様態観察」と「急性期病院」からの伝達事項から、私の「実情」は、通常の生活を行なえるレベルを100として、35程度であると判定されました。要は、普通の人の35%の能力しかない、ということでしょう。
PTは、毎回、「験しの歩行」をしたあと(最初は「四点杖」でしたが、すぐに「T字杖」になりました)、マットの上で横になり、先ず、右半身の「硬さをほぐす」ことと「体の左右のアンバランスの是正」、そして「体幹の矯正・補強」のための諸種の「訓練」を行ないました。「意識せずに入ってしまっている力(結構、これが多いようです)」を「抜く」方策もあったようです。
これらは、右手右脚に頼りすぎた結果生じた「現象」だったと思われ、先に触れたように、転院時にあった右膝の痛みも、その一つの現れと考えられます。
ただ、この各種の「施療」を具体的かつ適確に記すことは、私には不可能です(メカニズムが分らないのです)。
しかし、施療後、体が「軽い感じ」になり、体の「動き」も楽になったのは確かです。
一つだけ分りやすい例を挙げると、クッション材でつくった直径15cmほど、長さ70cmほどの円柱の上に、背骨を載せて上向きに寝転ぶ「訓練」があります。これは、私自身、その「効果」をよく実感できた訓練でした。
脚は立て膝の恰好で手は体の上に置きます。円柱ですから、この姿勢:円柱の上に背骨が載る:を、立て膝をした脚だけを頼りに維持するのは難しく、上半身自体でバランスをとらなければなりません。
何度かやっているうちに、上半身の左右のバランスを適切に按配することができるようになります。同時に、その時、背筋も伸びていることも実感できる。これが、載っていて「結構気持ちがいい」のです!
この「適切な按配」は、体が「感覚」で「読み取っている」のだと考えられます(かつて、自転車に乗れるようになったとき、おそらく同じような「読み取り」があったものと思います)。この円柱は「ストレッチポール」と呼んでいたと思います。
数分以上この姿勢を維持したあと、円柱から降りてみると、体の硬さはほぐれ、軽く、姿勢もよくなっているように思えました。これは、立ってみると一層よく分りました。当然歩き方にも反映し、歩きが軽快になります。
同様の円柱は、OTで、テーブル上に体の前に横一文字に置き、それを両手で前後に転がす訓練で使いました。
円柱の転がりを両手で制御するわけです。「急性期病院」での「雑巾がけ」と同じような「効果」があるようです。
ただこのとき、「右手のおせっかい」が出てしまう!。左手が転がす動きをとる前に右手が動いてしまうのです。
PTでは、スムーズな体重移動、つまりスムーズな歩行の基礎訓練として、平行棒での訓練がありました。平行棒の間に立ち、体を(腰を)左右に動かし、平行棒に当たるか当たらないかという位置で止める訓練です。右側は簡単ですが左側はなかなか望む位置で止められないのです。
療法士さんは、その様子から、どこに問題があるかを見抜くようで、それが次の訓練のメニューとなるようです。
メニューの最大の眼目は、「体幹の補強」:胸部、腹部、背部、腰部、大腿部・・の筋力の増強訓練だったと思います。
左大腿部の萎えた様子は自分でも目に見えて分りましたが他は分りません。筋肉には外から目に見えるものと、内部に隠れているもの(インナーと呼んでいるようでした。これに対して前者はアウターらしい)とがあるそうで、その内部の筋力も強化が必要で、そのための訓練もあったようです。メカニズムはよく分りませんが、こういった内外の筋が連携して作動しているようです。
人の体の構造、機構の「凄さ」には本当に驚きます。
具体的な施療はいろいろとありましたが、これも適確に記述することも私にはできません。言えるのは、訓練後、疲れておなかが空くこと!
転院ほぼ一週間、当初の右膝痛は解消していましたが、今度は右臀部に痛みが生じました。右脚の過剰な使用の結果の筋肉痛らしい。しかしこれも、ウソのように2日で消えました。徐々に、右脚への過度な負担が減って来た、体の硬さが消えてきたからのようです。
そして転院から8日ぐらい経って(記録では2月27日)、杖なしでの歩行を試みました。記録によると、15mほど歩いたようです。
それ以後、体幹補強訓練、体重移動訓練とあわせ、毎回、「杖なし歩行」の訓練を行ないました。リハビリ室内を一周するのですが、おそらく一周80mはあったのではないかと思います。
「杖なし歩行」は、出だしは好調に歩き出すのですが、右あるいは左へ方向を変えるとき(特に右へ曲るとき)に、体がふらつき「左脚を摺る」場面が生じます。
また、ある程度歩くと「左脚を摺る」場面が多発します。左脚への体重移動の制御がうまくゆかなくなるのです。疲れてくるからのようです。もちろん、疲れていない段階でも、ときおりそうなります。
3月に入りすぐ、「見守り付き」で「病棟内のT字杖歩行」が認められました。
車椅子からの解放です!
ただし、トイレに行くときもその旨伝え、「監視」がつきます。万一の事態に備えるためです。
リハビリは、それまでのメニューが、更に充実・強化されたようです。
リハビリ室での「杖なし歩行」も距離が伸びました。記録では、「3月6日杖なし歩行60m」とあるそうです。
その後、ほぼ毎日、室内を1周、あるいは2周しました。
「歩けるというのは、こんなにいいものなんだ」と、あらためて思ったものでした。
その数日後、歩行の訓練にあわせ、「T字杖での階段昇降の練習」を行ないました。
最初は、目指す段へ杖を置き、まず右脚をその段に乗せます。次いで、おもむろに左脚を載せる。これを繰り返して登ります。
降りるときは、左足を先に目指す段に置き、次いで右脚を置く。
慣れてくると、杖を使いながら、段に交互に脚を載せる普通の登り方、降り方の練習になります。
この杖を使う昇降に際し、以前に触れたような、登るときの「蹴上げ」面への爪先の擦り、降りるときの踵の擦りが起きました。療法士さんが背後で介護の構えをしていてくださるのですが、怖いものでした。
後に、杖なしで手摺につかまっての昇降訓練もしました。爪先・踵の擦りは同様に起きました。
いずれの場合でも、降りるときの方が怖さがあります。
更に3月13日になると、昼間の「病棟内のT字杖自立歩行」、つまり「見守りなし」が認められ、その5日後、発症から2ヶ月目の18日からは、夜間の「病棟内のT字杖自立歩行」も認められました。
トイレに行くのも連絡不要になったのです。とても気が楽になったことを覚えています。
また、リハビリの終わった後、病室まで、EVを使わずに見守り付きでT字杖を使い階段で帰る練習も何度か行ないました。
ほぼ同じ頃から、「T字杖での屋外歩行の練習」が始まりました。アスファルト舗装、コンクリート舗装、タイル敷き、砂利、芝生、土などいろいろな面を歩きました。一番歩き難かったのは、壊れかかったアスファルト舗装面。杖の石突が結構、路面のひび割れや穴に落ちるのです。砂利や土、芝生の方が楽でした。
この屋外歩行では、スロープでよく膝が崩れたり脚を摺りました。
僅かな勾配ではあっても、斜面では、体勢の制御がうまくゆかないのです(斜面では、脚の裏も斜面と同じ勾配の面を動かなければならないわけですが、その制御が難しいのです)。
特に、平らなところからスロープに差し掛かったその始まりのあたりでよく起き、スロープに慣れてしまえば、比較的起きなかったように記憶しています。
つまり、スロープは、車椅子にとっては段差解消であることは確かですが、脚が自在でない人にとっては、スロープも段差なのです。
前の記事で、段差をスロープに変えればバリアフリーになる、と考えるのは勘違いだと書きましたが、それはこの体験を通しての実感です。
この病院の玄関先の、駐車場から歩道に上がる縁石に鉄板の斜路(長さは1mもない)が設けてありますが、
この鉄板には、注意喚起のため、黄色のペンキで、ゼブラ模様が描かれていました。危ないのです。
「病棟内のT字杖自立歩行」が認められて直ぐに、「杖なし歩行」の訓練を始めました。そして、それを契機に、リハビリ室への往復を、自力で(見守りなしで)行なうことにしました(EVを使ってのT字杖自立歩行)。
歩行の形態は変っても、訓練のメニューはほぼ同じで、より高度になりました。
たとえば、直線上を、右脚左脚を交互に線上に載せて歩く練習(スムーズにはゆかず、かなりふらつきました)、同じことを横方向に行なう練習、この場合は、片方の脚を他の脚の前を通過させて線上に移す動作をともないますから、ふらつきが更に大きくなります。
「病棟内のT字杖自立歩行」が認められてからほぼ1週間後の3月26日からは、「病棟内の杖なし自立歩行」が認められました。
発症から約2ヶ月と1週間、「晴れて」普通に歩けるようになったのです!そして、数日後には、屋外の杖なし歩行の練習も始めました。
4月に入り、駅のホームでの電車に乗り降りを想定した訓練や、身をかがめて高さの低い所をくぐる訓練なども加わりました。生活をしてゆく上に起こるいろいろな場面を想定した訓練、基礎的な動作の応用・組立てと言えるかもしれません。
しかし、身をかがめるのは、筋力を鍛えないと容易ではありません(今でもふらつきます)。
人間というのは、本当にいろんなことをやっているんだ、とあらためて感心したことを覚えています。
理学療法:PTでは、退院まで、体力づくり、基本的訓練と応用訓練を続けました。自分でも、時折り、リハビリ室から3階の病室まで、EVを使わず階段を使う「自主練習」をやっていました。
そのころ、私の病室は、病棟北端部の部屋に変りました(退院間近な人の場所だそうです)。同じ階の南端に食堂があるので、最も食堂から遠い病室です。その間約70m。食堂から遠い病室では病室での食事も可能なのですが、その往復も歩行訓練になると思い、お断りし、毎回(一日3回、都合約500mになります)往復しました。

路傍のヨイマチグサ(オオマツヨイグサ:通称月見草)の群落。午前中は咲いています。
次に「回復期病院」での手のリハビリ:「作業療法:OT」について、書くことにします。
脚の場合は、「歩行」という「分りやすい」「動作」が主役ですが、手の場合は、そのような「代表的な主役」がありません。先回、次のように記しました。
・・・・
左手が自在に動かせないということは、思った以上に「不便」でした。
手先を目的とする位置にもってゆくことなどは、とてもできない。
たとえば、眼鏡の曇りをとりたくて、眼鏡ををはずすため、左側の「ツル」を掴もうとしても、手先はそこに届かず、頬をのあたりをさまよう。
健常なとき、手先は、右も左も、目で確認しなくても、目で確認できなくても、「思った」ところへもってゆくことができました。
考えてみたら、これは大変な「習慣」です。
おそらく、この「習慣」は、目で見て位置を知ったのではなく、手先で触ろうとする何度かの「試行」の結果、長年のうちに「体が覚えこんだ習慣」なのだと思います。
人の「動作」には、こういうのがいっぱいありそうです。
・・・・
そうなのです。(左)手の動作は、実に多様なのです。そして、欠かせない動作なのです。ところが、まったく気付いていなかった!!
そこで、左手が自在でないときの「作業」の「様態」を、思いつくまま、記してみます。
い)ボタン付きのシャツに着替える。
先ず、右手の援けのもとで左腕を袖に通す。先に右腕を通してしまったら、後が続かない(つまり、左腕を通すのは至難のワザになる)。
シャツを脱ぐときは、右腕が先。左腕を先にしてしまうと、右腕のときが、面倒になる・・・。
ズボンを穿くのも自在でない左を先にした方が早い。
ろ)ボタンをかける。
ボタンの裏側に右の親指をあて右の人差し指で表側を押さえ、そのまま左身頃の所定のボタン孔近くにもってゆく。孔の近くになったとき、人差し指を身頃の孔の方に移す。布越しに人差し指で孔をボタンに近づけ、その孔に親指でボタンを捻じ込む。これを繰り返す。結構時間がかかります。
普通は、左身頃のボタンの孔のあたりを左手指先で持ち、右手指先が持つボタンの近くへ運んでいるはずです。
私の左手は、この動作が出来なかった。
だから、利き手のマヒだったら、大変です。私は右利きだったから右手だけでも出来たのです。
けれども、「ボタンの掛け違い」をすると「悲劇」です!
「悲劇」を避けるには、一番下のボタンから始めるのがいいようでした。右手だけで、一番上のボタンを探り当てるのは容易ではありませんが、一番下のボタンの位置なら目視できるのです。
は)歯を磨くために歯ブラシに歯磨きをつける。
右手で持つ歯ブラシに歯磨きのチューブを押す。これも左手ではできない。押す力が出ないのです。かと言って、左手は歯ブラシを持てない。ゆえに、歯ブラシを台に横たえ、右手でチューブを押す羽目になる。
に)コップを持つ。
取っ手付きのコップでも取っ手を持てない。取っ手がない場合は、コップをうまく握れない。つまり、左手ではコップが持てない。
それゆえ、すべての作業を右手でするため、作業が連続的に、スムーズには進まないのです。
ご飯茶碗を持つ、味噌汁の碗を持つのも「恐怖」でした。持てても、「ご飯やミソ汁の重心」にうまく対応できなかった・・・。特に、重心の移動しやすい「液体」は難しかった。
ほ)髭を剃る。
普通は右手に剃刀を持ち、左手の指先で剃ったあとを確認しつつ剃る。しかしそれができず、剃っては剃刀を置き、右指で確認する・・・という手間の掛かる作業になります(やむなく途中から電動剃刀に変えました)。
へ)手で水を掬う。タオルを絞る。
顔を洗おうとして、両手で水を掬うという動作、これも、左の手の掌を、碗型にすることができない、右手だけでは水量が少ない。ゆえにタオルを濡らして顔を拭うことになりますが、肝心の濡らしたタオルを絞ることができない!絞るという動作にも、左手が大きな役割を担っているのです。それゆえ、タオルを少しだけ濡らして拭うことになる・・・・。
と)眼鏡をはずす。再掲です。
左側の「ツル」を掴もうとしても、手先はそこに届かず、頬をのあたりをさまよう。
右手ではずし、左手に持ち替えようとする。親指と人差し指で「ツル」を挟むも、滑ってしまう。
親指の押す力のベクトルと、人差し指のそれとが、「ツル」の芯をはずれて、相手を回転させるような状態なり、「ツル」は極端な場合、手から落ちてしまう。
右手でやってみるとそうはならない。実に「微妙」。
これは、先回触れたコーン状カップの移動訓練と同じく、
この動作は一見指先の問題のように見えるが、そうではないのだ、という「事実」を示していたのです。
ち)爪を切る。
右手に「爪切り」を持ち、左手の爪を切る。
このとき、左の指は、切りやすいように、「爪切り」に対して都合のよい位置に動いています。はじめは、そうしていることにまったく気付きませんでした。
左が自在に動かないので、この調整ができず、苦労しました。
左手で「爪切り」を使う段になると、眼鏡の「ツル」を掴むときと同じ現象が起きました。ベクトルの向きが「爪切り」に向わず、「爪切り」が手から離れてしまう、つまり落ちてしまうのです。
これは、「洗濯挟み」を扱うときも同じでした。
しかし、後に、「洗濯挟み」は、この「加える力のベクトルの向きの適正化の訓練の道具」として有効でした。
り)PETボトルの蓋を開け締めする。
普通は左手でボトルを握り、右手で蓋を開けますが、左手の押さえが効かないと、難儀します。
・・・・・
結局、「作業療法:OT」の「リハビリ訓練」とは、私なりの「理解」で記せば、
基本は「理学療法:PT」と同じですが、いろいろな「具体的な作業」を通じて、たとえば、指先の動きは、「肩(の関節)」~「肩から肘までの腕」~「肘(の関節)」~「肘から手首までの腕」~「手首(の関節)」~「手首から各指までの掌」~「各指(の各関節)」~「指先」、これがスムーズに連携・連動して初めて可能になるという事実を体で実感・認識すること、、
つまり、いかなる「動作」にも、それを行なうための「適切な『体勢・姿勢』」があるということを、あらためて体に覚えこませる訓練であると言えるかもしれません。
握力や指先に力を加えることは、必要ではあっても、それだけではダメだということです。
たとえば、眼鏡の「ツル」を持てるようになったとき、あるいは、「爪切り」をうまく操作できるようになったとき、指先の力はきわめて小さなものでよいことを知るのです。
OTの施療も、PTと同じく、まず左手を中心に上体・上肢の「硬さ」をほぐすことから始まりました。
先に触れた机の上で円柱を両手で転がすのもその一つ、大きなボールを転がすこともありました。
これらはいずれも、動いてしまう物体に体が付いて行かざるを得ないことを利用した、いわば「他動的、受動的な方法」と言えばよいでしょう。
一方で、「自分自身が能動的に動かなければならない方法」もいくつかありました。
たとえば、直径30cmぐらいのボールを両手で頭より高く持ち上げたり、
高さ2mほどの細いパイプの幹に何本もの枝が45度に突き出ている樹木状、コート掛け状の「装置」で、この突き出た「枝」に、左手で、直径20cmぐらいの「輪」を掛ける練習。
「枝」は、高さも位置も多様に用意されている。高い位置に掛けるには、体を伸ばさなければならない。位置によって、体の向きも自分で調整しなければならない。
また、直径6cmぐらいの表面が網目状の材料でできた長さ2m程度のパイプを左手で握り、座っている場所から程遠い位置に立て、そのパイプを前後に倒す練習もありました。
そのとき、腕を、肘も含めて極力伸ばす。これも、自分で体を伸ばさなければならない。パイプを立てる位置を少し変えることで、体を伸ばす向きも変ってくる。
この練習で使うパイプが、普通の塩ビ管ではなく、表面がざらざらした網目状の材料の管である理由は、その手触りに拠るようです。
人によると、手の触覚もマヒする方が居られるようです。そこで、触感の異なる品々を用意し、その差を認識する訓練にも使うのだそうです。
私の場合は、触感の違いについては認識できますが、
少しばかり、温度に対する感覚に違和感があり、また、左手の指先では脈拍を感じることが出来ませんでした。
ところで、前者のコート掛け型・樹木状の「装置」は、療法士さんが製作されたものなのです。
材料は給水管に使う塩ビ管(通称20VP)。各種分岐部品を使って器用に組立てられています。
近くののホームセンターで材料を買い求めて作ったのだそうです。
そして、枝に掛ける「輪」は、ホースで輪をつくりビニルテープをぐるぐる巻きにしてつくったもの。
いずれも制作者は女性とのこと。ともに、出来は非常に見事。
また、後者の表面が網目状のパイプ。
実はこれは、農地の土壌改良などで使われる「透水管」です。土の中の余分な水だけを抜くために使います。
その他にも、お手製の「用具」が数多く見られました。
療法士さんたちは、日夜、よりよい施療の方法を考え続けていて、
街を歩いていても、店先に並んでいる商品を見ては、これはあの訓練に使える・・などと思い付くようです。
これは、建物づくりの「職人さん」たちが、常に、当面の「問題」を考え続け、
また、仕事を上手にこなすために、いろいろと工夫をこらした「道具」を手づくりするのに似ています。
私は、療法士さんたちの仕事ぶりに接して、この方たちは生粋の「職人さん」だ、と思ったものでした。
今回、「回帰の記」なる一文を書く契機になったのは、前にも触れましたが、
療法士さんたちの、「専門」:自分の「仕事」:に対する「真摯な態度」を目の当たりにしたからなのです。
しかも、この方たちは皆「謙虚」です。
他の「専門家」にえてして見られる、「専門」をひけらかす、などということは微塵もない!
副題に「敬意」の一語を入れたのも、この点に「感動」を覚えたからなのです。
さて、上半身の硬さ、特に肩、肘まわりはほぐれてきましたが、私の場合、硬さが消えなかったのが、手首から指先にかけてでした(現在もなお不全です)。
具体的に言うと、指の関節が痛み、完全な「グー」の形をつくれない、したがって、ものを握りづらい、掴みづらいのです。
そのために、いろいろな訓練が為されました。
先のコーン型のカップの練習もその一つですが、その他、たとえば、机の上の「お手玉」(療法士さんの手づくりです)1個ずつ左手で掴み、移動する、あるいは、鷲掴みにして出来るだけ多く掴む、それを別の場所に移動する・・・、ガラス玉を指先でつまんで別の場所に移す、金属の玉で同じことをする・・・などなど。
なかでも、一番「効果」があると思えたのは、容器に入っている、しかも容器にへばりついているプラスティック製の粘土(セラプラストと呼ぶようです)を、左手の指先を使って「掻き出す」作業。結構、力がいります。数分はかかります。
容器から出した粘土を、陶芸のように、両手でこねる。団子にする、指先だけでで紙のように薄くする・・・。
この練習をした後、しばらくの間は、指はかなり曲げられるようになります。つまり、一定程度「グー」ができる。
また、手首を柔軟にするために、3分の1ぐらい水の入ったPETボトルを握り、中の水を移動させる練習もありました。水の代りにガラス玉の入ったボトルでの練習もありました。いわば、「他動的」に手首を動かさざるを得ない状況にする練習です。
この場合も、練習後、手首の動きが柔らかくなります。
また、中にゴルフボールを入れたお碗を左手で持ち、それを動かして重心の移動に応じて手を動かす練習もありました。バランスを感じとる訓練と言えばよいでしょう。
問題は、こういう練習で「改善した状態」を、持続できないことでした。翌日には少し後戻りしているのです。3歩前進2歩後退・・・。
それでも、退院間際には、先に例に出した左手を使う「動作」のうち、ほとんどは7~8割は「復活」出来ていたように思います。
たとえば、眼鏡の「ツル」は、リハビリを開始して1週間後には自在に掴めるようになり、左手指先を思った場所に(目視できなくても)もってゆくことも出来るようになっていました。
もっとも、そういう状態になっていたゆえに退院が認められたのですが・・・。
ただ一つ、「復活」が遅れていたのが、に)のコップを持つ動作。茶碗を持つのも相変わらず不安でした。
そのため、退院後も、週1回の外来・通院リハビリでOT:手のリハビリを継続しています。
しかし、3歩前進2歩後退の状態は今も同じです。
今は、覚悟を決めて、3歩前進2歩後退で良しとしよう、焦らずに気長に直してゆこう、と考えています。

ヨイマチグサの花。昼過ぎにはしぼんでしまいます。
言語療法:STは、PT、OTとは別の小部屋で行なわれました。
その内容は急性期病院と同様、発声、発音の確認(それに関係する部位についてのPTと言えるでしょう)、脳機能の様態を確認するための各種のテストなどでした。
その中で、私の印象に強く残っているのは、療法士さんが、私に積極的に「話をさせる」「喋る」機会を設けられたことでした。
療法士さんご自身がいろいろなことに多様な関心をお持ちの方で、たとえば、リハビリ室に今日活けた花について語ったり、最近行ってきた旅先の話題をだしたりして、いろいろと「話のきっかけ」をつくり、それについて、私に「話をさせる」「喋らせる」のです。一言で言えば、話を「させ上手」そして「聞き上手」なのです。
おそらく、「話をする」「喋る」ことで、言うならば「脳の活性化」、あるいは「脳が休眠・退化することを押し止めよう」という意図があったのではないか、と後になって気が付きました。
実際、回復したように思えた方で、退院後しばらくして、脳の機能が衰え始める方が居られるのだそうです。
入院していると、「普通」の会話(仕事がらみの会話はもちろん、考えながら話すような会話)の機会が極端に減ります。脳が休眠化するのは目に見えています。
その意味で、STの時間は、今から考えると、貴重な時間でした。
PT、OTの療法士さんたちも、施療中、積極的に患者さんに話しかけています。
それも、同じような療法士さんの「気遣い」「心遣い」なのかもしれません。

庭先のヤマユリ。野山で見る方がきれいに思えます。
退院し、回復期病院での3ヶ月を振り返ってみて思ったのは、
PTもOTもSTも、つまり、re-habilitation では、根本的に、本人の「感覚」「能動性」が重視されているのだ、ということでした。
「これでよし」という判断は、結局のところ、本人が本人の「感覚」で「納得するかどうか」にかかっている、ということです。
これは、何でも「科学的物指し」で測るのがよしとされ、そうでないのは「非科学的」とされる当今、きわめて新鮮に感じられました。
そして、自らの「感覚」「五感」を研ぎ澄ますには、本人の「能動性」が不可欠なのだ、ということも、改めて認識させられました。
「能力」は、外から付加されるものではない、ということです。
ここでは、「生身の人間の存在」が、当然のこととして、認められていたのです!!
長くなりました、今回はここまでにします。
次回は、「回帰後」の今、これまで断片的に書いてきた「リハビリに於いて思ったこと」をまとめてみようかと考えています。
ところが、その後、当地域は北東風が流れこみ、まるで初秋のような気候が続いています。今朝の気温は18度でした。
例年ならとっくに盛りを迎える合歓の木(ネムノキ)の花も、やっと咲き始めたところで、しかも、このところの雨不足のせいか、きれいに咲いていません。

昨日の朝の合歓の木。まだ、ほとんどが蕾。
例年なら、このように咲いている頃です。

発症から一ヶ月経った 2月19日、「回復期病院」へ転院しました。
まだ車椅子でしたから、介護タクシーの厄介になりました。街ではよく見掛けていましたが、自分が乗るなどとは思ってもいませんでした。
転院先の病院では、「急性期病院」からの患者だからでしょう、ナースステーションの直ぐ前の病室に私のベッドが用意されていました。
トイレは、車椅子用のトイレを使うことになりましたが、自走できないので、その都度、看護師さんの援けを借らざるを得ませんでした。これは大変心苦しいものがありました。
翌日からリハビリが始まりました。
「回復期病院」のリハビリは、「理学療法:PT」「作業療法:OT」「言語療法:ST」各40分で、それぞれ主に担当する療法士さんが決まっています。
時間帯は日により異なり、午前は9時から11時半ごろまで、午後は1時半から5時半ごろまでのどこかに設定されます(前日の夕方、翌日の時間割が知らされます)。
その時間になると、担当の療法士さんが、わざわざ1階のリハビリ室から3階の病室まで迎えに来られます。転院当初は、リハビリ室まで、療法士さんに車椅子で搬送してもらいました。これも大変心苦しいものでした。
リハビリ室担当の療法士さんは、「理学療法士」「作業療法士」「言語療法士」合せて30人以上居られたようです。
「理学療法:PT」の初回は、リハビリ室に着くと、「急性期病院」と同じ「四点杖」で、片道20mほどを往復歩行しました。
療法士さんは、その歩行の様子から、私の「問題点」を判定されるようです。
PTで、最初に指摘された「問題点」は「猫背」つまり、姿勢の悪さと、左脚への体重移動のぎこちなさ(左の膝が「挫屈」を起こすことが多い)、右手右脚への過剰に頼り過ぎ(転院時にあった右膝痛は、その結果)、そしてそれに起因すると思われる右半身の「硬さ」などでした。
姿勢の悪さの他は、本人ははっきり気がついてはいないのですが、療法士さんには、たちどころに分るようです。
「作業療法:OT」の初回では、左手の動作の様態が観察され、私の「問題点」が判定されました。
そのとき、私の上肢は、左手は「万歳」の恰好を維持できず(後にそのとき撮った写真を見せていただきましたが、我ながら情けない姿でした!)、手の掌は、握ることも完全に開くこともできず(つまりグーパーができず)、指折り数えることなどまったくできませんでした。各指を独立に動かすことができないのです。すでに触れた「左手の置き忘れ」や車椅子の「左ブレーキの掛け忘れ」なども伝えられていました。
このPT、OTの初回の「様態観察」と「急性期病院」からの伝達事項から、私の「実情」は、通常の生活を行なえるレベルを100として、35程度であると判定されました。要は、普通の人の35%の能力しかない、ということでしょう。
PTは、毎回、「験しの歩行」をしたあと(最初は「四点杖」でしたが、すぐに「T字杖」になりました)、マットの上で横になり、先ず、右半身の「硬さをほぐす」ことと「体の左右のアンバランスの是正」、そして「体幹の矯正・補強」のための諸種の「訓練」を行ないました。「意識せずに入ってしまっている力(結構、これが多いようです)」を「抜く」方策もあったようです。
これらは、右手右脚に頼りすぎた結果生じた「現象」だったと思われ、先に触れたように、転院時にあった右膝の痛みも、その一つの現れと考えられます。
ただ、この各種の「施療」を具体的かつ適確に記すことは、私には不可能です(メカニズムが分らないのです)。
しかし、施療後、体が「軽い感じ」になり、体の「動き」も楽になったのは確かです。
一つだけ分りやすい例を挙げると、クッション材でつくった直径15cmほど、長さ70cmほどの円柱の上に、背骨を載せて上向きに寝転ぶ「訓練」があります。これは、私自身、その「効果」をよく実感できた訓練でした。
脚は立て膝の恰好で手は体の上に置きます。円柱ですから、この姿勢:円柱の上に背骨が載る:を、立て膝をした脚だけを頼りに維持するのは難しく、上半身自体でバランスをとらなければなりません。
何度かやっているうちに、上半身の左右のバランスを適切に按配することができるようになります。同時に、その時、背筋も伸びていることも実感できる。これが、載っていて「結構気持ちがいい」のです!
この「適切な按配」は、体が「感覚」で「読み取っている」のだと考えられます(かつて、自転車に乗れるようになったとき、おそらく同じような「読み取り」があったものと思います)。この円柱は「ストレッチポール」と呼んでいたと思います。
数分以上この姿勢を維持したあと、円柱から降りてみると、体の硬さはほぐれ、軽く、姿勢もよくなっているように思えました。これは、立ってみると一層よく分りました。当然歩き方にも反映し、歩きが軽快になります。
同様の円柱は、OTで、テーブル上に体の前に横一文字に置き、それを両手で前後に転がす訓練で使いました。
円柱の転がりを両手で制御するわけです。「急性期病院」での「雑巾がけ」と同じような「効果」があるようです。
ただこのとき、「右手のおせっかい」が出てしまう!。左手が転がす動きをとる前に右手が動いてしまうのです。
PTでは、スムーズな体重移動、つまりスムーズな歩行の基礎訓練として、平行棒での訓練がありました。平行棒の間に立ち、体を(腰を)左右に動かし、平行棒に当たるか当たらないかという位置で止める訓練です。右側は簡単ですが左側はなかなか望む位置で止められないのです。
療法士さんは、その様子から、どこに問題があるかを見抜くようで、それが次の訓練のメニューとなるようです。
メニューの最大の眼目は、「体幹の補強」:胸部、腹部、背部、腰部、大腿部・・の筋力の増強訓練だったと思います。
左大腿部の萎えた様子は自分でも目に見えて分りましたが他は分りません。筋肉には外から目に見えるものと、内部に隠れているもの(インナーと呼んでいるようでした。これに対して前者はアウターらしい)とがあるそうで、その内部の筋力も強化が必要で、そのための訓練もあったようです。メカニズムはよく分りませんが、こういった内外の筋が連携して作動しているようです。
人の体の構造、機構の「凄さ」には本当に驚きます。
具体的な施療はいろいろとありましたが、これも適確に記述することも私にはできません。言えるのは、訓練後、疲れておなかが空くこと!
転院ほぼ一週間、当初の右膝痛は解消していましたが、今度は右臀部に痛みが生じました。右脚の過剰な使用の結果の筋肉痛らしい。しかしこれも、ウソのように2日で消えました。徐々に、右脚への過度な負担が減って来た、体の硬さが消えてきたからのようです。
そして転院から8日ぐらい経って(記録では2月27日)、杖なしでの歩行を試みました。記録によると、15mほど歩いたようです。
それ以後、体幹補強訓練、体重移動訓練とあわせ、毎回、「杖なし歩行」の訓練を行ないました。リハビリ室内を一周するのですが、おそらく一周80mはあったのではないかと思います。
「杖なし歩行」は、出だしは好調に歩き出すのですが、右あるいは左へ方向を変えるとき(特に右へ曲るとき)に、体がふらつき「左脚を摺る」場面が生じます。
また、ある程度歩くと「左脚を摺る」場面が多発します。左脚への体重移動の制御がうまくゆかなくなるのです。疲れてくるからのようです。もちろん、疲れていない段階でも、ときおりそうなります。
3月に入りすぐ、「見守り付き」で「病棟内のT字杖歩行」が認められました。
車椅子からの解放です!
ただし、トイレに行くときもその旨伝え、「監視」がつきます。万一の事態に備えるためです。
リハビリは、それまでのメニューが、更に充実・強化されたようです。
リハビリ室での「杖なし歩行」も距離が伸びました。記録では、「3月6日杖なし歩行60m」とあるそうです。
その後、ほぼ毎日、室内を1周、あるいは2周しました。
「歩けるというのは、こんなにいいものなんだ」と、あらためて思ったものでした。
その数日後、歩行の訓練にあわせ、「T字杖での階段昇降の練習」を行ないました。
最初は、目指す段へ杖を置き、まず右脚をその段に乗せます。次いで、おもむろに左脚を載せる。これを繰り返して登ります。
降りるときは、左足を先に目指す段に置き、次いで右脚を置く。
慣れてくると、杖を使いながら、段に交互に脚を載せる普通の登り方、降り方の練習になります。
この杖を使う昇降に際し、以前に触れたような、登るときの「蹴上げ」面への爪先の擦り、降りるときの踵の擦りが起きました。療法士さんが背後で介護の構えをしていてくださるのですが、怖いものでした。
後に、杖なしで手摺につかまっての昇降訓練もしました。爪先・踵の擦りは同様に起きました。
いずれの場合でも、降りるときの方が怖さがあります。
更に3月13日になると、昼間の「病棟内のT字杖自立歩行」、つまり「見守りなし」が認められ、その5日後、発症から2ヶ月目の18日からは、夜間の「病棟内のT字杖自立歩行」も認められました。
トイレに行くのも連絡不要になったのです。とても気が楽になったことを覚えています。
また、リハビリの終わった後、病室まで、EVを使わずに見守り付きでT字杖を使い階段で帰る練習も何度か行ないました。
ほぼ同じ頃から、「T字杖での屋外歩行の練習」が始まりました。アスファルト舗装、コンクリート舗装、タイル敷き、砂利、芝生、土などいろいろな面を歩きました。一番歩き難かったのは、壊れかかったアスファルト舗装面。杖の石突が結構、路面のひび割れや穴に落ちるのです。砂利や土、芝生の方が楽でした。
この屋外歩行では、スロープでよく膝が崩れたり脚を摺りました。
僅かな勾配ではあっても、斜面では、体勢の制御がうまくゆかないのです(斜面では、脚の裏も斜面と同じ勾配の面を動かなければならないわけですが、その制御が難しいのです)。
特に、平らなところからスロープに差し掛かったその始まりのあたりでよく起き、スロープに慣れてしまえば、比較的起きなかったように記憶しています。
つまり、スロープは、車椅子にとっては段差解消であることは確かですが、脚が自在でない人にとっては、スロープも段差なのです。
前の記事で、段差をスロープに変えればバリアフリーになる、と考えるのは勘違いだと書きましたが、それはこの体験を通しての実感です。
この病院の玄関先の、駐車場から歩道に上がる縁石に鉄板の斜路(長さは1mもない)が設けてありますが、
この鉄板には、注意喚起のため、黄色のペンキで、ゼブラ模様が描かれていました。危ないのです。
「病棟内のT字杖自立歩行」が認められて直ぐに、「杖なし歩行」の訓練を始めました。そして、それを契機に、リハビリ室への往復を、自力で(見守りなしで)行なうことにしました(EVを使ってのT字杖自立歩行)。
歩行の形態は変っても、訓練のメニューはほぼ同じで、より高度になりました。
たとえば、直線上を、右脚左脚を交互に線上に載せて歩く練習(スムーズにはゆかず、かなりふらつきました)、同じことを横方向に行なう練習、この場合は、片方の脚を他の脚の前を通過させて線上に移す動作をともないますから、ふらつきが更に大きくなります。
「病棟内のT字杖自立歩行」が認められてからほぼ1週間後の3月26日からは、「病棟内の杖なし自立歩行」が認められました。
発症から約2ヶ月と1週間、「晴れて」普通に歩けるようになったのです!そして、数日後には、屋外の杖なし歩行の練習も始めました。
4月に入り、駅のホームでの電車に乗り降りを想定した訓練や、身をかがめて高さの低い所をくぐる訓練なども加わりました。生活をしてゆく上に起こるいろいろな場面を想定した訓練、基礎的な動作の応用・組立てと言えるかもしれません。
しかし、身をかがめるのは、筋力を鍛えないと容易ではありません(今でもふらつきます)。
人間というのは、本当にいろんなことをやっているんだ、とあらためて感心したことを覚えています。
理学療法:PTでは、退院まで、体力づくり、基本的訓練と応用訓練を続けました。自分でも、時折り、リハビリ室から3階の病室まで、EVを使わず階段を使う「自主練習」をやっていました。
そのころ、私の病室は、病棟北端部の部屋に変りました(退院間近な人の場所だそうです)。同じ階の南端に食堂があるので、最も食堂から遠い病室です。その間約70m。食堂から遠い病室では病室での食事も可能なのですが、その往復も歩行訓練になると思い、お断りし、毎回(一日3回、都合約500mになります)往復しました。

路傍のヨイマチグサ(オオマツヨイグサ:通称月見草)の群落。午前中は咲いています。
次に「回復期病院」での手のリハビリ:「作業療法:OT」について、書くことにします。
脚の場合は、「歩行」という「分りやすい」「動作」が主役ですが、手の場合は、そのような「代表的な主役」がありません。先回、次のように記しました。
・・・・
左手が自在に動かせないということは、思った以上に「不便」でした。
手先を目的とする位置にもってゆくことなどは、とてもできない。
たとえば、眼鏡の曇りをとりたくて、眼鏡ををはずすため、左側の「ツル」を掴もうとしても、手先はそこに届かず、頬をのあたりをさまよう。
健常なとき、手先は、右も左も、目で確認しなくても、目で確認できなくても、「思った」ところへもってゆくことができました。
考えてみたら、これは大変な「習慣」です。
おそらく、この「習慣」は、目で見て位置を知ったのではなく、手先で触ろうとする何度かの「試行」の結果、長年のうちに「体が覚えこんだ習慣」なのだと思います。
人の「動作」には、こういうのがいっぱいありそうです。
・・・・
そうなのです。(左)手の動作は、実に多様なのです。そして、欠かせない動作なのです。ところが、まったく気付いていなかった!!
そこで、左手が自在でないときの「作業」の「様態」を、思いつくまま、記してみます。
い)ボタン付きのシャツに着替える。
先ず、右手の援けのもとで左腕を袖に通す。先に右腕を通してしまったら、後が続かない(つまり、左腕を通すのは至難のワザになる)。
シャツを脱ぐときは、右腕が先。左腕を先にしてしまうと、右腕のときが、面倒になる・・・。
ズボンを穿くのも自在でない左を先にした方が早い。
ろ)ボタンをかける。
ボタンの裏側に右の親指をあて右の人差し指で表側を押さえ、そのまま左身頃の所定のボタン孔近くにもってゆく。孔の近くになったとき、人差し指を身頃の孔の方に移す。布越しに人差し指で孔をボタンに近づけ、その孔に親指でボタンを捻じ込む。これを繰り返す。結構時間がかかります。
普通は、左身頃のボタンの孔のあたりを左手指先で持ち、右手指先が持つボタンの近くへ運んでいるはずです。
私の左手は、この動作が出来なかった。
だから、利き手のマヒだったら、大変です。私は右利きだったから右手だけでも出来たのです。
けれども、「ボタンの掛け違い」をすると「悲劇」です!
「悲劇」を避けるには、一番下のボタンから始めるのがいいようでした。右手だけで、一番上のボタンを探り当てるのは容易ではありませんが、一番下のボタンの位置なら目視できるのです。
は)歯を磨くために歯ブラシに歯磨きをつける。
右手で持つ歯ブラシに歯磨きのチューブを押す。これも左手ではできない。押す力が出ないのです。かと言って、左手は歯ブラシを持てない。ゆえに、歯ブラシを台に横たえ、右手でチューブを押す羽目になる。
に)コップを持つ。
取っ手付きのコップでも取っ手を持てない。取っ手がない場合は、コップをうまく握れない。つまり、左手ではコップが持てない。
それゆえ、すべての作業を右手でするため、作業が連続的に、スムーズには進まないのです。
ご飯茶碗を持つ、味噌汁の碗を持つのも「恐怖」でした。持てても、「ご飯やミソ汁の重心」にうまく対応できなかった・・・。特に、重心の移動しやすい「液体」は難しかった。
ほ)髭を剃る。
普通は右手に剃刀を持ち、左手の指先で剃ったあとを確認しつつ剃る。しかしそれができず、剃っては剃刀を置き、右指で確認する・・・という手間の掛かる作業になります(やむなく途中から電動剃刀に変えました)。
へ)手で水を掬う。タオルを絞る。
顔を洗おうとして、両手で水を掬うという動作、これも、左の手の掌を、碗型にすることができない、右手だけでは水量が少ない。ゆえにタオルを濡らして顔を拭うことになりますが、肝心の濡らしたタオルを絞ることができない!絞るという動作にも、左手が大きな役割を担っているのです。それゆえ、タオルを少しだけ濡らして拭うことになる・・・・。
と)眼鏡をはずす。再掲です。
左側の「ツル」を掴もうとしても、手先はそこに届かず、頬をのあたりをさまよう。
右手ではずし、左手に持ち替えようとする。親指と人差し指で「ツル」を挟むも、滑ってしまう。
親指の押す力のベクトルと、人差し指のそれとが、「ツル」の芯をはずれて、相手を回転させるような状態なり、「ツル」は極端な場合、手から落ちてしまう。
右手でやってみるとそうはならない。実に「微妙」。
これは、先回触れたコーン状カップの移動訓練と同じく、
この動作は一見指先の問題のように見えるが、そうではないのだ、という「事実」を示していたのです。
ち)爪を切る。
右手に「爪切り」を持ち、左手の爪を切る。
このとき、左の指は、切りやすいように、「爪切り」に対して都合のよい位置に動いています。はじめは、そうしていることにまったく気付きませんでした。
左が自在に動かないので、この調整ができず、苦労しました。
左手で「爪切り」を使う段になると、眼鏡の「ツル」を掴むときと同じ現象が起きました。ベクトルの向きが「爪切り」に向わず、「爪切り」が手から離れてしまう、つまり落ちてしまうのです。
これは、「洗濯挟み」を扱うときも同じでした。
しかし、後に、「洗濯挟み」は、この「加える力のベクトルの向きの適正化の訓練の道具」として有効でした。
り)PETボトルの蓋を開け締めする。
普通は左手でボトルを握り、右手で蓋を開けますが、左手の押さえが効かないと、難儀します。
・・・・・
結局、「作業療法:OT」の「リハビリ訓練」とは、私なりの「理解」で記せば、
基本は「理学療法:PT」と同じですが、いろいろな「具体的な作業」を通じて、たとえば、指先の動きは、「肩(の関節)」~「肩から肘までの腕」~「肘(の関節)」~「肘から手首までの腕」~「手首(の関節)」~「手首から各指までの掌」~「各指(の各関節)」~「指先」、これがスムーズに連携・連動して初めて可能になるという事実を体で実感・認識すること、、
つまり、いかなる「動作」にも、それを行なうための「適切な『体勢・姿勢』」があるということを、あらためて体に覚えこませる訓練であると言えるかもしれません。
握力や指先に力を加えることは、必要ではあっても、それだけではダメだということです。
たとえば、眼鏡の「ツル」を持てるようになったとき、あるいは、「爪切り」をうまく操作できるようになったとき、指先の力はきわめて小さなものでよいことを知るのです。
OTの施療も、PTと同じく、まず左手を中心に上体・上肢の「硬さ」をほぐすことから始まりました。
先に触れた机の上で円柱を両手で転がすのもその一つ、大きなボールを転がすこともありました。
これらはいずれも、動いてしまう物体に体が付いて行かざるを得ないことを利用した、いわば「他動的、受動的な方法」と言えばよいでしょう。
一方で、「自分自身が能動的に動かなければならない方法」もいくつかありました。
たとえば、直径30cmぐらいのボールを両手で頭より高く持ち上げたり、
高さ2mほどの細いパイプの幹に何本もの枝が45度に突き出ている樹木状、コート掛け状の「装置」で、この突き出た「枝」に、左手で、直径20cmぐらいの「輪」を掛ける練習。
「枝」は、高さも位置も多様に用意されている。高い位置に掛けるには、体を伸ばさなければならない。位置によって、体の向きも自分で調整しなければならない。
また、直径6cmぐらいの表面が網目状の材料でできた長さ2m程度のパイプを左手で握り、座っている場所から程遠い位置に立て、そのパイプを前後に倒す練習もありました。
そのとき、腕を、肘も含めて極力伸ばす。これも、自分で体を伸ばさなければならない。パイプを立てる位置を少し変えることで、体を伸ばす向きも変ってくる。
この練習で使うパイプが、普通の塩ビ管ではなく、表面がざらざらした網目状の材料の管である理由は、その手触りに拠るようです。
人によると、手の触覚もマヒする方が居られるようです。そこで、触感の異なる品々を用意し、その差を認識する訓練にも使うのだそうです。
私の場合は、触感の違いについては認識できますが、
少しばかり、温度に対する感覚に違和感があり、また、左手の指先では脈拍を感じることが出来ませんでした。
ところで、前者のコート掛け型・樹木状の「装置」は、療法士さんが製作されたものなのです。
材料は給水管に使う塩ビ管(通称20VP)。各種分岐部品を使って器用に組立てられています。
近くののホームセンターで材料を買い求めて作ったのだそうです。
そして、枝に掛ける「輪」は、ホースで輪をつくりビニルテープをぐるぐる巻きにしてつくったもの。
いずれも制作者は女性とのこと。ともに、出来は非常に見事。
また、後者の表面が網目状のパイプ。
実はこれは、農地の土壌改良などで使われる「透水管」です。土の中の余分な水だけを抜くために使います。
その他にも、お手製の「用具」が数多く見られました。
療法士さんたちは、日夜、よりよい施療の方法を考え続けていて、
街を歩いていても、店先に並んでいる商品を見ては、これはあの訓練に使える・・などと思い付くようです。
これは、建物づくりの「職人さん」たちが、常に、当面の「問題」を考え続け、
また、仕事を上手にこなすために、いろいろと工夫をこらした「道具」を手づくりするのに似ています。
私は、療法士さんたちの仕事ぶりに接して、この方たちは生粋の「職人さん」だ、と思ったものでした。
今回、「回帰の記」なる一文を書く契機になったのは、前にも触れましたが、
療法士さんたちの、「専門」:自分の「仕事」:に対する「真摯な態度」を目の当たりにしたからなのです。
しかも、この方たちは皆「謙虚」です。
他の「専門家」にえてして見られる、「専門」をひけらかす、などということは微塵もない!
副題に「敬意」の一語を入れたのも、この点に「感動」を覚えたからなのです。
さて、上半身の硬さ、特に肩、肘まわりはほぐれてきましたが、私の場合、硬さが消えなかったのが、手首から指先にかけてでした(現在もなお不全です)。
具体的に言うと、指の関節が痛み、完全な「グー」の形をつくれない、したがって、ものを握りづらい、掴みづらいのです。
そのために、いろいろな訓練が為されました。
先のコーン型のカップの練習もその一つですが、その他、たとえば、机の上の「お手玉」(療法士さんの手づくりです)1個ずつ左手で掴み、移動する、あるいは、鷲掴みにして出来るだけ多く掴む、それを別の場所に移動する・・・、ガラス玉を指先でつまんで別の場所に移す、金属の玉で同じことをする・・・などなど。
なかでも、一番「効果」があると思えたのは、容器に入っている、しかも容器にへばりついているプラスティック製の粘土(セラプラストと呼ぶようです)を、左手の指先を使って「掻き出す」作業。結構、力がいります。数分はかかります。
容器から出した粘土を、陶芸のように、両手でこねる。団子にする、指先だけでで紙のように薄くする・・・。
この練習をした後、しばらくの間は、指はかなり曲げられるようになります。つまり、一定程度「グー」ができる。
また、手首を柔軟にするために、3分の1ぐらい水の入ったPETボトルを握り、中の水を移動させる練習もありました。水の代りにガラス玉の入ったボトルでの練習もありました。いわば、「他動的」に手首を動かさざるを得ない状況にする練習です。
この場合も、練習後、手首の動きが柔らかくなります。
また、中にゴルフボールを入れたお碗を左手で持ち、それを動かして重心の移動に応じて手を動かす練習もありました。バランスを感じとる訓練と言えばよいでしょう。
問題は、こういう練習で「改善した状態」を、持続できないことでした。翌日には少し後戻りしているのです。3歩前進2歩後退・・・。
それでも、退院間際には、先に例に出した左手を使う「動作」のうち、ほとんどは7~8割は「復活」出来ていたように思います。
たとえば、眼鏡の「ツル」は、リハビリを開始して1週間後には自在に掴めるようになり、左手指先を思った場所に(目視できなくても)もってゆくことも出来るようになっていました。
もっとも、そういう状態になっていたゆえに退院が認められたのですが・・・。
ただ一つ、「復活」が遅れていたのが、に)のコップを持つ動作。茶碗を持つのも相変わらず不安でした。
そのため、退院後も、週1回の外来・通院リハビリでOT:手のリハビリを継続しています。
しかし、3歩前進2歩後退の状態は今も同じです。
今は、覚悟を決めて、3歩前進2歩後退で良しとしよう、焦らずに気長に直してゆこう、と考えています。

ヨイマチグサの花。昼過ぎにはしぼんでしまいます。
言語療法:STは、PT、OTとは別の小部屋で行なわれました。
その内容は急性期病院と同様、発声、発音の確認(それに関係する部位についてのPTと言えるでしょう)、脳機能の様態を確認するための各種のテストなどでした。
その中で、私の印象に強く残っているのは、療法士さんが、私に積極的に「話をさせる」「喋る」機会を設けられたことでした。
療法士さんご自身がいろいろなことに多様な関心をお持ちの方で、たとえば、リハビリ室に今日活けた花について語ったり、最近行ってきた旅先の話題をだしたりして、いろいろと「話のきっかけ」をつくり、それについて、私に「話をさせる」「喋らせる」のです。一言で言えば、話を「させ上手」そして「聞き上手」なのです。
おそらく、「話をする」「喋る」ことで、言うならば「脳の活性化」、あるいは「脳が休眠・退化することを押し止めよう」という意図があったのではないか、と後になって気が付きました。
実際、回復したように思えた方で、退院後しばらくして、脳の機能が衰え始める方が居られるのだそうです。
入院していると、「普通」の会話(仕事がらみの会話はもちろん、考えながら話すような会話)の機会が極端に減ります。脳が休眠化するのは目に見えています。
その意味で、STの時間は、今から考えると、貴重な時間でした。
PT、OTの療法士さんたちも、施療中、積極的に患者さんに話しかけています。
それも、同じような療法士さんの「気遣い」「心遣い」なのかもしれません。

庭先のヤマユリ。野山で見る方がきれいに思えます。
退院し、回復期病院での3ヶ月を振り返ってみて思ったのは、
PTもOTもSTも、つまり、re-habilitation では、根本的に、本人の「感覚」「能動性」が重視されているのだ、ということでした。
「これでよし」という判断は、結局のところ、本人が本人の「感覚」で「納得するかどうか」にかかっている、ということです。
これは、何でも「科学的物指し」で測るのがよしとされ、そうでないのは「非科学的」とされる当今、きわめて新鮮に感じられました。
そして、自らの「感覚」「五感」を研ぎ澄ますには、本人の「能動性」が不可欠なのだ、ということも、改めて認識させられました。
「能力」は、外から付加されるものではない、ということです。
ここでは、「生身の人間の存在」が、当然のこととして、認められていたのです!!
長くなりました、今回はここまでにします。
次回は、「回帰後」の今、これまで断片的に書いてきた「リハビリに於いて思ったこと」をまとめてみようかと考えています。