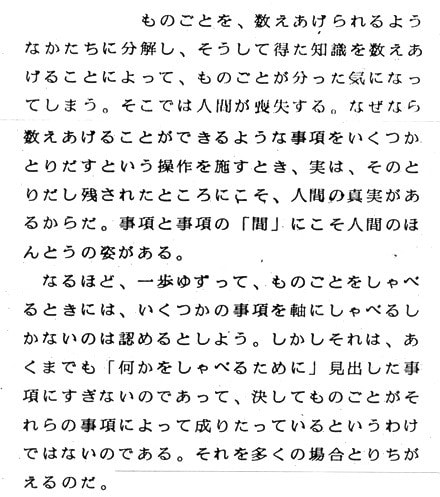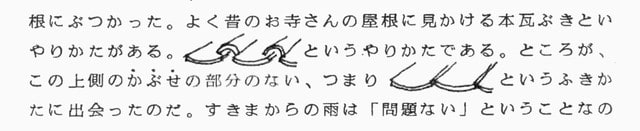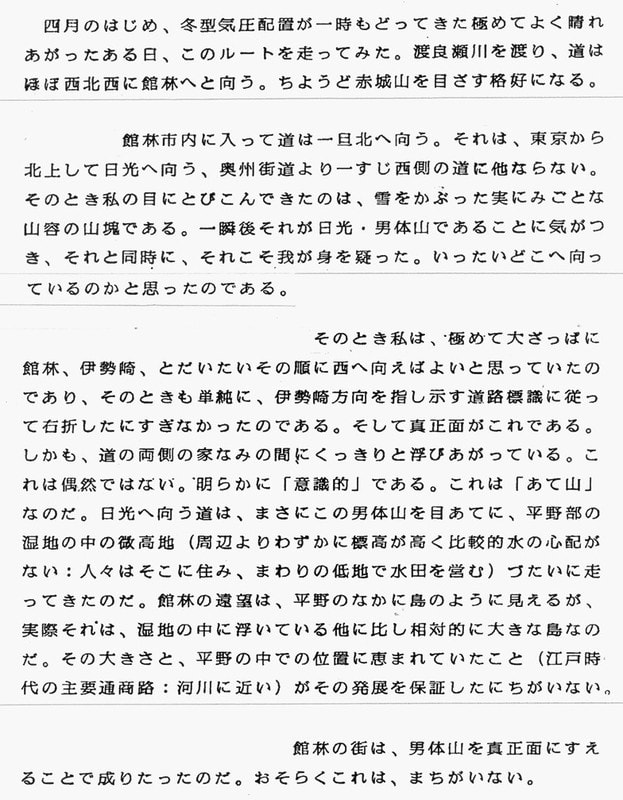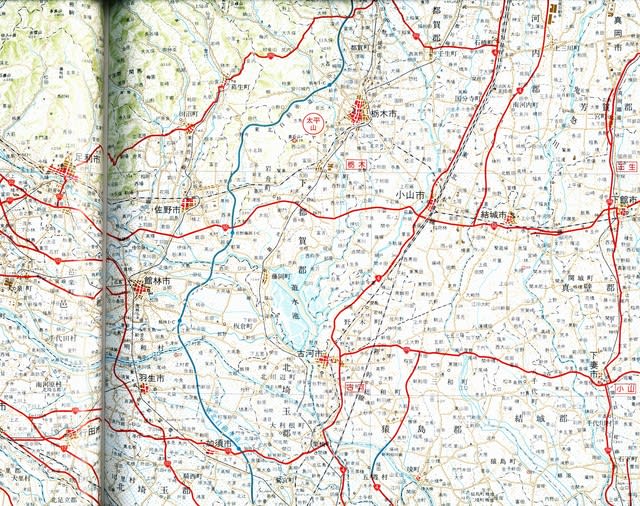「間」抜けの話・・・・・「間」が抜かされるということ 1981年度「筑波通信 №4」
五月の末から六月のはじめ、季節はずれの夕立が数日続いた。それも雷雨である。
そんなある夜、私の研究室に、学生の某君が興奮したおももちで本をかかえてとびこんできた。どうしてもこの本を見てもらいたいというのである。その本とは、帝国書院から出されている世界の地理教科書シリーズのうちのスイスの地理教科書(中学生対象ではないかと思う)であった。もちろん日本語訳である。不勉強でこういう本があるなどということは、ついぞ知らなかった(因みに、このシリーズに続いて、世界各国の歴史教科書シリーズが刊行されつつあることが、六月八日付朝日新聞読書欄に紹介されている)。
たかが教科書ぐらいで、何をそんなに、と思うかも知れない。しかし、それにはそれなりの訳がある。今回は、この教科書をめぐって、この学生と語りあったこと、そしてそのあと考えたことをもとに書いて見ようと思う。
それにしても、こういうように、心のうちになにか言いたいことをいっぱいもって話しにくる、そういうときの人の目の輝きというのが無性に好きだ。近ごろ、そういうきらきら輝くような目を見ることが少なくなったように思う。そういう人が居なくなったのか、こちらの目が曇っているのか。
何故その学生が話をしたくなったか。実物を目のまえにすれば、それは直ちに分ると思うがいまそれができないのが残念である。
ざっと目を通してみて、その学生が何かを言いたくなった気持が、私にもよく分った。私たちが学んだ(学ばされた)日本の地理教科書とは、まるっきり違うからである。常日ごろ望んでいたことが、この中学生あいての教科書に、大げさに言えば物の見事に書かれている(いま同じようなことを大学生に話さなければならないというのが、あほらしくなってくる)。
一言で言ってしまえば、この教科書は、国土について、諸「知識」を単に並べたてたものではなく、国土を(そこに生活してゆくという視点で)どのように「把握」するかという見方で貫かれている、ということに尽きるだろう。(先に書いた目下刊行中の歴史教科書シリーズの紹介で、評者は、各国の教科書は日本のそれと違い、歴史を「羅列でなく構造として呈示しよう」と努めていると書いていたが、その点全く同様である)。
詳しくいえば、スイスという国土を(子どもたちが)どのように把えるか、その把えかたを述べてある。たとえば、〇〇山脈がどこにどう走って、高さがどうで、地質やそのできかたがどうであるかというような、いわば物知りおじさん的「知識」ではなく、もちろんそれについても書いてはあるが、その「知識」だけで終るのではなく(従ってそれを無理して覚えればよいというのではなく)、そういう山脈があるところでは、どのような「自然」が展開し、そのような「自然環境」に在って人々はどのようにして暮さなければならなかったか、暮してきたか、暮しているか、つまりどのように人々の生活が変ってきたか、人々はどのようにその「自然」に対処してきたか、等々といったいわば現存の学問分野でいうところの「歴史地理学」「人文地理学」そして「集落地理学」にかかわる話が、実に分り易く淡々と述べられている。これが、それぞれの特性をもった地域ごとに語られ(特性が存在するからこそ、地方、地域という概念が生まれた、在ったのではなかったか。いま日本で「地方」「地域」というときは、はたして、そういう特性の存在を認めた上で言っているのだろうか)、それにより、スイスという国土とそこでの人々の生活が、実にはっきりと浮き彫りにされるのだ。そこには、何故ある地域がそういう地域となったのか、それを見る見かた把えかたが、それこそ懇切丁寧に書かれており、その一環としてたとえば、ある地域で暮らす人々の一日の、そして一年の生活が、その「地理」との関係で、さしずめ日課表の如くに語られ、もちろんそういう生活との関連で、彼らの家づくりのありかたにも触れられる。だから、これを読んでいると、私の行ったこともなく見たこともないスイスのある地方のありさまが、目のまえにありありと浮んでくる。そして、これが大事なことなのだと思うが、それは決して単にその地域について知ったということではないということだ。そう見てゆくなかで、たとえば我が国のあの地方のありさまは、いったいどうなのであろうか、といった具合に、それとの対比でものを見る私の視野が自ずと拡がってくるのである。つまり、一つのことを見ることが、十のことを見る見かたを示唆しているということである。ここまで書いて、私は私の好きな作家サン・テグジュペリのある文章を、どうしても引用したくなる。少し長いが読んでほしい(下段に引用、中途を省略してある)。
サン・テグジュペリ「城砦」 山崎康一郎訳より
……それゆえ私は、諸学舎の教師たちを呼び集め、つぎのように語ったのだ。「思いちがいをしてはならぬ。おまえたちに民の子供たちを委ねたのは、あとで、彼らの知識の総量を量り知るためではない。彼らの登山の質を楽しむためである。昇床に運ばれて無数の山頂を知り、かくして無数の風景を観察した生徒など、私にはなんの興味もないのだ。なぜなら、第一に、彼は、ただひとつの風景も真に知ってはおらず,また無数の風景といっても、世界の広大無辺のうちにあっては、ごみ粒にすぎないからである。たとえ、ただひとつの山にすぎなくても、そのひとつの山を登撃しておのれの筋骨を鍛え、やがて眼にするべきいっさいの風景を理解する力をそなえた生徒、まちがった教えられかたをしたあの無数の風景を、あの別の生徒より、おまえたちのでっちあげたえせ物識りより、よりよく理解する力を備えた生徒、そういう生徒だけが、私には興味があるのだ。
……私が山と言うとき、私の言葉は、茨で身を切り裂き、断崖を転落し、岩にとりついて汗に濡れ、その花を摘み、そしてついに、絶頂の吹きさらしで息をついたおまえに対してのみ、山を言葉で示し得るのだ。言葉で示すことは把握することではない。
……言葉で指し示すことを教えるよりも、把握することを教える方が、はるかに重要なのだ。ものをつかみとらえる操作のしかたを教える方が重要なのだ。おまえが私に示す人間が、なにを知っていようが、それが私にとってなんの意味があろう? それなら辞書と同様である。
言いかたを変えれば、このスイスの地理教科書では、現象あるいはものごとの「結果」だけではなく、「過程」が語られているということである。この私をたずねてきた学生は、常日ごろ世のなか一般に「結果」だけ問題にされ、「結果」だけをつなげてものが語られ、学問・研究がされ、つまるところ、それに至る「過程」の無視されていることに言いようのない怒りを抱いており、たまたま私も、およそ人のやること、もちろん「結果」も大事だが、その「過程」:私の常用する言いかたで言えば「人間の営為」こそ大事であり、それを見るべきであると日ごろ言い続けていたものだから、私なら怒りをきいてくれるだろうと室をたずねてきたのである。
そうなのである。毎回のように書くのだが、そしてこれからも言い続けると思うが、人が「どうしたか」「どうするか」こそ大事なのである。人のなした現象的結果をあれこれ言うことぐらい易しいことはない。しかしそこからは決して「人がどうしたか」は見えない。逆に人がどうするかが見えたとき、私たちはある一つの地域やあるいはある一つの現象を見ることで「やがて目にするべき一切の風景を理解する」ことができるようになるはずなのだ。もっともサン・テグジュペリなら、この教科書でも未だ不十分だと言うかも知れない。
この教科書は、では、どういうかたちでその記述をしめくくっているかというと、地域ごとにその地域の特性:人々の生活を通観したあとすなおにその国土の将来の(あるべき)姿を、将来の(国土の)「景観」というかたちで書いて終っているのである。我々(スイス人)は将来へ向けて、いま何をなすべきかで終っているのである。
ひととおり目を通して、たずねてきた学生に劣らず私も少なからず興奮し、なぜスイスではこうで、日本ではそうでないのか、少し大げさに言えば夜の白むまで話がはずんだのである。そして話をしてゆくなかで、その学生が頭にきたのには、もう一つ別の理由があることも、だんだん分ってきた。この学生は、実はこの本を地理の先生にその授業で紹介されたのだそうである。そこでこの学生は、先に少し触れたお得意の「過程」重視諭を述べたところ、彼の先生いわく、では書きかたの順序を逆にすれば良いのですかね、と言われたのだそうである。そこで先ず頭にきた。そんな書きかたの形式を言っているのではない、もっと本質的なことなのにというわけだ。そして更に、この先生、こうも言われたというのである。近ごろ建築(を学ぶあるいは研究する人たち)をはじめとして、地理学以外の人たちがどんどん地理学の分野に入りこんでくるものだから、地理学の独自性を保つために(実際こういう表現で言われたのではない。私がその趣旨をかいつまんで述べているにすぎない)地理学はいったい何をしたらよいのか、いろいろと論議がある、と。なるほど、これは私も頭にくる。この学生が頭にきて当然である。頭にこなければうそである。「ね、そうでしょう」と言って、この学生はほっとしたおももちになった。それが印象的であった。もちろん、ここでいう先生とは、大学の先生である。
私は、なぜ日本にはこのような教科書が存在しないのか、考えた。そして、いまからでも、こんな具合の地理教科書をつくることができるだろうかと、しばらく考えた。子どもの教科書もながめてみた。そして、悲しいかな、書けないだろうという結論に達したのである。
なぜか。なぜ在り得ないか。
一つは、日本の現状が、このような具合の書きかたを受けいれないものとなっているからである。なるほどたしかに、ある時代までは、スイスと同じようなかたちで、国土と人々の生活について、つまり、「地理」と「人間の営為」とについて、雄弁に語ることができる。しかし、あるとき突然(ほんとは突然ではなく、下準備は着々となされていたのだが、時間を圧縮して書くと、ほんとにとうとつに見えるはずだ)、それからあと、地域の特性と人々の生活とは無関係となり、国土はそれぞれ特性をもった「土地」としてではなく、単なる「地面」として扱われ、特性もへったくれもなく、従ってどこでも全く軌をーにした生活が行い得るのだ、それがよいことなのだ、というはなしになってしまっている。だからいま(現代に生活するには)、「地理」は不要である。「地理」を学ぶこととその「生活」とは直接的に関係がないように見える。そうなっている。だからスイスの教科書のようには、すなおに淡々として書くことはできないのである。書こうとすればするほど、歴史的な意味での「断絶」と、「地理」を学ぶことと現実に行なわれている「生活」との間に横たわる「断絶」とが、より一層目に見えて明らかになってくるだけだからである。従って、できるのは、いままで慣習的(というより因習的)に行なわれてきたように、それに最新のものを盛りこむだけで、要するに地理学の諸「知識」を系統的にきれいに整理して記述することしかないのである。かわいそうなのは子どもたちだ。彼らは、それらの諸「知識」が、自分たちの「生活」と何の関係があるのか分らずじまいのまま、つまり何のために「地理」を学ぶのか、学ばされるのか分らないままに、ただいたずらに暗記を強いられる。ということは、どういうことか。それは、前々号に書いた私の言いかたで言えば、子どもたちに、「それはそれ、昔は昔、いまはいま」というものの見かたを教えていることに他ならないのである。
しかし、「地理」は、「地理学」は、「地理の教科書」は、その「現実」との不整合に目をつぶってはいけないのだ。そこから逃げてはいけないのだ。「地理学」はいま何をしたらよいか、などというような世迷いごとを言うべきではないのである。まさに、この不整合な事態の不都合についてこそが、「地理学」が言及しなければならないことなのではないのか。それこそが、「地理学」の本務ではなかったのか。「地理学」とはそもそも何であったかということだ。それを忘れて、自らすすんで自分のなわばりを狭めてゆく。それから先はもう決りきっている。「学際的」研究とやらをとなえるだけだ。そして、だがしかし、そうしたからといって決して、先の不整合な事態の不都合については言及できないだろう。言及できないものがいくつ集まったところで言及できるようになるわけがないではないか。私はここに、いまの学問のありようの象徴的な姿を見る。
そして、なぜスイス(別にスイスでなくてもよい)のような書きかたが在り得ないと私が思うか、そのもう一つの理由がここにある。
つまり、このような書きかたのできる人が、「地理学者」「地理の教師」(つまるところ、地理の教科書を書くのは、地理学者か地理の先生である)のなかに、はたしているかということである。もしいるのならば、そんな教科書が一つや二つあってもよいではないか(それとも文部省の規制が強いからなのか?全部の教科書を調べたわけではないから、断言はできないが、必らずしもそういう外圧だけのせいではなさそうだ)。しかし、ありそうにない。ということは、私がその昔習ったことを思いだしてみてもそうだが、もともと「地理」を学ぶということは、我が国土を知るということ=我が国土についての地理学的諸知識を辞書的に積み重ねること、で長いあいだ済んできたのであって、そのことについて(その意味について)何ら考えられてこなかったのではないかと思う。辞書的編集に対し、何ら疑いがはさまれたことがないということである。もちろんそれは、書く側つまり教える側に、何の反省がなかったということであり、教えられる側は、意味不鮮明のまま(現実との不整合のまま)、やみくもに、それこそ字の本義どおりに「勉強」させられたのだ。(商人が勉強しときましよう、というようなときの「勉強」が勉強のもともとの意味であって、それが自らへ問題を課すというような自制的な意をこめた「学ぶ」ということのありかたの意に転じたのではないかと思う。いまそれは、他動的なそして受動的なそれに変ってきた。つまり「学習」がなくなった)。
おそらく、こういう言いかたをしてくると、何も全てが現実(の生活)との係わりをもって語られる必要はないではないか。学問の成果は成果として教えてよいではないか。なぜならそれこそが、いま人間の到達している最先端なのであって、教育とは、その先端を将来更に延ばすことにあるのだ、と。そして(自然)科学・技術(にかかわる分野の教育)は、まさにこういう局面で実践しており、人文科学の分野もこれに追随しようとしているように、私には思えてならない。
しかし私はあえて、これは誤っていると言おうと思う。なぜなら、いまの最先端とは、いかに、どれだけ、「人間として」の立場から遠く離れるかという意味の先端でしかないからである。
学問というものが、進めば進むほど鋭角化し、知識自体もより細部にわたるようになることはそれは当然である。しかし、そうなるまでの過程が忘れ去られ、ただ目前の状況から前へのみその意味さえ忘れて進むということ、そして、それを最先端だと思ってしまって平気でいられるということに対して、私は疑いをさしはさみたい。過程を忘れるということは、人間としての立場から、どんどん遠くなってゆくことに他ならないのである。
そしてまた、なぜなら、こういう人間としての立場からほど遠くなった、あるいは失なったものの見かたが平気で教えられる一方で、かならず、他人へのいたわりのこころ、だとか、自然を愛するこころだとか、はたまた「道徳」だとかが、これまた平然と教えられるのが常だからである。考えてもみたまえ、こんな論理的に矛盾するはなしはないではないか。いったい、どうやったら人間としての立場を失なったものの見かたに、人間的なるものが接ぎたすことができるのだろうか。私たちは、先ずもって人間なのだ。これは疑いようのない事実である。いや、事実以前のはなしである。だから、「人間的な」とか「人間として」とかいうことを、さしづめ形容詞の如くに、あとから追加しあるいは付加すればこと足りるとするようなやりかたは私には我慢がならないのである。それは、ごまかしであり、確実に誤まっている。
言葉を変えて言えば、いかなる最先端であろうとも、それは、人間のなしてきた営為の一環としてあるのだという認識をもつ必要があるということである。そして私たちは、常にそれを問う必要がある。私が、現実との、あるいは、いまとの係りを問うのも、その為だ。そしてそれは、なにも私が、現実と係わりをもたざるを得ない建築という仕事をしているから言うのではない。それは、本質的なことだからである。
ふり返って、もしかなり昔から、この「地理」の教育において、指折り数えて知識を積めこむのではなく、「地理」を把える教育が行なわれていたとしたならば、短絡的にすぎるかも知れないが、我が国の現在のような状況、つまり、先に記したような「地理」がもはや「生活」とは無縁な状態だとか、「それはそれ、昔は昔、いまはいま」というが如き対しかた、にはなっていなかったのではないかと、私は思う。なぜなら単に学校の成績のためとしてでなく(従って、学校を出ればきれいさっぱりと忘れてしまうのではなく)生活上の「常識」となっていたならば、すなわち極く自然にその「把えかた」でものが見れるようになっていたならば、現在のような状況にいたる以前に、だれでもが極めて正当な批判力を行使したと思うからである。然るに、ばらばらの知識を教えることによって、その知識ではなく、ものごとをばらばらにしてみる見かたを教えてしまったのだ。この修復は大変である。
いま、全ての領域にわたって、こういう傾向が見られる。ものごとを、数えあげられるようなかたちに分解し、そうして得た知識を数えあげることによって、ものごとが分った気になってしまう。そこでは人間が喪失する。なぜなら数えあげることができるような事項をいくつかとりだすという操作を施すとき、実は、そのとりだし残されたところにこそ、人間の真実があるからだ。事項と事項の「間」にこそ人間のほんとうの姿がある。
なるほど、一歩ゆずって、ものごとをしゃべるときには、いくつかの事項を軸にしゃべるしかないのは認めるとしよう。しかしそれは、あくまでも「何かをしゃべるために」見出した事項にすぎないのであって、決してものごとがそれらの事項によって成りたっているというわけではないのである。それを多くの場合とりちがえるのだ。問題なのは「何をしゃべろうとしたか」つまり「何を見たか」なのだ。全く同様に何故それらの事項で見るようなくせになっているかをも省りみずに、はじめから当然のことのようにそれら事項が在るものとして、それによりものごとを見て平然としているのも誤まりである。それは、前に書いた、星を見るに、星を見ずに星座を見る見かたに他ならないからだ。
こうしてみてくると、いまの世のなか、ものの見かた、把えかたが基幹であるというあたりまえなことが、いかに忘れ去られているかが、空恐ろしいほど浮きあがってくる。言うなれば「間」の抜けた、あるいは抜かれた、デジタル思考が横行しているのである。事項を指折り数え(デジタルの原義)その量でものごとが分るというのならば、サン・テグジュペリではないが、辞書でたくさんである。
そして、それ以上に。教育(小学校から大学まで)の現状の空恐ろしさもまた、目に見えたかたちで見えてくる。
いま教育は、そのどのステージにおいても、その場限りでは「知識」豊富な、あるいは、ある限られた範囲についてのみ「知織」豊富な、けれどもそうであるが故に、「間」抜けな(見かたしかできない)人間?をせっせと養成しているのではなかろうか。いまさかんに教科書問題が世上をにぎわしている。しかしそれは、どう見ても、そこに盛られる「知識」の質とその相対的な量の多少だけで論じられていて、もっと重要な。「問」抜け人間入門書になっていることについては、全くと言ってよいほど何も指摘されていないのが、私は残念でならない。意地悪く勘ぐるならば、敵は、世のなかの構造的な不整合が目に見えたかたちで見えてきて、それにつれて、ものごとを構造的に把えようとする人たちも増えてきた、そのくらい(彼らにとって)不都合なことはないから、教科書に盛りこみ羅列する事項の議論へ話をずらしこみ、ものの構造的な把えかたから焦点をずらさせようとしているのではないかとさえ思いたくなる。そしてまた、残念ながら、この構造的に把えようとすることについては、敵も味方も同様に欠けているのは。先に見た通りである。
先日のこと、東大入学率の高さで有名な某国立大学付属高校の先生と話す機会があった。かねてから疑問であったことを、私は尋ねてみた。彼らは東大で何を学ぼうとしているのか、何をしようとして東大を選ぶのか、と。ところが、彼らは特に何かをしてみたい、というような関心というものがないというのが特徴なのだ(全部がそうだというわけではないが、ほとんどそうだ)というこたえが返ってきた。彼らが理科系や文科系を選ぶのは、全く単に自分の「点」によるのだそうである。私は、ある程度は予想はしていたものの、驚くというよりあきれてものが言えなかった。これは更に言えば恐ろしいことなのだ。このデジタル思考に秀でた「間」抜け人間たちは、いずれの日にか、その多くが役人として行政その他に絶大な権力をもつべく予定されているのである。とんでもない再生産が、むしろ悪循環が、堂々と行なわれているわけである。
そして、私たちは、その抜かされた「間」に止むを得ず放り出され、不特定多数として十把一からげにして、まとめて数えあげられる対象にされてしまうのだ。彼らには、私たちがあまりにも多種多様、十人十色であるために、そのデジタル能力からはみだしてしまい、そのままでは数えられないからである。
いま私は、止むを得ずり放り出され、と書いた。しかしそれは、彼らの視点からみてのはなしであって、私たちにとっては、それはあたりまえだ。止むを得ずどころか、十把一からげにされることの方こそが、私たちの望まざる姿なのだ。止むを得ず、そうされて黙ってきた。なぜなら指折り数えることのできない世界にいる私たちにとって、指折り数えるやりかたには、指折り数えられることを、それのみを、善とするやりかたには、一見したところ、打つ手がないからである。指折り数えられるものしか分らない、分ろうとしない、そういう人に、どうしたら指折り数えることのできないものごと:「間」を分らせたらよいのだろうか。はたして「間」抜けの人に「間」を分らせることができるのだろうか。
しかし私たちは、ついうっかりと、彼らに抵抗しようとして、数えあげることのできないものを、数えあげてみようなどという気をおこして、彼らの土俵にひきこまれて失敗をくりかえす。私たちのなかのどこかに、未だに。「数」に対しての絶大なる信仰が巣くっているからだろうと思う。そして、よく考えてみると、そのような信仰がはじめから私たちのなかに在ったのではなく、それらはあとから私たちのなかに植えつけられたことに気がつくはずだ。何が、だれが、それを植えつけたのか。その一つが、そしてその最たるものが教育、特に初等教育であることは、隠れもない事実である。
余談だが、このごろの小学生たち特に高学年の子どもたちは、大概腕時計をもっている。そしてその大半以上がデジタル表示である。その方が先進的でかっこよく、ナウいのだそうである(もっとも、これは小学生だけでなく大学生でもそうらしいが)。心配性の私は、また心配したくなる。先きゆき、「時」に対する見かたが、変ってしまうのではないか。永遠の時の流れ:時間、という発想はなくなって、時間とは時刻の集積であるという発想が先にくるようになるのではなかろうか(いまも、既に、そのような気配が感じられるが)。そもそも、私たちにとって、時の流れという感覚があった。いまと、一瞬まえと、一瞬あとと、そしてそのまえ、うしろと延々と、決して断続的でなく連続的に、絶えることなく続く流れの感覚があった。そしてそれを、それをなぞらえるものとして、針の回転運動(による時計)が考案された。砂や水の流れに、それをなぞらえた。それは、私たちの感じている時の流れそのものではないが、それをなぞらえたものである。そういう意味で、こういう表示のしかたを、デジタル表示に対して、アナログ(なぞらえる)表示というのである。なぞらえるやりかたのとき、時刻というのは、あくまでも便宜的なものなのであった。時刻が先に存在したのではない。時の流れ(の感覚)が先ず存在した。時刻は、あくまでも、人々の便宜のために設定されたのだ。このことが忘れられて、私たちにとっての時間というものが、この便宜的に(勝手に)設定された時刻によって左右されるというような。全くの逆転現象があたりまえのことになってしまうのではないかというのが、私の心配である。それは、ますます「それはそれ、‥‥」的思考に拍車をかけることになるだろうと思われるからである。ますます「間」抜けになると思われるからである。
私が今回、地理の教科書の話からはじめたのは、別段「地理」に対して他意があったからではもちろんない。私たちのものの見かたが、私たちをとりかこむものごとが、あるいはそれらのつくられかた、ものの言われかた全てが「間」抜けな状況になっていること、そしてそれに気づいていないこと、気がつかなくてあたりまえになっていること、更にそれを押し進めようとしていること、それらの空恐ろしさを言いたかったからにすぎない。ものごとを指折り数えるその指のすきまから、だれかがつくった枠組によってものごとを見るその枠組から、私たちのほんとの姿がみなこぼれおち、捨てられる。その空恐ろしさを、どうしても言いたかったからなのだ。そして、なんとかしなければ、というあせりに似た気持になるからだ。
でも、どうしたらよいのだ。いったいどうしたら「間」抜けを「聞」抜けでなくすることができるだろう。
それとも、こんなことを思うのは、全くばかげているのであって、「現実」に逆らわずに、すなおに世の大勢に従うのが、りこうというものなのかも知れない。
しかし、たとえ「現実」に逆らうことになったとしても、「私」自身には逆らいたくない、そのような「現実」に、人の心を逆なでしてもらいたくない、ということに、結局は行きついてしまう。きざっぽく言えば、人間を、人間の営為を、ばかにしてもらいたくないからだ。
でも、どうしたらよいのか。 どうしたら「間」抜けでなく、私たちは在り得るか。 どうしたら、「間」を抜かされて扱われてしまい、捨てられることに抵抗できるか。
どうしたら、「間」に生きる私たちの、十把-からげにできない、十人十色、多種多様の私たち個々の、その存在を、「間」抜けな人たちに分らすことができるのか。
「返信」のなかから‥‥「あとがき」にかえて
〇この「通信」に対して、たくさんの返信をいただいている。「通信」のなかみそのものに対する感想、それに関係しての所感、近況報告を混えたもの、いろいろである。
そのなかで不思議に思ったことがある。私の室をたずねて話をしてゆく学生諸君は、今回の通信の例のように、過去にも多少あった。その人たちが卒業し、この通信を介してのみ話を交わすことになった。そうしてみて、どうも、こういう通信を介してのやりとりの方が、面と向って話をしているときよりも、いわば奥行のある話ができているということに気づいたのだ。
そんなことを思っているとき、ある文章に出会った。「小さな家でぼくが不便を感じるのは、むずかしいことばでむずかしい思想を議論しはじめると、相手と十分な距離がとれなくなるときだ。ぼくらの考えがちゃんと港へ着くには航海の準備をし、一度や二度走ってみるだけの余裕が必要なのだ。思想という弾丸は、聞くものの耳にとどく前に上下左右のゆれに打ち勝ち、最終的な安定した弾道に落ちつかなければならない。さもないと、それは相手の頭からこぼれおちてしまう‥‥。‥‥もしぼくらがそれぞれの内部にあって話すことのできないもの、あるいはそれを越えたなにかと深みのある交わりをしようとするならば、ぼくらは沈黙をまもるだけでなく、‥‥お互いの声が聞こえないほど肉体的にも離れていなければならないのだ。‥‥」
〇そんな返信のなかに次のようなのがあった。 「‥‥年年歳歳花相似タリ、歳歳年年人同ジカラズ。(という詩があるが)私はそう(ことばどおりには)思わない。人もまた花と同じではないだろうか。同じように見える花にも‥‥それぞれの個性があり美しさがある。花は一時咲きほこり、先を急ぐように散ってゆく。そして次の年になれば、また同じような、でも一本一本がそれぞれに異なった唯一の花を咲かせる。人もまた、大地の流れから、命の流れから見るならば、一時の間花開き次々に移りかわってゆく。どれ一つとして同じものはない。それは、花とどれだけのちがいがあるというのだろう」という趣旨のものであった。
私は一瞬たじろいだ。それまで私は、たしかにこの句は知ってはいても、単に、人の世の無常を表わす常識的「成句」として扱い済ましていたからだ(つまり、「星座」で見ていたのである)。たしかに、この人のいう通りである。おそらくこれは、多少まだ観念的な気配も見えるけれども、自分がどう生きるべきか考えぬいたその延長上の解釈なのではないかと思う。私にも「星」があらためて見えてきた。そして、次の展開として。こんな詩を思いだした。「‥‥‥どのものも一度在る。一度だけでそれ以上ではない。そしてわれらもまた/一度だけ存在する。二度とない、しかし/たとえ一度だけだが一度存在したこと、/地上に存在したこと、これはかけ換えの無いことらしい。/‥‥‥旅びとが高い山の絶壁から谷間へと持ち帰るのは/だれにも言葉で確かにつかめぬような一握の土ではなく/それはむしろ、確かに獲得した純粋な一語--すなわち黄色や青のりんどうだ。たぶんわれらは、言うためにここに存在しているー一一/家・橋・泉・門・甕・果樹・窓一一一/せいぜいまた一一円柱・塔‥‥と言うために。しかし理解せよ、それは/物たち自身さえも内心に、そういうもので在るとは思いもかけなかったような風に言うためだ。‥‥‥・‥」 この返信の主のような人生観を、もしこの年年歳歳‥の作者がもっていて(多分もっていたと思うが)なおかつこういう「表現」をしたのであるとするとき、この詩の意味が、また一つ深いものになるなあ、私はそう思った。 いずれにしろこういう奥行のある「交流」は机をはさんでの対話では、たしかになかなか生まれないように思う。
〇次のような返信もいただいた。 「障害児や障害児の親のため、援助して下さる方がたくさんいます。その人たちは、逃げられるけれど逃げない状態でいるときは、不安定ですけれど、楽しそうに気分よく手伝ってくれます。けれど、本職になったり、押しつけられたりして、逃げられない状態に追い込まれると、とてもつらそうになり、疲れるようなのです。はじめから逃げられない親にしては、何とも複雑な気持です。時には淋しくなります。そうしたことが見えた時に。
親はまだ一部分逃げられるし、逃げられていた時代もあったのだけれど、本人ははじめから終わりまで逃げれないのだからと思いなおすのですけれど。‥‥」 私は先回、態度としての「逃げる」「逃げない」ということを、そのはじめの所で書いた。しかし、書いていま一つふっきれないものがあった。そこのところを、この返信は、もののみごとに掘りあててくれてしまった。 要は、いま何をするか、しているか、なのではないだろうか(常に苦い思いをかみしめつつ)。
〇返信の一部を勝手に引用したことを。お許しください。 〇今回から字の大きさを変え、レイアウトも変えました。省資源のためです! 〇それぞれなりのご活躍を祈ります。
1981年7月1日 下山 眞司