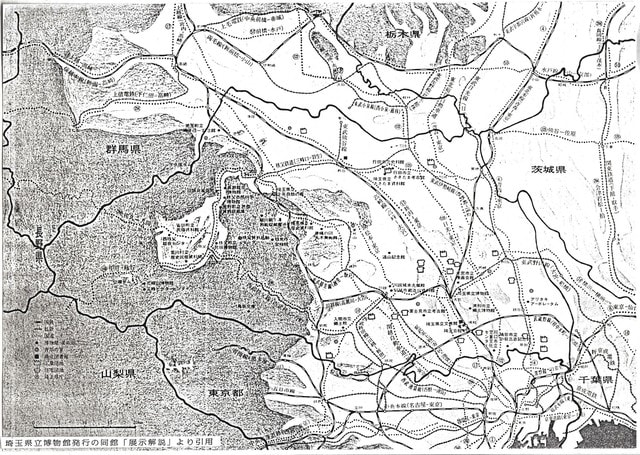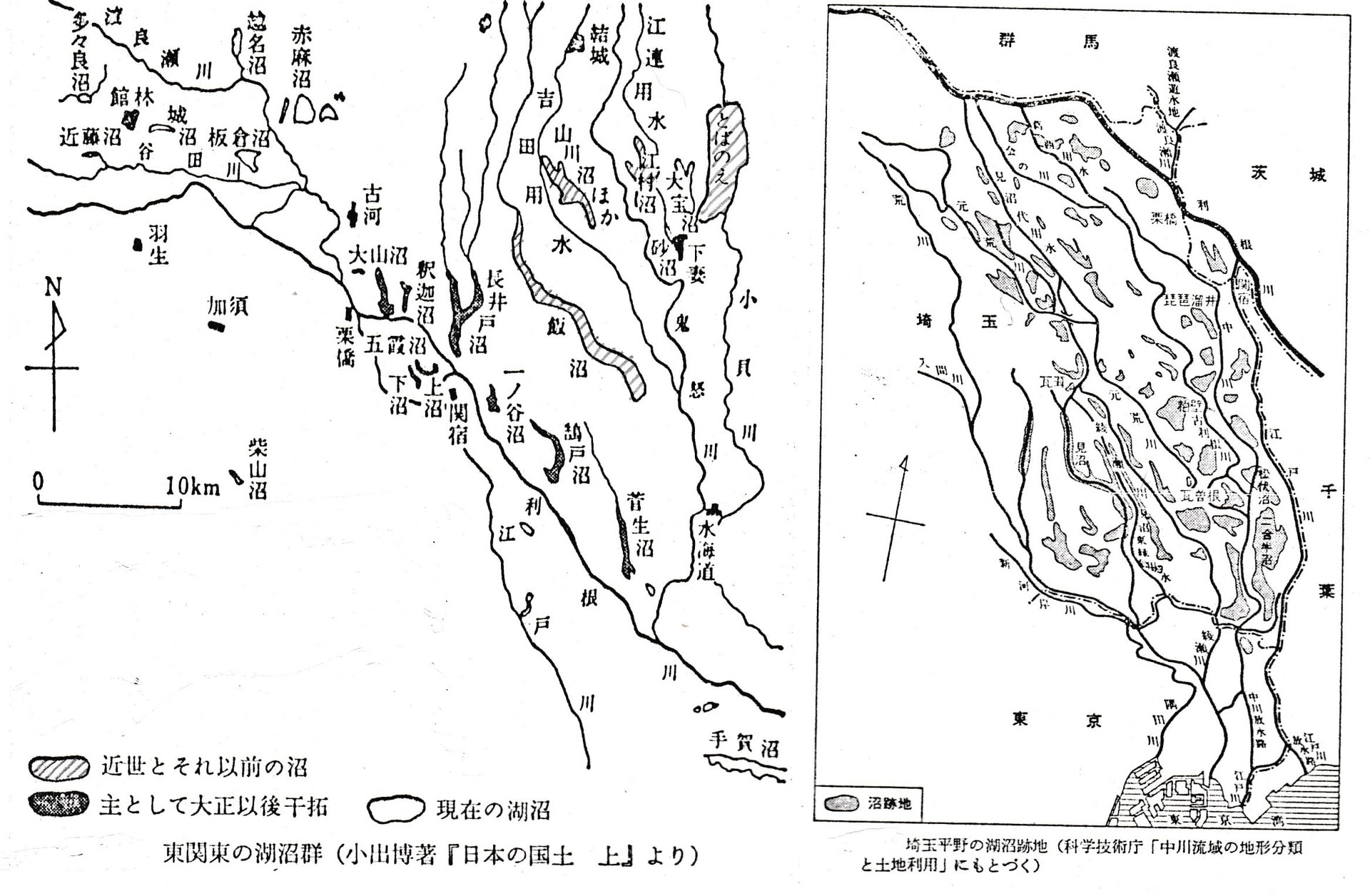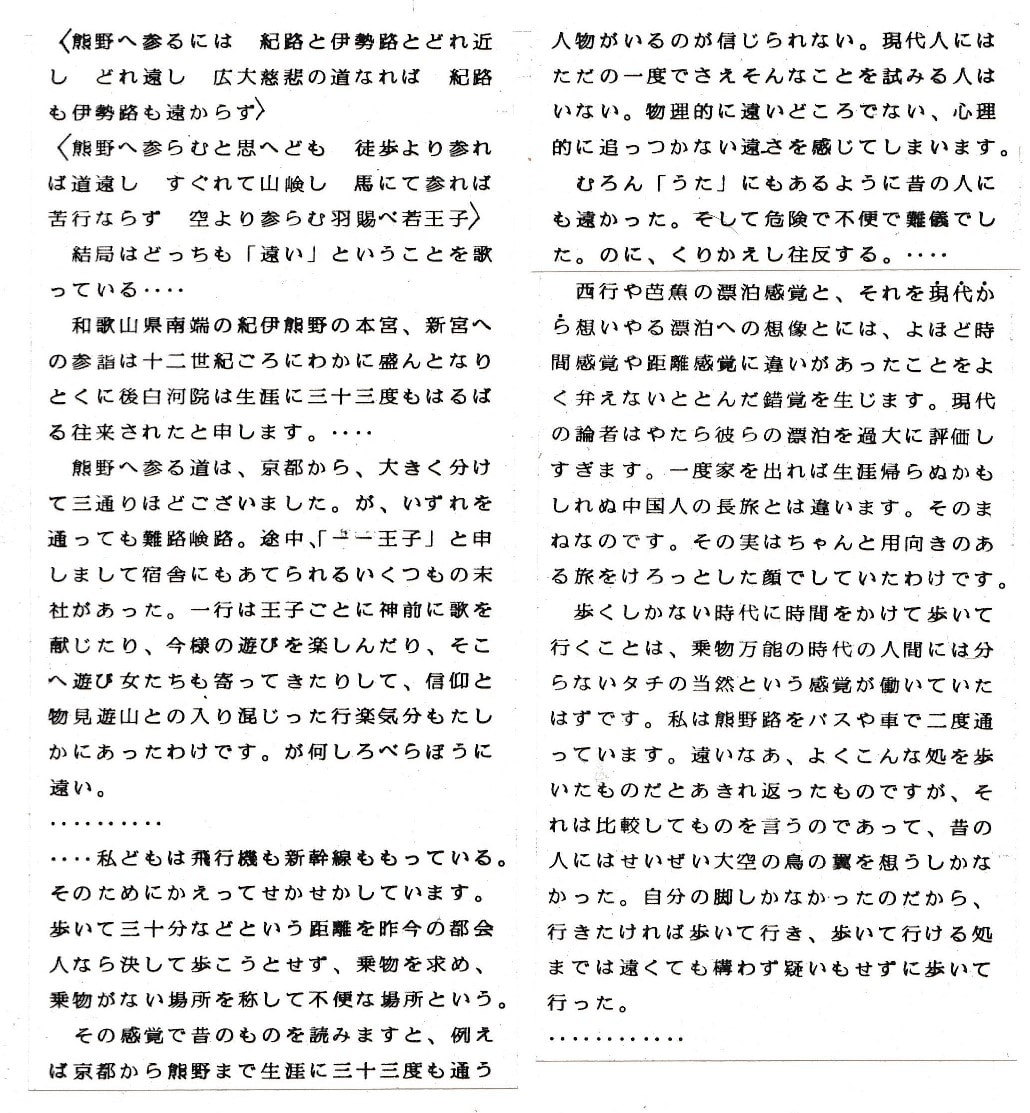復刻・「筑波通信」―15・・・・建物は雨露さえしのげればよい? 筑波通信1983年3月刊の復刻
二年ほど前であったか、上州の山あいを、気の向くままに車で巡り訪ねたことがあった。
夏の終りの暑い日の昼下がりではなかったかと思う。空が都会の空と違って、抜けるように晴れあがっていたのを覚えている。
一休みしようかと思っていたところ、谷あいの小さな村、というより集落にさしかかった。私は小さな谷川沿いに下ってきたのだが、そこで、別の道が同じように小さな川に沿って下ってきて合わさっている。一般に「落合」と通称される所である。
前方に、見るからに村の社が在ると分るこんもりと繁った木々が見え、それに隣り合って、これも見るからに小学校だと分る木造の昔懐かしい形の小さな建物が在り、校庭はいい具合に木陰となって涼しそうだ。校庭には大人が数人いるだけで子どもの姿は見えない。きょうは日曜だったな、そう思いながら、あそこで一休みさせてもらおうと決め、車を乗りつけた。学校は家並みよりほんの少し高みに在り、別天地のように涼風がそよぎわたっていた。校庭の大人たちはゲートボールに興じていたのである。後者の沓脱石に腰を下ろし一息入れ、あたりを見回すと、光景は明らかに私の見知った學校そのものなのに、何となく學校らしくいないにおいがある。そこであらためて門柱の表札をみると〇〇縫製工場とある。しかし、その表札の下には、「〇〇小学校」という表札が隠れていた。おそらく、近くに鉄筋コンクリート造の建物に建替えられ、その跡地利用で工場が間借りしているのだろう。村の女性たちが子どもに代ってここへ通い多分自分たちは着ないであろう服などをしたてているのである。都会でもてはやされるいわゆるブランド品の多くは、このような地方の小さな工場で生産されるものが多いのだそうである。
そこが私の予想に反し学校ではなく工場であったことは、私の中にかなり強い違和感とでも言うべきものを湧きおこらせた。その理由の一つは、私が前方に認めた「建物の形」が、見るからに「学校らしい形」をしていたからだ。
私たちは、町中を歩いていたり、車窓から外の景色を眺めているようなとき、ある建物が目に入ると、大体その用途、建物種類を推定できているように思える。
これは、おそらく建築に係わる職業の人特有の「習性」ではなく、普通の人たちも同じように、ある用途に対して「それらしい形」を思い浮かべるのではなかろうか。最近は見かけなくなったが、新築の建物の紹介する新聞記事などで「ホテルのような〇〇」という形容句が使われることがよくあった。その根には「建物で豪華なのはホテルである」という〈認識〉と、「その種の建物は本来かくかくしかじかのものだ」という〈認識〉(しかし目の前にしている建物はその〈認識〉にあてはまらない)が在るからと見なしてよいだろう。私自体が係わった建物についても、単に「學校らしくない」というのではなく、「鶏小屋のような」とか「工場のような」とか形容されたことがある。おそらくその場合は、そこでなされている教育が質が一定のブロイラーや画一的製品が大量生産されているという皮肉が込められているわけではなく、全く単純に日ごろ見慣れている鶏小屋や工場みたいだという意味に過ぎないだろう。
私たちは、自らの経験を通してだと思うが、学校だとか工場というものについて一定の《知見》を持っているから、そういった「言葉」を目にしたり耳にするだけで、自分が知っている学校や工場の姿を思い浮かべることができるのだ。
しかし、そのとき頭の中に思い浮かべているのは、単に、「學校、工場・・・といった建物の形」だけなのだろうか?
しばし考え直してみると、こういった「ことば」で私たちが頭に思い浮かべているのは、その「建物そのものだけ」ではなく、「その建物を含めたある場景」であることに気が付く。
すなわち、私たちは、「學校」「工場」・・という「ことば」で、私たちが、「それぞれの体験・経験で獲得したある場景の中の學校や工場を思い描いている」のである。
この「場景」は、必ずしもある具体的な特定のそれではない。むしろ、その「ことば」によって頭のなかに浮んでくるいろいろな個々の場面の場景を越えた、それらを統べるそのことばに最も相応しいと思われる場景を描いているのである。その意味では、「場景」よりも「情景」と表記する方が適切なのかもしれない。
私たちは、日常、多種多様な場面に遭遇しているが、私たちはそれらの場面の場景を、便宜的に括り分け、そのそれぞれにある名前を付ける。その一つが「學校」や「工場」ということばなのだ。逆に言えば、「個々の例を統べる場景:情景」として記したことは、「學校」とか「工場」ということばに、(私が)託している「概念」の姿だと言ってよいだろう。
つまり、ある建物を工場である、とか学校であるとする私たちの判別は、建物の形自体によることもないわけではないが、むしろ、その建物が在るその背景をも含んだ光景:先の言葉で言えば場景:情景そのものによることがより大きいのではないかと思われる。
しかし、この場景:情景というのは、建物のように物として固定し得るものではないから、便宜上言葉として置き換えることが容易な物:建物が前面にしゃしゃりでてくるのであり、更には、その物に対応していることばに、その係わる場景:情景も付託されていたのだ、ということが忘れ去られるのである。そしてその結果、このように、「私たちは固定できるものだけを見ている」、あるいは、「ことばというものは、ある物的に固定できる対象のみに対応している」かのような誤解を抱いてしまうのである。
要するに、私たちは、工場、学校という判別を、「場景」をもって察している、ということだ。
私たちが工場、学校という「ことば」で知っているもの、それはすなわち経験を通じて身に着けた「知見」に」ほかならないが、それぞれの用途の建物(それは、それぞれの建物での人びとの「生活」に他ならないのだが)の持つ特有の場景:情景なのである。もっとくだいて言えば、私たちは、たちどころに「それなりの雰囲気」を察知しているのである。
ひと昔前なら、木造の平屋建ての長屋状の建物は、学校、工場、病院、兵舎・・・など、いろいろな用途の建物として見られたものである。その用途の判断は、その建物のあたりに漂う雰囲気によっていたと言えるだろう。
今はどうだろうか?駅前によく見かける鉄筋コンクリートのビジネスホテルと町なかの会社の独身寮、だいたい外形はよく似ている。しかし、駅前のビジネスホテルを独身寮と見ることはほとんどないだろう。私たちは「場違い」だと思うからである。それぞれがあるべき:それぞれにふさわしい「場」を《知っている》からである。すなわち、私たちは、建物の姿・恰好:つくりを見て、そういう建物において展開し得る生活(の場面)を知っているからである。
つまり、私たちは私たちの生活の「場面」を一定程度《知っている》ものだから、ある建物を見ると、たちどころに《その場であり得る場面》を思い描いてみることができるのだ。
しかし、当然であるが、この《ある場面》は、決してその「場面」を厳密に規定・限定しているわけではない。
以上のことをまとめると以下のようになる。
私の前方に「ある形をした建物」が見えてきた。すると私は、先ず、そういう形をした建物において展開し得るとそのとき思った《生活の全て》を頭の中に描いてみる。次いで、そこの「場景」全体を勘案して、先ほど描いた《全て》の中から、そこで「あり得る(妥当と思える〉」「生活」を選び出す。そして、あれは〇〇か〇〇だ、あるいは〇〇のような用途の建物だという《判断》を下すのである。もちろん、通常は、こういう判断を、こんな手順を意識的に踏んで下すわけではなく、瞬時にやってしまう。そしてまた、この「あり得る」との「判断」は、誰かに教えられたものではなく(教えられるようなものではなく)、私たちそれぞれの「経験・体験」によって私たち自身が会得したものだ、と言えるだろう。すなわち、その根本的な判断は、私たちそれぞれの「感性」の所業なのである。
現代では、このような「言いかた」は、きわめて個人的な主観的な判断で客観性に欠けるとして、ひんしゅくをかうのがあたりまえだ。しかし、この《指摘》は、誤りである、と私は思う。
私には、現代というのは、私たち自らの感性に自信を持たなくなった時代、私たち自身の「経験」をもないがしろにしたがる時代のように思える。
私たちはそれぞれの毎日の生活を《だてに》送っているわけではない。私たちの日常(の「経験・体験」)は、私たちそれぞれの「感性」に拠っているのである。
筑波に暮すようになってから、いわゆる田舎の「風景」に、より強く魅かれるようになった気がする。
もちろん、ここでいう「風景」は、絵に描いてきれいな風景、というような意味ではない。それは、先に書いた「場景」という言葉の方が適切なのかもしれない。おそらく、私が忘れかけていたいろいろなことをあらためて考えさせてくれるきっかけを私に与えてくれたこと、それが私を強く惹きつけたのだと思う。
そして、あらためて思う。都会や新興の開発地で見かける建物には、どうしてああも多種多様な形があるのだろうか、と。
住居ひとつ例にしても、まずことごとく《異なった形》をしていると言ってよい。それは個人の住居に限らない。研究学園都市の公務員住宅にも、数えきれないほどの型があり、当然それに応じて一個の間取りも変ってくるのだが、なぜそうなるのか、その「必然性」は、私には皆目わからない。更に最近では、勾配屋根にして瓦を載せ、凸凹を設け、あるいはジグザグギクシャクさせる、といったようなつくりも増えてきた。その結果、形はますます多種多様にして複雑・怪奇になる。これは、「それまでの、画一的なつくりかたへの反省の上に立ち、形や建物周辺にできる場所の単調さをなくし、一戸一戸に個性とプライバシーを与え、コミュニティを形成させやすくし、人間味のある居住環境をつくりだすべく、地域の伝統をも踏まえ考えだされた」のだそうで、いまや全国的に流行りつつある。そこで私たちの目に入ってくるものは、あたかも私たちの目を傷つけんばかりに次ぎ次ぎに飛び込んでくる建物の角々。互いに競って見えたがるそれらの複雑・怪奇な形をした物たちは、私たちのなかに、いかんともしがたい「苛立たしさ」だけを積み上げてくれる。そして、そういう場景が尽きることなく単調に、延々と続くのである。その意味では、意図に反し《画一的》なのである。
これは、「個性」とか「人間味」とか言う以前の問題なのだ。こういう場景は、私にとっては、決して人の住む場景ではないし、決して住まいの場所として選ぶことないだろう。
これは、当時の状況について記している。現在も大差なく、あるいはさらに劣化しているのではないだろうか。
このような場景には何がふさわしいか考えてみたが、遊園地のビックリハウスぐらいしか思い浮かばない。だが、こういう場景が、今の世は、あたりまえになっていて、大都会周辺だけではなく、全国的にひろまっているようだ。学園都市のまわりにも、多く目にするようになった。
一方、学園都市のまわりに目を向ければ、そこには、大きく変わりつつはあるが、相変らず昔ながらの村々の佇まいが現存する。ゆえに、そこに立てば、はからずも、《新しいもの》と《旧いもの》を対比しながら眺めることができるのである。
これらの《近代的・先進的な》建物群を見ていて、いつも思う。あの住宅群は、たしかに住宅以外の何ものでもないが、どれも住宅でしかないな、しかも、ある極めて限定されたパターンでしか対応できないな、ことによると一代限りだな、と。つまり、そこで目にする場景には、私にいろいろな生活の場面を思い起こさせるようなところが何もない、ある場面だけ、それしかないのである。そこに物的に設定されてしまっている場景は、ある限定された生活の場面にしか対応できないのである。逆に言えば、ある限定した生活の場面を、物的に固定している、ということに他ならない。あの住宅群のなかに入って感じる《苛立たしさ》は、多分、第三者の手に拠り設定されてしまった生活の場面に自らを嵌め込まなければならない息苦しさからくるものなのだろう。第三者の意のままに(己の意のままにではなく)動かないと、十全にそこでは暮せないのである。もちろん、そこに住み着けば《慣れる》ことはあるだろう。しかしそれは、場景に応じた判断によるのではなく、いろいろな苦き経験の結果身についてしまった、いわば、「条件反射的行動」に過ぎない。しかし、これは、たとえば、《よい図書館の建物では、すぐれた図書館活動が為されている》かの「錯覚」を起こさせ、更には「よい図書館活動は、よい図書館(の建物)がないと為されない」という「誤解」をも生じさせてしまう。「専用の建物」がなくても、「活動」は行えるのだ。
さて、学園都市のまわりを取り囲む旧くから在る村々の方を見てみよう。
その光景は、今見てきたあの近代的な建物群が織りなすにぎやかなそれに比べて、ため息が出るほど、静かで単純だ。同じような屋根、同じような形の建物、同じような杜・・・。ある意味では、《画一的》だ、と言ってもよいだろう。そのなかで、際立って形の違いを見せているのは、学園都市建設で土地を売ったとおもわれる新興成金の家ぐらい。これは、(復刻・「筑波通信」―10「十人十色:人それぞれ」 とはどういうことか」)で触れた蔵の目立つ村のそれとは異なる。そこでは、単なる《形の主張》は見られなかった。そこでの《形》は、いろいろな生活の場面の可能性を想起させてくれる「示唆」に富んでいる。つまり、そこに在り得る(在って然るべき)生活の場面を「ああだ、こうだ」と規定するようなところがない。近代的な建物の多くがそうであるように、用意された器に適合した生活:誰かの手に拠る《期待される生活像》に我と我が身をあてはめる必要はない。
それでは、その用途、すなわちその使い分けは、何に拠っていたのだろうか?明らかにそれは、その建物の在る場景に拠っていたのである。その置かれる場景により、そこで在り得る生活の場面が異なることを、人びとは知っていたのである。それ故逆に、ある生活の場面のために、ある場所を選び、建物は同じ形でよしとしていたのである。彼らは、場違いということを知っていた。彼らは、杜のわきの元小学校を工場として使おうなどとは思わなかったに違いない。既存の場景のなかに、自分が求めている生活の場面が展開し得る場景が見出せなければ、そのときは、既存の場景に手を加え、それに相応しい新たな場景にしてしまうことさえ厭わなかった。「屋敷」の造成などは、そのよい例と言えるだろう。しかしそのとき、そこに建つ家は、まわりにあるのと変らない《同じ形》をしているのである。
しかし、この事実を《誤解する》と、「建物は、雨露さえしのげればよい」ではないか、という「言いかた」に行き着くのではなかろうか。
この「言いかた」を更につめれば、「・・・だから、建物など、どうでもいいんだ」という「言いかた」に行きつくだろう。この言いかたの行き着く先こそ、「建物は、雨露さえしのげればよい」という「言いかた」なのではあるまいか。
「方丈記」に「人の一生にとって『仮の住まい』」に過ぎない「家」に、気を遣って何になる・・・との一文がある。彼は、組み立て式の仮小屋をつくり、好みの場所に据えて住み家とした、とのこと。彼にとっては、「場所の選択」が重要だったらしい。
しかし、私たちは、学校だとか病院だとか・・・、ある一定の用途のための建物をつくろうとする。
では、「ある用途のための建物をつくる」というのはどういうことなのか?用の様態に応じて形を整えるということだろうか?
いわゆる建築計画学では、そのために、はじめに、「そこで行われる生活様態を設定すること」が必要と考えられた。
すなわち、先ず《期待される生活像》の設定が肝要と見なされたのである。暮しかた・使いかたの《設定・限定》に他ならない。
しかし、私たちは、必ずしも、黙ってそれに従ってはいない。私たちは、人であり続ける。
私たちに先ず必要なのは、私たちの「ごく自然な日常の振舞いのありようを再認識してみること」ではないだろうか。
二年ほど前であったか、上州の山あいを、気の向くままに車で巡り訪ねたことがあった。
夏の終りの暑い日の昼下がりではなかったかと思う。空が都会の空と違って、抜けるように晴れあがっていたのを覚えている。
一休みしようかと思っていたところ、谷あいの小さな村、というより集落にさしかかった。私は小さな谷川沿いに下ってきたのだが、そこで、別の道が同じように小さな川に沿って下ってきて合わさっている。一般に「落合」と通称される所である。
前方に、見るからに村の社が在ると分るこんもりと繁った木々が見え、それに隣り合って、これも見るからに小学校だと分る木造の昔懐かしい形の小さな建物が在り、校庭はいい具合に木陰となって涼しそうだ。校庭には大人が数人いるだけで子どもの姿は見えない。きょうは日曜だったな、そう思いながら、あそこで一休みさせてもらおうと決め、車を乗りつけた。学校は家並みよりほんの少し高みに在り、別天地のように涼風がそよぎわたっていた。校庭の大人たちはゲートボールに興じていたのである。後者の沓脱石に腰を下ろし一息入れ、あたりを見回すと、光景は明らかに私の見知った學校そのものなのに、何となく學校らしくいないにおいがある。そこであらためて門柱の表札をみると〇〇縫製工場とある。しかし、その表札の下には、「〇〇小学校」という表札が隠れていた。おそらく、近くに鉄筋コンクリート造の建物に建替えられ、その跡地利用で工場が間借りしているのだろう。村の女性たちが子どもに代ってここへ通い多分自分たちは着ないであろう服などをしたてているのである。都会でもてはやされるいわゆるブランド品の多くは、このような地方の小さな工場で生産されるものが多いのだそうである。
そこが私の予想に反し学校ではなく工場であったことは、私の中にかなり強い違和感とでも言うべきものを湧きおこらせた。その理由の一つは、私が前方に認めた「建物の形」が、見るからに「学校らしい形」をしていたからだ。
私たちは、町中を歩いていたり、車窓から外の景色を眺めているようなとき、ある建物が目に入ると、大体その用途、建物種類を推定できているように思える。
これは、おそらく建築に係わる職業の人特有の「習性」ではなく、普通の人たちも同じように、ある用途に対して「それらしい形」を思い浮かべるのではなかろうか。最近は見かけなくなったが、新築の建物の紹介する新聞記事などで「ホテルのような〇〇」という形容句が使われることがよくあった。その根には「建物で豪華なのはホテルである」という〈認識〉と、「その種の建物は本来かくかくしかじかのものだ」という〈認識〉(しかし目の前にしている建物はその〈認識〉にあてはまらない)が在るからと見なしてよいだろう。私自体が係わった建物についても、単に「學校らしくない」というのではなく、「鶏小屋のような」とか「工場のような」とか形容されたことがある。おそらくその場合は、そこでなされている教育が質が一定のブロイラーや画一的製品が大量生産されているという皮肉が込められているわけではなく、全く単純に日ごろ見慣れている鶏小屋や工場みたいだという意味に過ぎないだろう。
私たちは、自らの経験を通してだと思うが、学校だとか工場というものについて一定の《知見》を持っているから、そういった「言葉」を目にしたり耳にするだけで、自分が知っている学校や工場の姿を思い浮かべることができるのだ。
しかし、そのとき頭の中に思い浮かべているのは、単に、「學校、工場・・・といった建物の形」だけなのだろうか?
しばし考え直してみると、こういった「ことば」で私たちが頭に思い浮かべているのは、その「建物そのものだけ」ではなく、「その建物を含めたある場景」であることに気が付く。
すなわち、私たちは、「學校」「工場」・・という「ことば」で、私たちが、「それぞれの体験・経験で獲得したある場景の中の學校や工場を思い描いている」のである。
この「場景」は、必ずしもある具体的な特定のそれではない。むしろ、その「ことば」によって頭のなかに浮んでくるいろいろな個々の場面の場景を越えた、それらを統べるそのことばに最も相応しいと思われる場景を描いているのである。その意味では、「場景」よりも「情景」と表記する方が適切なのかもしれない。
私たちは、日常、多種多様な場面に遭遇しているが、私たちはそれらの場面の場景を、便宜的に括り分け、そのそれぞれにある名前を付ける。その一つが「學校」や「工場」ということばなのだ。逆に言えば、「個々の例を統べる場景:情景」として記したことは、「學校」とか「工場」ということばに、(私が)託している「概念」の姿だと言ってよいだろう。
つまり、ある建物を工場である、とか学校であるとする私たちの判別は、建物の形自体によることもないわけではないが、むしろ、その建物が在るその背景をも含んだ光景:先の言葉で言えば場景:情景そのものによることがより大きいのではないかと思われる。
しかし、この場景:情景というのは、建物のように物として固定し得るものではないから、便宜上言葉として置き換えることが容易な物:建物が前面にしゃしゃりでてくるのであり、更には、その物に対応していることばに、その係わる場景:情景も付託されていたのだ、ということが忘れ去られるのである。そしてその結果、このように、「私たちは固定できるものだけを見ている」、あるいは、「ことばというものは、ある物的に固定できる対象のみに対応している」かのような誤解を抱いてしまうのである。
要するに、私たちは、工場、学校という判別を、「場景」をもって察している、ということだ。
私たちが工場、学校という「ことば」で知っているもの、それはすなわち経験を通じて身に着けた「知見」に」ほかならないが、それぞれの用途の建物(それは、それぞれの建物での人びとの「生活」に他ならないのだが)の持つ特有の場景:情景なのである。もっとくだいて言えば、私たちは、たちどころに「それなりの雰囲気」を察知しているのである。
ひと昔前なら、木造の平屋建ての長屋状の建物は、学校、工場、病院、兵舎・・・など、いろいろな用途の建物として見られたものである。その用途の判断は、その建物のあたりに漂う雰囲気によっていたと言えるだろう。
今はどうだろうか?駅前によく見かける鉄筋コンクリートのビジネスホテルと町なかの会社の独身寮、だいたい外形はよく似ている。しかし、駅前のビジネスホテルを独身寮と見ることはほとんどないだろう。私たちは「場違い」だと思うからである。それぞれがあるべき:それぞれにふさわしい「場」を《知っている》からである。すなわち、私たちは、建物の姿・恰好:つくりを見て、そういう建物において展開し得る生活(の場面)を知っているからである。
つまり、私たちは私たちの生活の「場面」を一定程度《知っている》ものだから、ある建物を見ると、たちどころに《その場であり得る場面》を思い描いてみることができるのだ。
しかし、当然であるが、この《ある場面》は、決してその「場面」を厳密に規定・限定しているわけではない。
以上のことをまとめると以下のようになる。
私の前方に「ある形をした建物」が見えてきた。すると私は、先ず、そういう形をした建物において展開し得るとそのとき思った《生活の全て》を頭の中に描いてみる。次いで、そこの「場景」全体を勘案して、先ほど描いた《全て》の中から、そこで「あり得る(妥当と思える〉」「生活」を選び出す。そして、あれは〇〇か〇〇だ、あるいは〇〇のような用途の建物だという《判断》を下すのである。もちろん、通常は、こういう判断を、こんな手順を意識的に踏んで下すわけではなく、瞬時にやってしまう。そしてまた、この「あり得る」との「判断」は、誰かに教えられたものではなく(教えられるようなものではなく)、私たちそれぞれの「経験・体験」によって私たち自身が会得したものだ、と言えるだろう。すなわち、その根本的な判断は、私たちそれぞれの「感性」の所業なのである。
現代では、このような「言いかた」は、きわめて個人的な主観的な判断で客観性に欠けるとして、ひんしゅくをかうのがあたりまえだ。しかし、この《指摘》は、誤りである、と私は思う。
私には、現代というのは、私たち自らの感性に自信を持たなくなった時代、私たち自身の「経験」をもないがしろにしたがる時代のように思える。
私たちはそれぞれの毎日の生活を《だてに》送っているわけではない。私たちの日常(の「経験・体験」)は、私たちそれぞれの「感性」に拠っているのである。
筑波に暮すようになってから、いわゆる田舎の「風景」に、より強く魅かれるようになった気がする。
もちろん、ここでいう「風景」は、絵に描いてきれいな風景、というような意味ではない。それは、先に書いた「場景」という言葉の方が適切なのかもしれない。おそらく、私が忘れかけていたいろいろなことをあらためて考えさせてくれるきっかけを私に与えてくれたこと、それが私を強く惹きつけたのだと思う。
そして、あらためて思う。都会や新興の開発地で見かける建物には、どうしてああも多種多様な形があるのだろうか、と。
住居ひとつ例にしても、まずことごとく《異なった形》をしていると言ってよい。それは個人の住居に限らない。研究学園都市の公務員住宅にも、数えきれないほどの型があり、当然それに応じて一個の間取りも変ってくるのだが、なぜそうなるのか、その「必然性」は、私には皆目わからない。更に最近では、勾配屋根にして瓦を載せ、凸凹を設け、あるいはジグザグギクシャクさせる、といったようなつくりも増えてきた。その結果、形はますます多種多様にして複雑・怪奇になる。これは、「それまでの、画一的なつくりかたへの反省の上に立ち、形や建物周辺にできる場所の単調さをなくし、一戸一戸に個性とプライバシーを与え、コミュニティを形成させやすくし、人間味のある居住環境をつくりだすべく、地域の伝統をも踏まえ考えだされた」のだそうで、いまや全国的に流行りつつある。そこで私たちの目に入ってくるものは、あたかも私たちの目を傷つけんばかりに次ぎ次ぎに飛び込んでくる建物の角々。互いに競って見えたがるそれらの複雑・怪奇な形をした物たちは、私たちのなかに、いかんともしがたい「苛立たしさ」だけを積み上げてくれる。そして、そういう場景が尽きることなく単調に、延々と続くのである。その意味では、意図に反し《画一的》なのである。
これは、「個性」とか「人間味」とか言う以前の問題なのだ。こういう場景は、私にとっては、決して人の住む場景ではないし、決して住まいの場所として選ぶことないだろう。
これは、当時の状況について記している。現在も大差なく、あるいはさらに劣化しているのではないだろうか。
このような場景には何がふさわしいか考えてみたが、遊園地のビックリハウスぐらいしか思い浮かばない。だが、こういう場景が、今の世は、あたりまえになっていて、大都会周辺だけではなく、全国的にひろまっているようだ。学園都市のまわりにも、多く目にするようになった。
一方、学園都市のまわりに目を向ければ、そこには、大きく変わりつつはあるが、相変らず昔ながらの村々の佇まいが現存する。ゆえに、そこに立てば、はからずも、《新しいもの》と《旧いもの》を対比しながら眺めることができるのである。
これらの《近代的・先進的な》建物群を見ていて、いつも思う。あの住宅群は、たしかに住宅以外の何ものでもないが、どれも住宅でしかないな、しかも、ある極めて限定されたパターンでしか対応できないな、ことによると一代限りだな、と。つまり、そこで目にする場景には、私にいろいろな生活の場面を思い起こさせるようなところが何もない、ある場面だけ、それしかないのである。そこに物的に設定されてしまっている場景は、ある限定された生活の場面にしか対応できないのである。逆に言えば、ある限定した生活の場面を、物的に固定している、ということに他ならない。あの住宅群のなかに入って感じる《苛立たしさ》は、多分、第三者の手に拠り設定されてしまった生活の場面に自らを嵌め込まなければならない息苦しさからくるものなのだろう。第三者の意のままに(己の意のままにではなく)動かないと、十全にそこでは暮せないのである。もちろん、そこに住み着けば《慣れる》ことはあるだろう。しかしそれは、場景に応じた判断によるのではなく、いろいろな苦き経験の結果身についてしまった、いわば、「条件反射的行動」に過ぎない。しかし、これは、たとえば、《よい図書館の建物では、すぐれた図書館活動が為されている》かの「錯覚」を起こさせ、更には「よい図書館活動は、よい図書館(の建物)がないと為されない」という「誤解」をも生じさせてしまう。「専用の建物」がなくても、「活動」は行えるのだ。
さて、学園都市のまわりを取り囲む旧くから在る村々の方を見てみよう。
その光景は、今見てきたあの近代的な建物群が織りなすにぎやかなそれに比べて、ため息が出るほど、静かで単純だ。同じような屋根、同じような形の建物、同じような杜・・・。ある意味では、《画一的》だ、と言ってもよいだろう。そのなかで、際立って形の違いを見せているのは、学園都市建設で土地を売ったとおもわれる新興成金の家ぐらい。これは、(復刻・「筑波通信」―10「十人十色:人それぞれ」 とはどういうことか」)で触れた蔵の目立つ村のそれとは異なる。そこでは、単なる《形の主張》は見られなかった。そこでの《形》は、いろいろな生活の場面の可能性を想起させてくれる「示唆」に富んでいる。つまり、そこに在り得る(在って然るべき)生活の場面を「ああだ、こうだ」と規定するようなところがない。近代的な建物の多くがそうであるように、用意された器に適合した生活:誰かの手に拠る《期待される生活像》に我と我が身をあてはめる必要はない。
それでは、その用途、すなわちその使い分けは、何に拠っていたのだろうか?明らかにそれは、その建物の在る場景に拠っていたのである。その置かれる場景により、そこで在り得る生活の場面が異なることを、人びとは知っていたのである。それ故逆に、ある生活の場面のために、ある場所を選び、建物は同じ形でよしとしていたのである。彼らは、場違いということを知っていた。彼らは、杜のわきの元小学校を工場として使おうなどとは思わなかったに違いない。既存の場景のなかに、自分が求めている生活の場面が展開し得る場景が見出せなければ、そのときは、既存の場景に手を加え、それに相応しい新たな場景にしてしまうことさえ厭わなかった。「屋敷」の造成などは、そのよい例と言えるだろう。しかしそのとき、そこに建つ家は、まわりにあるのと変らない《同じ形》をしているのである。
しかし、この事実を《誤解する》と、「建物は、雨露さえしのげればよい」ではないか、という「言いかた」に行き着くのではなかろうか。
この「言いかた」を更につめれば、「・・・だから、建物など、どうでもいいんだ」という「言いかた」に行きつくだろう。この言いかたの行き着く先こそ、「建物は、雨露さえしのげればよい」という「言いかた」なのではあるまいか。
「方丈記」に「人の一生にとって『仮の住まい』」に過ぎない「家」に、気を遣って何になる・・・との一文がある。彼は、組み立て式の仮小屋をつくり、好みの場所に据えて住み家とした、とのこと。彼にとっては、「場所の選択」が重要だったらしい。
しかし、私たちは、学校だとか病院だとか・・・、ある一定の用途のための建物をつくろうとする。
では、「ある用途のための建物をつくる」というのはどういうことなのか?用の様態に応じて形を整えるということだろうか?
いわゆる建築計画学では、そのために、はじめに、「そこで行われる生活様態を設定すること」が必要と考えられた。
すなわち、先ず《期待される生活像》の設定が肝要と見なされたのである。暮しかた・使いかたの《設定・限定》に他ならない。
しかし、私たちは、必ずしも、黙ってそれに従ってはいない。私たちは、人であり続ける。
私たちに先ず必要なのは、私たちの「ごく自然な日常の振舞いのありようを再認識してみること」ではないだろうか。