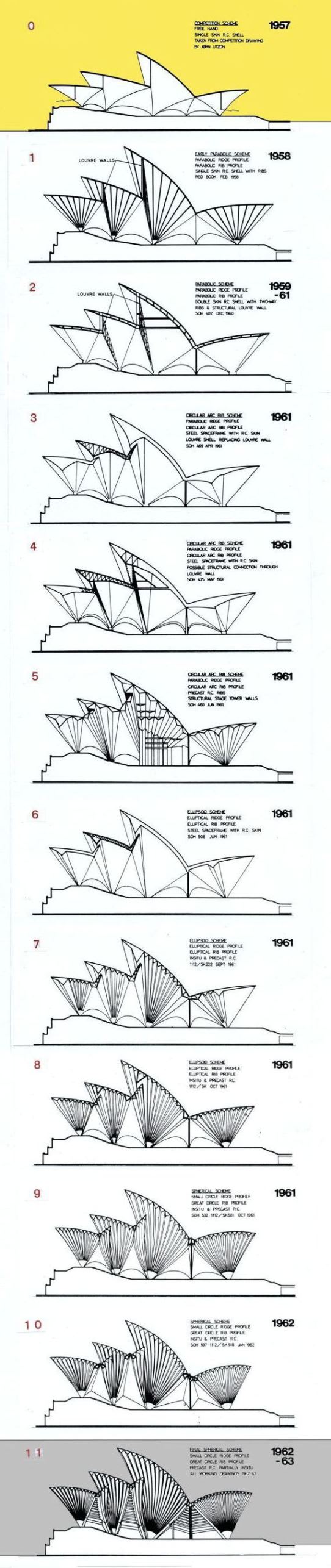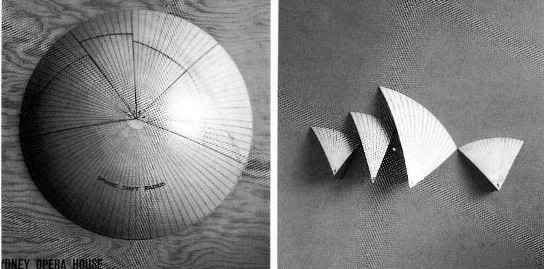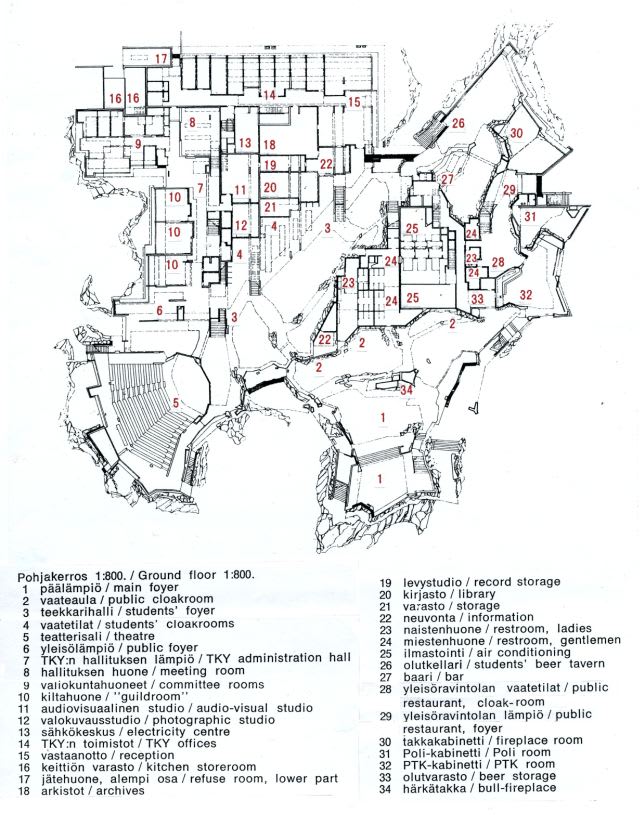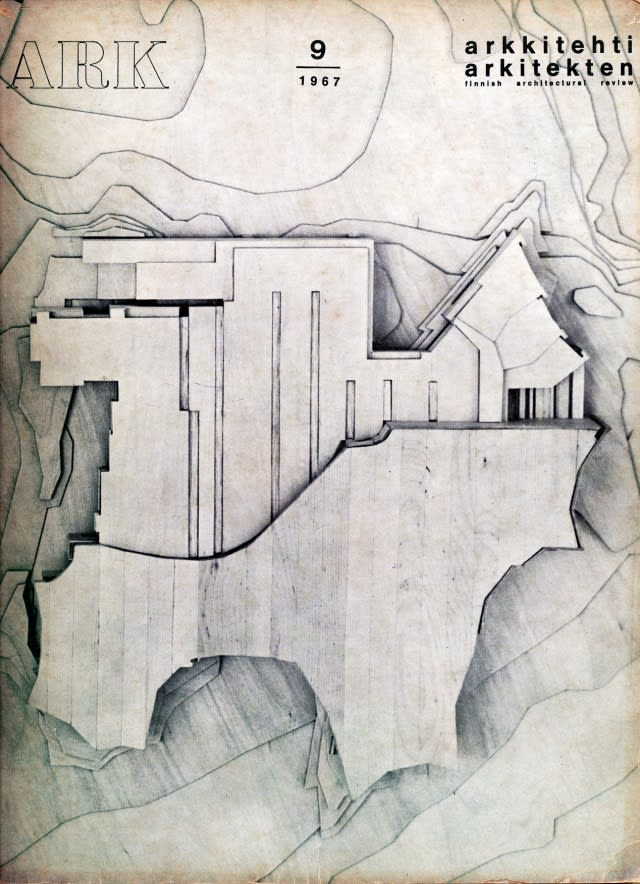残暑お見舞い申し上げます。
立秋とともに、猛暑がやってきました!

雨水を一時的に溜めている池に、毎朝ヒメスイレンが咲きます。
[註記追加 14日 8.50]
学校の校舎の「耐震化:耐震補強」が進んでいない、という報道がありました。私の暮す茨城県はワースト5に入るそうです。
学校校舎の「耐震補強」で一般的なのは、既存の校舎の開口部のいくつかに、鉄骨製または鉄筋コンクリート製のX型の「筋違(すじかい)」を設置する方策です。
以前にも書きましたが、この施策の必要が報道されるたびに、私は「違和感」を感じます。
その違和感は、大きく分けて二つあります。
一つは、「耐震補強」の拠って立つ「建物の骨組み:架構についての考え方」についての「違和感」、もう一つは surroundings の観点からの「違和感」です。
いずれも、「これでいいのか?」という「疑問」に連なります。
前者:架構についての考え方:に対しては、すでにその「可笑しさ」「異常さ」( non-scientific であること)については、何度も書いてきましたので(後註記事もその一つ)、今回は、後者: surroundings の観点からの「違和感」:について特に触れることにします。
言うまでもなく、学校の校舎は、たとえば小学校は、6歳から12歳までの子どもたちが、昼間の大半を過ごす場所です。
すなわち、四六時中子どもたちを取り囲んでいる surroundings 、「居住環境・居住空間」にほかなりません。
そのとき、開口部に設けられている大きなX型の筋違は、surroundings として、なくてはならないものでしょうか?
当然ですが、必要ありません。
必要だ、と思われる方は居られますか?
6歳から12歳というのは、感受性豊かな子どもたちが、各自の感性に磨きをかける大切な時期です。
子どもたちは、surroundings との「応答」のなかで、感性に磨きをかけるのです。
そのとき、日常的に接する surroundings が、重要な意味をもつのは言うまでもないでしょう。
そして、開口部に設けられるX型は、邪魔以外の何ものでもないのです。それとも、必要ですか?
明らかに、現在進められている「耐震補強」は、人の暮す surroundings を損なうことになる、という点については一考だにされていないのです。
つまり、子供たちの成長に好ましくない環境が、教育を管轄するはずの文部科学省の推奨の下で、「耐震補強」という《大義》を立て、つくられているのです。
これはきわめて恐ろしいことだ、と私は思います。
いわゆる重要文化財建造物も、同じような耐震補強が求められていて、「文化財」の意義が失われつつあるようです。これも文部科学省の管轄!
世の中には、この「耐震という必要不可欠な策」に異論を唱えるなどは、(国家の)《大義》に反するという「言論統制」に近いフンイキが漂っています。
私はそれを「霊感商法」と同じだ、と書きました(後註参照)。なんだか、戦時下を思い出させます。
なお、茨城県がワースト5であるということは、環境破壊が幸いまだ進んでいないということかもしれません!
もちろん私は、地震の際の安全性を確保することを不要と言っているのではありません(あえて「耐震」とは言いません。「耐震」などと「おこがましい」ことを言うから、進むべき方向を間違えるのです)。
カテゴリー「地震への対し方・対震」で、この点に関する記事35編ほどがまとめてありますので、お読みください。[註記追加]
必要なのは、surroundings を確保したうえで、地震の際の安全性を確保することのはずです。
それを為し得ていない方策は、「技術」と呼んではならないのです。
なぜなら、「技術」とは、「人間の生活に役立たせるために、その時代の最新の知識に基づいて知恵を働かせ様ざまなくふうをして物を作ったり加工したり操作したりする手段」のことです(「新明解国語辞典」による)。
しかし、現在行われている《耐震補強技術》には、「人の生活・暮し」の視点が全く欠けているのです。
こういう耐震《技術》の「誕生」の背景には、どこか、原発《技術》の「誕生」と似たような状況があるように思えます。
かかわる《技術者》たちは前後左右が見えなくなり、「技術」の本来の意味を見失ってっているのです。
これは、もしかしたら、「理」を忘れ、「利」の追及に走りたがる現在の日本の「工学」の世界特有の現象かもしれません。
「壁は自由な存在であった」シリーズで紹介したように、
日本の建物づくりでは、
surroundings を確保したうえで、地震時の安全性をも確保する技術を、中世~近世初頭には確立していたと考えられます。
まったく「壁」のない「風通しの良い」「今でも暮せる」建屋が、400年近く、何度も地震に遭いながらも健在なのです。
こういう例は多数あります。しかし、工学研究者たちの目には入らないようで、研究の対象にさえなっていません。何故か?
「解析」の方法が(分ら)ないからのようです・・・。
しかし、かつての工人たちは、そういう「技術」を習得していたのです。もちろん「学」の存在しない時代に、です!
彼らは「理」を「感覚」で把えることができたのです。「直観」による理解です。
耐震補強の名の下での私たちの surroundings の破壊を、私たちは黙認してしまっているのではないでしょうか。
註 下記もお読みください(カテゴリー「地震への対し方・対震」にも入っています)。
「耐震診断・耐震補強の怪-1」
「耐震診断・耐震補強の怪-2」
「耐震診断・耐震補強の怪-3」
立秋とともに、猛暑がやってきました!

雨水を一時的に溜めている池に、毎朝ヒメスイレンが咲きます。
[註記追加 14日 8.50]
学校の校舎の「耐震化:耐震補強」が進んでいない、という報道がありました。私の暮す茨城県はワースト5に入るそうです。
学校校舎の「耐震補強」で一般的なのは、既存の校舎の開口部のいくつかに、鉄骨製または鉄筋コンクリート製のX型の「筋違(すじかい)」を設置する方策です。
以前にも書きましたが、この施策の必要が報道されるたびに、私は「違和感」を感じます。
その違和感は、大きく分けて二つあります。
一つは、「耐震補強」の拠って立つ「建物の骨組み:架構についての考え方」についての「違和感」、もう一つは surroundings の観点からの「違和感」です。
いずれも、「これでいいのか?」という「疑問」に連なります。
前者:架構についての考え方:に対しては、すでにその「可笑しさ」「異常さ」( non-scientific であること)については、何度も書いてきましたので(後註記事もその一つ)、今回は、後者: surroundings の観点からの「違和感」:について特に触れることにします。
言うまでもなく、学校の校舎は、たとえば小学校は、6歳から12歳までの子どもたちが、昼間の大半を過ごす場所です。
すなわち、四六時中子どもたちを取り囲んでいる surroundings 、「居住環境・居住空間」にほかなりません。
そのとき、開口部に設けられている大きなX型の筋違は、surroundings として、なくてはならないものでしょうか?
当然ですが、必要ありません。
必要だ、と思われる方は居られますか?
6歳から12歳というのは、感受性豊かな子どもたちが、各自の感性に磨きをかける大切な時期です。
子どもたちは、surroundings との「応答」のなかで、感性に磨きをかけるのです。
そのとき、日常的に接する surroundings が、重要な意味をもつのは言うまでもないでしょう。
そして、開口部に設けられるX型は、邪魔以外の何ものでもないのです。それとも、必要ですか?
明らかに、現在進められている「耐震補強」は、人の暮す surroundings を損なうことになる、という点については一考だにされていないのです。
つまり、子供たちの成長に好ましくない環境が、教育を管轄するはずの文部科学省の推奨の下で、「耐震補強」という《大義》を立て、つくられているのです。
これはきわめて恐ろしいことだ、と私は思います。
いわゆる重要文化財建造物も、同じような耐震補強が求められていて、「文化財」の意義が失われつつあるようです。これも文部科学省の管轄!
世の中には、この「耐震という必要不可欠な策」に異論を唱えるなどは、(国家の)《大義》に反するという「言論統制」に近いフンイキが漂っています。
私はそれを「霊感商法」と同じだ、と書きました(後註参照)。なんだか、戦時下を思い出させます。
なお、茨城県がワースト5であるということは、環境破壊が幸いまだ進んでいないということかもしれません!
もちろん私は、地震の際の安全性を確保することを不要と言っているのではありません(あえて「耐震」とは言いません。「耐震」などと「おこがましい」ことを言うから、進むべき方向を間違えるのです)。
カテゴリー「地震への対し方・対震」で、この点に関する記事35編ほどがまとめてありますので、お読みください。[註記追加]
必要なのは、surroundings を確保したうえで、地震の際の安全性を確保することのはずです。
それを為し得ていない方策は、「技術」と呼んではならないのです。
なぜなら、「技術」とは、「人間の生活に役立たせるために、その時代の最新の知識に基づいて知恵を働かせ様ざまなくふうをして物を作ったり加工したり操作したりする手段」のことです(「新明解国語辞典」による)。
しかし、現在行われている《耐震補強技術》には、「人の生活・暮し」の視点が全く欠けているのです。
こういう耐震《技術》の「誕生」の背景には、どこか、原発《技術》の「誕生」と似たような状況があるように思えます。
かかわる《技術者》たちは前後左右が見えなくなり、「技術」の本来の意味を見失ってっているのです。
これは、もしかしたら、「理」を忘れ、「利」の追及に走りたがる現在の日本の「工学」の世界特有の現象かもしれません。
「壁は自由な存在であった」シリーズで紹介したように、
日本の建物づくりでは、
surroundings を確保したうえで、地震時の安全性をも確保する技術を、中世~近世初頭には確立していたと考えられます。
まったく「壁」のない「風通しの良い」「今でも暮せる」建屋が、400年近く、何度も地震に遭いながらも健在なのです。
こういう例は多数あります。しかし、工学研究者たちの目には入らないようで、研究の対象にさえなっていません。何故か?
「解析」の方法が(分ら)ないからのようです・・・。
しかし、かつての工人たちは、そういう「技術」を習得していたのです。もちろん「学」の存在しない時代に、です!
彼らは「理」を「感覚」で把えることができたのです。「直観」による理解です。
耐震補強の名の下での私たちの surroundings の破壊を、私たちは黙認してしまっているのではないでしょうか。
註 下記もお読みください(カテゴリー「地震への対し方・対震」にも入っています)。
「耐震診断・耐震補強の怪-1」
「耐震診断・耐震補強の怪-2」
「耐震診断・耐震補強の怪-3」