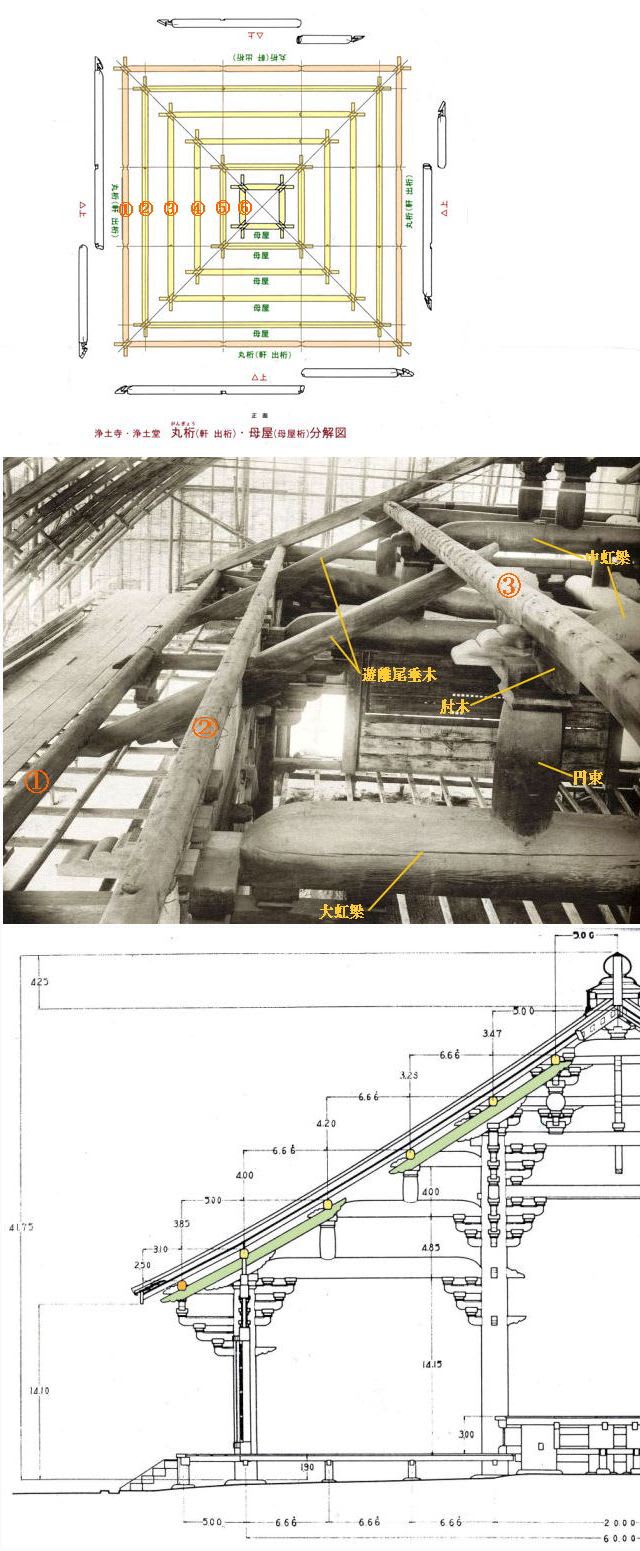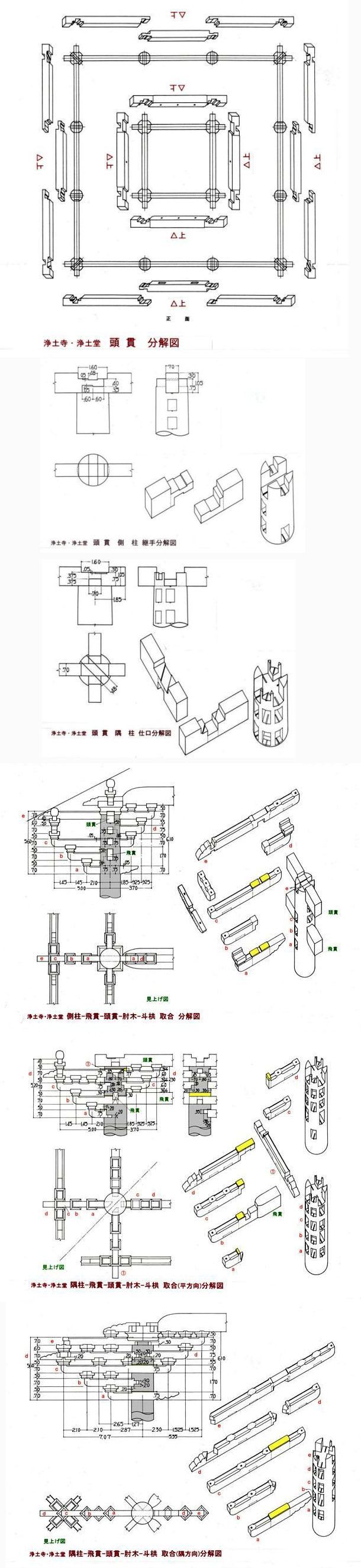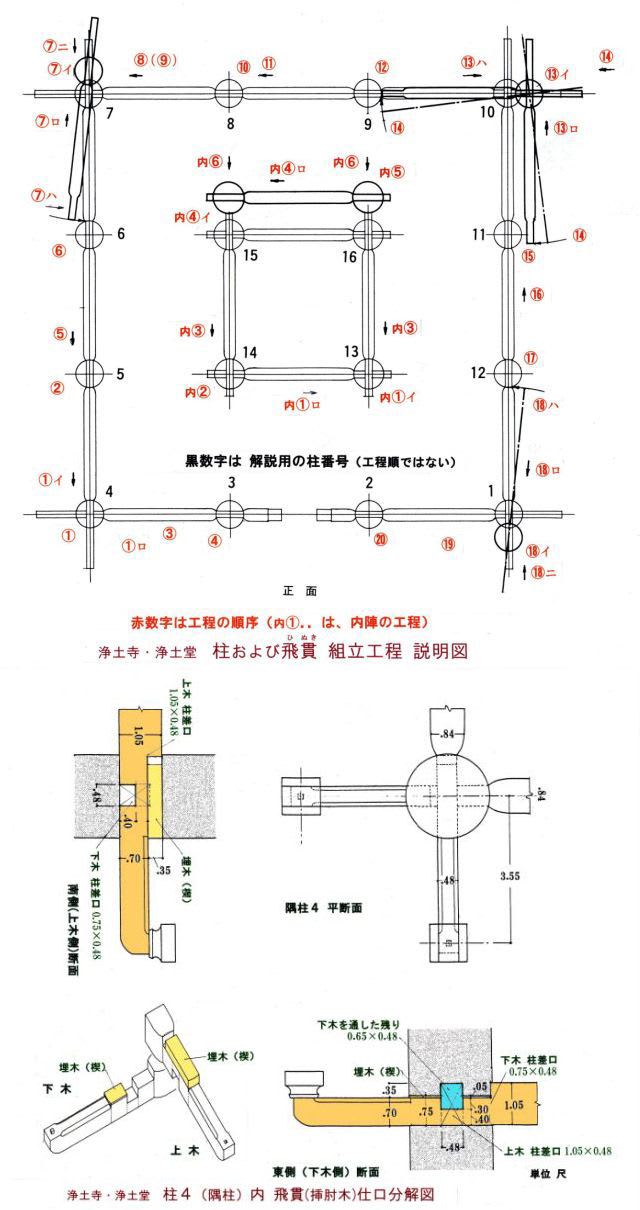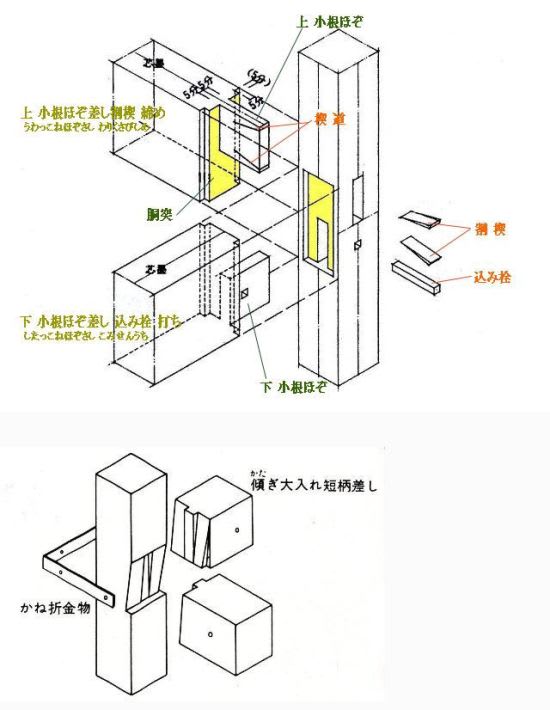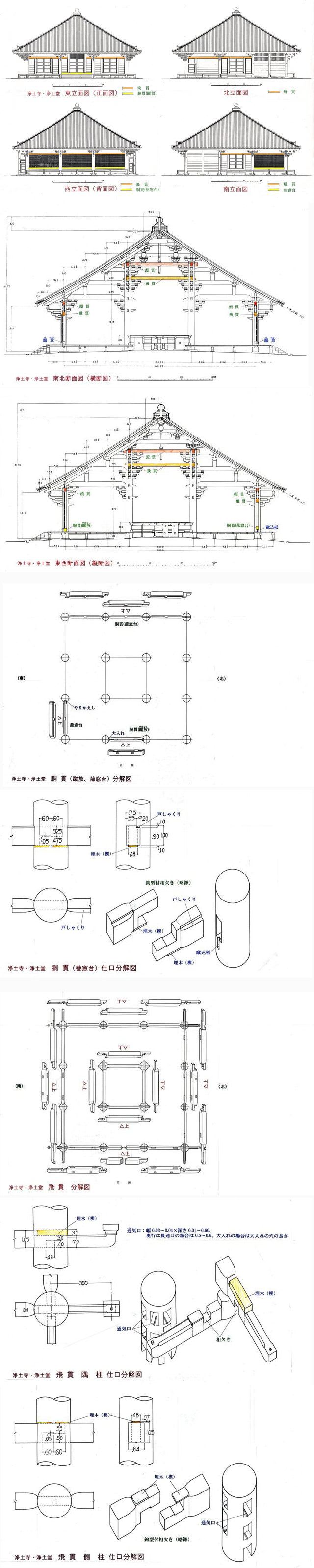私は読んだことはないし、その気もないのだが、最近、中谷巌氏の「資本主義はなぜ自壊したか」という書物が売れているのだそうである。
氏は「グローバル資本主義」「市場原理主義」・・・といったアメリカ式の「思想」をひっさげてときの政府にかかえられ「構造改革」路線へわが国を推し進めた張本人を自認する経済学者である。かの竹中平蔵氏は、その継承者。
今になって、それが誤りだった、と気付いての「懺悔の書」だとのこと。
それはそれとして、29日のNHKのニュースの本人とのインタビューのなかで彼が語った言葉が気になった。
正確ではないが、「経済が、その国の文化、歴史、社会・・と関係深いものであることを忘れていた・・」「経済は人を幸せにするものでなければならない、ということに気がついた・・」との旨の言葉。
私は思わず「えっ」と思った。そうだったんだ!
別に経済でなくてもいい。なにごとによらず、そんなことは「いろはのいの字」ではないか、いい年をして何を言ってるんだ!それで学者だというのか?いや、だから学者でいられたんだ!日本はきっとそういう国なのだ!!
漢語の「経済」の出所を考えて欲しい。そして、eco‐nomy と eco-logy の eco についても・・・。考えたことがあったなら、そんな「思想」に囚われることもなかったろうに・・。
しかし、ふと気がついた。これが「いろはのいの字」と思うのは今の世では変人奇人なのかもしれない(中谷氏や竹中平蔵氏に従った小泉純一郎氏は、変人奇人どころか、いまの世の中のごく「普通」の人)。
なぜならそれは、学校の教科で、「歴史」がいい加減に扱われていることに現われている。知らなかったのだが、高校では(だったと思うが)、「世界史」か「日本史」のどちらかを選択すればいいのだそうである。それでいて「国際化」・・が平然と語られる。
「国際化」とは、「米語」を習えば済むらしい。そしてそこでさらに気がついた。かつて明治の「近代化」推進の際、西欧:英・仏・独に倣うべく努めたが、いまは米国に倣うのが「最先端」なのだ。英語(米語)を小学校の教科にしよう、などということの「理由」も分るというもの。
明治の「先進者」は、西欧に留学することを、世間の普通の人から「西洋かぶれ」と言われようが、勲章のように大事にし、願望した。
戦後、それにかわって「アメリカかぶれ」が流行った。「先進諸国」への留学はあいかわらず一部の人たちには勲章らしい。それでいて日本は先進国なんだそうだ。
中谷氏も、インタビューのなかで、アメリカが憧れだったと語っている。そういえば、竹中氏もアメリカ留学者。
私などは、そんなに憧れて、いいところなら、定住すればいいのに、と思ってしまう。アメリカは、「移民」を受けいれてくれるではないか。
だが、そうはしないらしい。「留学」という勲章をぶら下げて母国で顔を売ることに専念する。
おそらく、向うには見合う職がなかったのだろう(向うに引き留められている、あるいは日本から引張られる本当の日本人学者が、たくさんいるではないか・・)。
それとも「母国」日本が好きだったからなのだろうか。
そんなことはない。自国の歴史、文化、社会・・について知らない、と言うのだから。それゆえに、「留学」という勲章をぶら下げて母国で顔を売ることに専念する・・・。
それにしても、政治家を操って、いまの状況をつくってしまったことの責任はどのようにとるのだろうか。「懺悔の書」を著して売れればいいのだろうか。
実は、29日のニュースでもう一つ気になったのは、中谷氏の「転向」:アメリカ式「思想」からの撤退を、企業の中堅の若い世代の人たちの多くが批判していることだった。
市場原理主義で、日本は(企業は、なんだろうが)成長した、というのである。
例の、「できる人」が上に上がれば上がるほど、全体が底上げされる、という安直な「論理」?である。
これにも「えっ」と思ってしまった。「選民意識」がギラギラしていて、気分が悪かった。住む世界が違うらしい。
やはり、かつての「近江商人」はすぐれていた。彼らの多くは「経世済民」の意味を分っていた。「商売」「商い」の意味が分っていた。そして、「儲ける」ことの意味も分っていた。
註 私は、終戦時にその人が何歳であったかが、
その人の「考え方」に大きな影響を与えている、と
勝手に思っている。
中谷氏は1942年生まれ、ものごころついたころから
アメリカ、アメリカ・・の世の中だった。
竹中平蔵氏は1951年生まれ。生まれたときから
アメリカ、アメリカ・・の世の中だった。
きっと、相対的にものを見ること、観ることを
学ばなかったに違いない。
言うならばアメリカ絶対主義。
これが1960年代以降生まれになると少し変ってくるのだが、
しかし、TVで市場原理主義を是としていたのはこの世代。
誰かに何か「洗脳」されているように、私には思えた。
「氏より育ち」とは、よく言ったものだ、と思う。
氏は「グローバル資本主義」「市場原理主義」・・・といったアメリカ式の「思想」をひっさげてときの政府にかかえられ「構造改革」路線へわが国を推し進めた張本人を自認する経済学者である。かの竹中平蔵氏は、その継承者。
今になって、それが誤りだった、と気付いての「懺悔の書」だとのこと。
それはそれとして、29日のNHKのニュースの本人とのインタビューのなかで彼が語った言葉が気になった。
正確ではないが、「経済が、その国の文化、歴史、社会・・と関係深いものであることを忘れていた・・」「経済は人を幸せにするものでなければならない、ということに気がついた・・」との旨の言葉。
私は思わず「えっ」と思った。そうだったんだ!
別に経済でなくてもいい。なにごとによらず、そんなことは「いろはのいの字」ではないか、いい年をして何を言ってるんだ!それで学者だというのか?いや、だから学者でいられたんだ!日本はきっとそういう国なのだ!!
漢語の「経済」の出所を考えて欲しい。そして、eco‐nomy と eco-logy の eco についても・・・。考えたことがあったなら、そんな「思想」に囚われることもなかったろうに・・。
しかし、ふと気がついた。これが「いろはのいの字」と思うのは今の世では変人奇人なのかもしれない(中谷氏や竹中平蔵氏に従った小泉純一郎氏は、変人奇人どころか、いまの世の中のごく「普通」の人)。
なぜならそれは、学校の教科で、「歴史」がいい加減に扱われていることに現われている。知らなかったのだが、高校では(だったと思うが)、「世界史」か「日本史」のどちらかを選択すればいいのだそうである。それでいて「国際化」・・が平然と語られる。
「国際化」とは、「米語」を習えば済むらしい。そしてそこでさらに気がついた。かつて明治の「近代化」推進の際、西欧:英・仏・独に倣うべく努めたが、いまは米国に倣うのが「最先端」なのだ。英語(米語)を小学校の教科にしよう、などということの「理由」も分るというもの。
明治の「先進者」は、西欧に留学することを、世間の普通の人から「西洋かぶれ」と言われようが、勲章のように大事にし、願望した。
戦後、それにかわって「アメリカかぶれ」が流行った。「先進諸国」への留学はあいかわらず一部の人たちには勲章らしい。それでいて日本は先進国なんだそうだ。
中谷氏も、インタビューのなかで、アメリカが憧れだったと語っている。そういえば、竹中氏もアメリカ留学者。
私などは、そんなに憧れて、いいところなら、定住すればいいのに、と思ってしまう。アメリカは、「移民」を受けいれてくれるではないか。
だが、そうはしないらしい。「留学」という勲章をぶら下げて母国で顔を売ることに専念する。
おそらく、向うには見合う職がなかったのだろう(向うに引き留められている、あるいは日本から引張られる本当の日本人学者が、たくさんいるではないか・・)。
それとも「母国」日本が好きだったからなのだろうか。
そんなことはない。自国の歴史、文化、社会・・について知らない、と言うのだから。それゆえに、「留学」という勲章をぶら下げて母国で顔を売ることに専念する・・・。
それにしても、政治家を操って、いまの状況をつくってしまったことの責任はどのようにとるのだろうか。「懺悔の書」を著して売れればいいのだろうか。
実は、29日のニュースでもう一つ気になったのは、中谷氏の「転向」:アメリカ式「思想」からの撤退を、企業の中堅の若い世代の人たちの多くが批判していることだった。
市場原理主義で、日本は(企業は、なんだろうが)成長した、というのである。
例の、「できる人」が上に上がれば上がるほど、全体が底上げされる、という安直な「論理」?である。
これにも「えっ」と思ってしまった。「選民意識」がギラギラしていて、気分が悪かった。住む世界が違うらしい。
やはり、かつての「近江商人」はすぐれていた。彼らの多くは「経世済民」の意味を分っていた。「商売」「商い」の意味が分っていた。そして、「儲ける」ことの意味も分っていた。
註 私は、終戦時にその人が何歳であったかが、
その人の「考え方」に大きな影響を与えている、と
勝手に思っている。
中谷氏は1942年生まれ、ものごころついたころから
アメリカ、アメリカ・・の世の中だった。
竹中平蔵氏は1951年生まれ。生まれたときから
アメリカ、アメリカ・・の世の中だった。
きっと、相対的にものを見ること、観ることを
学ばなかったに違いない。
言うならばアメリカ絶対主義。
これが1960年代以降生まれになると少し変ってくるのだが、
しかし、TVで市場原理主義を是としていたのはこの世代。
誰かに何か「洗脳」されているように、私には思えた。
「氏より育ち」とは、よく言ったものだ、と思う。