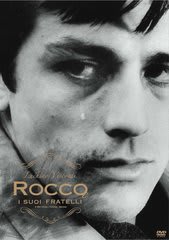
『若者のすべて』 ルキノ・ヴィスコンティ監督 ☆☆☆☆
日本版のブルーレイを入手して鑑賞。1960年のモノクロ作品。
ヴィスコンティの映画は『ベニスに死す』程度しか観たことがなく、いかにも貴族的で耽美的、退廃的な映画を撮る監督だと思っていたが、この『若者のすべて』はまだ初期のネオリアリスモ的要素を残していて、そういう「いかにもヴィスコンティ」な映画とはちょっと印象が異なる作品だった。田舎からミラノに出てきた貧しい労働者階級の一家を描いた大河ドラマ風の物語で、映画は五つの章に分かれ、それぞれに五人兄弟ひとりひとりの名前が振られている。が、それぞれの兄弟の物語が連作風に繋がっていくというより、メインのストーリーはどんどん堕落していく次男シモーネと聖人のような三男ロッコ(アラン・ドロン)、そしてこの二人と関係を持つ娼婦ナディアの三人である。
シモーネは有望なボクサーとして一時名前を売り、ナディアと恋人になるが、自堕落な性格からだんだんドロップアウトしていく。まじめにクリーニング屋で働くロッコもシモーネの素行のせいで解雇されるが、ロッコは兄弟愛からシモーネをかばう。やがてナディアもシモーネに愛想を尽かして別れるが、後にロッコと再会し、彼の純真さに打たれて愛し合うようになる。が、それを知ったシモーネは嫉妬に狂って不良仲間とデート中のロッコとナディアを襲い、ナディアをレイプする。聖人のようなロッコは「兄貴があんなことをしたのはあなたは愛しているからだ。彼を支えてやってくれ」とナディアに頼み、自暴自棄になったナディアはまたシモーネとヨリを戻す。一方、ナディアを愛しながらも別れたロッコはシモーネの代わりにボクサーになり、徐々に頭角を現す。が、シモーネの堕落はもはやとどまるところを知らず、更なる災厄を一家にもたらすのだった…。
貧乏な一家の苦闘をネオリアリスモ的なタッチで描いた映画だが、あらすじからも分かるように、シモーネの悪とロッコの善はかなり極端に描かれている。ロッコの善良さ、博愛はまるでキリストのようで、その美貌とあいまってリアルには感じられない。そういう意味では、ネオリアリスモ風のこの物語は一方でどこか寓話性、神話性を帯びている。
ところで私が所有するブルーレイには淀川長治さんの解説がついているが、ざっくりまとめて言うと「敗北」を描くヴィスコンティがシモーネを軸に敗北と崩壊を残酷なまでに描いた映画、ということのようだ。確かに、この映画で観客にもっとも強烈に訴えかけてくるのは、何よりもシモーネが堕ちていく過程とその崩壊の無残さであり、それが本人の人生を破壊し不幸にするだけでなく、いかに家族をはじめとする周囲の人々を不幸にするか、というこの一点だろう。
そしてその描写の姿勢の基本にあるのは哀しみや憂愁というより、残酷であり、厳しいほどの辛辣さである。シモーヌがロッコの眼前でナディアをレイプするシーンなど、正視できないほどに無残だ。そしてナディアの末路とロッコの苦しみには、旧約聖書的といいたくなるほどの厳しさがある。そしてこの残酷さ、仮借のない辛辣さが、先ほど書いた神話性とあいまって荘厳な構築美をこの映画に与えている。そういう意味では、やはりこの映画もヴィスコンティ的壮麗美の映画なのである。ただしその壮麗美は視覚面にではなく、物語の精神と構図とタッチの中にある。
では視覚面ではどうかというと、ネオリアリスモ的な生活感の中に、ヴィスコンティ的壮麗美としてアラン・ドロンの美貌、ミラノの町並み、大聖堂のビジュアルなどがちりばめられることによって、哀感と構築美が一定のバランスのもとに共存している。モノクロ映像の禁欲性が、この残酷な崩壊の物語を厳しい美しさで彩っている。
しかしやはり、この映画の感動はビジュアルよりも物語の余韻の中にあると思う。それぞれが異なる五人兄弟の対比と歳月がもたらす変化によって、映画のラストシーンでは大河ドラマ特有の感慨を抱かせる。それは、ここには確かに人生の手触りがある、という実感である。ちなみに、本作はヴィスコンティが一番思い入れがある自作ということだ。
日本版のブルーレイを入手して鑑賞。1960年のモノクロ作品。
ヴィスコンティの映画は『ベニスに死す』程度しか観たことがなく、いかにも貴族的で耽美的、退廃的な映画を撮る監督だと思っていたが、この『若者のすべて』はまだ初期のネオリアリスモ的要素を残していて、そういう「いかにもヴィスコンティ」な映画とはちょっと印象が異なる作品だった。田舎からミラノに出てきた貧しい労働者階級の一家を描いた大河ドラマ風の物語で、映画は五つの章に分かれ、それぞれに五人兄弟ひとりひとりの名前が振られている。が、それぞれの兄弟の物語が連作風に繋がっていくというより、メインのストーリーはどんどん堕落していく次男シモーネと聖人のような三男ロッコ(アラン・ドロン)、そしてこの二人と関係を持つ娼婦ナディアの三人である。
シモーネは有望なボクサーとして一時名前を売り、ナディアと恋人になるが、自堕落な性格からだんだんドロップアウトしていく。まじめにクリーニング屋で働くロッコもシモーネの素行のせいで解雇されるが、ロッコは兄弟愛からシモーネをかばう。やがてナディアもシモーネに愛想を尽かして別れるが、後にロッコと再会し、彼の純真さに打たれて愛し合うようになる。が、それを知ったシモーネは嫉妬に狂って不良仲間とデート中のロッコとナディアを襲い、ナディアをレイプする。聖人のようなロッコは「兄貴があんなことをしたのはあなたは愛しているからだ。彼を支えてやってくれ」とナディアに頼み、自暴自棄になったナディアはまたシモーネとヨリを戻す。一方、ナディアを愛しながらも別れたロッコはシモーネの代わりにボクサーになり、徐々に頭角を現す。が、シモーネの堕落はもはやとどまるところを知らず、更なる災厄を一家にもたらすのだった…。
貧乏な一家の苦闘をネオリアリスモ的なタッチで描いた映画だが、あらすじからも分かるように、シモーネの悪とロッコの善はかなり極端に描かれている。ロッコの善良さ、博愛はまるでキリストのようで、その美貌とあいまってリアルには感じられない。そういう意味では、ネオリアリスモ風のこの物語は一方でどこか寓話性、神話性を帯びている。
ところで私が所有するブルーレイには淀川長治さんの解説がついているが、ざっくりまとめて言うと「敗北」を描くヴィスコンティがシモーネを軸に敗北と崩壊を残酷なまでに描いた映画、ということのようだ。確かに、この映画で観客にもっとも強烈に訴えかけてくるのは、何よりもシモーネが堕ちていく過程とその崩壊の無残さであり、それが本人の人生を破壊し不幸にするだけでなく、いかに家族をはじめとする周囲の人々を不幸にするか、というこの一点だろう。
そしてその描写の姿勢の基本にあるのは哀しみや憂愁というより、残酷であり、厳しいほどの辛辣さである。シモーヌがロッコの眼前でナディアをレイプするシーンなど、正視できないほどに無残だ。そしてナディアの末路とロッコの苦しみには、旧約聖書的といいたくなるほどの厳しさがある。そしてこの残酷さ、仮借のない辛辣さが、先ほど書いた神話性とあいまって荘厳な構築美をこの映画に与えている。そういう意味では、やはりこの映画もヴィスコンティ的壮麗美の映画なのである。ただしその壮麗美は視覚面にではなく、物語の精神と構図とタッチの中にある。
では視覚面ではどうかというと、ネオリアリスモ的な生活感の中に、ヴィスコンティ的壮麗美としてアラン・ドロンの美貌、ミラノの町並み、大聖堂のビジュアルなどがちりばめられることによって、哀感と構築美が一定のバランスのもとに共存している。モノクロ映像の禁欲性が、この残酷な崩壊の物語を厳しい美しさで彩っている。
しかしやはり、この映画の感動はビジュアルよりも物語の余韻の中にあると思う。それぞれが異なる五人兄弟の対比と歳月がもたらす変化によって、映画のラストシーンでは大河ドラマ特有の感慨を抱かせる。それは、ここには確かに人生の手触りがある、という実感である。ちなみに、本作はヴィスコンティが一番思い入れがある自作ということだ。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます