
『ぼくたちの家族』を新宿ピカデリーで見ました。
(1)『舟を編む』を制作した石井裕也監督の作品ということで映画館に行ってきました。
映画の冒頭は、吉祥寺(注1)の喫茶店で友人と話をしている主婦・玲子(原田美枝子)。とはいえなんだか上の空で、友人の話を満足に聞いていない感じです(注2)。

会合が終わって中央線に乗って家に帰りますが、だいぶ西に向かい、車窓から中央高速が見えますから山梨県に入ってしまっています。
着いた駅は「三好」(注3)、駅からしばらく歩くと住宅街が一帯に広がっています。
多分、バブル期にここに家を求めたのでしょう(注4)。
少しすると、家の主・克明(長塚京三)が戻ってきます。「駅に迎えに来ていなかったじゃないか?食事は?」と、暗い中でぼんやり座り込んでいる妻に尋ねると、玲子は「ごめんなさい、忘れちゃった」と答え、慌てて支度に取り掛かります。
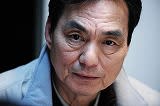
それから、長男・浩介(妻夫木聡)に子供が出来たということで、長男の妻・深雪(黒川芽以)の両親たちと一緒に食事会が行われます。ただ、その席で玲子は酷くおかしなことを言い出します(注5)。
そんなこんなで、克明は浩介と一緒に玲子を病院に連れて行ったところ、医師は、脳腫瘍が7つ見つかり(なかにはピンポン球くらいのものも)、「ここ1週間が山になる」と宣告します。
さあ大変です。この事態に対して、長男・浩介は、頼りにならない父親・克明や次男の俊平(池松壮亮)と一緒になって対処しようとするところ、果たしてうまくいくのでしょうか、………?


実に典型的な中流家庭が取り上げられ、一つ一つはありふれている出来事をいくつもその家族に集中的に生じさせたらどうなるか、という視点から作られている感じの映画ながら、石井監督の映画作りのうまさと、出演俳優の巧みな演技が融合して(注6)、最後まで画面に見入ってしまいます。
(2)これまでの石井裕也監督の作品との関連で言えば、お馴染みの“とにかく頑張っていこう”の精神が、本作でも描かれていることは間違いありません(注7)。
ただ、従来、何かしら顔を出していたファンタジー的な要素が殆ど見られないために(注8)、そのぶんだけ一層リアルさということが浮かび上がってくるように思われます。
ですが、そんなにリアルかというと、少々疑問に思える点もないではありません。
例えば、浩介の両親が住んでいる場所の「三好」です。確かに、バブル期には東京のベッドタウンが小仏峠を越えて山梨県にまで延びたものの、都心からだと通勤に相当の時間を要するのは間違いないでしょう(注9)。
父親・克明の会社の所在地がはっきりしないので何とも言えないとはいえ、会社に何が起こるかわかりませんから、いやしくも経営者であるならば、そんな遠隔地ではなくとにかく会社の近辺に家を持つのが常識ではないでしょうか?
また、父親・克明は、妻・玲子の入院に際しても長男・浩介に頼りきりで、ダメな父親振りを発揮しています(注10)。とはいえ、定年間際の窓際族でもなく、思わしくない企業とはいえその経営者なのですから、普通であれば、問題に対して逃げるのではなく、自分が率先して乗り出して解決しようとするのではないでしょうか(注11)?
さらに、下記の(3)で触れる渡まち子氏が「母の治療に奔走する姿よりも、金銭面でのゴタゴタの方が印象に残ってしまう」と言うように、この家族にはローンの問題が重くのしかかってきます(注12)。
それで浩介は、克明が自己破産するしかないと言うものの(注13)、ただそうなると、次男・俊平が大学をやめて克明のところで働くという計画もご破算になってしまうのではないでしょうか?
他にも、母親・玲子の病気について、脳腫瘍か悪性リンパ腫かで皆が一喜一憂する感じです。確かに、脳腫瘍ならば自宅かホスピスで死を待つほかありませんが(注14)、悪性リンパ腫の場合には治療を受けることができるので、当面を凌げることにはなります。でも、悪性リンパ腫はやはり癌であり、事態が深刻なことはそれほど変わりがないように思えるのですが?
しかしながら、これらのことは、本作の原作が原作者の実体験に基づいて書かれていること(注15)から一蹴されてしまうでしょうし、さらに、本作では、ウケ狙いの演技は極力抑えられていて、登場人物が皆ごく自然に振舞っているように見えますから、その意味でもリアルな作品といえるでしょう。
(3)渡まち子氏は、「母の余命宣言で揺れる家族の本音と再生を描く「ぼくたちの家族」。難病ものなのに湿っぽさがないところがいい」として65点をつけています。
相木悟氏は、「時代と共に移りかわる家族の在り方。そこに静かに一石を投じる良作の登場である」と述べています。
(注1)「さとう」のメンチカツや「おざさ」の羊羹やモナカを求めて行列が作られる広場などが映し出されています。
(注2)でも、そこで玲子が耳にしたハワイについては、本作全編にわたって様々に取り上げられます(玲子が、フラダンスの手つきをしたり、一度くらいハワイへ行きたかったと言ったりするなど)。
(注3)実際の駅は、劇場用パンフレットの「Production Note」によれば「四方津」。
なお、この記事が参考になります。
(注4)この記事が参考になるでしょう。
(注5)浩介の妻の名前を間違って言ったりするのです。
(注6)本作に出演している俳優の内、最近では、妻夫木聡は『小さいおうち』、原田美枝子は『ミロクローゼ』、池松壮亮は『横道世之介』でそれぞれ見ています。
(注7)「三好」の住宅街を眺め下ろせる小高い山の上で、浩介は「いろいろあるけど、まずはお母さんを助けよう。俺、悪あがきしてみるよ」と俊平に言います。そして二人は、母親・玲子を受け入れてくれる病院探しに奔走するのです(この拙エントリの(3)も参照して下さい)。
なお、本作を浩介と俊平の物語と見れば、この拙エントリの(3)で触れました「2人組」という枠組みからも捉えることができるかもしれません。
(注8)これまでの石井監督の作品では、例えば、『あぜ道のダンディ』における「兎のダンス」を踊るシーンとか、『ハラがコレなんで』における不発弾が爆発するシーンなど(『舟を編む』は、作品全体がファンタジーではないでしょうか?)。
強いて言えば、本作においては、その日のラッキーカラーの黄色とラッキーナンバーの8を星座占いで耳にした俊平が、「黄色」の上着を着て病院に行き、受付番号88を引き当てて医者に面会すると、玲子の治療の可能性を言われる場面が描かれていますが、これが相当するのではないかと思われます。
(注9)このサイトの記事によれば、通勤特別快速で四方津から新宿まで73分(八王子まで25分)。
(注10)克明は、玲子が入院した晩、病院から浩介や俊平と一緒に帰宅しようとして、「今夜はオヤジが付き合って」とたしなめられたり、頻繁に病院から電話をかけてきたりします(それも、「母さんがタバコを吸いたいと言っているが、どうしよう?」といったくだらない内容のもの)。
この父親には、石井裕也監督作品でお目にかかることの多い“ダメ男”に通じるものが見られます〔この拙エントリの(3)をご覧ください〕。
(注11)ごくつまらないことを申し上げれば、父親・克明は、浩介と俊平をジョギングに連れ出します。息子から「いつから始めたの?」と訊かれると「おととい」と答えますが、普通、ジョギングを始めたばかりでは(特に、克明位の年齢になると)、酷い筋肉痛に悩まされ、そうは簡単に続けられないのではないでしょうか?まして、「三好」は坂道の多い街でしょうから、なかなか大変だと思われます。
とはいえ、息子たちの頑張りを目にし、心境の変化をきたした克明を描き出すためには説得力あるシーンだと思います。
(注12)その内訳は、父親・克明が言うところによれば家と会社のを合わせると6,500万円、それに次男・俊平が調べて母親・玲子に300万円のサラ金ローンがあることがわかります。
(注13)自己破産すれば、家のローンの1,200万円が連帯保証人の浩介にかぶさることになる(バブル期の高い金利からその後の安い金利に借り換えた時に、浩介は連帯保証人を求められたため)、と克明はその難しさを説明します。
確かにそうかもしれませんが、家のローンの場合、住宅ローンを組んだ金融機関が1番抵当権を持っているでしょうから(会社の借金の抵当にも入っているとはいえ)、「三好」の家を売却することによって、むろんバブル期ほどの高額にはならないものの、かなりの程度債務額は減額されるのではと思われます。
(注14)Wikipedia の脳腫瘍のところでは、「医学の発達にもかかわらず生命予後の改善は芳しくな」いとか「日本国外では考え方や医療制度の関係もあって、悪性腫瘍という診断がついた時点で、積極的治療を断念するのが主流のようである」とされています。
(注15)原作は、早見和真著『ぼくたちの家族』(未読)。
そして、原作についてのWikipediaの記事に、「著者の早見和真が自らの実体験を元に描いた作品」とあります。
★★★★☆☆
象のロケット:ぼくたちの家族
(1)『舟を編む』を制作した石井裕也監督の作品ということで映画館に行ってきました。
映画の冒頭は、吉祥寺(注1)の喫茶店で友人と話をしている主婦・玲子(原田美枝子)。とはいえなんだか上の空で、友人の話を満足に聞いていない感じです(注2)。

会合が終わって中央線に乗って家に帰りますが、だいぶ西に向かい、車窓から中央高速が見えますから山梨県に入ってしまっています。
着いた駅は「三好」(注3)、駅からしばらく歩くと住宅街が一帯に広がっています。
多分、バブル期にここに家を求めたのでしょう(注4)。
少しすると、家の主・克明(長塚京三)が戻ってきます。「駅に迎えに来ていなかったじゃないか?食事は?」と、暗い中でぼんやり座り込んでいる妻に尋ねると、玲子は「ごめんなさい、忘れちゃった」と答え、慌てて支度に取り掛かります。
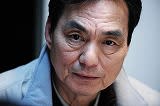
それから、長男・浩介(妻夫木聡)に子供が出来たということで、長男の妻・深雪(黒川芽以)の両親たちと一緒に食事会が行われます。ただ、その席で玲子は酷くおかしなことを言い出します(注5)。
そんなこんなで、克明は浩介と一緒に玲子を病院に連れて行ったところ、医師は、脳腫瘍が7つ見つかり(なかにはピンポン球くらいのものも)、「ここ1週間が山になる」と宣告します。
さあ大変です。この事態に対して、長男・浩介は、頼りにならない父親・克明や次男の俊平(池松壮亮)と一緒になって対処しようとするところ、果たしてうまくいくのでしょうか、………?


実に典型的な中流家庭が取り上げられ、一つ一つはありふれている出来事をいくつもその家族に集中的に生じさせたらどうなるか、という視点から作られている感じの映画ながら、石井監督の映画作りのうまさと、出演俳優の巧みな演技が融合して(注6)、最後まで画面に見入ってしまいます。
(2)これまでの石井裕也監督の作品との関連で言えば、お馴染みの“とにかく頑張っていこう”の精神が、本作でも描かれていることは間違いありません(注7)。
ただ、従来、何かしら顔を出していたファンタジー的な要素が殆ど見られないために(注8)、そのぶんだけ一層リアルさということが浮かび上がってくるように思われます。
ですが、そんなにリアルかというと、少々疑問に思える点もないではありません。
例えば、浩介の両親が住んでいる場所の「三好」です。確かに、バブル期には東京のベッドタウンが小仏峠を越えて山梨県にまで延びたものの、都心からだと通勤に相当の時間を要するのは間違いないでしょう(注9)。
父親・克明の会社の所在地がはっきりしないので何とも言えないとはいえ、会社に何が起こるかわかりませんから、いやしくも経営者であるならば、そんな遠隔地ではなくとにかく会社の近辺に家を持つのが常識ではないでしょうか?
また、父親・克明は、妻・玲子の入院に際しても長男・浩介に頼りきりで、ダメな父親振りを発揮しています(注10)。とはいえ、定年間際の窓際族でもなく、思わしくない企業とはいえその経営者なのですから、普通であれば、問題に対して逃げるのではなく、自分が率先して乗り出して解決しようとするのではないでしょうか(注11)?
さらに、下記の(3)で触れる渡まち子氏が「母の治療に奔走する姿よりも、金銭面でのゴタゴタの方が印象に残ってしまう」と言うように、この家族にはローンの問題が重くのしかかってきます(注12)。
それで浩介は、克明が自己破産するしかないと言うものの(注13)、ただそうなると、次男・俊平が大学をやめて克明のところで働くという計画もご破算になってしまうのではないでしょうか?
他にも、母親・玲子の病気について、脳腫瘍か悪性リンパ腫かで皆が一喜一憂する感じです。確かに、脳腫瘍ならば自宅かホスピスで死を待つほかありませんが(注14)、悪性リンパ腫の場合には治療を受けることができるので、当面を凌げることにはなります。でも、悪性リンパ腫はやはり癌であり、事態が深刻なことはそれほど変わりがないように思えるのですが?
しかしながら、これらのことは、本作の原作が原作者の実体験に基づいて書かれていること(注15)から一蹴されてしまうでしょうし、さらに、本作では、ウケ狙いの演技は極力抑えられていて、登場人物が皆ごく自然に振舞っているように見えますから、その意味でもリアルな作品といえるでしょう。
(3)渡まち子氏は、「母の余命宣言で揺れる家族の本音と再生を描く「ぼくたちの家族」。難病ものなのに湿っぽさがないところがいい」として65点をつけています。
相木悟氏は、「時代と共に移りかわる家族の在り方。そこに静かに一石を投じる良作の登場である」と述べています。
(注1)「さとう」のメンチカツや「おざさ」の羊羹やモナカを求めて行列が作られる広場などが映し出されています。
(注2)でも、そこで玲子が耳にしたハワイについては、本作全編にわたって様々に取り上げられます(玲子が、フラダンスの手つきをしたり、一度くらいハワイへ行きたかったと言ったりするなど)。
(注3)実際の駅は、劇場用パンフレットの「Production Note」によれば「四方津」。
なお、この記事が参考になります。
(注4)この記事が参考になるでしょう。
(注5)浩介の妻の名前を間違って言ったりするのです。
(注6)本作に出演している俳優の内、最近では、妻夫木聡は『小さいおうち』、原田美枝子は『ミロクローゼ』、池松壮亮は『横道世之介』でそれぞれ見ています。
(注7)「三好」の住宅街を眺め下ろせる小高い山の上で、浩介は「いろいろあるけど、まずはお母さんを助けよう。俺、悪あがきしてみるよ」と俊平に言います。そして二人は、母親・玲子を受け入れてくれる病院探しに奔走するのです(この拙エントリの(3)も参照して下さい)。
なお、本作を浩介と俊平の物語と見れば、この拙エントリの(3)で触れました「2人組」という枠組みからも捉えることができるかもしれません。
(注8)これまでの石井監督の作品では、例えば、『あぜ道のダンディ』における「兎のダンス」を踊るシーンとか、『ハラがコレなんで』における不発弾が爆発するシーンなど(『舟を編む』は、作品全体がファンタジーではないでしょうか?)。
強いて言えば、本作においては、その日のラッキーカラーの黄色とラッキーナンバーの8を星座占いで耳にした俊平が、「黄色」の上着を着て病院に行き、受付番号88を引き当てて医者に面会すると、玲子の治療の可能性を言われる場面が描かれていますが、これが相当するのではないかと思われます。
(注9)このサイトの記事によれば、通勤特別快速で四方津から新宿まで73分(八王子まで25分)。
(注10)克明は、玲子が入院した晩、病院から浩介や俊平と一緒に帰宅しようとして、「今夜はオヤジが付き合って」とたしなめられたり、頻繁に病院から電話をかけてきたりします(それも、「母さんがタバコを吸いたいと言っているが、どうしよう?」といったくだらない内容のもの)。
この父親には、石井裕也監督作品でお目にかかることの多い“ダメ男”に通じるものが見られます〔この拙エントリの(3)をご覧ください〕。
(注11)ごくつまらないことを申し上げれば、父親・克明は、浩介と俊平をジョギングに連れ出します。息子から「いつから始めたの?」と訊かれると「おととい」と答えますが、普通、ジョギングを始めたばかりでは(特に、克明位の年齢になると)、酷い筋肉痛に悩まされ、そうは簡単に続けられないのではないでしょうか?まして、「三好」は坂道の多い街でしょうから、なかなか大変だと思われます。
とはいえ、息子たちの頑張りを目にし、心境の変化をきたした克明を描き出すためには説得力あるシーンだと思います。
(注12)その内訳は、父親・克明が言うところによれば家と会社のを合わせると6,500万円、それに次男・俊平が調べて母親・玲子に300万円のサラ金ローンがあることがわかります。
(注13)自己破産すれば、家のローンの1,200万円が連帯保証人の浩介にかぶさることになる(バブル期の高い金利からその後の安い金利に借り換えた時に、浩介は連帯保証人を求められたため)、と克明はその難しさを説明します。
確かにそうかもしれませんが、家のローンの場合、住宅ローンを組んだ金融機関が1番抵当権を持っているでしょうから(会社の借金の抵当にも入っているとはいえ)、「三好」の家を売却することによって、むろんバブル期ほどの高額にはならないものの、かなりの程度債務額は減額されるのではと思われます。
(注14)Wikipedia の脳腫瘍のところでは、「医学の発達にもかかわらず生命予後の改善は芳しくな」いとか「日本国外では考え方や医療制度の関係もあって、悪性腫瘍という診断がついた時点で、積極的治療を断念するのが主流のようである」とされています。
(注15)原作は、早見和真著『ぼくたちの家族』(未読)。
そして、原作についてのWikipediaの記事に、「著者の早見和真が自らの実体験を元に描いた作品」とあります。
★★★★☆☆
象のロケット:ぼくたちの家族




















いつも僕は極めて些細なことに引っかかります。そんなこと“まで”…下らない。と考えるのが普通でしょうが僕に言わせれば、そんなこと“ぐらい”ちゃんとしろ、です。
例えば冒頭のカフェのシーン。友人2人はケーキを3つ以上注文しています。しかし玲子は飲み物だけ。もちろんダイエットとか借金がかさんでいるからとか理由付けはできるし、そこまで考えての表現なら見事と言うべきかもしれないが、いかにも不自然。
そして相手の1人がハワイ旅行のみやげでチョコレートをくれます。まあハワイ(以外でも)定番のみやげですが、手提げ袋に入っている。これも絶対ないとは言えないが、普通ならデューティ・フリーのビニール袋のはず。何人分の土産を買ったか知らないが、それぞれに1つの紙袋なんて、特に依頼しないとありえないこと。
これもみやげがハワイのチョコレートだと示すためのパッケージだろうが。
このトップシーンで僕は“ダメだな”と感じます。以下は書かないが、このような些細で“不自然”なことが続きます。
そして何より(事実に基づくなら仕方ないが)、余命一週間という驚くべき設定。
もちろん映画がそう展開するようにセカンド・オピニオンを求めて複数の医者に当たったり金の工面などの“家庭の事情”が描かれるわけだが、普通なら処置なしの1週間なら“せめてハワイに連れて行こう”(実際にはパスポートがなければ1週間ではむりだが)
とか“残された時間”を大切にしようとするはず。あるいは逆に葬儀などの手配とか?
長男夫婦の関係や背景は明確ではないは“余命一週間”という緊急事態なのに“たいしたことなかった”などと病状を隠す理由が分からない。
そして4日目だったかに医者は“家で最後を”と退院させるが“処置なし”なら最初から検査が終われば退院させるはず。しかも家には(わが家もレンタルしているが)介護用のベッドが用意されている。数日の命なら借りるとは思えない。
つまり“家庭の事情”を描く映画なら、せめて余命1ヶ月程度に設定しないと何もかもが不自然に思える…
さすがに「milou」さんは、クマネズミには及びもつかないような鋭さで映画をご覧になっていると感心いたしました。例えば、クマネズミにとって、トップシーンは、よく行く吉祥寺だなということだけが重要で、細かなことはどうでも良くなってしまいます。
ただ、「余命一週間という驚くべき設定」の件ですが、もしかしたら、玲子が認知症的な症状を呈していること、ステロイドの投与といった治療がなされていることとか、突然の発病・入院で家族が動転したこと(治療費をどう捻出するのかなど慌てふためきます)などもあって、「処置なしの1週間なら“せめてハワイに連れて行こう”」などといった「普通」のことは、浩介らの念頭にとても浮かばなかったのではないでしょうか(あるいは、「病状を隠」したのも、判断力が低下している玲子の病状を見てそうしたのかもしれません。原作では、高輪台病院での手術の後に玲子に克明が告知していますが)?
確かに、「介護用のベッド」が三好の家に置かれているのはなぜなのかよく理解できないところです(それも、わざわざ浩介が購入したような感じでした)。でも、あるいは、浩介は、いくらなんでも「余命一週間」ということはないだろうと思い(「まずはお母さんを助けよう」と決意したことの現われなのかもしれません)、転院先が見つからない間はそのベッドを使おうと思ったのかもしれません(原作によれば、高輪台病院での手術の後2週間して日本がんセンターに転院しています)。
全体としては、「余命一週間という驚くべき設定」にしたからこそ、かえって「“家庭の事情”」が凝縮されて巧く描き出されているのではないか、とクマネズミは思っています(事実に基づく原作に依りながら映画は作られていますが、仮にそうしたものがなくとも、本作はリアルなものとして見る者に迫ってくるのではないかと思っています)。
それはいいのだが、最初に病院に行くときも当然“車”で行く。車の知識はないがコンパクトカーではなく(社長だし?)3ナンバーだろう。何分ぐらい映ったか覚えていないが会話もそこそこあるし少なくとも5キロぐらいはありそう。
そして父親は病院にそのまま泊まるが病室は3人か6人の大部屋。いったいどこに泊まるのか(転院先は立派な個室だが)。
以後“車”が出てこない。中華料理店でもビールを3本飲んでいるし当然車じゃないが兄弟が病院から帰るときも夜道の坂道を歩いて降りる。バスだとしても恐らく最終より遅い時間だろうがバス停なら絶対病院前にあるはずだしタクシーでも病院前から乗るはず。まさか家まで歩くつもり?
つまり、このようなシーンは“リアル”さではなく、しばしば監督が“絵”として夜道を歩く兄弟を入れたい、とかの思いで入れるこだわりだろうし、そう見るべきだとは分かっているのだが、やはり見ているときに違和感を感じると興ざめしてしまう。
ただ、大雑把なクマネズミとしては、「milou」さんが挙げられている点についても「違和感」を覚えませんでした。
それに、病院の大部屋での付き添いは、例えば下記の記事を見ると、今でも行われている事例がないわけでもなさそうです(昔は普通に、付添婦や家政婦が大部屋で付き添っていました)。
http://www4.ocn.ne.jp/~tanasho/jirei.html(事例19)
http://ameblo.jp/haru110410/entry-11019064452.html
また、車については、玲子の入院後、車庫入れの際(?)にぶつけてしまったと克明が言っていましたから、使用できなくなっているのではないでしょうか?
さらに、玲子が当初入院する“三好市立中央病院”が、自宅からそれほど遠くないところに位置するもの(入院に際しては車を使うにしても、歩いて自宅に戻れるくらいの距離)と想定されているのではないでしょうか?ただし、実際の上野原市立病院は、四方津から随分と離れていますが。