先月末、陽気 に誘われて、御徒町界隈を散歩
に誘われて、御徒町界隈を散歩 してきましたので、遅まきながら、そのお話を。
してきましたので、遅まきながら、そのお話を。
この散歩の目的地は2つ ありまして、一つは梅が盛りの湯島天神、もう一つは、わが故郷と縁の深い久保田(秋田)藩の上屋敷跡でした。
ありまして、一つは梅が盛りの湯島天神、もう一つは、わが故郷と縁の深い久保田(秋田)藩の上屋敷跡でした。
途中、昼食を摂る店を求めて寄り道しましたが、基本的に、JR御徒町駅から春日通りを西へ東へと歩きました。

まずは、西に向かって、2年ぶりの湯島天神へ。
ちょうど見頃を迎えていた梅がきれいだし、香りが楽しい

女坂を上って行くと、ほんとに目の前 で咲いていてしっかりと愛でられます
で咲いていてしっかりと愛でられます
ちょうど梅と受験のシーズンだけに、境内はかなりの賑わいでした。
拝殿の前にはズラリ と行列ができていて、とりあえず切実な願い事の無い私は、今回は参拝をパスしました
と行列ができていて、とりあえず切実な願い事の無い私は、今回は参拝をパスしました

2年前に参拝&梅見物したときは、猿まわしも楽しんだのですが、今回はちょうど休憩時間 に入ったばかりだったらしく、トレーナーさん(?)と手を繋いで退場していくお猿さん
に入ったばかりだったらしく、トレーナーさん(?)と手を繋いで退場していくお猿さん の後ろ姿だけを見かけました。
の後ろ姿だけを見かけました。
せっかくですので(?)、2年前に見たお猿さん(りきクン)の竹馬ジャンプ(幅跳び)の写真を載っけておきます。

湯島天神の社殿は、1995年に改築された新しい建物で、それだけに、きらびやかで壮麗 です
です

拝殿の後ろに廻って、本殿を拝見。

拝殿と本殿とを弊殿で繋ぐ典型的な「権現造り」ですな

湯島天神はこの辺で切り上げ、帰りは男坂を下り、春日通りを今度は東へと歩きました。
時刻はちょうど昼時で、久しぶりに上野の天ぷら屋さんに行ってみることにしました。
中央通りとの交差点で左折し、さらに「この辺りだったはず」と小路に左折して進むと、お目当ての天ぷら屋さんがあったのですが、、、、、なんと休業 定休日ではなく、「予定していた臨時休業」だったみたい
定休日ではなく、「予定していた臨時休業」だったみたい
まぁ、上野にはしょっちゅう出かけているし、また機会はあるでしょう
そして、上野~アメ横~御徒町界隈では食事をする場所に困りません。っつうか、平日の昼間に酒 をかっくらっていても「普通」に見える街です。
をかっくらっていても「普通」に見える街です。
で、私にとって2度目になる某焼肉店でランチ をいただきました。
をいただきました。

かつて私がよく行っていた別の焼肉店(この界隈には焼肉店が多い)は、いつのまにやらずいぶん高くなってしまい 、そこにはちょっと行きづらくなってしまいました
、そこにはちょっと行きづらくなってしまいました
それはさておき、昼食を終えた私は再び春日通りに戻り、東へ…。

昭和通りを横断し、ちょっと行ったあたりのカフェで、食後の一服

 そして、スマホに入れてある「大江戸今昔めぐり」というアプリで、現在地と目的地をチェックしました。
そして、スマホに入れてある「大江戸今昔めぐり」というアプリで、現在地と目的地をチェックしました。
このアプリは、現代の地図に、江戸時代の古地図をオーバーラップさせて表示できるもので、東京を街歩きするときには楽しませていただいています。
さて、私がコーヒーブレイク をとった店は、福岡・柳川藩の上屋敷跡の正面で、目的地にしていた久保田藩上屋敷跡までは至近
をとった店は、福岡・柳川藩の上屋敷跡の正面で、目的地にしていた久保田藩上屋敷跡までは至近 の地点でした
の地点でした
ところで、江戸切絵図のルールとして、家名の上に当たる部分が正門のある側で、柳川藩邸の正門は現在の春日通りに、久保田藩邸の正門は現在の清洲橋通りを向いていたことが判ります。
一息入れた後、久保田藩邸跡を反時計回り にほぼ一周しました。
にほぼ一周しました。
当然ながら、江戸時代の雰囲気を今に伝えるものはほとんど無く、「佐竹」に由来する地名と町会の名前(と後で紹介する商店街)程度のものでした。

それにしても「平成小学校」 だなんて、地域性の欠片も無い
だなんて、地域性の欠片も無い
ちなみに公園の名前は「竹町公園」でした。

竹町公園には新幹線 を模した遊具(ロッキング遊具)がありまして、その一つが「こまち」型でした。
を模した遊具(ロッキング遊具)がありまして、その一つが「こまち」型でした。
現在なら、ここからほど近い上野駅から秋田新幹線「こまち」に乗れば4時間弱 で秋田に到着するのですが、江戸時代には、3週間近く
で秋田に到着するのですが、江戸時代には、3週間近く を要して江戸⇔秋田を移動していたらしい
を要して江戸⇔秋田を移動していたらしい 陸路だけですから、それは大変だったろうなと思います。
陸路だけですから、それは大変だったろうなと思います。
ちなみに、別邸 の近くには、江戸に出立する久保田藩主御一行と国許に残る藩士たちが別れのお茶
の近くには、江戸に出立する久保田藩主御一行と国許に残る藩士たちが別れのお茶 を飲んだという謂れの橋があります。
を飲んだという謂れの橋があります。
さて、上に載せた「大江戸今昔めぐり」の画像の右下に「三味線堀」という風流な名前の堀が描かれています。
その形が三味線に似ているから、というのが名前の由来だそうですが(三味線よりも八分音符 に似てる)、既に埋め立てられていて、現在は、都営アパートの建て替えが行われていました。
に似てる)、既に埋め立てられていて、現在は、都営アパートの建て替えが行われていました。

この写真は久保田藩邸跡の南東角から撮ったもので、この交差点近くにその名も「佐竹町商店街」の南端があって、その入口には、台東区教育委員会による説明板がありました。

この一部を転記します。
佐竹家上屋敷の当地開設年代は、『武鑑』からみて、元禄2年(1689)もしくは翌3年と考えられる。屋敷地は広大で、現在の台東3・4丁目東半分にわたっていた。
佐竹家八代藩主佐竹義敦(よしあつ・号曙山)は、日本初の本格的西洋医学書の翻訳書『解体新書』(安永3年[1774]刊)付図を描いた藩士小田野直武らとともに、洋風画の一派「秋田蘭画」の基礎を築いた。また天明年間(1781~1789)の狂歌師手柄岡持も藩士であり、当時の文化人がここを中心に活躍していたことがうかがわれる。
ここに登場する「手柄岡持(てがらのおかもち)」なる狂歌師、本名は「平沢常富」、ペンネームは「朋誠堂喜三二」。
 そう、大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」のオープニングロールで、ほぼ毎回、
そう、大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」のオープニングロールで、ほぼ毎回、
平沢常富 尾美としのり
とクレジットされるのに、番組が終わると「あれ? 出てた?」「尾美としのりを探せ 」と話題になっている御仁
」と話題になっている御仁 です。私もリアタイ視聴では一度も見つけていません
です。私もリアタイ視聴では一度も見つけていません
番組の「登場人物紹介」では、
のちに蔦重にとって最高かつ最大の協力者となる戯作者。
とありますので、いつ、画面に堂々 と登場するのか、また、蔦重とどんな絡みを見せてくれるのか、楽しみです
と登場するのか、また、蔦重とどんな絡みを見せてくれるのか、楽しみです

 説明板を読んだ後、私は佐竹商店街に足を踏み入れました。
説明板を読んだ後、私は佐竹商店街に足を踏み入れました。
なんでも、この商店街は、金沢の片町商店街(私が今愛用している九谷焼の飯茶わんは、去年、片町商店街にある陶磁器店で買ってきた)に次いで、日本で二番目に古い(組合組織が結成された)商店街だそうな。
アーケードには、
 何でも揃う お買い物は商店街で
何でも揃う お買い物は商店街で
というバナーが掲げられていましたが、なかなかのさびれっぷりで、仕舞た屋のなんと多いこと
「何でも揃う」は盛り過ぎだろ と思ってしまいました。
と思ってしまいました。
ところで、佐竹商店街のシンボルマークは、「竹に留まったフクロウ」です。
こちらのサイトによると、
この地は、秋田の佐竹藩の上屋敷跡で、藩内に学校があったことから、知恵の神ふくろうを商標にしようということになった。
皆で足立美術館を訪れた時、横山大観の竹に止まったみみずくの絵を見て、竹にすずめではなく、みみずくもありだと思い、竹に止まるふくろうのデザインにしたとのこと!
だとありますが、「横山大観の竹に止まったみみずくの絵」は、横山大観記念館所蔵の作品とか福岡市美術館所蔵の作品とか何点かあるみたいですな。
と、こんな胸像がありました。
 暖かそうなマフラーをしてもらっています
暖かそうなマフラーをしてもらっています
で、銘板には「吉田太郎吉翁像」とありますが、吉田太郎吉さんって誰??
調べたところ、テレ東のサイトに行き着きました。
去年8月放送の「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ!」で佐竹商店街を採り上げたのだそうで、その紹介サイトで、
明治時代に「吉田商店」として創業し、80年ほど前に呉服屋を開店。その後、隣で家電店やピザ店を営業し、今は店が一階に入るマンションに建て替え中です。
という記述につづいて、
初代・太郎吉は不動産業なども営み、区議まで務めた名士ということで、(以下略)
とな。
でも知らんなぁ~
こんなことで(途中、竹町公園のトイレ を使った
を使った ) 久保田藩上屋敷跡の散策を終了
) 久保田藩上屋敷跡の散策を終了
JR御徒駅まで戻り、自宅に帰りました。
今後は、久保田藩の中屋敷・下屋敷の跡にも行ってみよう
と思い立ったのですが、そういえば、京都や大阪(大坂)にも藩邸があったはずだよな
Wikipediaによれば、
大坂布屋町に大坂藩邸、京都柳馬場通四条上ルに京都藩邸を持つ。
だとか。
こんど調べてみます。
 です。
です。 を持って行きつけの皮膚科クリニックで診察を受けたところ、患部の皮膚が再生しているし、「陥没」もだいぶ回復してきたということで、先生から「治療終了
を持って行きつけの皮膚科クリニックで診察を受けたところ、患部の皮膚が再生しているし、「陥没」もだいぶ回復してきたということで、先生から「治療終了 」の宣言をいただきました
」の宣言をいただきました
 」でなんとも気分が爽快になりました
」でなんとも気分が爽快になりました が脳天を貫いたのには参りました
が脳天を貫いたのには参りました
 、3か月ほどシャワーで我慢したことでした。
、3か月ほどシャワーで我慢したことでした。 は、浴室も脱衣所もめちゃくちゃ寒くて大変でした。あらかじめシャワーを誰もいない浴室で流して、ある程度室温が上がったところでシャワーを浴びるのですが、それでも寒いったらありゃしない
は、浴室も脱衣所もめちゃくちゃ寒くて大変でした。あらかじめシャワーを誰もいない浴室で流して、ある程度室温が上がったところでシャワーを浴びるのですが、それでも寒いったらありゃしない
 の使用量が一気が増えて
の使用量が一気が増えて 、検針の係員さん
、検針の係員さん から「異常に使用量が多いのですが、なにかありましたか?」と尋ねられる始末
から「異常に使用量が多いのですが、なにかありましたか?」と尋ねられる始末
 、しかも今度は咳が出て喉が痛い
、しかも今度は咳が出て喉が痛い
 と行きつけの内科クリニックに行き検査してもらったところ、幸いにも「ただの風邪」で一安心でした。
と行きつけの内科クリニックに行き検査してもらったところ、幸いにも「ただの風邪」で一安心でした。
 を完食さえできませんでした
を完食さえできませんでした
 は2月末まで続きました。
は2月末まで続きました。
 に改善する
に改善する のだと知ったことです。
のだと知ったことです。 は発症前のレベルに「復帰」しています
は発症前のレベルに「復帰」しています
 です。
です。





















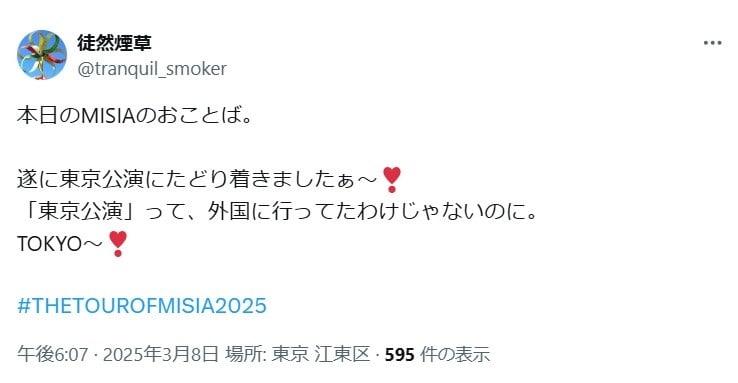



 を
を を振る
を振る 」
」 は、アリーナの
は、アリーナの 判ったのは、
判ったのは、




 を測る
を測る
 と、ペンライトをバッグに収めました。
と、ペンライトをバッグに収めました。
 ってヤツ
ってヤツ


 してきましたので、遅まきながら、そのお話を。
してきましたので、遅まきながら、そのお話を。










 をかっくらっていても
をかっくらっていても をいただきました。
をいただきました。









 に似てる)、既に埋め立てられていて、現在は、
に似てる)、既に埋め立てられていて、現在は、

 そう、
そう、

 と思ってしまいました。
と思ってしまいました。
 を使った
を使った



