「今年最初の関西旅行記 #2-4」のつづきです。
 大阪市立東洋陶磁美術館では、特別展「中国陶磁・至宝の饗艶」が開催中です。
大阪市立東洋陶磁美術館では、特別展「中国陶磁・至宝の饗艶」が開催中です。
2024年、大阪市と上海市の友好都市提携50周年を記念し、上海博物館から日本初公開作品32件(うち海外初公開19件)を含む計50件の中国陶磁の名品が出品されます。中国陶磁の世界的な殿堂である上海博物館と大阪市立東洋陶磁美術館の至極のコレクションが一堂に会し、「競艶(きょうえん)」することで、悠久の歴史を誇る中国陶磁の真髄に触れるとともに、現在においても斬新さや新たな美の発見をもたらすその魅力に迫る機会となれば幸いです。
私は、20年ほど前に出張で上海に行ったとき、上海博物館を見物したような気がするのですが、建物が青銅器でよく見る「鼎」のような形をしていたということ以外、記憶がさっぱりと飛んでいます
それはともかく、会期が 5か月以上と長い長い…
陶磁器展ならではですな 日本画や浮世絵版画だと到底無理な話です。
日本画や浮世絵版画だと到底無理な話です。
さて、「#2-3」で、中国では「時代遅れの遺物」と見なされた天目茶碗が日本にやって来た話を書きましたが、上海博物館所蔵の天目茶碗が出陳されていました。
茶碗の内側が何やら変色している、、、と思ったら、
黒釉木葉文茶碗(木葉天目) 南宋時代(1127-1279/吉州窯
南宋時代の吉州窯では鼈甲を彷彿とさせる玳皮(たいひ)天目をはじめとした建窯産天目とは異なる茶碗が生産された。吉州には禅宗寺院が数多くあり、禅に通じるとされた桑の葉を用いたこうした木葉天目は、禅僧の需要と美意識を反映したものである。
葉っぱを載せて焼き上げたのか
安宅コレクションにも木葉天目があって、こちらはもっと桑の葉が葉脈まできれいに残って、鮮やかでした。
こちらも南宋時代の吉州窯産で、加賀・前田家伝来の品とか。

自然採光 展示室(第10室)には、大阪市立東洋陶磁美術館が所蔵する2点の国宝
展示室(第10室)には、大阪市立東洋陶磁美術館が所蔵する2点の国宝 のもう一つ「飛青磁 花生(はないけ)」が展示されていました。
のもう一つ「飛青磁 花生(はないけ)」が展示されていました。
 飛青磁 花生 元時代・14世紀/龍泉窯
飛青磁 花生 元時代・14世紀/龍泉窯
鉄斑を散らした青磁は、日本では「飛青磁」と呼ばれている。優美な形のこうした瓶は中国では「珠壺春(ぎょっこしゅん)」の名で知られ、主として酒器として用いられたが、日本では花器としてとして珍重された。本作は鴻池家伝来品であり、伝世する飛青磁の最高傑作といえる。
私はあまり好みではありませんが(あやうく見落とすところだった )、園芸で斑入りの葉っぱを珍重するようなものなのでしょうねぇ
)、園芸で斑入りの葉っぱを珍重するようなものなのでしょうねぇ
ところで、大阪市立東洋陶磁美術館ご自慢の一つ「自然採光展示」は、
陶磁器はさまざまに光を反射し、また光の質によって見え方も大きく影響されるので、照明にはたいへん気を使います。当館には、展示ケースのなかに天窓から自然光をとりこんだ世界初、そして世界唯一の自然採光展示室があり、陶磁器本来の色合いと質感を鑑賞することができます。
だそうです。
私が行った日は陽光燦燦 の良い天気でしたが、曇天
の良い天気でしたが、曇天 や雨天
や雨天 だとどのように見えるんだろ?
だとどのように見えるんだろ?

中国の陶磁器の窯でまず思い浮かぶ、というか、ほぼこれしか知らない窯は景徳鎮です。
この特別展では、普段は上海と大阪に分かれて所蔵されている景徳鎮産の陶磁器が一堂に会していました。
私が「いいなぁ~ 」と思った作品をいくつか紹介します。
」と思った作品をいくつか紹介します。
まず、景徳鎮といえば白磁の染付のイメージですが、、、
意表をついて青磁です
青磁暗花蓮唐草文碗 明時代・正統~天順(1436-1464)/景徳鎮窯
上海博物館
全体に淡い青磁釉が施され、釉下の浅い陰刻(「暗花」)による文様は釉がたまり濃く発色している。永楽・宣徳期の景徳鎮官窯ではすでに龍泉窯風の青磁も生産しており、正統から天順期にも引き続き造られていたことが2014年の景徳鎮珠山明代御窯遺址の発掘で明らかになった。
色の美しさもさることながら、形がイイ 口縁に無限に感じる、なんて言ったら盛り過ぎかも知れませんが…
口縁に無限に感じる、なんて言ったら盛り過ぎかも知れませんが…
次は「景徳鎮らしい」と私は思うこちら。
 この「青花蓮唐草文壺」(上海博物館蔵)は「青磁暗花蓮唐草文碗」と同じ明の正統~天順年間だそうな。
この「青花蓮唐草文壺」(上海博物館蔵)は「青磁暗花蓮唐草文碗」と同じ明の正統~天順年間だそうな。
堂々としていて、ちょっと肩を張った形もイイし、余白を残しつつ壺の側面全体に蔓を張る唐草もイイ
一方、こちらの皿はシンプルな幾何学模様で(はない )、現代でも普段使いできそうです。
)、現代でも普段使いできそうです。
 青花花卉文盤
青花花卉文盤
明時代・天順~成化(1457-1487)/景徳鎮窯
上海博物館
端正な造形の盤で、見込みには宝相華を中心に、二種の十字状の花卉文が配されている。明の歴代皇帝は仏教も信仰しており、この文様も仏教的なものと思われる。
対称的に、こちらは皇帝専用の文様「五爪の龍」が描かれていて、ちょっと畏れ多い
 青花龍蓮唐草文盤
青花龍蓮唐草文盤
明時代・成化(1465-1487)/景徳鎮窯
上海美術館 一級文物
本作は内面中央に蓮唐草に囲まれた五爪の団龍文、その周囲に団花状の花卉文、さらに外側面には蓮唐草の中をかける二頭の龍が、国産のコバルト顔料により精緻かつ上品に描かれている。
説明にある「蓮唐草の中をかける二頭の龍」は、写真で観るしかなかったのは残念でした。
この作品は「回転台 」に載せて見せていただきたかったな
」に載せて見せていただきたかったな
白磁染付が続きましたので、カラフルな作品も載せます。
五彩百朝鳳図盤 清時代・康煕(1662-1722)/景徳鎮窯
上海博物館 一級文物
梧桐(アオギリ)、牡丹、太湖石、蓮池のある風景の中央に一対の向かい合った鳳凰が描かれている。空には祥雲がたなびき、孔雀、鶴、燕、鷺等の鳥が鳳凰を祝福している。
名君の遺徳を称える「百鳥朝鳳図」は康熙年間に流行し、なかでも本作は景徳鎮民窯の代表作と言える。
いやぁ、なんとも華やかというかにぎやかというか…
なんとなく、伊藤若冲の絵(例えば動植彩絵)と雰囲気が似ているような気がするのは私だけでしょうか?
 「五彩百朝鳳図盤」の説明文の中に「太湖石」ということばが出てきますが、私が故宮(紫禁城)の御花園で観たこの穴ボコボコの変な岩がそれかな?
「五彩百朝鳳図盤」の説明文の中に「太湖石」ということばが出てきますが、私が故宮(紫禁城)の御花園で観たこの穴ボコボコの変な岩がそれかな?
話を戻しまして、更に時代もさかのぼりまして、
釉裏紅四季花卉文瓜形壺
明時代・洪武(1368-1398)/景徳鎮窯
上海博物館
明を建国した太祖・朱元璋、すなわち洪武帝は、赤色を好んだ。
酸化銅による朱紅色の発色を見せる釉裏紅磁器は、景徳鎮では元代にすでに見られるが、明の洪武年間に御用磁器として優品が多く見られる。
朱元璋(洪武帝)は赤色が好きだったと…。
まさか自分の姓・朱に絡めたゲン担ぎだったりして…
仮にそうだとすれば、この壺のような赤い陶磁器を洪武帝の目の前で割ったり欠けさせたりしたら、そうとうにマズいこと になったんだろうな
になったんだろうな
時代が行ったり来たりで申しわけありませんが、清時代の一級文物 です。
です。
 琺瑯彩竹菊鶉図瓶
琺瑯彩竹菊鶉図瓶
清時代・乾隆(1736-1795)/景徳鎮窯
上海博物館 一級文物
雪のように白い白磁胎は、つややかな釉色を見せる。胴部には琺瑯彩で太湖石、竹、菊、鶉、花卉などが緻密で瀟洒な絵付けで表されている。
鶉と菊は「安居楽業」、すなわち人々が平穏に暮らし、楽しく仕事に励む善政の象徴とされる。
この徳利 じゃない
じゃない 、瓶(へい)に入れたら、安酒も美味しくなるかもしれませんな
、瓶(へい)に入れたら、安酒も美味しくなるかもしれませんな
ところで、今さらながらですが、ここまで何点か出てきた「一級文物」、これは、日本でいえば「国宝」に相当する国家による最高のレーティングです。
ふ~ 大阪市立東洋陶磁美術館の見聞録
大阪市立東洋陶磁美術館の見聞録 も残りもうわずか。
も残りもうわずか。
ですが、諸般の事情(文字数が増えるとトラブル が起きがち
が起きがち )により、「#2-6」につづきます。
)により、「#2-6」につづきます。
 つづき:2025/02/07 今年最初の関西旅行記 #2-6
つづき:2025/02/07 今年最初の関西旅行記 #2-6



















 」
」

















 で、私も読みました(別邸にある)。
で、私も読みました(別邸にある)。



















 です。
です。




 やプリンター
やプリンター




 をしてから外に出ました。
をしてから外に出ました。

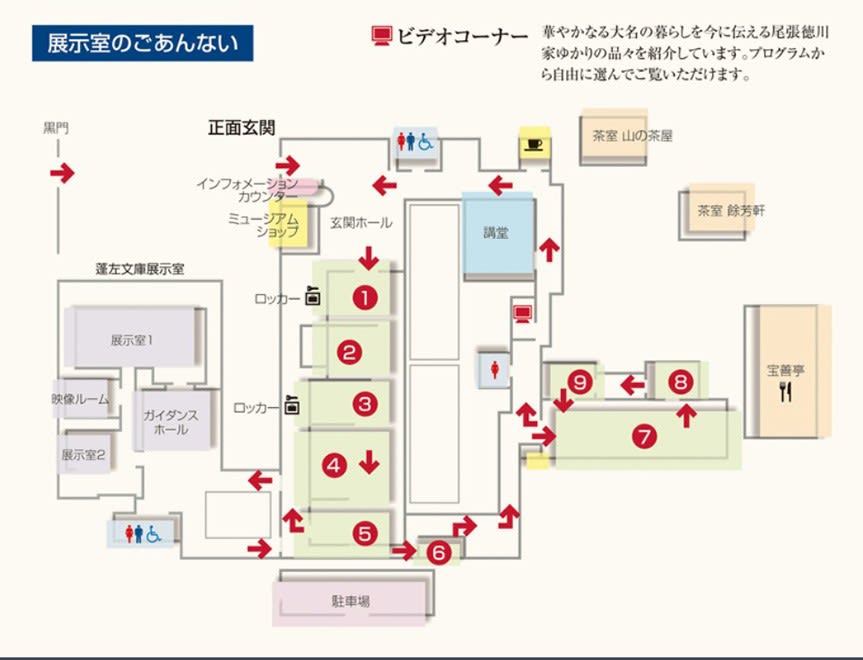




 と待たずにやって来た
と待たずにやって来た



 は何だと思いますか?
は何だと思いますか?
 サイズとしてはこんなものですから…
サイズとしてはこんなものですから…







 を視ていた人にはすっかり
を視ていた人にはすっかり
























 をちょいと過ぎた頃に行動を開始し、まずは名古屋駅へ。
をちょいと過ぎた頃に行動を開始し、まずは名古屋駅へ。








 しますと、
しますと、









 し直して、もう一度載せます。
し直して、もう一度載せます。



 に座る
に座る




 と歩いていくと、、、、
と歩いていくと、、、、
 に乗り込み(鶴岡市散策は約4時間
に乗り込み(鶴岡市散策は約4時間 を食べた経験がありまして、
を食べた経験がありまして、







 と一緒に暮らしていたというわけですな。
と一緒に暮らしていたというわけですな。





