先週のクラウンカップを逃げ切ったスプリングマンの父はローズキングダムです。
父はキングカメハメハ。母は2001年にフィリーズレビュー,2003年にマーメイドステークスを勝ったローズバド。祖母は1995年にデイリー杯3歳ステークスを勝ったロゼカラー。
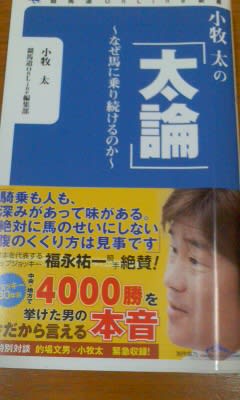
2歳10月のデビュー戦でヴィクトワールピサを2着に降して勝利。続く東京スポーツ杯2歳ステークスも勝って重賞ウイナーに。さらに朝日杯フューチュリティステークスも勝って大レース制覇。3戦3勝でこの年のJRA賞の最優秀2歳牡馬に選出されました。
3歳初戦のスプリングステークスは3着。皐月賞はヴィクトワールピサの4着。ダービーは2着と,好走を続けたものの3歳春は未勝利。
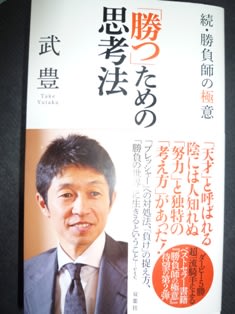
夏休みを挟んだ神戸新聞杯で重賞3勝目。菊花賞は2着。ジャパンカップに出走すると2着入線でしたが1着入線馬の降着により繰り上がって優勝。現行制度ではたぶん着順が入れ替わらなかった筈で,これは制度が変わる契機ともなったレース。現行制度には不満をもたれる方が多くいるようですが,僕は前制度より現制度の方がずっと合理的であると考えています。ラッキーな形ではあったかもしれませんが大レース2勝目。有馬記念は出走取消でした。
重篤な症状であったわけでなく年が明けてすぐに日経新春杯に出走。これはルーラーシップの3着。東日本大震災の影響で阪神での開催となった日経賞も3着。天皇賞(春)で11着と,初の惨敗を喫しました。宝塚記念は持ち直して4着。
秋初戦の京都大賞典で重賞5勝目。ところがここから天皇賞(秋)が10着,ジャパンカップは9着,有馬記念がオルフェーヴルの12着と,大きく崩れ続けてしまいました。
5歳も現役を続行。大阪杯は4着でしたが天皇賞(春)は15着。安田記念に向かいましたが13着と大敗の連続。
秋は京都大賞典が6着,ジャパンカップが16着,有馬記念も12着と巻き返しはならず。
翌年の大阪杯でオルフェーヴルの12着と大敗を喫した後,相手が楽な新潟大賞典に進みましたが11着。ここで現役生活に幕を下ろすことになりました。
大レースを2勝していますが,トップクラスの能力があった馬というより,それに近い能力があった馬だったと僕は思っています。種牡馬としては重賞の勝ち馬が出るか出ないかといった成績になるのではないでしょうか。
『エチカ』において非礼の反対の概念notioは端正honestumといわれます。ただ,ここでも注意を要する点があります。
これは岩波文庫版の訳者である畠中尚志もいっていることですが,『エチカ』でごく全般的に端正といわれる場合,理性ratioに従って生活する人,すなわち自由の人homo liberが賞賛することを意味します。したがってここでは賞賛されることをなした人が,理性に従って能動的にそれをなしたか,そうではなく受動的に強制されてそれをなしたかは問われていません。そして『エチカ』全般においては端正というのは確かにそのような意味を有していると解するのがよいと僕は思います。たとえば第三部諸感情の定義二七の説明の最後の方で次のようにいわれているからです。
「ある人にとって神聖なことが他の人にとって讀神的であり,またある人にとって端正なことが他の人にとって非礼だからである」。
この部分は,僕たちがどのように教育されるかによって,何を悔いたり何を誇ったりするかは異なるということを示すために記述されています。ただ,第四部定理三五によって,理性に従う限りでは現実的に存在する人間の本性naturaは一致するのですから,その限りにおいては何が端正であって何が非礼であるのかということも,すべての人間の間で一致しなければなりません。それなのに何が端正であって何が非礼であるのかということについて一致がみられない場合があるということを明らかにこの説明は認めています。よってこれは第三部定理五七の観点からいわれているのであり,端正であるといわれる人が,必ずしも理性に従っているというわけではない,理性に従っている場合もあるでしょうが,そうではない場合も含まれていると解しておくのが適当であると考えるからです。そもそもこの説明は,理性に従う人が何を賞賛するのかということについて,各人は異なった見解opinioを有し得るといっているようなものであり,この前提そのものが,端正とは理性に従うことによってのみ生じ得ることではないということの証明であるように思えるからです。
しかし一方で,この説明が明らかに端正と非礼を反対概念として扱っていることも明白だといえるでしょう。
父はキングカメハメハ。母は2001年にフィリーズレビュー,2003年にマーメイドステークスを勝ったローズバド。祖母は1995年にデイリー杯3歳ステークスを勝ったロゼカラー。
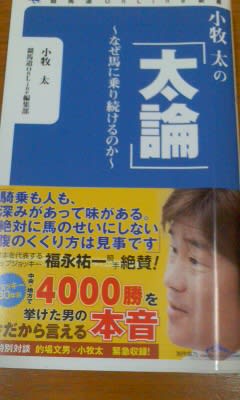
2歳10月のデビュー戦でヴィクトワールピサを2着に降して勝利。続く東京スポーツ杯2歳ステークスも勝って重賞ウイナーに。さらに朝日杯フューチュリティステークスも勝って大レース制覇。3戦3勝でこの年のJRA賞の最優秀2歳牡馬に選出されました。
3歳初戦のスプリングステークスは3着。皐月賞はヴィクトワールピサの4着。ダービーは2着と,好走を続けたものの3歳春は未勝利。
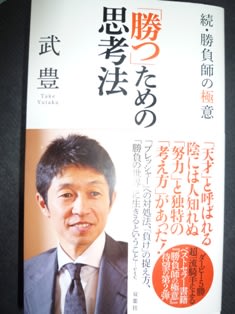
夏休みを挟んだ神戸新聞杯で重賞3勝目。菊花賞は2着。ジャパンカップに出走すると2着入線でしたが1着入線馬の降着により繰り上がって優勝。現行制度ではたぶん着順が入れ替わらなかった筈で,これは制度が変わる契機ともなったレース。現行制度には不満をもたれる方が多くいるようですが,僕は前制度より現制度の方がずっと合理的であると考えています。ラッキーな形ではあったかもしれませんが大レース2勝目。有馬記念は出走取消でした。
重篤な症状であったわけでなく年が明けてすぐに日経新春杯に出走。これはルーラーシップの3着。東日本大震災の影響で阪神での開催となった日経賞も3着。天皇賞(春)で11着と,初の惨敗を喫しました。宝塚記念は持ち直して4着。
秋初戦の京都大賞典で重賞5勝目。ところがここから天皇賞(秋)が10着,ジャパンカップは9着,有馬記念がオルフェーヴルの12着と,大きく崩れ続けてしまいました。
5歳も現役を続行。大阪杯は4着でしたが天皇賞(春)は15着。安田記念に向かいましたが13着と大敗の連続。
秋は京都大賞典が6着,ジャパンカップが16着,有馬記念も12着と巻き返しはならず。
翌年の大阪杯でオルフェーヴルの12着と大敗を喫した後,相手が楽な新潟大賞典に進みましたが11着。ここで現役生活に幕を下ろすことになりました。
大レースを2勝していますが,トップクラスの能力があった馬というより,それに近い能力があった馬だったと僕は思っています。種牡馬としては重賞の勝ち馬が出るか出ないかといった成績になるのではないでしょうか。
『エチカ』において非礼の反対の概念notioは端正honestumといわれます。ただ,ここでも注意を要する点があります。
これは岩波文庫版の訳者である畠中尚志もいっていることですが,『エチカ』でごく全般的に端正といわれる場合,理性ratioに従って生活する人,すなわち自由の人homo liberが賞賛することを意味します。したがってここでは賞賛されることをなした人が,理性に従って能動的にそれをなしたか,そうではなく受動的に強制されてそれをなしたかは問われていません。そして『エチカ』全般においては端正というのは確かにそのような意味を有していると解するのがよいと僕は思います。たとえば第三部諸感情の定義二七の説明の最後の方で次のようにいわれているからです。
「ある人にとって神聖なことが他の人にとって讀神的であり,またある人にとって端正なことが他の人にとって非礼だからである」。
この部分は,僕たちがどのように教育されるかによって,何を悔いたり何を誇ったりするかは異なるということを示すために記述されています。ただ,第四部定理三五によって,理性に従う限りでは現実的に存在する人間の本性naturaは一致するのですから,その限りにおいては何が端正であって何が非礼であるのかということも,すべての人間の間で一致しなければなりません。それなのに何が端正であって何が非礼であるのかということについて一致がみられない場合があるということを明らかにこの説明は認めています。よってこれは第三部定理五七の観点からいわれているのであり,端正であるといわれる人が,必ずしも理性に従っているというわけではない,理性に従っている場合もあるでしょうが,そうではない場合も含まれていると解しておくのが適当であると考えるからです。そもそもこの説明は,理性に従う人が何を賞賛するのかということについて,各人は異なった見解opinioを有し得るといっているようなものであり,この前提そのものが,端正とは理性に従うことによってのみ生じ得ることではないということの証明であるように思えるからです。
しかし一方で,この説明が明らかに端正と非礼を反対概念として扱っていることも明白だといえるでしょう。













