日本はなかなか禁煙できず 放射線対策をしながらJT株を保有する政府(フィナンシャル・タイムズ)
福島第一原発の事故による放射線の危険から市民を守ろうと苦労している日本において、政府が、発がん性のあるたばこで収益を増やそうとしているのは、一見すると奇妙に思えるかもしれない。
しかしこれは実は、それほど荒唐無稽な話ではない。日本たばこ産業(JT)はフィリップス・モリス・インターナショナルとブリティッシュ・アメリカン・タバコに続いて売り上げ世界3位の上場たばこ会社だが、日本の財務省はJT株の50%超を保有しているので、すでにけっこうな利益を上げているのだ。
昨年度だけでJTは配当金300億円以上を財務省に支払っている。これは主に国内の喫煙者にたばこ1350億本を売った利益によるものだ。たばこのかぐわしい香りは、がん発生のリスク上昇という代償とセットなのだが。
(中略)
そしてその結果、日本政府に倫理的な矛盾が生じ、組織として目指すものが衝突する状態が生まれてしまったのだ。政府は、福島第一原発から漏出する発がん性のある放射線による被ばくリスクを最小限に留めようと、巨額の費用を使っている。その同じ政府が一方では、同じ国民に「発がんスティック」を売りつけた利益でもうけているのだから。
さらに、たばこそのものに放射性鉛や放射性ポロニウムといった放射性物質が含まれているし、米環境保護庁はこうした放射性物質が「喫煙者の肺に非常に高い濃度で蓄積することもある」と指摘しているのは、実に皮肉なことだ。
(中略)
政府がJT株を保有する根拠のひとつに、日本国内で生産されるたばこ葉をJTが全て買い取らなくてはならないという取り決めがある。これはかつてたばこ農家が市場開放に反対した名残だ。しかし日本国内に残るたばこ農家は1万戸しかないし、そんなに小さな利益集団に平伏していたのでは、是非とも必要な農業改革の妨げとなる。
癌のリスクを基準にすると、常習的な喫煙は年間2000ミリシーベルトの被曝量に相当するそうです(受動喫煙の場合は100ミリシーベルト相当、ちなみに話題の「汚染牛」を毎日200g欠かさず食べ続けた場合の被曝量は約4ミリシーベルトです)。4月には福島で煙草の作付けが見合わせられることになったと聞いたものですが、煙草が元から抱えている癌リスクを考えれば意味はあるのか、「安全で健康に影響のない煙草」でも目指しているのかと苦笑したことを思い出します。癌リスクが年間2000ミリシーベルトから2100ミリシーベルト相当に変わっても大した差にはならない、それ以前に健康を気にするなら煙草を止めたらと言う話になるわけです。まさか煙草に起因する癌は良い癌、放射「能」に由来する(と、本人が信じている)癌は悪い癌だということもないでしょうに。まぁ、蒟蒻ゼリーは規制されてもモチは規制されないもの、危険の度合いよりも普及の度合いの方が世間では重視されるもののようです。
そう言えば福島第一原発の作業現場で、防護マスクを外して煙草を吸っていた作業員の存在が話題になりました。例によって大元の管理責任者たる東京電力に非難が殺到したのはさておき、他人に煙草を吸わせないようにするのは本当に大変ですよね。私の勤務先でも「協力会社」として作業員を工事発注元(残念ながら東京電力ではありません)に送り込んだりするのですが、禁煙区域なのに作業員が隠れて煙草を吸っていたと工事発注元からクレームと是正勧告が飛んでくることは頻繁にあります。仕事を終えて家に帰るまで我慢したらどうかと思わないでもないのですが、非喫煙者には理解の出来ない世界があるのでしょう。何を言っても煙草を吸う人は吸うのだと諦めるほかありません。大麻の中毒性は煙草以下なんて話もありますけれど、むしろ煙草の中毒性は大麻以上、と逆の視点から考えた方がいいような気がしてきます。
たばこ自動販売機の成人識別カード「タスポ(taspo)」が未成年者の喫煙を防ぐ効果が薄れているらしいことが、厚生労働省研究班(代表者=大井田隆・日本大学教授)の調査でわかった。たばこを毎日吸っている中高生の使用経験が6割を超え、2年前の4割より増加していた。
昨年10月~今年2月、全国の中高生約10万人から回答があった研究班のアンケートによると、毎日たばこを吸っているという1612人の63%が「タスポを使ったことがある」と答えた。2008年調査では42%で、大きく増えていた。
月に1日でも吸ったことがあるという3852人でみても、今回は46%と、前回の29%より増加した。
中高生の喫煙経験者のうち、昨年10月1日のたばこ値上げ以降に禁煙した生徒は約2割に上ることが、厚生労働省の研究班(代表者=大井田隆・日本大学教授)の全国調査でわかった。
調査は昨年10月から今年3月にかけて、全国244校の中学、高校を無作為に選んで実施。170校約9万9000人から回答を得た。
その結果、2854人が値上げ後も喫煙を続ける一方、656人が禁煙したと回答した。禁煙した生徒の約4割がその理由として、「お金の節約・たばこの値段が高い」と答えた。
また、毎日喫煙する生徒の63%、月1回喫煙する生徒の46%が、未成年の喫煙防止を目的として2008年に導入されたカード「タスポ」を使って、たばこを購入していることも判明した。大井田教授は「自動販売機の撤去とさらなる値上げが、中高生の喫煙防止に効果的だ」と話している。
さて、同じ調査を元にしているにも関わらず、朝日と読売で随分と印象の異なる報道がなされています。どっちも嘘は吐いていないのでしょうけれど、ピックアップする部分が違うのですね。両方の記事を並べて読めば全貌をつかむのに丁度良いのかも知れません。ただし、読売の本文ではなく見出しの方には流石に首を傾げるところで、「たばこ値上げの意外な効用…中高生の2割やめた」とありますが、私なんかは「値上げにも関わらず喫煙を続ける中高生が8割」と読めてしまいます。取りあえず理解できるのは、成人識別カード(タスポ)を導入すれば未成年が煙草を買えなくなるかと言えばさに非ず、タスポを使って煙草を買う中高生が大幅に増えていること、そして2854人が値上げ後も喫煙を続けると回答したのに対し、禁煙したと回答したのは656人に止まるということです。
やはり正直に喫煙を申告した中高生は少ないのか、9万9000人から回答を得たにも関わらず、「月に1日でも吸ったことがあるという3852人」とか、「2854人が値上げ後も喫煙を続ける」「656人が禁煙」等々、喫煙者として回答した生徒の数は全体の5%にも満たず、相当な暗数が存在するであろうことが考えられます。実は煙草を吸っているけれど、調査には「吸っていない」と回答した人が何万人もいることでしょう。ただ、その辺を差し引いても窺われるのは、中高生の少ない小遣いの中でも喫煙を続けようとする中毒度合いの高さでもあります。
なお読売の報道によると2854人が値上げ後も喫煙を続け、656人が禁煙、うち4割が理由として「お金の節約・たばこの値段が高い」と回答していることになります。項目的に果たして値上がりの効果なのか、値上がりがなくとも別の理由でお金の節約が必要になっただけではないか、と訝しく思えるところがないでもありません。それに656人の4割に当たる262人を、2854+656の3510人で割り算すると、僅かに7%にしかならないわけで、値上がりを理由に煙草を止める中高生というのは、2割どころかほとんどいないとすら考えられます。たばこ税の引き上げが企図されると決まって「煙草が値上がりすると喫煙する人が減るので税収増には結びつかない」と主張する人が少なくありませんけれど、結局のところ値段が上がったくらいで煙草は止められないもののようです。
まぁ個人の嗜好にはとやかく干渉するつもりもありませんので他人が煙草を吸うのは勝手ですが、人前で煙を吐き出すのは止めろよと感じるところもあります。煙は全部、吸いこんでこそマナーでしょうね。それから火の点いた方を他人に向けるのもマナーが良くないので止めた方がいいでしょう。ともあれ、たばこ税は引き上げれば引き上げた分だけ税収増が見込めるであろう美味しい税でもありますが、フィナンシャルタイムズに皮肉を言われているように政府がそれで儲けてしまうのはどうなのかとか、どうあっても煙草を止められない人々から金を取るのは、ある意味で依存症のジャンキーにクスリを売りつけて儲けるのに似ているのではないかという気がしないでもありません。本人の嗜好の範囲を超えて、そろそろ治療が必要な頃合いなのではないかと思えてくるところです。











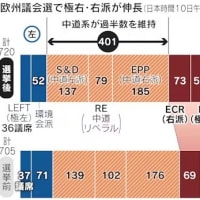


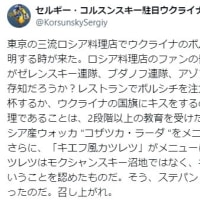

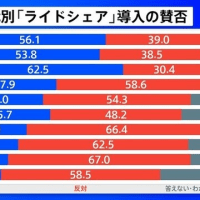
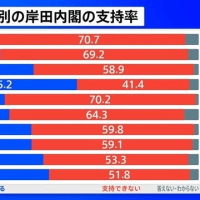
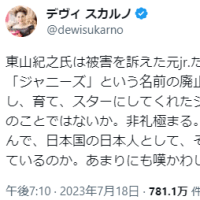
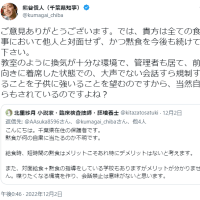
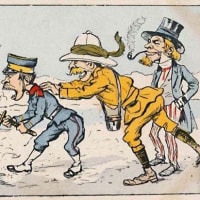






青少年の喫煙習慣は、他の薬物依存の誘因にもなるんじゃないかなあ。(大麻もそういう理由で批判される)
私立高校なら、喫煙は退学にするとか。とくに保守的教育を売り物にするんだったら、違法行為は厳罰にすべきではないかしらん。
指導要領に、喫煙の健康被害を特記して、授業で禁煙教育するというのも、社会政策上はあり得ると思う。
そうならならないのは社会衛生、国民の健康より経済的利益が優先ということで、そういう点ではこれまでの原発推進政策と同じと言えるかもしれません。
どうですかね、「原発推進政策」とやらが経済的利益のために国民の健康を犠牲にしてきたかと言えば、それは世間一般の認識を鵜呑みにしただけにも見えますが。元より国民の健康を蔑ろにしてきたのは社会全般であって原発に限った話ではありませんし、少なくとも弱者切り捨てを進め、働く人を休日労働や深夜労働に駆り立てる脱原発に比べれば優しいものですから。