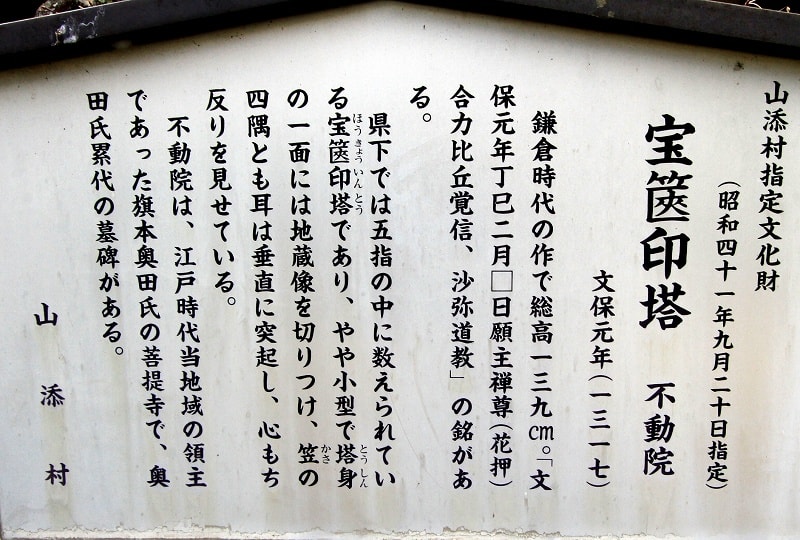多分、政所の中心地だと思われる集落の鎮守、八幡神社入口に建つ茅葺き民家。

政所入口集落よりダラダラ峠を越し、御池川沿いに少し遡り、目の前に現れる家並がこの辺り・・・大きなグランド越し、鎮守の杜をバックに懐かしい家並が美しく映える。

この茅葺き民家は、鎮守八幡神社前に在り、もしかして社家なのだろうか??
>
下屋は現代風のアルミサッシや瓦棒葺きにと手を加えられて居ますが、上家はスッキリ寄棟茅葺き。

棟仕舞はトタンを被せた箱棟・・・・見た感じ下屋の庇は後の継ぎ足し??、元は葺き下ろし屋根では無かったのかと思える。

小さな破風脇は東近江地域に多いフックラ丸みを帯びた仕上げに成って居る。

裏側、神社境内から見るとこんな風・・・・やはり日裏部分は屋根の傷みが進んでる。

立ち去り難く、御池側を挟んだ高台より遠望すると、それはまさしく緑に包まれた山里風情・・・・・。
こんな景観はそうそう出遇えるもんじゃない。
撮影2013.6.23:2012.6.24