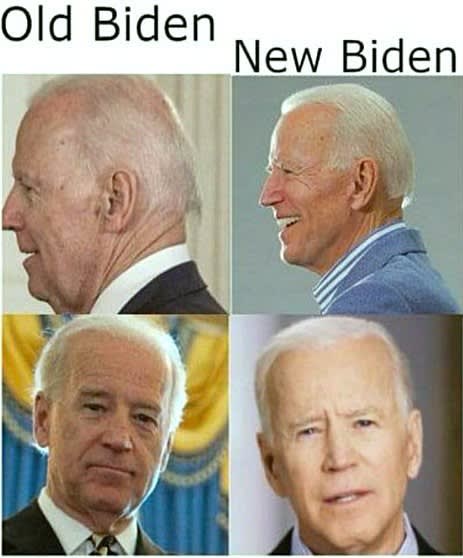内陸の盆地に住む舞衣にとって、津波の心配は皆無であったが、祖父母の代からの旧家で築六十年を裕に超えるだろう我が家が無事であるかの保障は、その限りではなかった。
もし、主婦である母親や小学生の弟が、家の巻き添えにでもなっていたら…と、ちらりとでも脳裏に浮かぶや、その胸は早鐘のように激しく高鳴るのだった。
(どうぞ、無事であって。
お母さん。
さとしぃ…)
舞衣は、次第に歩調が早まって、いつしか小走りになっていた。
十数キロを走るなんて、高校時代の合宿以来のことである。
でも、今は、まさに非常時である。
つい半年前まで、現役のバレーボール選手だったことが彼女にとっては、幸いであった。
まだ、その脚力が、さほどに衰えてはいなかったからである。
母親の芳枝も、中高とバレーの選手で、二人を産むまでは、ママさんバレーでも活躍していたことがある。
弟の智史も、小4からスポ少でバレーを始めたので、一家揃ってのバレー家族である。
父親の将文(まさふみ)だけが、中高大とテニス一筋であった。
そんなんで、舞衣は時折、智史とも母とも、全日本女子の試合をテレビで共に観戦していた。
気が付けば、小走りからランニングのスピードになっていた。
気が急いてならなかったのだ。
一刻も早く帰宅せねば、という切迫した気分は、舞衣の胸を圧迫して苦しめていた。
女の子らしいベージュの肩掛けポシェットは、いつしか彼女の背後へと廻り、そのお尻の上でポンポン跳ね上がっていた。
その姿は、あたかも中学時代の国語の教科書に出てきた太宰治の『走れメロス』のようであった。
自分を信じて待つ親友セリヌンティウス。
メロスは走った。
舞衣も走った。
・・・・・・路行く人を押しのけ、跳はねとばし、メロスは黒い風のように走った。
野原で酒宴の、その宴席のまっただ中を駈け抜け、酒宴の人たちを仰天させ、犬を蹴けとばし、小川を飛び越え、少しずつ沈んでゆく太陽の、十倍も早く走った。
一団の旅人と颯(さ)っとすれちがった瞬間、不吉な会話を小耳にはさんだ。
「いまごろは、あの男も、磔にかかっているよ」
(ああ、その男、その男のために私は、いまこんなに走っているのだ。
その男を死なせてはならない。)
急げ、メロス。
おくれてはならぬ。
愛と誠の力を、いまこそ知らせてやるがよい。
風態なんかは、どうでもいい。
メロスは、いまは、ほとんど全裸体であった。
呼吸も出来ず、二度、三度、口から血が噴き出た。
見える。
はるか向うに小さく、シラクスの市の塔楼が見える。
塔楼は、夕陽を受けてきらきら光っている。
「ああ、メロス様」
うめくような声が、風と共に聞えた。
「誰だ?」
メロスは走りながら尋ねた。
「フィロストラトスでございます。
貴方のお友達セリヌンティウス様の弟子でございます」
その若い石工も、メロスの後について走りながら叫んだ。
「もう、駄目でございます。
むだでございます。
走るのは、やめて下さい。
もう、あの方かたをお助けになることは出来ません」
「いや、まだ陽は沈まぬ」
「ちょうど今、あの方が死刑になるところです。
ああ、あなたは遅かった。
おうらみ申します。
ほんの少し、もうちょっとでも、早かったなら!」
「いや、まだ陽は沈まぬ」
メロスは胸の張り裂ける思いで、赤く大きい夕陽ばかりを見つめていた。
走るより他は無い。
「やめて下さい。
走るのは、やめて下さい。
いまはご自分のお命が大事です。
あの方は、あなたを信じて居りました。
刑場に引き出されても、平気でいました。
王様が、さんざんあの方をからかっても、メロスは来ます、とだけ答え、強い信念を持ちつづけている様子でございました」
「それだから、走るのだ。
信じられているから走るのだ。
間に合う、間に合わぬは問題でないのだ。
人の命も問題でないのだ。
私は、なんだか、もっと恐ろしく大きいものの為に走っているのだ。
ついて来い!
フィロストラトス」
「ああ、あなたは気が狂ったか。
それでは、うんと走るがいい。
ひょっとしたら、間に合わぬものでもない。
走るがいい」
言うにや及ぶ。
まだ陽は沈まぬ。
最後の死力を尽して、メロスは走った。

メロスの頭は、からっぽだ。
何一つ考えていない。
ただ、わけのわからぬ大きな力にひきずられて走った。
陽は、ゆらゆら地平線に没し、まさに最後の一片の残光も、消えようとした時、メロスは疾風の如く刑場に突入した。
間に合った。
・・・・・・
舞衣は12㎞の帰路を完走した。
後半は全力で疾駆した。
そして、一時間内で到着した彼女を待っていたのは、無残に倒壊した我が家だった。