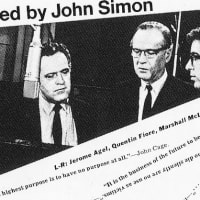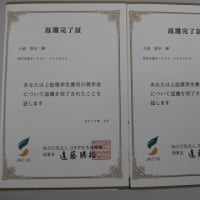エドワード・ルトワック『エドワード・ルトワックの戦略論:戦争と平和の論理』武田康裕, 塚本勝也訳, 毎日新聞出版, 2014.
軍事、安全保障。著者は軍事コンサルタントで、すでに新書二冊を採りあげたことがある(参考)。これは彼の主著で、オリジナルはStrategy: The logic of war and peace (Belknap Press of Harvard University Press, 1987)で、2001年の改訂版がこの邦訳の元となっている。
一応、技術、戦術、作戦、戦域、大戦略とレベルを分けてはいるものの、体型的な記述とはなっておらず難解である。こちらに軍事知識がないためにわからなくなる箇所もある(例えば「ミサイル歩兵」と書かれても装備のイメージが湧かない)。内容は、ある極限点を超えると勝者が敗者となり敗者が勝者となるという「逆説的論理」の事例をこれでもかと挙げていくものだ。ある国による攻撃・防衛あるいは軍事的イノベーションは、必然的に敵国に反応を引き起こしてしまうため、事前に期待した通りの結果とはならないというのがその主旨である。
事例は主に第二次世界大戦と中東戦争から集められており、朝鮮戦争、湾岸戦争、ユーゴ内戦、冷戦などにも言及がある。第二次大戦における英国によるドイツ都市への空爆作戦や、ドイツの電撃的なソビエト侵攻、1973年のイスラエル対エジプトの戦争などは、著者のいう逆説的論理が作動する様子がわかりやすく捉えられている(湾岸戦争のように圧倒的戦力差がある場合はその論理が働かないこともある)。著者のチャーチル、スターリン、ロンメルの評価も面白い。一般的な法則を得ることを期待しなければ、事例集として興味深いだろう。
太平洋戦争における日本についても言及があるが、それは真珠湾攻撃が大失敗していればよりマシな条件で敗北できた、というもの。日本側に、カリフォルニアを目指して進軍し、ワシントンを制圧する計画が無かった以上、そもそも勝ち目は無かった、と。そんなことわかってる。というわけで日本についての話はあまり新しい知見はない。
軍事、安全保障。著者は軍事コンサルタントで、すでに新書二冊を採りあげたことがある(参考)。これは彼の主著で、オリジナルはStrategy: The logic of war and peace (Belknap Press of Harvard University Press, 1987)で、2001年の改訂版がこの邦訳の元となっている。
一応、技術、戦術、作戦、戦域、大戦略とレベルを分けてはいるものの、体型的な記述とはなっておらず難解である。こちらに軍事知識がないためにわからなくなる箇所もある(例えば「ミサイル歩兵」と書かれても装備のイメージが湧かない)。内容は、ある極限点を超えると勝者が敗者となり敗者が勝者となるという「逆説的論理」の事例をこれでもかと挙げていくものだ。ある国による攻撃・防衛あるいは軍事的イノベーションは、必然的に敵国に反応を引き起こしてしまうため、事前に期待した通りの結果とはならないというのがその主旨である。
事例は主に第二次世界大戦と中東戦争から集められており、朝鮮戦争、湾岸戦争、ユーゴ内戦、冷戦などにも言及がある。第二次大戦における英国によるドイツ都市への空爆作戦や、ドイツの電撃的なソビエト侵攻、1973年のイスラエル対エジプトの戦争などは、著者のいう逆説的論理が作動する様子がわかりやすく捉えられている(湾岸戦争のように圧倒的戦力差がある場合はその論理が働かないこともある)。著者のチャーチル、スターリン、ロンメルの評価も面白い。一般的な法則を得ることを期待しなければ、事例集として興味深いだろう。
太平洋戦争における日本についても言及があるが、それは真珠湾攻撃が大失敗していればよりマシな条件で敗北できた、というもの。日本側に、カリフォルニアを目指して進軍し、ワシントンを制圧する計画が無かった以上、そもそも勝ち目は無かった、と。そんなことわかってる。というわけで日本についての話はあまり新しい知見はない。