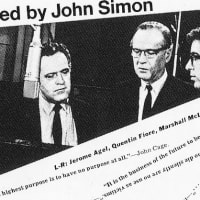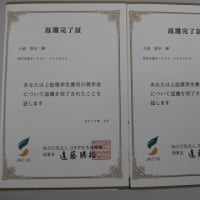ロバート・ダーントン『検閲官のお仕事』上村敏郎, 八谷舞, 伊豆田俊輔訳, みすず書房, 2023.
読書史研究者として知られる著者による、検閲についての研究書籍。事例として用いられているのは、アンシャンレジーム下のフランス、植民地時代のインド、旧東ドイツの検閲の三つである。原書はCensors at Work : How States Shaped Literature (WW Norton, 2015)となる。
18世紀のフランスでは、王室や貴族、教会への批判はタブーだと考えられてきた。ただし、それらと無関係な主題であっても、文章が下手だったりすると検閲官の厳しいコメントが入ったとのこと。主題とは無関係に、書籍中で批判されている人物が有力者か、あるいは有力者お抱えの人物かという点も検閲の論点となったようだ。ただし、仮に検閲官が低い評価を下しても、必ずしも発行が禁じられたというわけでもなく、その辺りは人脈次第の面もあったとという。一方で、検閲回避のための外国での発行や、地下発行もあり、そのための市場が存在していたことは知られている通りである。
英国統治下のインドにおける検閲はすべて発行後のもので、発行書籍の目録作りには図書館員らが協力していた。英国統治が盤石だった19世紀においては、書籍における英国に批判的な記述は特に問題視されなかった。だが、独立運動が激しくなった20世紀初頭は、過去にさかのぼって作品や著者に「扇動罪」を適用するようになった。東ドイツでは事前検閲が行われていた。だが、政府は抑圧的な体制だというイメージを受け容れたくないので、検閲を行っていることを認めていなかったらしい。検閲では「西ドイツからの視線」が意識され、「東側で抑圧された結果、西側で作者が英雄視される」という事態を招かないよう配慮されていた。
以上。著者には、検閲の実態を伝えるだけでなく、「検閲なんかどのレベルにでもある。ポリコレやら検索アルゴリズムがそう」という相対主義言説に対抗する意図もあったようだ。死刑になるような酷いケースは挙げられていないもの、国家による検閲は、単に該当作品の発表機会を失わせるというだけでなく、その作品の著者が牢屋に入れられて数年にわたって自由を奪われたり、社会からの信用を失って失意のまま死を迎えるなどの悲惨な結果をもたらすことがある、ということである。
読書史研究者として知られる著者による、検閲についての研究書籍。事例として用いられているのは、アンシャンレジーム下のフランス、植民地時代のインド、旧東ドイツの検閲の三つである。原書はCensors at Work : How States Shaped Literature (WW Norton, 2015)となる。
18世紀のフランスでは、王室や貴族、教会への批判はタブーだと考えられてきた。ただし、それらと無関係な主題であっても、文章が下手だったりすると検閲官の厳しいコメントが入ったとのこと。主題とは無関係に、書籍中で批判されている人物が有力者か、あるいは有力者お抱えの人物かという点も検閲の論点となったようだ。ただし、仮に検閲官が低い評価を下しても、必ずしも発行が禁じられたというわけでもなく、その辺りは人脈次第の面もあったとという。一方で、検閲回避のための外国での発行や、地下発行もあり、そのための市場が存在していたことは知られている通りである。
英国統治下のインドにおける検閲はすべて発行後のもので、発行書籍の目録作りには図書館員らが協力していた。英国統治が盤石だった19世紀においては、書籍における英国に批判的な記述は特に問題視されなかった。だが、独立運動が激しくなった20世紀初頭は、過去にさかのぼって作品や著者に「扇動罪」を適用するようになった。東ドイツでは事前検閲が行われていた。だが、政府は抑圧的な体制だというイメージを受け容れたくないので、検閲を行っていることを認めていなかったらしい。検閲では「西ドイツからの視線」が意識され、「東側で抑圧された結果、西側で作者が英雄視される」という事態を招かないよう配慮されていた。
以上。著者には、検閲の実態を伝えるだけでなく、「検閲なんかどのレベルにでもある。ポリコレやら検索アルゴリズムがそう」という相対主義言説に対抗する意図もあったようだ。死刑になるような酷いケースは挙げられていないもの、国家による検閲は、単に該当作品の発表機会を失わせるというだけでなく、その作品の著者が牢屋に入れられて数年にわたって自由を奪われたり、社会からの信用を失って失意のまま死を迎えるなどの悲惨な結果をもたらすことがある、ということである。